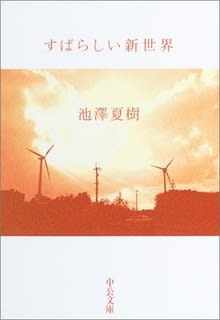池澤夏樹 「すばらしい新世界 」読了
主人公は風力発電用の風車を作る技術者である。奥さんは環境保護のNGOで働いていてその流れから、ネパールに小型の風力発電機を設置することになる。
そこでの体験の物語となっている。
池澤夏樹の本はずっと昔、30年ほど前だろうか、「母なる自然のおっぱい」という本を読んだことがあるだけだった。内容もまったく覚えていなくてネットに上がっている感想文などを読んでいると、人と自然のかかわりや文明論、環境問題について書かれていたらしい。タイトルだけはよく覚えていた。
この本のストーリーも、行き過ぎた文明、自然と人間、そして信仰、そんなものの関係の中で、何が一番人々に幸せをもたらすのかというようなものを考えさせられるものになっている。
この本が出版されたのは2000年。5年前には地下鉄サリン事件があり、1年前には東海村JCO臨界事故があった。このような状況を見て、著者はきっと人の心も文明も袋小路のようなものに入ってしまったのではないかと思ったにちがいない。
インターネットや経済のグローバル化が顕著に発達したのもこの頃だ。エントロピーは極大化し、世界はどこを見ても同じになりつつある世界を見て、これでいいのか、人が幸せに生きることができる世界のサイズはもっと小さいはずではなかったかというのがこの小説の主題になっていると思う。
一方ではエントロピーの極大化に反して富やエネルギーは先進国と言われる世界に集中しつつある。そんな矛盾した世界のなかで幸せに生きる方法を著者自身が模索しているようにも思える。
エネルギー=電気というものは今や人の生活には欠かせない。あればあるほど便利になる。しかし使いたいだけ使うためには巨大なシステムが必要だ。しかしながらそれは人が操れないほどのものである。事実11年後には世界を驚愕させる事故が起こった。
グローバル化というものが本当に人に幸せをもたらすのか、効率的な生活が本当に人に幸せをもたらすのか。その対極にあるのがネパールのナムリン王国に建設しようとする風車である。そしてその社会のサイズは宗教が決める。人々が共通の宗教を共有する。それができる範囲はかなり小さい。日本でいうと、檀家であり氏子である。その中で生きてゆけるのが一番幸せではないのか。エネルギーもそのサイズで賄えることが一番効率的ではないのか。
主人公はそれをナムリンでの信仰の姿をみて悟る。それが小説のタイトルの、「素晴らしき新世界」だというのである。
経済と情報のグローバル化というのはどこまで行きつくのか僕には分からないけれども、それが破綻したその先には再び小さな範囲で完結する世界が生まれるのかもしれない。
僕にもそういう世界が人々に本当の幸せをもたらすのではないかと思えた。
700ページを超える小説であるけれどもまったく長さを感じさせない1冊であった。
主人公は風力発電用の風車を作る技術者である。奥さんは環境保護のNGOで働いていてその流れから、ネパールに小型の風力発電機を設置することになる。
そこでの体験の物語となっている。
池澤夏樹の本はずっと昔、30年ほど前だろうか、「母なる自然のおっぱい」という本を読んだことがあるだけだった。内容もまったく覚えていなくてネットに上がっている感想文などを読んでいると、人と自然のかかわりや文明論、環境問題について書かれていたらしい。タイトルだけはよく覚えていた。
この本のストーリーも、行き過ぎた文明、自然と人間、そして信仰、そんなものの関係の中で、何が一番人々に幸せをもたらすのかというようなものを考えさせられるものになっている。
この本が出版されたのは2000年。5年前には地下鉄サリン事件があり、1年前には東海村JCO臨界事故があった。このような状況を見て、著者はきっと人の心も文明も袋小路のようなものに入ってしまったのではないかと思ったにちがいない。
インターネットや経済のグローバル化が顕著に発達したのもこの頃だ。エントロピーは極大化し、世界はどこを見ても同じになりつつある世界を見て、これでいいのか、人が幸せに生きることができる世界のサイズはもっと小さいはずではなかったかというのがこの小説の主題になっていると思う。
一方ではエントロピーの極大化に反して富やエネルギーは先進国と言われる世界に集中しつつある。そんな矛盾した世界のなかで幸せに生きる方法を著者自身が模索しているようにも思える。
エネルギー=電気というものは今や人の生活には欠かせない。あればあるほど便利になる。しかし使いたいだけ使うためには巨大なシステムが必要だ。しかしながらそれは人が操れないほどのものである。事実11年後には世界を驚愕させる事故が起こった。
グローバル化というものが本当に人に幸せをもたらすのか、効率的な生活が本当に人に幸せをもたらすのか。その対極にあるのがネパールのナムリン王国に建設しようとする風車である。そしてその社会のサイズは宗教が決める。人々が共通の宗教を共有する。それができる範囲はかなり小さい。日本でいうと、檀家であり氏子である。その中で生きてゆけるのが一番幸せではないのか。エネルギーもそのサイズで賄えることが一番効率的ではないのか。
主人公はそれをナムリンでの信仰の姿をみて悟る。それが小説のタイトルの、「素晴らしき新世界」だというのである。
経済と情報のグローバル化というのはどこまで行きつくのか僕には分からないけれども、それが破綻したその先には再び小さな範囲で完結する世界が生まれるのかもしれない。
僕にもそういう世界が人々に本当の幸せをもたらすのではないかと思えた。
700ページを超える小説であるけれどもまったく長さを感じさせない1冊であった。