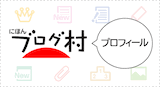今夜から、憲法改正問題に於ける最大のポイント、第9条について触れて参りたく思います。
同条の主題は「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」であり
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。
の2項により構成されています。
第1項は同条の精神であるとされ、本項が今日まで保持された事が主にアジアの周辺諸国の信頼を得て、それにより我国の長きに亘る平和と安定に大きく寄与して参ったのは厳然たる事実であり、我国の国是として恒久的に存続するのは私も異議のない所です。
ただし、第2項の「戦力及び交戦権の否認」については「諸国家に固有の権利である自衛力までも否定するものではないのでは?」との議論が日本国憲法の発足当時より存在し、同憲法の制定に指導的役割を果たしたGHQ=連合国進駐軍よりも、1950=昭和25年の朝鮮動乱の勃発を機に、我国自衛組織の結成を要請。これに基づき後に自衛隊となる組織、警察予備隊が発足しています。1954=同29年に現在の組織に改組、今や陸海空を合わせれば20数万人と言われる大組織に発展した自衛隊が、本当に我国の安全を守るのに必要最低限の自衛組織と言えるのか、との疑問がある事も理解はしておりますが、私もやはり、最低限の自衛力までも否定している訳ではないとの視点を支持したく思います。
戦後長く続いた東西冷戦の頃は、とかく米合衆国の軍事戦略と関連づけて論議された我国の自衛力問題でしたが、やはり必要最低限とする、第9条1項による歯止めは必要でしょう。外国の戦地にまで赴く「集団的自衛権」の是非も取り沙汰されますが、一定限度以上に認めるのは危険だと思います。
又、昨年の読売新聞紙上で紹介された、平和の為に当事国双方が武力を放棄し合うシステム「不戦共同体」構築への模索と取り組みへの努力も引き続き求めたい所です。*(地球)*
同条の主題は「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」であり
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。
の2項により構成されています。
第1項は同条の精神であるとされ、本項が今日まで保持された事が主にアジアの周辺諸国の信頼を得て、それにより我国の長きに亘る平和と安定に大きく寄与して参ったのは厳然たる事実であり、我国の国是として恒久的に存続するのは私も異議のない所です。
ただし、第2項の「戦力及び交戦権の否認」については「諸国家に固有の権利である自衛力までも否定するものではないのでは?」との議論が日本国憲法の発足当時より存在し、同憲法の制定に指導的役割を果たしたGHQ=連合国進駐軍よりも、1950=昭和25年の朝鮮動乱の勃発を機に、我国自衛組織の結成を要請。これに基づき後に自衛隊となる組織、警察予備隊が発足しています。1954=同29年に現在の組織に改組、今や陸海空を合わせれば20数万人と言われる大組織に発展した自衛隊が、本当に我国の安全を守るのに必要最低限の自衛組織と言えるのか、との疑問がある事も理解はしておりますが、私もやはり、最低限の自衛力までも否定している訳ではないとの視点を支持したく思います。
戦後長く続いた東西冷戦の頃は、とかく米合衆国の軍事戦略と関連づけて論議された我国の自衛力問題でしたが、やはり必要最低限とする、第9条1項による歯止めは必要でしょう。外国の戦地にまで赴く「集団的自衛権」の是非も取り沙汰されますが、一定限度以上に認めるのは危険だと思います。
又、昨年の読売新聞紙上で紹介された、平和の為に当事国双方が武力を放棄し合うシステム「不戦共同体」構築への模索と取り組みへの努力も引き続き求めたい所です。*(地球)*