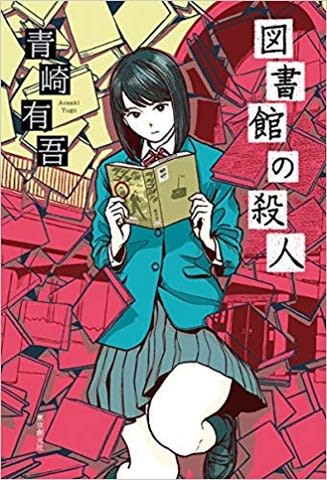
『図書館の殺人』 青崎有吾 ☆☆☆☆
「平成のエラリー・クイーン」こと青崎有吾の三つ目の長編小説を読了した。一作目の『体育館の殺人』にはかなり感心し、二作目の『水族館の殺人』はちょっと落ちると思ったが、この『図書館の殺人』の推理の緻密さはまたデビュー作並みだ。「密室」「アリバイ崩し」と続いた本格ミステリの王道テーマを掲げる趣向も踏襲され、今回のテーマは「ダイイング・メッセージ」。ずっとこの調子でいくつもりだろうか。なかなか大変だろうが、自らハードルを設定するというこのチャレンジ精神はとても美しい。
さて、今回の舞台はもちろん図書館である。図書館員が朝出勤すると大学生が床に倒れて死んでいる。何の理由か分からないが夜の間に侵入したらしい。死体のまわりには本が散らばっている。そして床の上に血文字、本の表紙に丸が描かれている。出ました、ダイイング・メッセージ。
ダイイング・メッセージものはクイーンもいくつか書いているし他にも色々あるが、なかなか難しいところがあって、ダイイング・メッセージの解読がそのまま犯人の指摘につながる例はあまり見たことがない。なぜならば疑問の余地なく犯人を示すメッセージではミステリがなくて面白くないし、解釈に苦しむメッセージの場合は、それが特定の人物を指しているというロジカルな断定が困難になる。だからメッセージそのものの意味よりもそれを残した状況や残し方が手がかりになる場合が多く、そういう意味で私が完璧だと思うのは名作『Xの悲劇』だが、本書もなかなか好印象である。
好印象の理由を詳しく書くとネタバレになるのでもちろん書かないが、本書をすでに読んだ方はもうお分かりの通り、メッセージの意味やそのひねり方ではない。その観点ではむしろ凡庸で、血でのたくった文字や絵の中のキャラクターを示すというありきたりのやり方だ。問題は、これが果たして本当にダイイング・メッセージか犯人の偽装か、という点だが、高校生探偵・裏染天馬が死体の置かれていた状況とその制約から導き出す結論は実に巧妙だ。言われてみれば確かにそうなのだが、これに気づく読者はなかなかいないだろう。なるほどなあ、と思わずうなってしまった。
その他の裏染の推理も、デビュー作同様入り組んでいてしかもきわめて論理的である。刃の欠けたカッターや血を拭った床のあとなど、例によって何の変哲もない手がかりからあれこれと犯人の条件を絞り込んでいく。特に、ちょっとだけ刃の欠けたカッターとその欠けた部分が発見された場所から彼が導き出す、犯人の犯行直後の不思議な行動、それが何を意味するか、そしてそれでどう犯人像が絞り込まれるか、というあたりの展開は非常にスリリングだった。「平成のエラリー・クイーン」の名に恥じない緻密さだ。論理的推理が好きなミステリ・ファンはたまらないだろう。
しかしその一方で、欠点もある。まず、なんといっても真犯人の動機が苦し過ぎる。犯人と被害者との関係を考えればあまりにも非現実的である。それに、この犯罪にはある少女が書いた小説が関係しているのだが、その小説本をこっそり図書館の本棚に置いたことで恐喝だの犯罪だのいう話になるのは、いかにも大げさ過ぎる。この著者は論理的推理の組み立てに関してはクイーン並みに素晴らしいのだが、犯罪の背景となる人間関係や説得力のある人間ドラマを作る点に関しては、まだまだ開発途上のようだ。
さて、本書は三作目の長編ということで、裏染天馬はなぜ学校に住んでいるのか、誰も愛せなくなってしまったという過去の出来事とは何だったのか、というあたりの真相もちょっとずつ開示しつつある。が、まだ全部は分からない。レギュラー高校生たちのキャラも固まり、ギャグのパターンもほぼ確立されて安定感が出てきた。登場人物が時折もらす擬音語、「はぷす!」とか「ふにゃあ!」には結構笑わせていただきました。それに今回は期末試験中という趣向だが、高校生たちが一喜一憂するイベントに殺人事件を絡めたのも悪くなかったと思う。
それにしても、主人公の裏染天馬はアニメオタクという設定であり「ダメ人間」と呼ばれているが、学力は余裕で学年一位だし、ルックスはほぼ完璧なイケメンらしい。年下男が好みの女刑事が彼を見て「百点!」とつぶやく場面がある。もしこれがTVドラマ化されるようなことになったら、裏染役はやっぱりジャニーズがやるんだろうか。
「平成のエラリー・クイーン」こと青崎有吾の三つ目の長編小説を読了した。一作目の『体育館の殺人』にはかなり感心し、二作目の『水族館の殺人』はちょっと落ちると思ったが、この『図書館の殺人』の推理の緻密さはまたデビュー作並みだ。「密室」「アリバイ崩し」と続いた本格ミステリの王道テーマを掲げる趣向も踏襲され、今回のテーマは「ダイイング・メッセージ」。ずっとこの調子でいくつもりだろうか。なかなか大変だろうが、自らハードルを設定するというこのチャレンジ精神はとても美しい。
さて、今回の舞台はもちろん図書館である。図書館員が朝出勤すると大学生が床に倒れて死んでいる。何の理由か分からないが夜の間に侵入したらしい。死体のまわりには本が散らばっている。そして床の上に血文字、本の表紙に丸が描かれている。出ました、ダイイング・メッセージ。
ダイイング・メッセージものはクイーンもいくつか書いているし他にも色々あるが、なかなか難しいところがあって、ダイイング・メッセージの解読がそのまま犯人の指摘につながる例はあまり見たことがない。なぜならば疑問の余地なく犯人を示すメッセージではミステリがなくて面白くないし、解釈に苦しむメッセージの場合は、それが特定の人物を指しているというロジカルな断定が困難になる。だからメッセージそのものの意味よりもそれを残した状況や残し方が手がかりになる場合が多く、そういう意味で私が完璧だと思うのは名作『Xの悲劇』だが、本書もなかなか好印象である。
好印象の理由を詳しく書くとネタバレになるのでもちろん書かないが、本書をすでに読んだ方はもうお分かりの通り、メッセージの意味やそのひねり方ではない。その観点ではむしろ凡庸で、血でのたくった文字や絵の中のキャラクターを示すというありきたりのやり方だ。問題は、これが果たして本当にダイイング・メッセージか犯人の偽装か、という点だが、高校生探偵・裏染天馬が死体の置かれていた状況とその制約から導き出す結論は実に巧妙だ。言われてみれば確かにそうなのだが、これに気づく読者はなかなかいないだろう。なるほどなあ、と思わずうなってしまった。
その他の裏染の推理も、デビュー作同様入り組んでいてしかもきわめて論理的である。刃の欠けたカッターや血を拭った床のあとなど、例によって何の変哲もない手がかりからあれこれと犯人の条件を絞り込んでいく。特に、ちょっとだけ刃の欠けたカッターとその欠けた部分が発見された場所から彼が導き出す、犯人の犯行直後の不思議な行動、それが何を意味するか、そしてそれでどう犯人像が絞り込まれるか、というあたりの展開は非常にスリリングだった。「平成のエラリー・クイーン」の名に恥じない緻密さだ。論理的推理が好きなミステリ・ファンはたまらないだろう。
しかしその一方で、欠点もある。まず、なんといっても真犯人の動機が苦し過ぎる。犯人と被害者との関係を考えればあまりにも非現実的である。それに、この犯罪にはある少女が書いた小説が関係しているのだが、その小説本をこっそり図書館の本棚に置いたことで恐喝だの犯罪だのいう話になるのは、いかにも大げさ過ぎる。この著者は論理的推理の組み立てに関してはクイーン並みに素晴らしいのだが、犯罪の背景となる人間関係や説得力のある人間ドラマを作る点に関しては、まだまだ開発途上のようだ。
さて、本書は三作目の長編ということで、裏染天馬はなぜ学校に住んでいるのか、誰も愛せなくなってしまったという過去の出来事とは何だったのか、というあたりの真相もちょっとずつ開示しつつある。が、まだ全部は分からない。レギュラー高校生たちのキャラも固まり、ギャグのパターンもほぼ確立されて安定感が出てきた。登場人物が時折もらす擬音語、「はぷす!」とか「ふにゃあ!」には結構笑わせていただきました。それに今回は期末試験中という趣向だが、高校生たちが一喜一憂するイベントに殺人事件を絡めたのも悪くなかったと思う。
それにしても、主人公の裏染天馬はアニメオタクという設定であり「ダメ人間」と呼ばれているが、学力は余裕で学年一位だし、ルックスはほぼ完璧なイケメンらしい。年下男が好みの女刑事が彼を見て「百点!」とつぶやく場面がある。もしこれがTVドラマ化されるようなことになったら、裏染役はやっぱりジャニーズがやるんだろうか。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます