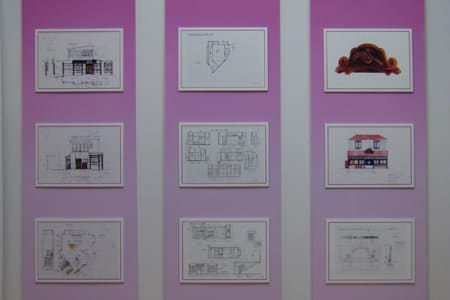モブログでも紹介してたのですが、先週の後半は出張で東京に出かけてきました。
自由時間で少し東京を散策したのですが、以前から行ってみたかったカフェや、散策の途中、気になったカフェを紹介します。
『BERG(ベルク)』です。ここはモブログでも紹介したのですが、JR新宿駅東口改札の近くルミネエストの地下1階にあるカフェです。

お店は、とても小さなお店ですがなんかホッとする空気が漂っています~


当日は、モーニングセットのミール(472)を頂きました。珈琲もしっかりとした味で美味しかったです。

ルミネと立ち退き問題でもめているようですが、頑張って残ってほしいです。
◆『BERG(ベルク)』詳細データ
住 所:東京都新宿区新宿3-38-1ルミネエストB1
営業時間:7時~23時
ベルクで珈琲を飲んだ後、浅草へ移動しました。浅草寺周辺を散策してる途中に見かけた『ローヤル珈琲店 本店』です。創業50年以上の老舗喫茶店のようです。

さて、浅草では『アンヂェラス』に行きました。ここは作家の池波正太郎が通った老舗のお店でもあるようです。

ケーキも気にはなったのですが、モブログでも紹介したように「梅ダッチコーヒー」を頂きました。写真でもわかるように、ダッチコーヒーの中に梅が浮かんでおります。このまま半分ほど、上品な味わいのダッチコーヒーを味わいます。半分味わった後、グラスに入った梅酒をダッチコーヒーのグラスに注ぎこみます。するとあら不思議。。。まろやかな味わいの梅珈琲に変化します。もちろん浮かんでる梅も味わいました(^^)v

◆『アンヂェラス』詳細データ
住 所:東京都台東区浅草1-17-6
営業時間:10時~21時半
定休日 :月曜日(祝日の場合は木曜日)
28日(土)は、上野~根津~谷中と散策しました。散策途中気になったカフェたちです。
お昼御飯は「はん亭 根津本店」で頂いたのですが、食後、根津神社に向かってる途中見かけた『ゆうcafe』です。シチューが美味しいお店のようです。

根津神社近くで見かけた『みのりCafe』です。お店から漂ってくる香りがとてもよかったです。

谷中銀座の『満満堂』です。ここではモブログでも紹介したようにじゃジャコウネココーヒーを頂きました。香り高くてとても美味しい珈琲でした。飲み終わった後も、残り香がとても心地よかったです(^^)v

『カヤバコーヒー店』です。戦前からある老舗喫茶店だそうです。

29日(日)は、終日美術館&博物館を満喫したのですが、夕方に御徒町の『丘』という地下純喫茶に行きました。創業40年の老舗です。看板も時代を感じさせてとてもよいですね~。

店内もいい感じです。小腹もすいてきてたので、おさかなの大好きなナポリタンにも心ひかれたのですが、珈琲を頂きました(^^)v

やっぱ東京は、ちょっと歩いただけでも、気になるカフェがたくさんあり、次回の散策が楽しみになってきますね~。。。でも、次はいつ行けるだろうか(^^;;