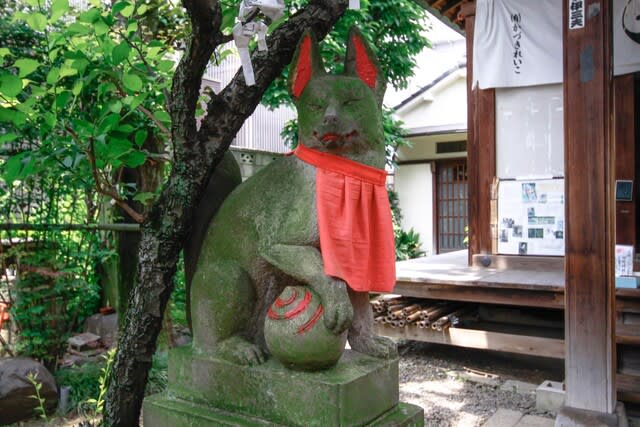神宮外苑にある美術館『聖徳記念絵画館』です。渋谷区に位置する明治神宮の管理下にある美術館ですが、所在地は新宿区になります。建築年は大正15年(1926)です。明治天皇崩御後に建築計画が持ち上がり、大喪の礼が行われた旧青山練兵場の葬場殿跡地に建てられています。設計は公募による建築設計競技(1918)で1等となった大蔵省臨時建築部技手小林正紹の案がもとになっています。佐野利器の指導のもと、明治神宮造営局の高橋貞太郎が設計をまとめ、後任の小林政一が完成させています。外観は花崗岩貼り、中央に径15mのドームを戴く左右対称の構成で、重厚感のある建物となっています。平成23年(2011)に国の重要文化財に指定されています。