かごめの歌。
これも悟りの道しるべの1つと言えるだろう。
まるで意味不明で逆説が交差している禅の公案のような詩でもある
しかしながら、例えば悟りが、自らの解放、解脱であると知るならば、
その歌の言わんとするところが、よくわかるかもしれない。
かーごめ、かごめ、
籠の中の鳥は、
いついつ、出やる
夜明けの晩に、
鶴とかめがすべった、
後ろの正面、だーれ?
スピリチュアル系等で、この不可思議な詩(うた)がよく話題になる時があるが、
日本で昔から何気なく歌われている、
いかようにも解釈できる、実に不可思議な詩(うた)。
いつ習ったのか、いつ覚えたのか、絵本だったか、音楽の時間だったか、
ラジオだったか、テレビだったか・・よく覚えていないかもしれない。
何気ない、意味不明な、憶えやすい日本の童謡として、
だからこそ今まで生き延びてきたのだろう。
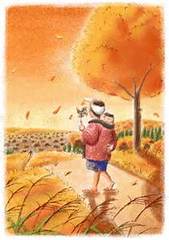
・・・
かごめ・かごめ・・
籠目(かごめ)というのは、六芒星であって、△が上下合わさっている姿をしている。
また籠(かご)は編まれている、閉じられた空間、つまり3次元マトリクスのことだ。
かごの中の鳥は・・・
籠(かご)つまり3次元マトリクス世界、この世界の、
その中にいる、羽ばたけない鳥・・・、
勇躍と大空を飛び交うべき、本来自由なはずの鳥、
飛ぶのを怖がっている・・鳥。
すなわち、それぞれの「わたし」のこと。
つまりあなたのことでもある。
いついつ出やる・・・
飛べない鳥、本来あり得ない姿に身をやつしている、
不自由極まりない状態から、いつ出るのだろうか。
出される・・のではなく、自らで、いつ出るのだろうか。
夜明けの晩に、・・・
夜明けは、太陽が昇り始める薄明りの時であり、
晩は、逆に太陽が沈む薄暗い時。
それが同時に起きるような時。
光と闇の交差する時といえようか。
それが明確にわかる時期、
苦しくも、同時に輝かしい光の射し込む時だ。
鶴と亀がすべった、
つるとカメ、万年と千年で象徴される「時間」
地球がくるくる、滑るように回る悠久の時を経たのち。
あるようで無い、長い時間での経験と記憶の蓄積と昇華の後。
長い繰り返し転生と輪廻の後。
後ろの正面、だーれ?
わたしの後ろ・・の正面とは、
わたしの背後にあって、そこから正面を観ている、
それは誰だろうか・・と言っている。
わたしの背後にあって、わたしが観ている正面を、
一緒に見ているものは誰だ?と言っている。
外の世界や、私という現象を、観ているのは誰か?と言っているようだ。
わたしの後ろで、私と一緒に観ているものは、誰だと思う?
籠の中にいる、閉じられた世界の中にいるのは私という個人、
不自由な肉体と束縛された社会環境の中にいる肉体個人、
宇宙・存在全体から、いつか分離した小さな小さな自己、
そのわたしを、
後ろから観ているのは、誰だろう?
わたしを観ている、わたしを通して正面を観ているのは誰だろう?
物理的な後ろの空間の他の誰か、他の人、他の存在ではなく、
また、高次元の存在、背後霊とか、宇宙人とか何かというのも正直言って的外れ、
それらはまったく他人事にしてしまう、面白おどろしい「概念」の遊びでしかない。
私自身を観ているのは、そう、
わたし・・以外にいない。
自分自身を観ている、観察している者は、
誰あろう・・わたし以外にない。
それぞれの世界の根源は<わたし>である。
世界には人間がそれこそ、大勢いるわけだが、
わたしの見渡す世界のなかで、
『わたしは・・わたし・・である』と気付いて、意識している存在は、
自分に気付いている・・・当の者は・・・、
全宇宙、存在諸世界の中で・・・わたし・・しかいない。
カゴメの歌は、肉体個人という分離した私へと次元降下し、
個人我の殻に自己幽閉して、それに全く気付いていなかった、
本質の<わたし>への、その解放の時を示す詩(うた)であるといえようか。
かーごめ、かごめ、
籠の中の鳥は、
いついつ、出やる
夜明けの晩に、
鶴とかめがすべった、
後ろの正面、だーれ?

本日も拙い記事をご覧いただきまして、誠に有難うございました。
これも悟りの道しるべの1つと言えるだろう。
まるで意味不明で逆説が交差している禅の公案のような詩でもある
しかしながら、例えば悟りが、自らの解放、解脱であると知るならば、
その歌の言わんとするところが、よくわかるかもしれない。
かーごめ、かごめ、
籠の中の鳥は、
いついつ、出やる
夜明けの晩に、
鶴とかめがすべった、
後ろの正面、だーれ?
スピリチュアル系等で、この不可思議な詩(うた)がよく話題になる時があるが、
日本で昔から何気なく歌われている、
いかようにも解釈できる、実に不可思議な詩(うた)。
いつ習ったのか、いつ覚えたのか、絵本だったか、音楽の時間だったか、
ラジオだったか、テレビだったか・・よく覚えていないかもしれない。
何気ない、意味不明な、憶えやすい日本の童謡として、
だからこそ今まで生き延びてきたのだろう。
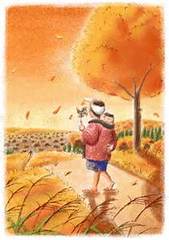
・・・
かごめ・かごめ・・
籠目(かごめ)というのは、六芒星であって、△が上下合わさっている姿をしている。
また籠(かご)は編まれている、閉じられた空間、つまり3次元マトリクスのことだ。
かごの中の鳥は・・・
籠(かご)つまり3次元マトリクス世界、この世界の、
その中にいる、羽ばたけない鳥・・・、
勇躍と大空を飛び交うべき、本来自由なはずの鳥、
飛ぶのを怖がっている・・鳥。
すなわち、それぞれの「わたし」のこと。
つまりあなたのことでもある。
いついつ出やる・・・
飛べない鳥、本来あり得ない姿に身をやつしている、
不自由極まりない状態から、いつ出るのだろうか。
出される・・のではなく、自らで、いつ出るのだろうか。
夜明けの晩に、・・・
夜明けは、太陽が昇り始める薄明りの時であり、
晩は、逆に太陽が沈む薄暗い時。
それが同時に起きるような時。
光と闇の交差する時といえようか。
それが明確にわかる時期、
苦しくも、同時に輝かしい光の射し込む時だ。
鶴と亀がすべった、
つるとカメ、万年と千年で象徴される「時間」
地球がくるくる、滑るように回る悠久の時を経たのち。
あるようで無い、長い時間での経験と記憶の蓄積と昇華の後。
長い繰り返し転生と輪廻の後。
後ろの正面、だーれ?
わたしの後ろ・・の正面とは、
わたしの背後にあって、そこから正面を観ている、
それは誰だろうか・・と言っている。
わたしの背後にあって、わたしが観ている正面を、
一緒に見ているものは誰だ?と言っている。
外の世界や、私という現象を、観ているのは誰か?と言っているようだ。
わたしの後ろで、私と一緒に観ているものは、誰だと思う?
籠の中にいる、閉じられた世界の中にいるのは私という個人、
不自由な肉体と束縛された社会環境の中にいる肉体個人、
宇宙・存在全体から、いつか分離した小さな小さな自己、
そのわたしを、
後ろから観ているのは、誰だろう?
わたしを観ている、わたしを通して正面を観ているのは誰だろう?
物理的な後ろの空間の他の誰か、他の人、他の存在ではなく、
また、高次元の存在、背後霊とか、宇宙人とか何かというのも正直言って的外れ、
それらはまったく他人事にしてしまう、面白おどろしい「概念」の遊びでしかない。
私自身を観ているのは、そう、
わたし・・以外にいない。
自分自身を観ている、観察している者は、
誰あろう・・わたし以外にない。
それぞれの世界の根源は<わたし>である。
世界には人間がそれこそ、大勢いるわけだが、
わたしの見渡す世界のなかで、
『わたしは・・わたし・・である』と気付いて、意識している存在は、
自分に気付いている・・・当の者は・・・、
全宇宙、存在諸世界の中で・・・わたし・・しかいない。
カゴメの歌は、肉体個人という分離した私へと次元降下し、
個人我の殻に自己幽閉して、それに全く気付いていなかった、
本質の<わたし>への、その解放の時を示す詩(うた)であるといえようか。
かーごめ、かごめ、
籠の中の鳥は、
いついつ、出やる
夜明けの晩に、
鶴とかめがすべった、
後ろの正面、だーれ?

本日も拙い記事をご覧いただきまして、誠に有難うございました。









