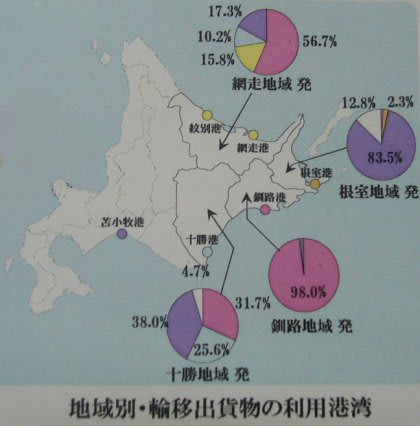根室での仕事の帰り際に、根室の人たちのソウルフード(魂の食べ物)と言われる喫茶店「どりあん」の「エスカロップ」を食べてきました。
このエスカロップという料理は、タケノコ入りバターライスの上に、薄いとんかつを乗せ甘めのデミグラスソースをかけた独特な料理。ここどりあんはこの料理を発案した老舗の喫茶店として知られていて、エスカロップと言えばどりあんと言われているのだとか。

【これがエスカロップだ!】
根室市民にはあまりに一般的なのですが、根室以外ではほとんど知られておらず、根室の人たちは外へ旅行などに行って初めてエスカロップが根室限定料理であることを知った、というエピソードもあるのだそうです。
ここどりあんのエスカロップは、まさに他にはない独特な味わいですが、美味しくいただきました。こういう地域限定グルメは食べにゆきたくなりますね。今度根室へ行くときは必ずもう一度食べることにします。
※ ※ ※ ※ ※
さて、根室のソウルフードはエスカロップだとして、「では釧路のソウルフードはなんですか?」と何人かに訊いてみたところ、異論もあるでしょうけれど、泉屋さんのスパゲティという答えが多くありました。
泉屋さんのスパゲティは私も一度だけ食べたことがあるので「私も食べました。ナポリタンが美味しかったですね」と言うと、「泉屋でナポリタンですか?ははは、それはソウルフードではありませんよ。泉屋と言えば、①泉屋風という塩スパゲティ、②ピカタ、③スパカツの三つですよ、この三つ!」と言われてしまいました。
特にスパカツは、大盛り、大、大大、大大大と強烈な盛りのオプションがあるそうで、「高校生の時は大大を早食いしたもんだなあ」と地元の人たちで大いに盛り上がっていました。
こういう会話には参加できませんね。おまけに食べたものも違ってちょっとションボリ。あと三回は泉屋さんに行かなくちゃ。
このエスカロップという料理は、タケノコ入りバターライスの上に、薄いとんかつを乗せ甘めのデミグラスソースをかけた独特な料理。ここどりあんはこの料理を発案した老舗の喫茶店として知られていて、エスカロップと言えばどりあんと言われているのだとか。

【これがエスカロップだ!】
根室市民にはあまりに一般的なのですが、根室以外ではほとんど知られておらず、根室の人たちは外へ旅行などに行って初めてエスカロップが根室限定料理であることを知った、というエピソードもあるのだそうです。
ここどりあんのエスカロップは、まさに他にはない独特な味わいですが、美味しくいただきました。こういう地域限定グルメは食べにゆきたくなりますね。今度根室へ行くときは必ずもう一度食べることにします。
※ ※ ※ ※ ※
さて、根室のソウルフードはエスカロップだとして、「では釧路のソウルフードはなんですか?」と何人かに訊いてみたところ、異論もあるでしょうけれど、泉屋さんのスパゲティという答えが多くありました。
泉屋さんのスパゲティは私も一度だけ食べたことがあるので「私も食べました。ナポリタンが美味しかったですね」と言うと、「泉屋でナポリタンですか?ははは、それはソウルフードではありませんよ。泉屋と言えば、①泉屋風という塩スパゲティ、②ピカタ、③スパカツの三つですよ、この三つ!」と言われてしまいました。
特にスパカツは、大盛り、大、大大、大大大と強烈な盛りのオプションがあるそうで、「高校生の時は大大を早食いしたもんだなあ」と地元の人たちで大いに盛り上がっていました。
こういう会話には参加できませんね。おまけに食べたものも違ってちょっとションボリ。あと三回は泉屋さんに行かなくちゃ。