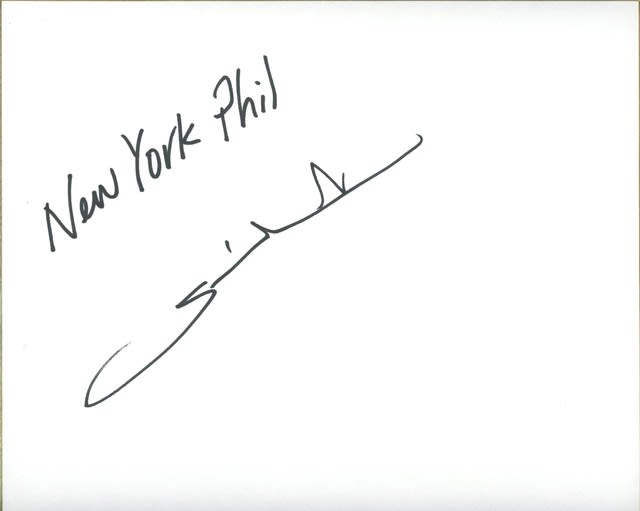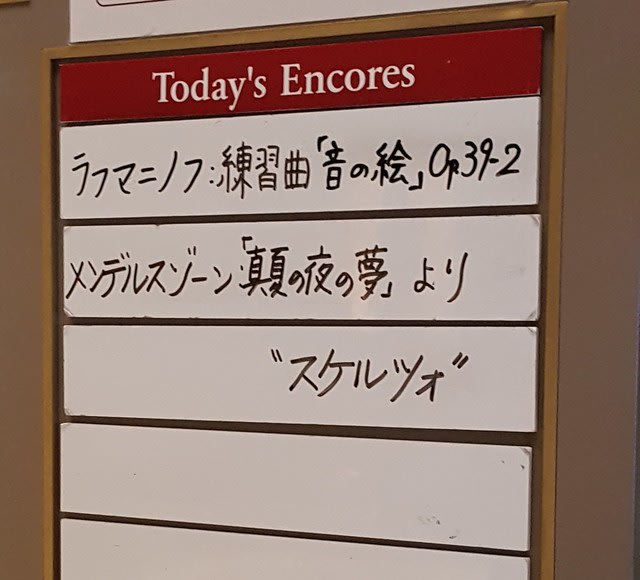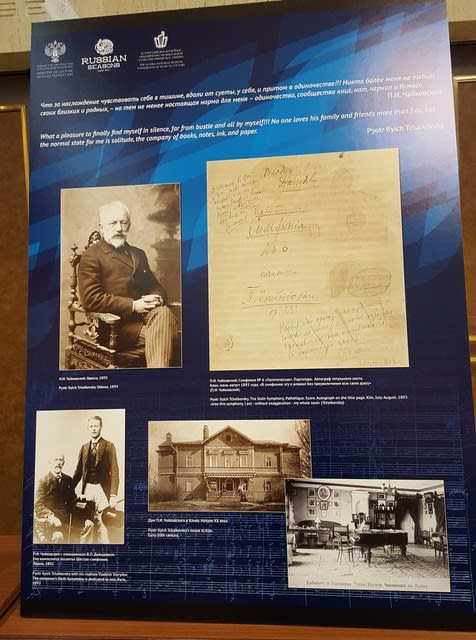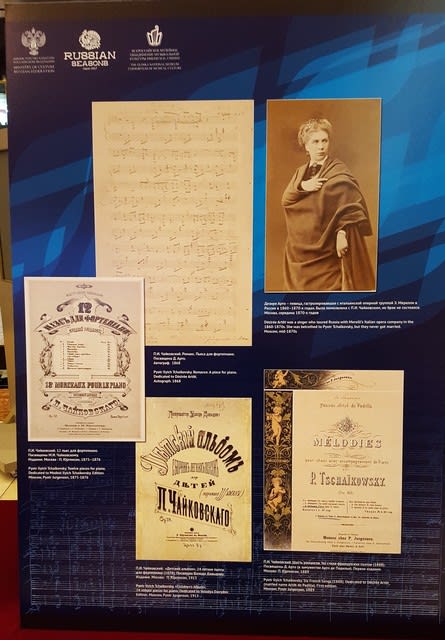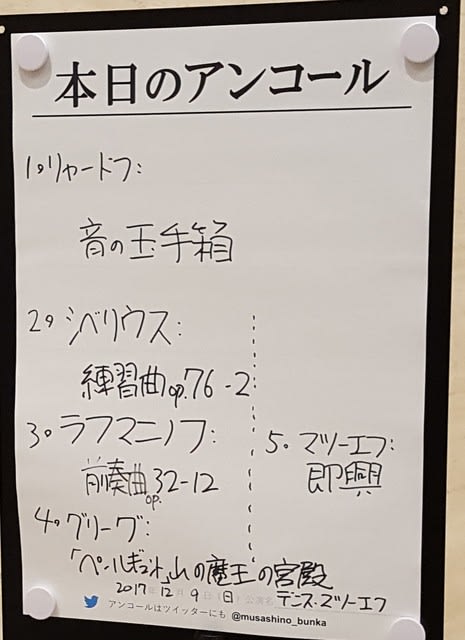2474- ベスト・ワースト2017
今年2017年は213回通いました。一覧は下記リンク。
2016-2017シーズン(一覧その1)
2016-2017シーズン(一覧その2)
2017-2018シーズン(一覧その1途中)
今年もいい演奏会がたくさんありました。オペラは昨年2016年とだぶっている公演はスキップ、それに来日団体も昨年ほどは無くて、いまひとつでした。ほかは色々と聴くことが出来て、総じて手応えのあるものでした。
昨年2016年のベストワーストはこちら。
2252- ベスト・ワースト2016
●
今年2017年は素晴らしい企画がありましたのでそれを神棚にしました。
【神棚企画】
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲、5/2、5/3、5/4、5/5、ガル祭2017
【オペラ・オケ伴付き歌 ベスト12】
1.蝶々夫人、笈田プロダクション、バルケ、読響、2/18
2.神々の黄昏、飯守、読響、10/4、10/11、10/17
3.ラインの黄金、ハンペ、沼尻、京響、3/4、3/5
4.神々の黄昏、ヤノフスキ、N響、4/1、4/4
5.角笛、ゲルネ、ワルキューレ1幕、ペトレンコ、バイエルン、10/1
6.ラ・ボエーム、園田、新日フィル、6/24
7.タンホイザー、ペトレンコ、バイエルン、9/25
8.ジークフリート、飯守、東響、6/1、6/4、6/7
9.ダムラウ、テステ、オペラ・アリア・コンサート、11/10
10.ノルマ、デヴィーア、沼尻、TMP、10/22
11.ヘンデル、ベルシャザル、三澤寿喜、キャノンズ、1/9
12.ラインの黄金、インキネン、日フィル、5/26、5/27
【管弦楽ベスト21】
1.ハイドン受難、亡き子、小野美咲、シュベ5、未完成、プレトニョフ、東フィル、10/18
2.ペトルーシュカ、ラフマニノフ3番、ラトル、ベルリン・フィル、11/25
3.浄夜、ハルサイ、ノット、東響、7/22
4.ツァラ、死と浄化、ティル、シャイー、ルツェルン、10/8
5.コープランド3番、スラットキン、デトロイト響、7/17
6.ブルックナー3番、上岡、新日フィル、5/11
7.復活、チョン・ミュンフン、東フィル、7/21、9/15
8.ブルックナー5番シャルク版、ロジェストヴェンスキー、読響、5/19
9.ショスタコーヴィッチ11番、井上道義、大阪フィル、2/22
10.ブルックナー5番、ノット、東響、5/20
11.ショスタコーヴィッチ11番、ネルソンス、ボストン響、11/7
12.コリリアーノ、サーカス・マキシマス、クワハラ、佼成、1/28
13.ブラレク、ブロムシュテット、ゲヴァハウ、ウィーン楽友協会、11/13
14.クレルヴォ、リントゥ、都響、11/8
15.マーラー6番、ヤルヴィP、N響、2/23
16.青ひげ、カンブルラン、読響、4/15
17.大地の歌、インバル、都響、7/16
18.ブルックナー9番、佐渡裕、東フィル、1/27
19.運命、ブラ1、ジョルダン、ウィーン響、12/3
20.第九、ゲッツェル、読響、12/20
21.エロイカ、ドゥネーヴ、ブリュッセル、6/11
【協奏曲ベスト10】
1.ラフマニノフ、PC3、PC4、マツーエフ、ゲルギエフ、マリインスキー、12/10
2.モーツァルト、hr協4曲、シュテファン・ドール、7/11
3.ラフマニノフ、PC3、反田恭平、秋山和慶、東響、8/11
4.ハチャトゥリアン、ピアノ協奏曲、ベレゾフスキー、リス、ウラル、5/6
5.リスト、PC1、田中正也、三ツ橋敬子、東フィル、2/10
6.シベリウスVn協、サラ・チャン、アッシャー・フィッシュ、新日フィル3/25
7.ベトコン3、ソンジン、サロネン、フィルハーモニア管、5/15
8.タコpfコン1、上原、シモノフ、モスクワ・フィル、7/3
9.ベトコン3、紗良、ウルバンスキ、エルプ・フィル、3/12
10.モーツァルト、PC12、PC9、小菅優、東響、8/26
【リサイタル・室内楽ベスト17】
1.ベトソナ32、竹田理琴乃、5/4
2.ベトソナ29、バリー・ダグラス、5/5
3.イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル、10/20
4.ベトソナ32、創作32、ディアベッリ、コンスタンチン・リフシッツ、10/6
5.バッハ、ブリテン、無伴奏チェロ組曲全曲、上森祥平、9/2
6.アンドラーシュ・シフ、ピアノ・リサイタル、3/23
7.シューベルトD959、D960、今峰由香、12/22
8.ベトソナ27,30,31,32、イリーナ・メジューエワ、8/26
9.カティア・ブリアティシヴィリ、ピアノ・リサイタル、11/6
10.ベトソナ11,23,30,31、変2曲、浜野与志男、菊地裕介、田部京子、6/18
11.ディートリヒ・ヘンシェル、岡原慎也、2017.2.19
12.小菅優 ピアノ・リサイタル、Water、11/30
13.ベトソナ17,31、チャイコフスキー、ドゥムカ、大ソナタ、マツーエフ、12/9
14.室内楽、上野優子、西江辰郎、工藤すみれ、12/19
15.大公、アキコ・マイヤーズ、レイコ・クーパー、バリー・ダグラス、5/5
16.ブラームスの室内楽、川本嘉子、竹澤恭子、マルディロシアン、4/14
17.バッハ、マルティヌー、ラフマニノフ、山崎伸子、小菅優、5/25
【いわゆる現代もの系・発掘系ベスト13】
1.メシアン、幼子イエスに注ぐ20のまなざし、スティーヴン・オズボーン、5/18
2.メシアン、アッシジの聖フランチェスコ、カンブルラン、読響、11/19、11/26
3.メシアン、彼方の閃光、カンブルラン、読響、1/31
4.アダムズ、シェヘラザード.2、ジョセフォウィッツ、ギルバート、都響、4/17、4/18
5.大澤壽人、cb協、佐野、神風、福間、交響曲第1番、ヤマカズ、日フィル、9/3
6.オール・タケミツ・プログラム、井上道義、新日フィル、1/26
7.尾高尚忠、山田一雄、伊福部昭、諸井三郎、下野竜也、東フィル、9/10
8.芥川、トリプティーク、團、飛天繚乱、黛、饗宴、千住、滝の白糸、大友、東響、8/20
9.ツェルハ、ハース、ボールチ、イラン・ヴォルコフ、東響、9/7
10.メシアン、幼子イエスにそそぐ20のまなざし、エマール、12/6
11.黛敏郎メモリアル VOL.1、オーケストラ・トリプティーク、4/5
12.一柳慧、湯浅譲二、杉山洋一、都響、10/30
13.From me武満、広上淳一、京響、9/18
【ワースト4】
1.ベンジャミン・ブリテンの世界、3/26 トーク多過ぎで、
2.ノルマ、藤原歌劇、7/2 歌が、
3.ハイドン、ゲリエ、ベト7、鈴木秀美、読響、7/12 ソリストとオケが、
4.ブルッフVC、ロザコヴィッチ、グレイト、ゲルギエフ、PMF、7/31 来年頑張って
以上