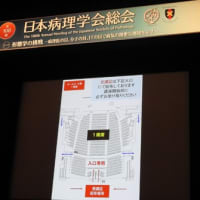プロレタリア文学者の佐多稲子の作品集に入りました。元々小説家を志した人ではなくて、貧困の中で自身が児童労働や低賃金労働を経験し、カフェの女給として働く中で社会運動家や文筆家と知己を得て文章を書き始めたのが発端だそうです。プロレタリア文学も当初は知識階級の運動だったのが、彼女のような本当の無産者が表現活動を始めることで厚みが出てきます。自身の体験である「キャラメル工場から」はなかなかユニークです。ただ、体験したのが十代前半だし、期間も短いので労働者全体の苦しみとか時代背景とか、記載に奥行きが欠けるのは仕方がありません。
「牡丹のある家」は結核で工場を辞め、田舎に帰った娘が自分の居場所がないのを感じ、悲壮な決意で町に戻る話。都会も田舎も豊かな人は一握りで、多くの労働者は十分な教育も受けられず、病気の療養もできずに働かざるを得ませんでした。自分が結核に感染したり、家族に病人が出たりすれば尚更です。こんな時代には軍人になって手柄を挙げてやろう、と考える若者が多くいても不思議ではありません。
長編の「くれない」は文学者同士の夫婦の軋轢を書いた物ですが、何が起きても労働運動の目線で「生活改善を」「労働者と連帯を」とタテマエ論で思考する夫婦がうまくいくはずがないですね。夫婦の間柄で、どっちが負ける、勝つとか競い合ってるのはともかく、負けたのを相手のせいにしているようでは安らぎなどないと思います。マルクス主義文学者の佐々木基一の解説ではこれを「名作」と評してあるのですが、ちょっと一般の読書家には理解しにくいんじゃないでしょうか。反体制文学の担い手としての苦労は伝わるとしても、家庭内のいざこざは自ら蒔いた種みたいな印象を抱かざるを得ず、佐多稲子という人はそもそも家庭生活に向かない人だったんじゃないかと思うばかり。家事は得意だったようですが、自分の家庭より政治活動を重視する人の家庭が荒れるのは仕方がないでしょう。
「くれない」では文章が整理されてなくて、小説としてもやや読み辛いです。例えば、「生活の綾の陰影と、人の組み合わせのお互いに作用する影響は大きいのである。負ける、勝つ、という言葉でお互いの生活の根本を主張し合いながら、仕事に熱している男を元気づける程の拡がった余裕もないくせに、甘くない目で水を打っかけることは鋭く、そして性格の強さでじりじりに押しっこをしている。」漱石あたりなら同じ内容をさらっと書くだろうと考えると、これはどう見ても悪文だよね。こんな文章が何回も繰り返し出てきます。もう少し後の作品では小説らしくなるのかな?
佐多さんは小説家としてのキャリアが非常に長い人で、この全集が出てからも多数の作品があるので、そちらの方が完成度は高いかもしれません。1930年頃のプロレタリア文学活動で名を馳せた人ではありますが、その枠組みだけで捉えることはできないと思います。今年のセンター試験国語では第2問に「三等車」の全文が使われています。こちらでは「くれない」のかな釘流のような引っ掛かる文体ではなく、もっとこなれています。佐多稲子を読んだことのある受験生は少ないでしょうが、これに関しては文章も問題も平易なので、平均点は高かったことと思います。