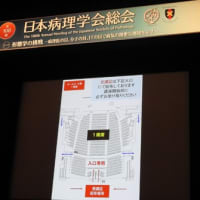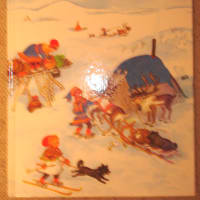軍艦建造の中心であった呉ですが、当初は欧米の模倣から始まっています。日本海海戦で旗艦を務めた三笠は1900年にイギリスのヴィッカースで建造。装甲にはドイツのクルップ鋼を採用。主砲は30cm砲でしたが、ここに展示されているのはフランスのホチキス製速射砲つまり「保式速射砲」で口径57mm。ステープラーの代名詞であるホッチキスと同じ名字ですが、開発したのは別人だそうです。

1912年に完成した戦艦金剛の建造もイギリス。これは金剛のボイラーで、石炭と重油を混ぜて使うヤーロー型と言われるものです。当時の蒸気機関車と同じく、人力作業で石炭を投入していたんですね。これだけでは出力が足りないため、同型のボイラーが36基。

金剛は高速戦艦と言われるほどの速力を誇りました。このような輸入軍艦をお手本に、国産軍艦の建造が始まります。

一足飛びに欧米並みの海軍力を自力整備しようという試みは現場に大きな負担を強いることになります。早くも1906年(明治39年)に竣工した第六潜水艇は、岩国沖で訓練中に浸水事故を起こして浮力を失い、14人の乗組員と共に海底で眠りにつきました。第六潜水艇という名称ですが、第一から第五は輸入の潜水艇なので、国産潜水艇の第一号です。アメリカ製の潜水艇を参考に建造したものですが、忠実な再現は難しかったらしく、より小型で安定性のない潜水艇だったようです。

殉職した乗組員が最後まで持ち場を守り、佐久間艇長が冷静に遺書を残したことから、「沈勇」として称賛されますが、潜水艇自体の完成度が不十分であったのに加えて、佐久間艇長の背伸びした運行が重なった上での事故らしく、現代であれば手放しで褒め称えられたものではないでしょう。今では事故の客観的な分析もなされています。

これは空母「赤城」かな。元々戦艦の予定だったのを改造し、独特の三段式飛行甲板を設置した特殊な空母で、1925年の建造当時は離着陸距離の短い複葉機が同時に離発着できる利点が認められていたものの、その後艦載機が高速化して長い飛行甲板が要求されたため、途中で1枚甲板に直されたものです。当初の設計を引きずったのか、甲板の位置が妙に高い高床式みたいな形が特徴的。加えて、左舷に艦橋のある空母は赤城と飛竜だけです。飛竜は横須賀建造なので、呉に縁のあるのは赤城のみ。

「ア」は赤城のアなのかな。着陸する艦載機が母艦を間違えないようにする標識だと思います。

呉海軍工廠から独立した広海軍工廠が海軍航空廠に。戦争への道をひた走ります。

伊号潜水艦の各型も呉海軍工廠の建造によります。

伊号第400潜水艦は世界初の潜水母艦でした。

サイパン、硫黄島と進行してきた米軍は、海軍の拠点であった呉に徹底した攻撃を加えます。14回もの空襲で海軍工廠は機能を失い、市民の生活も破壊されました。

海軍と呉の落日。広島の原爆は呉からもはっきり見えたそうです。