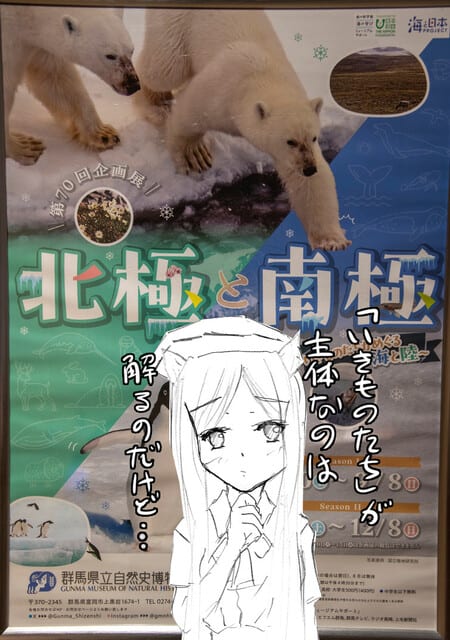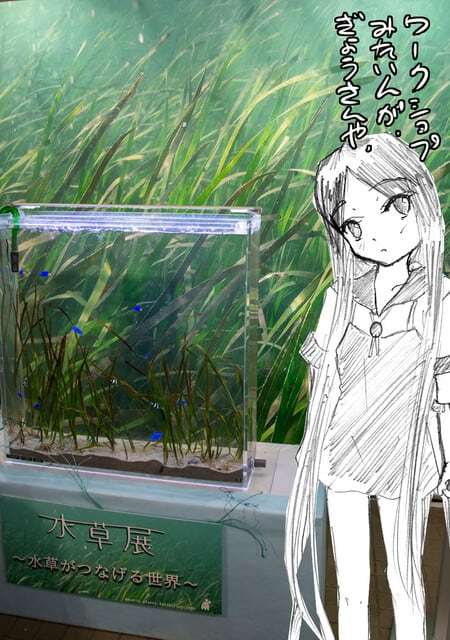私が所属している「久喜天文自然クラブ」で、前回に引き続き、今月の定例会も「遠足」になりまして、「入間市博物館」へ行ってきました。
この「入間市博物館」に決まったのは、まず「電子基準点」がある事が一つだったりします。
コレは前回「地図と測量の科学館」にて「電子基準点」をこの「地図と測量の科学館」以外で見たことが無い。と私が言ったのが発端で、「久喜から近い場所でどこにあるか?」で探したトコロ、この「入間市博物館」にあり、容易に見る事ができるとの事と、展示物が面白そうというので今回行く事になったのですよ。
さて、この「入間市博物館」ですが、「入間市」特に「狭山丘陵」を中心とした展示と市内で「狭山茶」が名産であるから「お茶」に関しての展示があるのです。「お茶」に関する展示があるという事も今回行く事になった大きなファクターであったりもします。
規模としては「市営」ですからそんなに大きい事もなく、ほとんどは学校の課外授業で見学するのが多いような感じですね。
入館料は大人200円で、「JAF」の会員証を提示する事により2割引となります。
館内の構成は「特別展示室」が1Fにあり、常設展示は2階からになり展示室内でスロープで下っていく感じになり出口は1階になりますね。
ただ、この「特別展示室」ですが、今回は博物館の展示ではなく「入間市工芸展」で入間市民からの陶器やらの展示がされていましたね。どうやら、博物館自体の特別展としてはあまり開催されていないようで、ほとんどは「市民団体等」の作品展示会が多いみたいです。
まずは2階へ上がり「こども科学館」へここでは「鏡」を使ったトリック的な展示や「ジャイロ」を使った体験型の展示が10種類ほどあり、我々はそれを原理を解説しながら実際に遊んでいましたよ。そして、ある程度遊んだところで、「こども科学館」から出て「常設展示」の「入間の自然」へ向かう時にまた「受付」を通るのですが、その時に大の大人5名がこども科学館で30分近く遊んでいたからでしょうか、「楽しまれていたようですね。ところで皆様たちは?」と話しかけられ、「天文自然クラブ」で来た事と、「「展示解説」を電話で申し込んだのですが、平日は受け付けてないと言われた」と話すと、どうやら今日(9月20日)は小学校が2校来るのでそれでできないことが説明されたのですが、その小学校が来るまでの間なら展示解説できますよ。との事で、「展示解説」をしてもらう事に。
そうなんですよ、ここ「入間市博物館」では土曜日・日曜日・祝日の11時と13時30分に展示解説員による展示解説を行っているそうで、それ以外でも「電話予約」により個人や団体でも展示解説をしてくれるのです。
小学校が来るまでの約30分程度ですが、常設展の展示解説をしてもらいましたよ。展示解説は今回の場合場所により、「入間の自然」「入間の歴史」「茶の世界」で解説される方が変わっていき、空き時間でしていただいたので早口かつ駆け足での解説になりましたが、通常では近くで見れない「茶室」を近くで見せていただけましたし、何よりも見どころやパネルにない説明があったり、こちらの疑問について答えていただいたり、どのように見るのかを教わる事ができましたよ。
で展示解説が終わり、一旦出口から出たのですが、再入場が当時限りで何度も可能なので、2周目開始です。
2周目は先ほどの展示解説で教えてもらった事を踏まえつつメンバーで意見を交わしながら見て行きます。
入間市ではありつつ「狭山」という地名が付く土地があったり「狭山茶」の産地でもあったりする入間市、その成り立ちと、お茶の育成に適した地形。関東ローム層と古玉川の礫地であるために水はけがよく、川に囲まれつつも、平坦な土地も多くある地形を利用し「古代」では丘陵を利用した登り窯で陶器の生産をしたりと、ある程度発展はしていたようですね。近代では鉱山と都市部の中間地点として、軽工業が発展し、お茶の生産により独自の発展をしていった都市である事が解ります。そして、「昭和の入間」のコーナーでは昭和の生活様式が展示されており、懐かしさも感じつつも生活様式の移り変わりを実感できますね。
この時点で13時半となってしまったので、博物館の同一敷地内あるレストラン「茶処 一煎」へ。レストランと言いつつも「そば」や「うどん」が中心となっており、「そば」は「茶そば」を使用していますよ。
ここで午前に見た事の意見交換を1時間ほどしたりして再度、3周目の展示を、「茶の世界」を見る事に。
「お茶」といっても「緑茶」が中心となりますが、それでも「お茶」が「中国」の「昆明」付近から「茶の木」の葉による「お茶」が登場し、そこから世界へ「無発酵茶」である「緑茶系」、「半発酵茶」である「烏龍茶系」そして「発酵茶」である「紅茶」への発展とその時代背景茶器を見る事ができ、「緑茶」の文化は当然ながら「中国」から伝わってきたのですが、「3回」伝わってきているんですね。
一番初めは「煎じる」「煮出し」でその後「抹茶」つまり「臼引き」のお茶が伝わり、最後今の「蒸す」、「急須」で入れるお茶が伝わってきたのです。
そして、中国では「新しい淹れ方」が出ると、以前の淹れ方は廃れてしまうそうで、現在の「蒸す」淹れ方以前の「臼引き」での「お茶」は現在中国では無いようですよ。
しかし、日本では「抹茶」は「茶道」として現在でも残っておりますし、当然一般的には「急須」で入れるお茶を飲んでいますからね。
ちなみに各展示室には「解説員」さんがいますので、気軽に質問等をする事ができます。
ただ、私たちの場合は、長時間同じ展示を見ながらあーだのこーだの言っていましたから、「解説員」さんの方から話しかける事が多かったですね。
そして、そこでまた一般的よりも学術的に踏み込んだ質問や、その事に関して詳しい意見やら言ったりするのでなんだかすごい事になっていましたよ。話の最後には必ず「皆さんどのような集まりなのですか?」と。
そんなこんなで「入間市博物館」にほぼ閉館時間ちかくの15時45分までいましたよ。
多くの方は1時間ほどで出てしまうところを開館から閉館近くまでおり、常設展示を3周もしただけあり、狭山とお茶を十分に堪能できましたよ。
それでは、本日の登場人物は「天文自然クラブ」な話でしたので、この方。「非公認」の「久喜天体自然クラブ」のパッチに登場しているキャラクターである「天体」が好きで「宇宙」に憧れる「桜宮 ツアイシア」さん、通称「シア」さんです。今回も前回に引き続きの「遠足」で「入間市博物館」へやってきた「天文自然クラブ」の面々でして…。ちなみに背景が入間市博物館の「入間の歴史」展示室なのです。