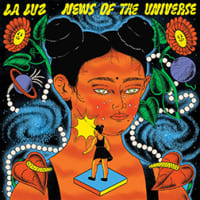Nico Icon@VHSビデオ、スザンネ・オフテリンガー監督(1995年ドイツ)
「私たちはパスポートなんて持つべきじゃない。『死を思え(メメント・モリ)』の反対で、バカげてるわ。誰それがどこで生まれたかなんて、いったい誰が気にするっていうの?」
アンディ・ウォーホルの『チェルシー・ガール』をはじめとする映画に出演し、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの伝説的1stアルバムで歌うなど、ウォーホルの“ファクトリー”の花形的存在だったニコ。
1938年10月16日にドイツのケルンでクリスタ・パフゲンとして生まれた彼女は、ニューヨークでウォーホルと会うまでに、既にヨーロッパで十分刺激的な人生を送っていた。
─パリコレのキャトウォークを歩き、VOGUE、ELLEの表紙を飾るファッション・モデルとして─フェリーニの『甘い生活』にも端役で顔を出し─『太陽がいっぱい』のロケで出会ったアラン・ドロンの子どもを産んだ母として─ロンドンで「I'm Not Sayin'」なるシングル盤を吹き込んだ歌手として─そして、そのシングル盤のB面で伴奏したブライアン・ジョーンズ(ローリング・ストーンズ)のガール・フレンドとして─。
ボブ・ディランとの出会いにより音楽の世界に引き込まれ、ルー・リードと、ジョン・ケイルと、ジャクソン・ブラウンと、そしてドアーズのジム・モリソンと出会うニコ。「彼は私が恋した初めての男だった。だって彼は私の容姿と心に愛情を示してくれたから。だけど私たちは愛の成就のため、あまりに酒を飲みすぎ、あまりにドラッグをやりすぎた。それが私たちの難点だった」。
やがて自分でも曲を作り始めた彼女は、ジョン・ケイルのプロデュースのもと『Marble Index』『Desertshore』『The End』という一連の傑作アルバムをリリース。ヨーロッパに渡って映画監督フィリップ・ガレルと出会ったのも同じころで、2人は『内なる傷痕』や『孤高』といった映画を制作するとともに、虚無的な生き方もつのらせ、ヘロインに溺れてゆく。
ニコは彼女をヘロイン中毒から助けようとしたマネージャーの尽力によりコンサート活動を再開し、東京にも2度訪れている。だが1988年7月、スペインのイビサ島で自転車に乗って転倒、脳出血のため49歳で世を去った。ハシシを買いに行く途上だったとされる。
このドキュメンタリー作品は、世界が最も強烈な激動を味わった1960年代から80年代にかけて、自分が自分であることを探し続けた真のボヘミアンであるニコを、関係者の証言や生前の映像を元に描いたものである。ニコと同じケルン出身のオフテリンガー監督はこう語る。「ニコは、単に人から美しいと思われるだけの存在から、独自のやり方で自分自身を表現できる人間になるまで、多大なステップアップを踏んでいった人だと思う。そしてそれこそが、私が彼女に興味を持ってやまない理由でした。人がいかに自分自身を鍛え、今ある姿からほんとうに自分がなりたい自分に変われるか、ということに」。

あ~~酒が飲みたい─酒が。
本来きのう、この映画の記事をやるはずだったのだが、同じことなんだよ。オラは日曜月曜と2日連続の休肝日を設けているので。
2日間飲めないのは長く感じる。土曜の25時から火曜の17時まで飲まないとすると、48時間ではなく、64時間も飲まずにいなければならない。が、老いても1日でも長くおいしく飲み食いするため、我慢するのだ。

《ぬか漬けのきゅうりは生のきゅうりに戻れない》─吾妻ひでおさんは、あれから一滴も飲んでおらず、健康を取り戻したようなのだが、きゅうりはぬか漬けにしなくても、やがてしなびる。
誰もが老い、いずれは死ぬ。子どものころなんてさあ、朝から元気いっぱいで、酒も薬物も必要とせず、夜にはぐっすり眠れたのに。

酒は涙かため息か─あるいは《進化したナメクジ》が、下等動物のままでいれば楽に生きられ楽に死ねたろうに─とこぼすグチのようなものか。
東京新聞の最終面に『わが街わが友』という、著名人が短期連載を引き継いでゆくコラムが載っており、たいていは成功者の自慢だが、あの乙武クンの連載は一風変わっていて、彼に対する認識を改めさせられた。彼が太陽のように明るいのは、人間の命に限りがあることを分かった上でのことだったんですね。
逆に、黙っていてもチヤホヤされる、何ひとつ欠けることのない美女に生まれついたニコは、生きながらにして常に死の匂いを振りまく、まるで死が親友であるかのよう。だが、その音楽は、不思議と優しい。
この映画は、以前のチェット・ベイカーの映画と同様、劇的とか感動を誘うとかではないけれども、一人の人間が背負った業がまざまざと描かれ、その光=まったく独自な音楽=と、影=酒や薬物浸りの暮らし=が、分かちがたい運命だったということが、静かに伝わってきます。
─と書いているうちに、酒が飲める時間が、少し近づいてきた。

「私たちはパスポートなんて持つべきじゃない。『死を思え(メメント・モリ)』の反対で、バカげてるわ。誰それがどこで生まれたかなんて、いったい誰が気にするっていうの?」
アンディ・ウォーホルの『チェルシー・ガール』をはじめとする映画に出演し、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの伝説的1stアルバムで歌うなど、ウォーホルの“ファクトリー”の花形的存在だったニコ。
1938年10月16日にドイツのケルンでクリスタ・パフゲンとして生まれた彼女は、ニューヨークでウォーホルと会うまでに、既にヨーロッパで十分刺激的な人生を送っていた。
─パリコレのキャトウォークを歩き、VOGUE、ELLEの表紙を飾るファッション・モデルとして─フェリーニの『甘い生活』にも端役で顔を出し─『太陽がいっぱい』のロケで出会ったアラン・ドロンの子どもを産んだ母として─ロンドンで「I'm Not Sayin'」なるシングル盤を吹き込んだ歌手として─そして、そのシングル盤のB面で伴奏したブライアン・ジョーンズ(ローリング・ストーンズ)のガール・フレンドとして─。
ボブ・ディランとの出会いにより音楽の世界に引き込まれ、ルー・リードと、ジョン・ケイルと、ジャクソン・ブラウンと、そしてドアーズのジム・モリソンと出会うニコ。「彼は私が恋した初めての男だった。だって彼は私の容姿と心に愛情を示してくれたから。だけど私たちは愛の成就のため、あまりに酒を飲みすぎ、あまりにドラッグをやりすぎた。それが私たちの難点だった」。
やがて自分でも曲を作り始めた彼女は、ジョン・ケイルのプロデュースのもと『Marble Index』『Desertshore』『The End』という一連の傑作アルバムをリリース。ヨーロッパに渡って映画監督フィリップ・ガレルと出会ったのも同じころで、2人は『内なる傷痕』や『孤高』といった映画を制作するとともに、虚無的な生き方もつのらせ、ヘロインに溺れてゆく。
ニコは彼女をヘロイン中毒から助けようとしたマネージャーの尽力によりコンサート活動を再開し、東京にも2度訪れている。だが1988年7月、スペインのイビサ島で自転車に乗って転倒、脳出血のため49歳で世を去った。ハシシを買いに行く途上だったとされる。
このドキュメンタリー作品は、世界が最も強烈な激動を味わった1960年代から80年代にかけて、自分が自分であることを探し続けた真のボヘミアンであるニコを、関係者の証言や生前の映像を元に描いたものである。ニコと同じケルン出身のオフテリンガー監督はこう語る。「ニコは、単に人から美しいと思われるだけの存在から、独自のやり方で自分自身を表現できる人間になるまで、多大なステップアップを踏んでいった人だと思う。そしてそれこそが、私が彼女に興味を持ってやまない理由でした。人がいかに自分自身を鍛え、今ある姿からほんとうに自分がなりたい自分に変われるか、ということに」。

あ~~酒が飲みたい─酒が。
本来きのう、この映画の記事をやるはずだったのだが、同じことなんだよ。オラは日曜月曜と2日連続の休肝日を設けているので。
2日間飲めないのは長く感じる。土曜の25時から火曜の17時まで飲まないとすると、48時間ではなく、64時間も飲まずにいなければならない。が、老いても1日でも長くおいしく飲み食いするため、我慢するのだ。

《ぬか漬けのきゅうりは生のきゅうりに戻れない》─吾妻ひでおさんは、あれから一滴も飲んでおらず、健康を取り戻したようなのだが、きゅうりはぬか漬けにしなくても、やがてしなびる。
誰もが老い、いずれは死ぬ。子どものころなんてさあ、朝から元気いっぱいで、酒も薬物も必要とせず、夜にはぐっすり眠れたのに。

酒は涙かため息か─あるいは《進化したナメクジ》が、下等動物のままでいれば楽に生きられ楽に死ねたろうに─とこぼすグチのようなものか。
東京新聞の最終面に『わが街わが友』という、著名人が短期連載を引き継いでゆくコラムが載っており、たいていは成功者の自慢だが、あの乙武クンの連載は一風変わっていて、彼に対する認識を改めさせられた。彼が太陽のように明るいのは、人間の命に限りがあることを分かった上でのことだったんですね。
逆に、黙っていてもチヤホヤされる、何ひとつ欠けることのない美女に生まれついたニコは、生きながらにして常に死の匂いを振りまく、まるで死が親友であるかのよう。だが、その音楽は、不思議と優しい。
この映画は、以前のチェット・ベイカーの映画と同様、劇的とか感動を誘うとかではないけれども、一人の人間が背負った業がまざまざと描かれ、その光=まったく独自な音楽=と、影=酒や薬物浸りの暮らし=が、分かちがたい運命だったということが、静かに伝わってきます。
─と書いているうちに、酒が飲める時間が、少し近づいてきた。