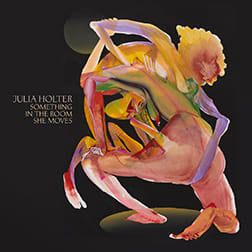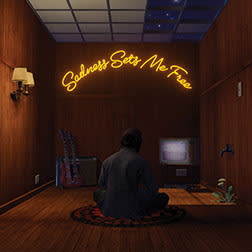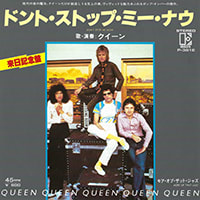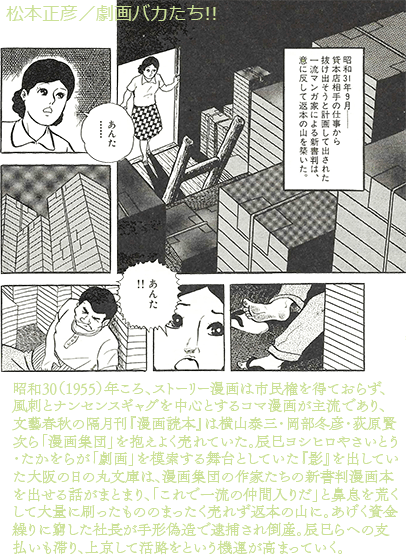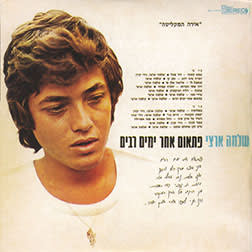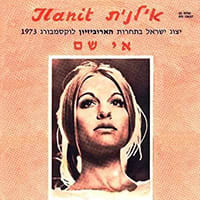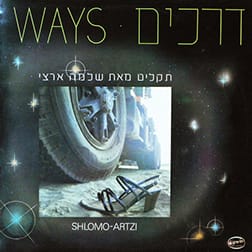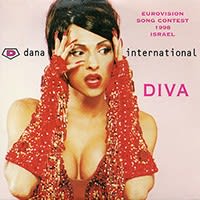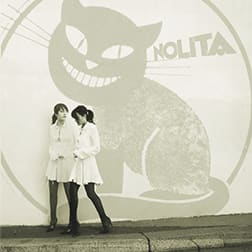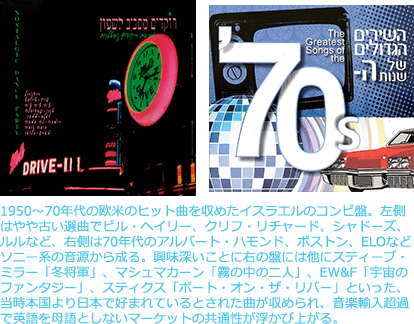100) Styx / Babe
99) 甲斐バンド / HERO(ヒーローになる時、それは今) (1978)
98) Toto / Hold the Line (1978)
97) Blondie / Sunday Girl (1978)
96) Godiego / 銀河鉄道999
95) Gino Vannelli / I Just Wanna Stop (1978)
94) Herb Alpert / Rise
93) Nils Lofgren / Shine Silently
92) Billy Joel / My Life (1978)
91) John Stewart / Gold
90) The Jacksons / Shake Your Body (Down to the Ground) (1978)
89) M / Pop Muzik
88) Sister Sledge / Lost in Music
87) 山口百恵 / いい日旅立ち (1978)
86) Chic / My Forbidden Lover
85) Camarón de la Isla / Volando voy
84) Eagles / Heartache Tonight
83) Sniff 'n' the Tears / Driver's Seat
82) The Crusaders / Street Life
81) J.D. Souther / You're Only Lonely
80) 八代亜紀 / 舟唄
79) Peaches & Herb / Reunited (1978)
78) Electric Light Orchestra / Shine a Little Love
77) Van Halen / Dance the Night Away
76) Donna Summer / Bad Girls
75) Amelinha / Frevo mulher
74) The Pointer Sisters / Fire (1978)
73) Blondie / Dreaming
72) Boston / A Man l'II Never Be (1978)
71) The Cars / Let's Go
70) Earth, Wind & Fire / After the Love Has Gone
69) Kiss / I Was Made for Lovin' You
68) Commodores / Sail On (12" Version)
67) Flash and the Pan / Hey, St. Peter (1977)
66) The Specials / Gangsters
65) Dschinghis Khan / Dschinghis Khan
64) Joy Division / Transmission
63) サザンオールスターズ / C調言葉に御用心
62) Lene Lovich / Lucky Number (1978)
61) Godiego / ガンダーラ (1978)
60) The Police / Message in a Bottle
59) Squeeze / Cool for Cats
58) Ramones / Rock 'n' Roll High School
57) Nicolette Larson / Lotta Love (1978)
56) Sister Sledge / We Are Family
55) Graham Parker / Discovering Japan
54) Dave Edmunds / Girls Talk
53) Sparks / Beat the Clock
52) Tavito / Rua Ramalhete
51) Roxy Music / Dance Away
50) Supertramp / The Logical Song
49) Joe Jackson / Is She Really Going Out With Him? (1978)
48) Kool & the Gang / Ladies Night
47) Rickie Lee Jones / Chuck E's in Love
46) クリスタルキング / 大都会
45) Village People / Y.M.C.A. (1978)
44) Chic / Le Freak (1978)
43) Bram Tchaikovsky / Girl of My Dreams
42) Ian Gomm / Hold On
41) Talking Heads / Life During Wartime
40) Frankie Miller / When I'm Away From You
39) Earth, Wind & Fire / Boogie Wonderland (with The Emotions)
38) Bee Gees / Tragedy
37) XTC / Making Plans for Nigel
36) 久保田早紀 / 異邦人
35) Blondie / One Way or Another (1978)
34) The Pop Group / She Is Beyond Good and Evil
33) AC/DC / Highway to Hell
32) Boca Livre / Toada (Na direção do dia)
31) Electric Light Orchestra / Last Train to London
30) Wings / Goodnight Tonight
29) SHŌGUN / 男達のメロディー
28) lan Dury & the Blockheads / Hit Me with Your Rhythm Stick (1978)
27) Nick Lowe / Cruel to Be Kind
26) Elvis Costello & the Attractions / Accidents Will Happen
25) The B-52's / Rock Lobster
24) Dire Straits / Sultans of Swing (1978)
23) The Knack / My Sharona
22) Rod Stewart / Da Ya Think I'm Sexy? (1978)
21) Elis Regina / O bêbado e a equilibrista
20) Squeeze / Up the Junction
19) Billy Joel / Honesty (1978)
18) 許冠傑 / 賣身契 (1978)
17) The Boomtown Rats / I Don't Like Mondays
16) Thin Lizzy / Waiting for an Alibi
15) Cheap Trick / Voices
14) Sad Café / Every Day Hurts
13) Gloria Gaynor / I Will Survive (1978)
12) Blondie / Heart of Glass (1978)
11) Elvis Costello & the Attractions / Oliver's Army
10) Queen / Don't Stop Me Now (1978)
9) Chic / Good Times
8) Michael Jackson / Don't Stop 'Til You Get Enough
7) Earth, Wind & Fire / September (1978)
6) León Gieco / Sólo le pido a Dios
5) Tubeway Army / Are 'Friends' Electric?
4) Donna Summer / Hot Stuff
3) Buggles / Video Killed the Radio Star
2) The Doobie Brothers / What a Fool Believes (1978)
1) 許冠傑 / 半斤八兩 (1976)