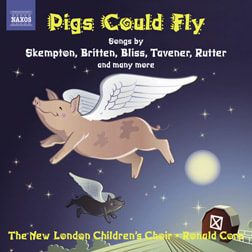【筒井康隆の短編20傑】
1.走る取的(メタモルフォセス群島)
2.おれに関する噂(おれに関する噂)
3.関節話法(宇宙衛生博覧會)
4.泣き語り性教育(革命のふたつの夜)
5.郵性省(日本列島七曲り)
6.顔面崩壊(宇宙衛生博覧會)
7.となり組文芸(革命のふたつの夜)
8.陰悩録(日本列島七曲り)
9.バブリング創世記(バブリング創世記)
10.夜を走る(国境線は遠かった)
11.鍵(バブリング創世記)
12.ホンキイ・トンク(ホンキイ・トンク)
13.佇むひと(ウィークエンド・シャッフル)
14.熊の木本線(おれに関する噂)
15.経理課長の放送(農協 月へ行く)
16.毟りあい(メタモルフォセス群島)
17.新宿祭(筒井順慶)
18.欠陥バスの突撃(国境線は遠かった)
19.コレラ(革命のふたつの夜)
20.肥満考(馬は土曜に蒼ざめる)

美女の大便はでかい、という記事を読んで益夫は猛烈な衝撃を受けた。
「郵性省」の書き出し。おもしろいんだよ。おもしろいんだけどね、全集で読みたいような性質ではない。昨今の若者はケータイ/パソコンが生まれた時からあるためか、なんらか物を買うのに《保存コスト》を重視するというのを聞き、常に整理整頓を心がけて、要らないものはどんどん削っていこうと。小説家で個人全集を揃えていた二人、筒井康隆と谷崎潤一郎。重い。かさばる。滅多に開くこともない。読み返すとしても、本当に必要なところだけ文庫本で持っておけば十分。
このたび処分するにあたって、筒井の初期のエッセイをぱらぱらめくってみると、とんでもないことが書いてあるな。─てんかんの患者はたいへん多い。隠して運転免許を取得していることも。くわばらくわばら。ぼくにだけは教えてください─。
石原慎太郎が知恵遅れなり強姦被害者なり、何重に保険をかけてでも相手の立場に立つ気がない態度は、いわば小説家のような連中の習い性だとも考えられる。筒井の小説で、主人公がなんらか被害者となる場合、相手側の理不尽な暴力によることがほとんど。主人公(=筒井)には落ち度はない。そこへ気づいてみると、教科書に載った自作がてんかん協会から問題視されて断筆へ至った経緯も、まったく違って見えてくるし、筒井のみならずそもそも小説なんていうものはマンガより下等な風俗商品で、本棚のいいところを占有させておく理由はまったくない。たとえば桐野夏生や奥田英朗は『闇金ウシジマくん』とも共通する題材を描くけれども、再読してみた場合に時代の証拠物件としての価値が歴然と下がる。
そして多くの小説家の場合、世に出ることになった前半生の作品のほうが良くて、その後に思想的な深まりが見られず、成熟するはずの後半生において過去の水準を超えられない。《作家として世に出る》ことが、一種の科挙のようなマスコミ特殊法人の就職試験となっており、ひとたび成功すると死ぬまで鈴なりにしがみつく。ゆえに、ものを作るための世界観を持たないような佐藤優とか雨宮処凛とかも、ヨコ入りしてしがみついたからには【作家】と名乗るのだ。
筒井康隆や谷崎潤一郎には世界観がある。筒井の「となり組文芸」などでは上記のようなマスコミ事情も辛辣に描かれるし、谷崎が一貫して自らの性癖にこだわりながら後半生にも物語世界を発展させてゆくさまも見事だ。ちなみに谷崎の『少将滋幹の母』でも“美女の大便”について触れられるくだりが─。
とわいうものの、手塚治虫やビートルズですら全作品を常に持っておく必要はないので、滅多に読み返すことのない小説などは厳しく選別してゆきたい。二人の全集は結局すべて処分。波及して本の並べ方を大幅に見直し、夢の本棚へ一歩近づく。いずれ小林信彦などもバッサリ削除となりそう、決して完成することはないが、それはそれでかまわない。

【谷崎潤一郎の本の星取表】
★★★★刺青・秘密
★★★お艶殺し・金色の死
★★人魚の嘆き・魔術師
★★★近代情痴集
★★★犯罪小説集
★★★★★痴人の愛
★★鮫人(未完)
★★★★卍
★★★盲目物語
★★★★吉野葛・蘆刈
★★★★★春琴抄
★★★文章讀本
★★武州公秘話(未完)・聞書抄
★★★★猫と庄造と二人のをんな
★★★★陰影礼賛
★★★★★細雪
★★★亂菊物語(未完)
★★★★少将滋幹の母
★★★★★鍵・瘋癲老人日記
★★台所太平記
★★★天鵞絨の夢(日本幻想文学集成5)

1.走る取的(メタモルフォセス群島)
2.おれに関する噂(おれに関する噂)
3.関節話法(宇宙衛生博覧會)
4.泣き語り性教育(革命のふたつの夜)
5.郵性省(日本列島七曲り)
6.顔面崩壊(宇宙衛生博覧會)
7.となり組文芸(革命のふたつの夜)
8.陰悩録(日本列島七曲り)
9.バブリング創世記(バブリング創世記)
10.夜を走る(国境線は遠かった)
11.鍵(バブリング創世記)
12.ホンキイ・トンク(ホンキイ・トンク)
13.佇むひと(ウィークエンド・シャッフル)
14.熊の木本線(おれに関する噂)
15.経理課長の放送(農協 月へ行く)
16.毟りあい(メタモルフォセス群島)
17.新宿祭(筒井順慶)
18.欠陥バスの突撃(国境線は遠かった)
19.コレラ(革命のふたつの夜)
20.肥満考(馬は土曜に蒼ざめる)

美女の大便はでかい、という記事を読んで益夫は猛烈な衝撃を受けた。
「郵性省」の書き出し。おもしろいんだよ。おもしろいんだけどね、全集で読みたいような性質ではない。昨今の若者はケータイ/パソコンが生まれた時からあるためか、なんらか物を買うのに《保存コスト》を重視するというのを聞き、常に整理整頓を心がけて、要らないものはどんどん削っていこうと。小説家で個人全集を揃えていた二人、筒井康隆と谷崎潤一郎。重い。かさばる。滅多に開くこともない。読み返すとしても、本当に必要なところだけ文庫本で持っておけば十分。
このたび処分するにあたって、筒井の初期のエッセイをぱらぱらめくってみると、とんでもないことが書いてあるな。─てんかんの患者はたいへん多い。隠して運転免許を取得していることも。くわばらくわばら。ぼくにだけは教えてください─。
石原慎太郎が知恵遅れなり強姦被害者なり、何重に保険をかけてでも相手の立場に立つ気がない態度は、いわば小説家のような連中の習い性だとも考えられる。筒井の小説で、主人公がなんらか被害者となる場合、相手側の理不尽な暴力によることがほとんど。主人公(=筒井)には落ち度はない。そこへ気づいてみると、教科書に載った自作がてんかん協会から問題視されて断筆へ至った経緯も、まったく違って見えてくるし、筒井のみならずそもそも小説なんていうものはマンガより下等な風俗商品で、本棚のいいところを占有させておく理由はまったくない。たとえば桐野夏生や奥田英朗は『闇金ウシジマくん』とも共通する題材を描くけれども、再読してみた場合に時代の証拠物件としての価値が歴然と下がる。
そして多くの小説家の場合、世に出ることになった前半生の作品のほうが良くて、その後に思想的な深まりが見られず、成熟するはずの後半生において過去の水準を超えられない。《作家として世に出る》ことが、一種の科挙のようなマスコミ特殊法人の就職試験となっており、ひとたび成功すると死ぬまで鈴なりにしがみつく。ゆえに、ものを作るための世界観を持たないような佐藤優とか雨宮処凛とかも、ヨコ入りしてしがみついたからには【作家】と名乗るのだ。
筒井康隆や谷崎潤一郎には世界観がある。筒井の「となり組文芸」などでは上記のようなマスコミ事情も辛辣に描かれるし、谷崎が一貫して自らの性癖にこだわりながら後半生にも物語世界を発展させてゆくさまも見事だ。ちなみに谷崎の『少将滋幹の母』でも“美女の大便”について触れられるくだりが─。
とわいうものの、手塚治虫やビートルズですら全作品を常に持っておく必要はないので、滅多に読み返すことのない小説などは厳しく選別してゆきたい。二人の全集は結局すべて処分。波及して本の並べ方を大幅に見直し、夢の本棚へ一歩近づく。いずれ小林信彦などもバッサリ削除となりそう、決して完成することはないが、それはそれでかまわない。

【谷崎潤一郎の本の星取表】
★★★★刺青・秘密
★★★お艶殺し・金色の死
★★人魚の嘆き・魔術師
★★★近代情痴集
★★★犯罪小説集
★★★★★痴人の愛
★★鮫人(未完)
★★★★卍
★★★盲目物語
★★★★吉野葛・蘆刈
★★★★★春琴抄
★★★文章讀本
★★武州公秘話(未完)・聞書抄
★★★★猫と庄造と二人のをんな
★★★★陰影礼賛
★★★★★細雪
★★★亂菊物語(未完)
★★★★少将滋幹の母
★★★★★鍵・瘋癲老人日記
★★台所太平記
★★★天鵞絨の夢(日本幻想文学集成5)