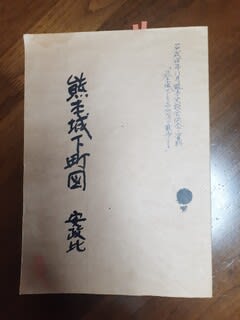日帳(寛永八年十一月)廿七日~晦日
|
| 廿七日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
|
|一、修理・兵庫当番也
小倉長崎町ノ米引 |一、吉田縫殿助登城にて被申候は、長崎町ノ喜右衛門、昨日籠ゟ出シ申由、被申候事、
負ノ町人釈放 |
宇佐宮ノ宮成掃部 |一、宮成掃ア登城仕ニ付而、 将軍様ゟ、掃アへ銀子拾枚被遣候間、御横目ニ三輪権内申付、御銀子
へ将軍下賜銀ヲ渡 | 掃ア相渡申候事、
ス |
|
| 廿八日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
|
|一、兵庫・助進当番也
| (有清)
彦山有清仁保慰英 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、彦山座主ゟ御状参候、就其、仁保太兵衛屋敷上り申候は、座主
ノ明屋敷ヲ乞ウ | 拝領仕度由、被仰越候、上り屋敷ニ成申候は、座主爰元ニ屋敷無之候間、座主へ被遣候様ニ可被
| (ママ)
| 仕候、兵庫返事申候は、未太兵衛屋敷上ヶ不申候、たとへ上り屋敷ニ成候さいわい座主此地ニ
| 屋敷無御座候間、渡り申様ニ可仕候と、御返事申候事、
| (長氏)
平野長氏方牢人ヲ |一、平野九郎右衛門尉方ゟ、使者を以、被申聞候ハ、在郷ニ置申候牢人之儀、煩為養生、上方へ差上
療養ノタメ上方へ | せ申度通、江戸へ得 御意申候ヘハ、上せ候へと、 御書成被下候間、上せ可申と存候、爲御心
遣サントス | 得申入由候、得其意申候通、返事申候事、
|
| 奥村少兵衛
| 廿九日 河本瀬兵衛
| 加来二郎兵衛
| 〃〃〃〃〃〃
|
|一、助進・修理当番也、
| (信茂)
新任ノ幕府横目大 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、城織ア様ゟ夜前預御状候、御横目替之衆、今月廿七、八日時
坂乗船ノ用意 | 分ニ、大坂御出船之様ニ申来候、定而来月十日時分ハ、豊後可為御着と存候間、御乗上り被成候
| 御舟廻シ申候様ニと、申来候間、去ル廿六日ニ、其地へ廻シ申由、御返事申遣候、爲御心得申入
| 由、被仰聞候、得其意存候由、御返事申候事、
沢村吉重惣奉行等 |一、大学殿・我々共三人、今日御本丸へ談合ニ上り申候事、
本丸ニテ談合 |
|
| 晦日 河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
|
|一、修理・兵庫当番也
|一、京・大坂へ被 召置候衆、御用調様之儀申上せ候状之下書、大学所にて被調、登城候て談合ノ上、
| 書状調申候事、
築城上毛郡ニ毎年 |一、沢少兵衛・荒木善兵衛登城にて被申候ハ、築城・上毛両郡ニ毎年御種子米六百石被借げ候、来春
種米六百石貸下グ | ハ三百石かり可申候、残ル三百石ハ、拾貫目御袖判ニテ被借下候代米ノ内を以、被借下、都合六
来春三百石分ハ拾 | 百石ニ仕度由、被申候、何も御米之儀候間、其分可然候ハん由、松丸衆談合之ノ上、右之分、申付
貫目ノ代米ヲ充テ | 候事、
ム |
(了)
今回を以て「福岡県史・近世史料ー細川小倉藩」は完了いたしました。
細川家の肥後入国迄、約一年前です。