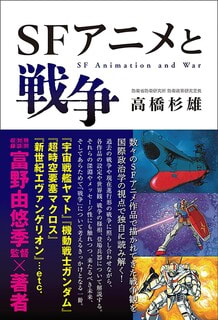日本政策金融公庫総合研究所/編集 「フードテック: 中小企業によるフード業界の変革」読了
この本もほぼ1日で読んでしまった。昨日の病院の待ち時間も3時間であったが、今日の帰宅に要した時間は先週に引き続き発生した人身事故のせいで4時間もかかってしまったからである。もっと読みが深ければ3時間で家に帰れたが甘かった。しかし、JRの情報提供は再び劣化してきたようだ。当初の情報では列車に異音を検知したということであったが次の情報では人身事故で運転再開が18:30、その次の情報で事故がトンネルの中で起こっているので運転再開は20:00とどんどん変わっていった。

どこからどんな情報を集めていたのか、異音と人身事故とでは全く違うし、その現場がどこかなどいうのをわからずに第一報を流したというのではまったくバカじゃないのかとしか思えない。最初から20:00の運転再開ということが分かっていたら振替輸送のルートを選んでいた。大半の人がそう思っていたようで、和泉砂川の駅のホームでは落胆の声が響いていた。
しかし、電車に轢かれた人というのはどうして山間部のトンネルの中を歩いていたのだろう。自殺の場所としては奇妙だが、こんな場所で事故が起こったらニュースになって世間に一矢報いることができるとでも思ったのだろうか。しかし、結局、この人が何者でどんなに世間を恨んで死んでいったかなど誰も知ることはなかったはずなので犬死でしかない。それとも単にボケ老人が家に帰る道筋を忘れてしまって線路に紛れ混んでしまったのだろうか。
どちらにしてもこういう人の供養のためにも事故の詳細を公表してあげてほしいものだ。この時に迷惑を被った人たちもどうして自分たちがこんな目に遭わねばならなかったのかということを知る権利があると思う。少なくとも僕はそう思っている。
そんな状況の中で読んでいたのがこの本である。
食品作業の生産性というのは他の産業に比べるとかなり低いそうだ。2021年の数値では全産業のひとり当たりの労働生産性803万円に対して農林水産業の生産性は214万円。食品製造業では製造業全体の従業員ひとり当たりの労働生産性1184万円に対して食品製造業は644万円、飲食サービス業についても199万円で産業全体の893万円を大きく下回っている。
それを様々なテクノロジーを投入することで生産性を向上させ、SDGsにも貢献しようとしている中小企業を紹介しているのがこの本である。
この本を作ったシンクタンクの日本政策金融公庫総合研究所が所属する日本政策金融公庫という政府系の会社は中小企業支援のための組織であるらしいので、紹介されている企業はここから融資を受けている会社なのであろう。
食品アレルギーでの事故を未然に防ぐITサービス、外食産業で食材の仕入れや人員配置を予測するシステムを開発、TI技術で魚の養殖を効率化、フードロスを削減するシステム開発、ドローンを使った農機具の開発、新しい冷凍技術の開発、小規模の植物工場、人工肉、野菜の人工栽培と魚の養殖を組み合わせた産業、加水分解で新たな食材を開発するなど、IT技術やロボット、バイオ技術などを農林水産業、食品製造、サービス業に組み合わせ、創業者たちが経験した困りごとや問題点の解決策をビジネスチャンスと捉えて起業している。
ユニークというかよくこんなことを思いつくものだと思うが、それよりも、ここでまた、こういう人たちと自分はどこが違ったのだろうと本題のフードテックよりもそんなことを考えてしまう。
編者のひとりは、『困りごとを当たり前と思わない』ことがそのひとつであるというが、確かに、僕は困りごとはこちら側がそれに合わせて修正するかそれでもだめなら迂回して生きてきたように思う。解決策を考えようにもいつもどこでもそのためのスキルが無かったというのも確かだ。
人脈を広げようともしなかった。長く働いていた会社は新しい取引先を連れてきても既存の取引先の間に割って入っていかせることができるような環境ではなかった。それは自分の力の限界でもあったのだが、成果が出る前に上の方からこんなものダメと決めつけられてしまう世界であった。上の人たちは基本的に既存の取引先の既得権を守るために存在していたようなものであった。
ここ数冊読んだ本は全部そんなことを思うばかりの本であった。自分が空しくなるばかりである。老人たちが読む本というのは時代小説でそれも実在の人物ではなく架空の主人公が活躍する痛快時代劇が多いと聞いたことがあるが、それ以外の本を読むと自分の来し方を顧みて空しくなってしまうからだったのかと自分なりに納得してしまった。
この本に取りあげられているテクノロジーは今のところおそらくコストも高くて市場に出ていたとしても僕の口に入るものではないだろう。今は紙の上で味わうしかないようである。
この本もほぼ1日で読んでしまった。昨日の病院の待ち時間も3時間であったが、今日の帰宅に要した時間は先週に引き続き発生した人身事故のせいで4時間もかかってしまったからである。もっと読みが深ければ3時間で家に帰れたが甘かった。しかし、JRの情報提供は再び劣化してきたようだ。当初の情報では列車に異音を検知したということであったが次の情報では人身事故で運転再開が18:30、その次の情報で事故がトンネルの中で起こっているので運転再開は20:00とどんどん変わっていった。

どこからどんな情報を集めていたのか、異音と人身事故とでは全く違うし、その現場がどこかなどいうのをわからずに第一報を流したというのではまったくバカじゃないのかとしか思えない。最初から20:00の運転再開ということが分かっていたら振替輸送のルートを選んでいた。大半の人がそう思っていたようで、和泉砂川の駅のホームでは落胆の声が響いていた。
しかし、電車に轢かれた人というのはどうして山間部のトンネルの中を歩いていたのだろう。自殺の場所としては奇妙だが、こんな場所で事故が起こったらニュースになって世間に一矢報いることができるとでも思ったのだろうか。しかし、結局、この人が何者でどんなに世間を恨んで死んでいったかなど誰も知ることはなかったはずなので犬死でしかない。それとも単にボケ老人が家に帰る道筋を忘れてしまって線路に紛れ混んでしまったのだろうか。
どちらにしてもこういう人の供養のためにも事故の詳細を公表してあげてほしいものだ。この時に迷惑を被った人たちもどうして自分たちがこんな目に遭わねばならなかったのかということを知る権利があると思う。少なくとも僕はそう思っている。
そんな状況の中で読んでいたのがこの本である。
食品作業の生産性というのは他の産業に比べるとかなり低いそうだ。2021年の数値では全産業のひとり当たりの労働生産性803万円に対して農林水産業の生産性は214万円。食品製造業では製造業全体の従業員ひとり当たりの労働生産性1184万円に対して食品製造業は644万円、飲食サービス業についても199万円で産業全体の893万円を大きく下回っている。
それを様々なテクノロジーを投入することで生産性を向上させ、SDGsにも貢献しようとしている中小企業を紹介しているのがこの本である。
この本を作ったシンクタンクの日本政策金融公庫総合研究所が所属する日本政策金融公庫という政府系の会社は中小企業支援のための組織であるらしいので、紹介されている企業はここから融資を受けている会社なのであろう。
食品アレルギーでの事故を未然に防ぐITサービス、外食産業で食材の仕入れや人員配置を予測するシステムを開発、TI技術で魚の養殖を効率化、フードロスを削減するシステム開発、ドローンを使った農機具の開発、新しい冷凍技術の開発、小規模の植物工場、人工肉、野菜の人工栽培と魚の養殖を組み合わせた産業、加水分解で新たな食材を開発するなど、IT技術やロボット、バイオ技術などを農林水産業、食品製造、サービス業に組み合わせ、創業者たちが経験した困りごとや問題点の解決策をビジネスチャンスと捉えて起業している。
ユニークというかよくこんなことを思いつくものだと思うが、それよりも、ここでまた、こういう人たちと自分はどこが違ったのだろうと本題のフードテックよりもそんなことを考えてしまう。
編者のひとりは、『困りごとを当たり前と思わない』ことがそのひとつであるというが、確かに、僕は困りごとはこちら側がそれに合わせて修正するかそれでもだめなら迂回して生きてきたように思う。解決策を考えようにもいつもどこでもそのためのスキルが無かったというのも確かだ。
人脈を広げようともしなかった。長く働いていた会社は新しい取引先を連れてきても既存の取引先の間に割って入っていかせることができるような環境ではなかった。それは自分の力の限界でもあったのだが、成果が出る前に上の方からこんなものダメと決めつけられてしまう世界であった。上の人たちは基本的に既存の取引先の既得権を守るために存在していたようなものであった。
ここ数冊読んだ本は全部そんなことを思うばかりの本であった。自分が空しくなるばかりである。老人たちが読む本というのは時代小説でそれも実在の人物ではなく架空の主人公が活躍する痛快時代劇が多いと聞いたことがあるが、それ以外の本を読むと自分の来し方を顧みて空しくなってしまうからだったのかと自分なりに納得してしまった。
この本に取りあげられているテクノロジーは今のところおそらくコストも高くて市場に出ていたとしても僕の口に入るものではないだろう。今は紙の上で味わうしかないようである。