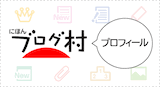『日本国憲法』
「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
先日来、性的少数勢力 LGBTの存り方を巡り、賛否の主張が繰り広げられて来た。ここへ来て、衆院第一野党 立憲民主党にて、同性婚を可能とすべく 法案整備を行う動きが出て来た由。しかしながら、これら法案整備の為には 日本国憲法改正が不可避とする見方が多く、立憲民主党案がそのまま通る可能性はなさそうだ。以下、前掲の日本国憲法第24条との整合性問題などを、ネット辞書「ウィキペディア」の記事を引用して見て参る事にしたい。
「同性結婚との関係」
日本で同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。
ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから、憲法学者の君塚正臣は、同性結婚は憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している。
自身が同性愛者であることを公表している市民活動家の明智カイトは、司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという。過去には青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった。法学者の植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え、憲法学者の八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている。法学者の辻村みよ子は憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している。
一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと説明している。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している。また、憲法第14条を根拠に同性婚を認めるべきだという見解も存在する。セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015=平成17年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した。(引用ここまで、敬称略)
賛否あるは分かっているが、憲法24条々文や、前出の引用記事を拝読した上で、拙者は 同性婚可能法案は違憲たる見解、つまり「現在の憲法学界の主流派解釈」を支持するものだ。違憲とする側の見解は、更には その上で同性婚可能法案整備の推進を志向する勢力と、それには少なくとも直ちには反対とする勢力に分かれる。拙者は後者に近い立場だ。どうしても法整備をと言うなら、やはり日本国憲法改正を目指すべきだろう。
立憲民主党が企てる所の 同性婚可能法案は、前掲引用記事後半の日本国憲法条文に 同性婚禁止の明確な規定がない事を盾に、同性婚は許容されるとの立場らしいが、同法の制定は 遠く 1946=昭和21年。この年代で、昨今の様に 同性婚が明らさまに語られる事のなかった時代に、法条文がないからと言って、それが許容されるとの強引な主張は、明らかに左派野党がよしとしない解釈改憲であり、法的にも無理筋だろう。
以前から気になっていた所だが、左派野党と折々親和的になり易い護憲原理勢力は、自勢力と対立する見解や思考は 現憲法の規定を真に受ける形で解釈し 一切認めようとしない一方で、自勢力を利する様な事共には、解釈改憲でも何でもありの恰好で 大甘に向き合って来た嫌いがある。以前からあるこうした「二重基準ダブスタ的性癖」は、決して見直されてはいないのだ。こんな姿勢は、決して国民的支持は得られまいて。
枝野立憲民主執行部は、同性婚可能法案を 現憲法を大きく見直す事なく成立を図る様だが、それは不成功に終わるだろう。現憲法の改正に踏み込めば 少しは展望が開けようが、それはあくまで LGBT本来の意味たる 少数者を守る法的保障に留まるべきで、国民多数に向けたものであるべきではない。その様に解釈する動きは、我国のあり様の根幹に関わる不良なものにつき、決して勢いを持たせてはならない。
先日の LGTBの生産性に言及して批判多数を招いた、杉田水脈(すぎた・みお)自民衆議の見解は、それは表現の配慮に欠ける所あったは糾されるべきだし、不適切箇所に見合った反省謝罪や記事訂正はされるべきだが、全部一切が間違いという訳ではない。国会議員といえど、一定の言論・表現などの自由は適用されるのであり、明らかに不良な所を除いては、過度の追及や指弾は見合せられるべきだ。今回画像は、新潟・群馬県境近くの 上越新幹線某駅にて見かけた、もうすぐ使命を終える 二階式の新幹線列車。関東一円では、新幹線利用の通勤通学も多く、二階式列車は、特に混雑時に威力を発揮するも、高齢・身障各位向けの「バリアフリー」に対処できず、再来年夏の東京五輪までに姿を消す見込みと言われます。
「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
先日来、性的少数勢力 LGBTの存り方を巡り、賛否の主張が繰り広げられて来た。ここへ来て、衆院第一野党 立憲民主党にて、同性婚を可能とすべく 法案整備を行う動きが出て来た由。しかしながら、これら法案整備の為には 日本国憲法改正が不可避とする見方が多く、立憲民主党案がそのまま通る可能性はなさそうだ。以下、前掲の日本国憲法第24条との整合性問題などを、ネット辞書「ウィキペディア」の記事を引用して見て参る事にしたい。
「同性結婚との関係」
日本で同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。
ただし、憲法24条1項に「両性の合意」「夫婦」という文言があることから、憲法学者の君塚正臣は、同性結婚は憲法の想定されたものではなく憲法問題と認められずに棄却されると推測している。
自身が同性愛者であることを公表している市民活動家の明智カイトは、司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見があると述べている。一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという。過去には青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった。法学者の植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え、憲法学者の八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている。法学者の辻村みよ子は憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している。
一方で、憲法学者の木村草太は、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと説明している。弁護士の濵門俊也は、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している。また、憲法第14条を根拠に同性婚を認めるべきだという見解も存在する。セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015=平成17年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した。(引用ここまで、敬称略)
賛否あるは分かっているが、憲法24条々文や、前出の引用記事を拝読した上で、拙者は 同性婚可能法案は違憲たる見解、つまり「現在の憲法学界の主流派解釈」を支持するものだ。違憲とする側の見解は、更には その上で同性婚可能法案整備の推進を志向する勢力と、それには少なくとも直ちには反対とする勢力に分かれる。拙者は後者に近い立場だ。どうしても法整備をと言うなら、やはり日本国憲法改正を目指すべきだろう。
立憲民主党が企てる所の 同性婚可能法案は、前掲引用記事後半の日本国憲法条文に 同性婚禁止の明確な規定がない事を盾に、同性婚は許容されるとの立場らしいが、同法の制定は 遠く 1946=昭和21年。この年代で、昨今の様に 同性婚が明らさまに語られる事のなかった時代に、法条文がないからと言って、それが許容されるとの強引な主張は、明らかに左派野党がよしとしない解釈改憲であり、法的にも無理筋だろう。
以前から気になっていた所だが、左派野党と折々親和的になり易い護憲原理勢力は、自勢力と対立する見解や思考は 現憲法の規定を真に受ける形で解釈し 一切認めようとしない一方で、自勢力を利する様な事共には、解釈改憲でも何でもありの恰好で 大甘に向き合って来た嫌いがある。以前からあるこうした「二重基準ダブスタ的性癖」は、決して見直されてはいないのだ。こんな姿勢は、決して国民的支持は得られまいて。
枝野立憲民主執行部は、同性婚可能法案を 現憲法を大きく見直す事なく成立を図る様だが、それは不成功に終わるだろう。現憲法の改正に踏み込めば 少しは展望が開けようが、それはあくまで LGBT本来の意味たる 少数者を守る法的保障に留まるべきで、国民多数に向けたものであるべきではない。その様に解釈する動きは、我国のあり様の根幹に関わる不良なものにつき、決して勢いを持たせてはならない。
先日の LGTBの生産性に言及して批判多数を招いた、杉田水脈(すぎた・みお)自民衆議の見解は、それは表現の配慮に欠ける所あったは糾されるべきだし、不適切箇所に見合った反省謝罪や記事訂正はされるべきだが、全部一切が間違いという訳ではない。国会議員といえど、一定の言論・表現などの自由は適用されるのであり、明らかに不良な所を除いては、過度の追及や指弾は見合せられるべきだ。今回画像は、新潟・群馬県境近くの 上越新幹線某駅にて見かけた、もうすぐ使命を終える 二階式の新幹線列車。関東一円では、新幹線利用の通勤通学も多く、二階式列車は、特に混雑時に威力を発揮するも、高齢・身障各位向けの「バリアフリー」に対処できず、再来年夏の東京五輪までに姿を消す見込みと言われます。