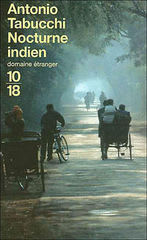
(前回からの続き)
本書は主人公である「僕」のインドへの旅行記の形式をとっており、12章から構成されている。「僕」は一人で都市から都市へと旅し、ホテルを渡り歩き、他の旅行者やインドの人々と出会う。「僕」が出会った人物があとで再び登場することはない。つまり、一つの筋(アクション)が次の結果に繋がることで展開していく因果律型の小説ではなく、各章がそれぞれ別の話として独立しているエピソード羅列側の小説である。と同時に、失踪した友人の探索という旅行の目的が、それらのエピソード全体を束ねている。
では、それぞれのエピソードが一つの小さな物語として結構が整っているかというと、いささか曖昧である。最初の章で「僕」はあるみすぼらしいホテルに泊まり、失踪した友人の恋人だった娼婦と会い、彼女の話を聞く。この章の主たる構成要素は、「僕」が失踪した友人シャヴィエルを探しているという事実の披露と、娼婦とシャヴィエルの哀しい恋物語である。前者が本書全体のモチーフの紹介だとすれば、後者が本エピソードの主体ということになるだろう。が、主体であるはずの恋物語の全体像は、仄めかされているだけではなはだ曖昧である。「僕」は彼女から詳しい話を聴くのだが、その詳細は読者に対してまったく明かされない。タブッキはただこう書く。「長い、まわりくどい、ディテールに満ちた物語だった」
これが普通の小説なら、この「ディテールに満ちた物語」こそ、この章の中心となるだろう。しかしそれが省かれているため、このエピソードは断片的で、単独では完結していない印象を与える。単なるプロローグのような、ちょっとした脇道という感じを受ける。ところが読み進めると分かるのだが、本書ではどういうわけか、どの章もこれと同じような印象を与えるのだ。何か豊穣な物語への単なるプロローグのような、ちょっとした脇道のような、そんなエピソードの連なりで本書は成り立っているのである。
つまりタブッキが呈示する断章は、それ自体が物語として閉じるのではなく、常にそこに書かれていない物語、いわば小説の枠の外にあるものへと読者を誘うベクトルを持っている。枠の外に何があるのか? 何もない。しかし、読者はあるように錯覚する。これが「文学的詐術」だ。そしてこの錯覚は、筒井康隆が驚きをもって体験したように、場合によっては作品そのものよりも大きな感動を与え得る。なぜなら読者の想像力に限界はない。紙に書かれてしまった小説作品よりも常に大きく膨らむ可能性を持っているし、時間とともに変化する柔軟性も持っている。
言葉を変えれば、本書の章の一つ一つは物語そのものではなく、物語の萌芽(もしくはそれに似た何か)だと言える。シャヴィエルと娼婦がどんな恋愛をしたかは明らかにせず、ただ「ディテールに満ちた物語だった」と書くことで、読者にそれをおぼろげに想像するように仕向ける。このような、枠の外にあるものへの誘いは、タブッキが各章に埋め込んだごく小さな種によって動き出す。「動き出す」という言葉が強すぎるなら、ほのかに香ってくる、と言ってもいい。本書の場合、それらの「種」の多くは幻想的な、あるいは幻覚的な、何かしら神秘的なものを暗示するモチーフとなっている。たとえば病院のベッドに横たわる巨大なペニスをもった老人。あるいは夜のバス停で出会う、猿のような畸形の予言者。夜汽車で出会った乗客が彼に告げる、肉体は鞄のようなもの、という言葉。あるいは海辺で出会うアメリカ人青年が語る、フィラデルフィアの街中で見た、あり得ない海。
これらの「種」はさほど掘り下げられることなく、ほんの一瞬、読者の眼前にひらめいては消えていく。その手さばきは非常に淡々としていて、実にさりげない。これらのひらめきを宝石を拾うように拾っていくことが、本書を読む悦びの一つである。
それからこの小説全体を通して、読者は「僕」が世界を眺める視点を共有することになるが、それは私たちの日常的な視点とは異なっている。もちろん、これはどんな小説でも多かれ少なかれそうなのだが、タブッキにおいて特筆すべきは、その視点における記憶と夢と現実の不思議なつながりであり、混淆である。娼婦が語るシャヴィエルとの恋物語は、彼女が記憶の中から取捨選択して作り上げた物語である。彼女は現実だと思っているが、実は現実ではない。また「僕」はシャヴィエルの顔立ちを聞かれた時に答えられず、思い出は描写できない、と奇妙な言葉を呟く。あるいはホテルの部屋で目を閉じた「僕」は、たちまち記憶の中の「丘」に「到着」し、そこでイザベルやマグダとピクニックをする。
イザベル、マグダは「僕」と非常にパーソナルな、そしてインティメートな絆を持つ女性たちである。少なくとも、そう推測される。この小説の中で「僕」はマグダに手紙を書き、それが実はイザベルに宛てた手紙だったことに気づく、という場面がある。しかし、この二人と「僕」の過去の物語は完全にこの小説の枠の外にある。それは確実にそこに存在するが、読者にそれを知るすべはない。ただその不在の物語が発する詩的な香気は、「僕」の記憶を通じて、たえずこの『インド夜想曲』という小説の中に流れ込み続ける。
旅行記という体裁も実にタブッキ的で、まさにタブッキ文学のために存在するような形式だと思う。まず重要なのは旅の一過性であり、エピソード性である。先に書いた通り、「僕」が出会う人々や事件は一度だけ物語にかかわった後は過ぎ去っていき、二度と戻ってこない。プロットは因果律型ではなくエピソード羅列的であり、シンプルに直線的である。タブッキの長編小説にはこのようなスタイルのものが多いが、本書では旅行記であることがその構造をより明確にしている。
ちなみに因果律型ではないという点はタブッキの小説全般の特徴で、伏線があり意外な展開があり、という通常の物語の組み立てはほとんど見られない。通常の小説、特にエンタメ小説では因果律の支配力がより強くなる傾向があり、「伏線がきちんと回収されるかどうか」というような読み方などその最たるものだ。従って通常、虚構の物語は現実よりもはるかに因果律に依存することになる。しかし、タブッキの小説はその印象がきわめて薄い。エピソード間の関係性も緩く、風通しが良い。タブッキの小説では因果律の支配力が弱いのである。
では、その結果プロットが単調になり、退屈になるかというと、そんなことはない。本書もそうだが、フィクションの構造はむしろ複雑であり、重層的だ。ただしその重層性はプロットを込み入らせることによってではなく、虚構のレベルの多重化という、メタフィクショナルな方法で成し遂げられている。その結果、プロットのシンプルさと風通しのよさはそのままに、作品世界が深化する。もちろん、虚構のレベルの多重化とはシャヴィエルと「僕」の関係、そして最終章で明かされる「僕」の小説のことであり、これらの(一見ごく単純な)仕掛けによって、この小説はメビウスの輪のような不思議な構造を持つことになる。
(さらに次回へ続く)
本書は主人公である「僕」のインドへの旅行記の形式をとっており、12章から構成されている。「僕」は一人で都市から都市へと旅し、ホテルを渡り歩き、他の旅行者やインドの人々と出会う。「僕」が出会った人物があとで再び登場することはない。つまり、一つの筋(アクション)が次の結果に繋がることで展開していく因果律型の小説ではなく、各章がそれぞれ別の話として独立しているエピソード羅列側の小説である。と同時に、失踪した友人の探索という旅行の目的が、それらのエピソード全体を束ねている。
では、それぞれのエピソードが一つの小さな物語として結構が整っているかというと、いささか曖昧である。最初の章で「僕」はあるみすぼらしいホテルに泊まり、失踪した友人の恋人だった娼婦と会い、彼女の話を聞く。この章の主たる構成要素は、「僕」が失踪した友人シャヴィエルを探しているという事実の披露と、娼婦とシャヴィエルの哀しい恋物語である。前者が本書全体のモチーフの紹介だとすれば、後者が本エピソードの主体ということになるだろう。が、主体であるはずの恋物語の全体像は、仄めかされているだけではなはだ曖昧である。「僕」は彼女から詳しい話を聴くのだが、その詳細は読者に対してまったく明かされない。タブッキはただこう書く。「長い、まわりくどい、ディテールに満ちた物語だった」
これが普通の小説なら、この「ディテールに満ちた物語」こそ、この章の中心となるだろう。しかしそれが省かれているため、このエピソードは断片的で、単独では完結していない印象を与える。単なるプロローグのような、ちょっとした脇道という感じを受ける。ところが読み進めると分かるのだが、本書ではどういうわけか、どの章もこれと同じような印象を与えるのだ。何か豊穣な物語への単なるプロローグのような、ちょっとした脇道のような、そんなエピソードの連なりで本書は成り立っているのである。
つまりタブッキが呈示する断章は、それ自体が物語として閉じるのではなく、常にそこに書かれていない物語、いわば小説の枠の外にあるものへと読者を誘うベクトルを持っている。枠の外に何があるのか? 何もない。しかし、読者はあるように錯覚する。これが「文学的詐術」だ。そしてこの錯覚は、筒井康隆が驚きをもって体験したように、場合によっては作品そのものよりも大きな感動を与え得る。なぜなら読者の想像力に限界はない。紙に書かれてしまった小説作品よりも常に大きく膨らむ可能性を持っているし、時間とともに変化する柔軟性も持っている。
言葉を変えれば、本書の章の一つ一つは物語そのものではなく、物語の萌芽(もしくはそれに似た何か)だと言える。シャヴィエルと娼婦がどんな恋愛をしたかは明らかにせず、ただ「ディテールに満ちた物語だった」と書くことで、読者にそれをおぼろげに想像するように仕向ける。このような、枠の外にあるものへの誘いは、タブッキが各章に埋め込んだごく小さな種によって動き出す。「動き出す」という言葉が強すぎるなら、ほのかに香ってくる、と言ってもいい。本書の場合、それらの「種」の多くは幻想的な、あるいは幻覚的な、何かしら神秘的なものを暗示するモチーフとなっている。たとえば病院のベッドに横たわる巨大なペニスをもった老人。あるいは夜のバス停で出会う、猿のような畸形の予言者。夜汽車で出会った乗客が彼に告げる、肉体は鞄のようなもの、という言葉。あるいは海辺で出会うアメリカ人青年が語る、フィラデルフィアの街中で見た、あり得ない海。
これらの「種」はさほど掘り下げられることなく、ほんの一瞬、読者の眼前にひらめいては消えていく。その手さばきは非常に淡々としていて、実にさりげない。これらのひらめきを宝石を拾うように拾っていくことが、本書を読む悦びの一つである。
それからこの小説全体を通して、読者は「僕」が世界を眺める視点を共有することになるが、それは私たちの日常的な視点とは異なっている。もちろん、これはどんな小説でも多かれ少なかれそうなのだが、タブッキにおいて特筆すべきは、その視点における記憶と夢と現実の不思議なつながりであり、混淆である。娼婦が語るシャヴィエルとの恋物語は、彼女が記憶の中から取捨選択して作り上げた物語である。彼女は現実だと思っているが、実は現実ではない。また「僕」はシャヴィエルの顔立ちを聞かれた時に答えられず、思い出は描写できない、と奇妙な言葉を呟く。あるいはホテルの部屋で目を閉じた「僕」は、たちまち記憶の中の「丘」に「到着」し、そこでイザベルやマグダとピクニックをする。
イザベル、マグダは「僕」と非常にパーソナルな、そしてインティメートな絆を持つ女性たちである。少なくとも、そう推測される。この小説の中で「僕」はマグダに手紙を書き、それが実はイザベルに宛てた手紙だったことに気づく、という場面がある。しかし、この二人と「僕」の過去の物語は完全にこの小説の枠の外にある。それは確実にそこに存在するが、読者にそれを知るすべはない。ただその不在の物語が発する詩的な香気は、「僕」の記憶を通じて、たえずこの『インド夜想曲』という小説の中に流れ込み続ける。
旅行記という体裁も実にタブッキ的で、まさにタブッキ文学のために存在するような形式だと思う。まず重要なのは旅の一過性であり、エピソード性である。先に書いた通り、「僕」が出会う人々や事件は一度だけ物語にかかわった後は過ぎ去っていき、二度と戻ってこない。プロットは因果律型ではなくエピソード羅列的であり、シンプルに直線的である。タブッキの長編小説にはこのようなスタイルのものが多いが、本書では旅行記であることがその構造をより明確にしている。
ちなみに因果律型ではないという点はタブッキの小説全般の特徴で、伏線があり意外な展開があり、という通常の物語の組み立てはほとんど見られない。通常の小説、特にエンタメ小説では因果律の支配力がより強くなる傾向があり、「伏線がきちんと回収されるかどうか」というような読み方などその最たるものだ。従って通常、虚構の物語は現実よりもはるかに因果律に依存することになる。しかし、タブッキの小説はその印象がきわめて薄い。エピソード間の関係性も緩く、風通しが良い。タブッキの小説では因果律の支配力が弱いのである。
では、その結果プロットが単調になり、退屈になるかというと、そんなことはない。本書もそうだが、フィクションの構造はむしろ複雑であり、重層的だ。ただしその重層性はプロットを込み入らせることによってではなく、虚構のレベルの多重化という、メタフィクショナルな方法で成し遂げられている。その結果、プロットのシンプルさと風通しのよさはそのままに、作品世界が深化する。もちろん、虚構のレベルの多重化とはシャヴィエルと「僕」の関係、そして最終章で明かされる「僕」の小説のことであり、これらの(一見ごく単純な)仕掛けによって、この小説はメビウスの輪のような不思議な構造を持つことになる。
(さらに次回へ続く)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます