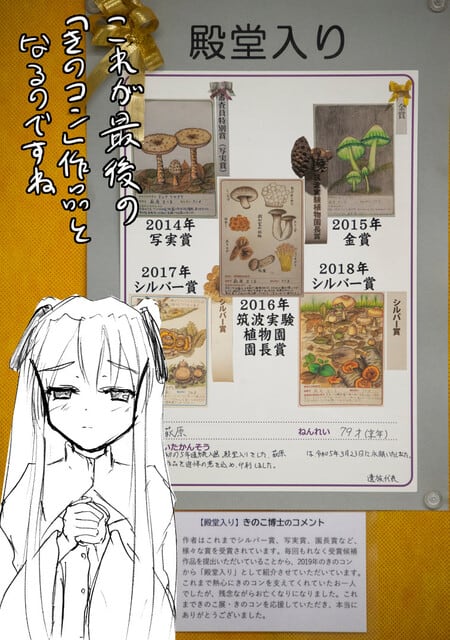昨日から仕事始めになられた方もおられるようで、だんだんと世間はお正月が終わってきたようですね。
「国立科学博物館 筑波実験植物園」も本日から開園ですよ。そして運よく非番でしたので、行ってきました「初筑波実験植物園」に。
「上野本館」の初開館は開館前から100名近くが居ましたが、今の時期という事もあるんでしょうかね。開園時間5分前に到着したのですが、私以外はいませんでしたね…。思わず受付の方と「誰もいませんね~」なんて話ちゃいましたよ。まぁその後、10時半くらいから結構人が入ってきていましたが。
コロナ禍明けでしたので何かイベントはあるかな?と思ったのですが、こちらも「上野本館」と同じく、何もお正月イベントはありませんでしたね。
でも、「冬咲き」の「クレマチス」である「ナパウレンシス」が年始くらいに咲き始めたようで、今日もまだ見れるという事もあり、臨時で「クレマチス園」が「ナパウレンシス」の所だけ見れるようになっています。
この「ナパウレンシス」はシルホサ系のクレマチスでして、ヒマラヤ東部から中国南西部に自生しているようで、夏は休眠し冬に咲くとのこと。花色は「帯緑乳白色」で小さめ。「カザグルマ」のような咲き方とは違うクレマチスなのです。どうやら例年よりも早く咲いたようで、まだ数週間は花を見る事はできるようですよ。
そして、こちらは昨年から見る事ができていました「ショクダイオオコンニャク」の「実」。昨年の5月20日に開花した後、結実し。いつからかは覚えていませんが、9月くらいからだと思いましたケド、「実」を見る事ができまして、それがどうやら今月いっぱいくらいまでが見れるようだ。との事。
私は何度か見ていますが、今回の結実では最後かも。と思いこちらも見てきました。
「花」は見る機会がありますが、「実」は今回初めて見たいですので、ある意味「花」よりも見る事はレアらしいですよ。
確かに今の時期、植物園はさみしい状態ですが、それでも「冬の森」の独特な感じを味わう事はできますので、寒いながらもそれなりに楽しむ事はできますよ。
それでは、本日の登場人物は「植物園関係」で登場している事が多いこの方、「命を見守り見届ける者」として「命の女神」の任に就いている「天元界 生物運脈省 霊魂運命監査室 霊魂運命監査室長」の「アルセレート・エリクス・エフォナー」さんです。今年の初植物園では「クレマチス・ナパウレンシス」と「ショクダイオオコンニャクの実」を見る事ができますよ。ちなみに背景が本日の「クレマチス・ナパウレンシス」と「ショクダイオオコンニャクの実」なのです。