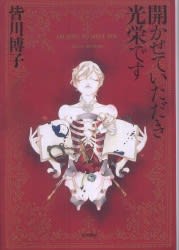『東京プレイボーイクラブ』を渋谷ユーロスペースで見ました。
(1)この映画は、ユーロスペースのHPに、「極めて個性的な新人監督のデビュー作の主演に、日本を代表する俳優が名乗りをあげた。いま、最も実力と人気を兼ね備える大森南朋」とか、「久々に大物新人監督、日本に現る!1986年生まれという、世界的にも最年少監督と言える若さで異例の注目を集める男の名は、奥田庸介」とまで述べられていたので、それなら見てみるかという気になって、映画館に足を運びました。
物語は、地方の自動車解体工場で働いていた勝利(大森南朋)が、傷害事件(注1)を起こしてそこにいられなくなり、昔面倒を見たことのある成吉(光石研)を頼って東京に出てきます。成吉は、場末の飲み屋街で実に物寂しいサロン「東京プレイボーイクラブ」を営んでいるところ(注2)、少ない売上げでもこうして店を経営できていることに満足している様子。
そんなところに流れ込んできた勝利ですが、その店を取り巻く状況を理解せずに、地元のチンピラ梅造(三浦貴大)らと暴力沙汰を起こしてしまいます(注3)。
さらには、店で働く従業員・貴弘(淵上泰史)が店の金を持ち逃げしたりと、成吉の店では立て続けに事件が起こるようになり、あげくは、ヤクザの仲間(梅造はヤクザ三兄弟の一番下なのです)がオトシマエをつけろと成吉を脅しにかかります。

さあ、勝利、成吉らはどうなるのでしょうか、……?
勝利役の大森南朋は、舞踏家・麿赤児の息子で、このところ色々な映画に登場するものの、はたして「日本を代表する俳優」とまでいえるかどうか、この作品でも随分と頑張っていますが、「日本を代表する俳優」の役所広司などと比べたらマダマダではないかという気がします(この作品で大森が扮する勝利は、『軽蔑』における山畑―主人公カズの幼馴染の金貸し―に類似している雰囲気を持っているように思います)。

また、成吉役の光石研も、『シャッフル』では刑事役、『あぜ道のダンディ』では頑張り屋の中年お父さん役、『マザーウォーター』ではお風呂屋の主人と、出る映画の度にめまぐるしく役どころを変えていますが、さすがに演技力はしたたかで、本作においても、寂れたサロンのオーナーという役柄を、これ以上はない的確さで演じきっています。
さらに、監督の奥田庸介氏は若干25歳で、そうなら『キツツキと雨』に登場する監督(小栗旬)に設定されている年齢と同じで、シンクロしているところが面白なと思いました(『川の底からこんにちは』の石井裕也監督よりも若干若くなります)。
むろん、若いから良いというわけではないところ、奥田監督は、この作品で脚本まで手がけていて、随分と将来が期待されると思いました。
なお、本作品には、『キツツキと雨』で、映画『UTOPIA』のヒロイン役を演じていた臼田あさ美がエリ子(サロン従業員・貴弘の彼女)に扮して登場していて、そういう点でも興味を惹かれました。

また、『麒麟の翼』に出演していた三浦貴大は、今度はチンピラの梅造の役(奥田監督と同じ年格好)ですが、まあ大きな声を張り上げればヤクザになるというものでもないよ、と言いたくなりますが、こういう役もこなしながら次第に実力を付けていくのでしょう。
(2)公式サイトのIntroductionでは、「既成のジャンル定義に収まらない新しいアジアン・ノワールを創出した」とか、「絶妙な笑いのセンスでユーモラスに描き出す」などといった言葉が踊っています。
確かに、思いがけないところで、観客の笑いを誘うようなシーンが挟み込まれています。ですが、映画全体に与える効果は、果たしてどんなもんでしょう?
例えば、ヤクザ三兄弟の一番上の松ノ介(佐藤佐吉)をエリ子が誤って感電死させてしまい、その事後処理として、勝利が、松ノ介の死体を鋸で切り刻んだ後、ビニール袋に入れて川に捨てようとしたところ、その内の一つが橋脚に引っかかってしまい、結局、車に積んであった成吉のゴルフクラブで下に突き落とすことになります。
凄惨なシーンの後のユーモアといったところかもしれないとはいえ、なんだかとってつけたような感じがしてしまいます。
というのも、実際には勝利は、鋸を手にしてエプロン姿にはなるものの、鋸の音がするだけで、死体を切り刻んでいる映像は映し出されないのです。こうなると、『冷たい熱帯魚』を見ている観客にとっては、随分と微温的な描き方に思えてしまい、Intoruductionが強調する「激しさ、毒、バイオレンス」は言葉だけなの、ナンテ言ってみたくなってしまいます(元々、大森南朋に「でんでん」の凄さを求めるのは難しいところですが)。
そして、肝心の場面が外されていることによって、エプロンを着用した勝利の姿とか、引っかかったビニール袋をゴルフのクラブで下に落とそうとしている勝利の格好が、映画全体の流れから浮き上がってしまっているような感じを受けてしまいます。
さらには、ヤクザ三兄弟の二番目の・竹男(赤堀雅秋)が、勝利を狙って拳銃の引き金を引くものの、それまで銃など持ったこともなかったのでしょうか、銃弾は大きく逸れて一番下の梅造にあたってしまいます。かと思うと、首を撃たれて瀕死のはずの梅造が、その拳銃を手にして打った弾が、あろうことか今度は、勝利と一緒に部屋を出ようとするエリ子の背中に正確に命中してしまうのです!
ここらあたりもユーモアといえばユーモアかもしれませんが、実のところはストーリーの展開上からそうしてあるようにも思えてしまいます(注4)。
奥田監督はまだ25歳と年若いのですから、そんなに周囲が騒ぎ立てることもないのではないか、実際とは離れたプレイアップをしすぎると、見ている方が引いてしまいかねないのではないか、と思われるのですが(尤も、過剰なPRがあったからこそ、クマネズミも映画館に足を向けたことは否定しませんが)。
とはいえ、劇場用パンフレットに掲載されている監督インタビューによれば、「そもそも『東京PBC』は、この曲にインスパイアされて生まれた物語」ということもあって、エンディングに流れるエレファントカシマシの「パワー・イン・ザ・ワールド」の迫力たるや物凄く、この曲を聴けただけでも儲け物といった感じになります。
(3)映画監督のいまおかしんじ氏は、雑誌『映画芸術』の2012年冬号に掲載された「おめでとう」と題するエッセイにおいて、「ウソをつきたくないという監督の映画に対する誠意を感じる」、「この映画の随所にある〝笑い〟は時として、ゾッとする残酷さを強調することにもなる。これはウソだけどウソじゃないんだよ。そう思わされるリアリティがこの映画を豊かなモノにしている」、「笑いと残酷さを同居させることによって、観客に強いインパクトを与えようとしているのだと思う」などと述べています。
(注1)勝利は、自動車解体作業の音が煩いと抗議に来た浪人生を、問答無用とばかりスパナで殴り倒してしまいます。このシーンによって、勝利は、カッとすると何をするか分からない喧嘩早い男との性格付けがなされます。
(注2)店にいる女の子たちは、店がヒマなので、四六時中つまらないお喋りばかりしています。実にくだらない内容ながらも、そうしたシーンを映画の中に取り入れたことは多とするものの、時折彼女たちのお喋りを途中カットしたことがあからさまになる編集の仕方をしているのは、監督の意図の中途半端さを考えざるを得ないところです。
(注3)飲み屋のトイレでチンピラの梅造は、勝利に対して、「見られていたら出ねえじゃないか!」と難癖を付けますが、逆に勝利にボコボコにされてしまいます。その梅造を連れた二番目の兄(ヤクザの三兄弟がここらあたりを取り仕切っています)は、「俺たちを敵に回して、この街で生きていけると思うなよ」と捨て台詞を吐いて、飲み屋から出て行きます。コレを見て、成吉は大いに驚き、勝利に対して、「やったらめったら喧嘩をするな。俺たちみたいな余所者が東京で生活していくのは大変なんだ」などと言って、地元のルールに従うようたしなめます。しかしながら、その飲み屋を出た勝利は、ソコにいた二番目の兄を「田舎者で悪かったな」と殴り倒してしまいます。
こうした経緯があるところから、ヤクザ三兄弟が成吉のところに乗り込んで来るわけです。
(注4)というのも、ラストでエンディングの曲が流れるまでのところが、なかなか良く作り込まれていますから。
すなわち、成吉のサロンに車で戻る途中、エリ子の話(「もし人生をやり直せたらと思いません?」、「モット勉強して、学校へ行っていたら、別だったのに」)を聞くうちに、勝利は、彼女と二人でここをオサラバしようと思ったのでしょうか、その後で、ピストルで撃たれて虫の息のエリ子を車に乗せて運転しながら、思うようにならない世の中を打ち壊そうとするかのように、「ワォー」と何回も咆吼し、そしてエンディングの曲が実に格好良く流れてくるのです(パワー・イン・ザ・ワールド エレファントカシマシ 歌詞情報 - goo 音楽)。
★★★☆☆
象のロケット:東京プレイボーイクラブ
(1)この映画は、ユーロスペースのHPに、「極めて個性的な新人監督のデビュー作の主演に、日本を代表する俳優が名乗りをあげた。いま、最も実力と人気を兼ね備える大森南朋」とか、「久々に大物新人監督、日本に現る!1986年生まれという、世界的にも最年少監督と言える若さで異例の注目を集める男の名は、奥田庸介」とまで述べられていたので、それなら見てみるかという気になって、映画館に足を運びました。
物語は、地方の自動車解体工場で働いていた勝利(大森南朋)が、傷害事件(注1)を起こしてそこにいられなくなり、昔面倒を見たことのある成吉(光石研)を頼って東京に出てきます。成吉は、場末の飲み屋街で実に物寂しいサロン「東京プレイボーイクラブ」を営んでいるところ(注2)、少ない売上げでもこうして店を経営できていることに満足している様子。
そんなところに流れ込んできた勝利ですが、その店を取り巻く状況を理解せずに、地元のチンピラ梅造(三浦貴大)らと暴力沙汰を起こしてしまいます(注3)。
さらには、店で働く従業員・貴弘(淵上泰史)が店の金を持ち逃げしたりと、成吉の店では立て続けに事件が起こるようになり、あげくは、ヤクザの仲間(梅造はヤクザ三兄弟の一番下なのです)がオトシマエをつけろと成吉を脅しにかかります。

さあ、勝利、成吉らはどうなるのでしょうか、……?
勝利役の大森南朋は、舞踏家・麿赤児の息子で、このところ色々な映画に登場するものの、はたして「日本を代表する俳優」とまでいえるかどうか、この作品でも随分と頑張っていますが、「日本を代表する俳優」の役所広司などと比べたらマダマダではないかという気がします(この作品で大森が扮する勝利は、『軽蔑』における山畑―主人公カズの幼馴染の金貸し―に類似している雰囲気を持っているように思います)。

また、成吉役の光石研も、『シャッフル』では刑事役、『あぜ道のダンディ』では頑張り屋の中年お父さん役、『マザーウォーター』ではお風呂屋の主人と、出る映画の度にめまぐるしく役どころを変えていますが、さすがに演技力はしたたかで、本作においても、寂れたサロンのオーナーという役柄を、これ以上はない的確さで演じきっています。
さらに、監督の奥田庸介氏は若干25歳で、そうなら『キツツキと雨』に登場する監督(小栗旬)に設定されている年齢と同じで、シンクロしているところが面白なと思いました(『川の底からこんにちは』の石井裕也監督よりも若干若くなります)。
むろん、若いから良いというわけではないところ、奥田監督は、この作品で脚本まで手がけていて、随分と将来が期待されると思いました。
なお、本作品には、『キツツキと雨』で、映画『UTOPIA』のヒロイン役を演じていた臼田あさ美がエリ子(サロン従業員・貴弘の彼女)に扮して登場していて、そういう点でも興味を惹かれました。

また、『麒麟の翼』に出演していた三浦貴大は、今度はチンピラの梅造の役(奥田監督と同じ年格好)ですが、まあ大きな声を張り上げればヤクザになるというものでもないよ、と言いたくなりますが、こういう役もこなしながら次第に実力を付けていくのでしょう。
(2)公式サイトのIntroductionでは、「既成のジャンル定義に収まらない新しいアジアン・ノワールを創出した」とか、「絶妙な笑いのセンスでユーモラスに描き出す」などといった言葉が踊っています。
確かに、思いがけないところで、観客の笑いを誘うようなシーンが挟み込まれています。ですが、映画全体に与える効果は、果たしてどんなもんでしょう?
例えば、ヤクザ三兄弟の一番上の松ノ介(佐藤佐吉)をエリ子が誤って感電死させてしまい、その事後処理として、勝利が、松ノ介の死体を鋸で切り刻んだ後、ビニール袋に入れて川に捨てようとしたところ、その内の一つが橋脚に引っかかってしまい、結局、車に積んであった成吉のゴルフクラブで下に突き落とすことになります。
凄惨なシーンの後のユーモアといったところかもしれないとはいえ、なんだかとってつけたような感じがしてしまいます。
というのも、実際には勝利は、鋸を手にしてエプロン姿にはなるものの、鋸の音がするだけで、死体を切り刻んでいる映像は映し出されないのです。こうなると、『冷たい熱帯魚』を見ている観客にとっては、随分と微温的な描き方に思えてしまい、Intoruductionが強調する「激しさ、毒、バイオレンス」は言葉だけなの、ナンテ言ってみたくなってしまいます(元々、大森南朋に「でんでん」の凄さを求めるのは難しいところですが)。
そして、肝心の場面が外されていることによって、エプロンを着用した勝利の姿とか、引っかかったビニール袋をゴルフのクラブで下に落とそうとしている勝利の格好が、映画全体の流れから浮き上がってしまっているような感じを受けてしまいます。
さらには、ヤクザ三兄弟の二番目の・竹男(赤堀雅秋)が、勝利を狙って拳銃の引き金を引くものの、それまで銃など持ったこともなかったのでしょうか、銃弾は大きく逸れて一番下の梅造にあたってしまいます。かと思うと、首を撃たれて瀕死のはずの梅造が、その拳銃を手にして打った弾が、あろうことか今度は、勝利と一緒に部屋を出ようとするエリ子の背中に正確に命中してしまうのです!
ここらあたりもユーモアといえばユーモアかもしれませんが、実のところはストーリーの展開上からそうしてあるようにも思えてしまいます(注4)。
奥田監督はまだ25歳と年若いのですから、そんなに周囲が騒ぎ立てることもないのではないか、実際とは離れたプレイアップをしすぎると、見ている方が引いてしまいかねないのではないか、と思われるのですが(尤も、過剰なPRがあったからこそ、クマネズミも映画館に足を向けたことは否定しませんが)。
とはいえ、劇場用パンフレットに掲載されている監督インタビューによれば、「そもそも『東京PBC』は、この曲にインスパイアされて生まれた物語」ということもあって、エンディングに流れるエレファントカシマシの「パワー・イン・ザ・ワールド」の迫力たるや物凄く、この曲を聴けただけでも儲け物といった感じになります。
(3)映画監督のいまおかしんじ氏は、雑誌『映画芸術』の2012年冬号に掲載された「おめでとう」と題するエッセイにおいて、「ウソをつきたくないという監督の映画に対する誠意を感じる」、「この映画の随所にある〝笑い〟は時として、ゾッとする残酷さを強調することにもなる。これはウソだけどウソじゃないんだよ。そう思わされるリアリティがこの映画を豊かなモノにしている」、「笑いと残酷さを同居させることによって、観客に強いインパクトを与えようとしているのだと思う」などと述べています。
(注1)勝利は、自動車解体作業の音が煩いと抗議に来た浪人生を、問答無用とばかりスパナで殴り倒してしまいます。このシーンによって、勝利は、カッとすると何をするか分からない喧嘩早い男との性格付けがなされます。
(注2)店にいる女の子たちは、店がヒマなので、四六時中つまらないお喋りばかりしています。実にくだらない内容ながらも、そうしたシーンを映画の中に取り入れたことは多とするものの、時折彼女たちのお喋りを途中カットしたことがあからさまになる編集の仕方をしているのは、監督の意図の中途半端さを考えざるを得ないところです。
(注3)飲み屋のトイレでチンピラの梅造は、勝利に対して、「見られていたら出ねえじゃないか!」と難癖を付けますが、逆に勝利にボコボコにされてしまいます。その梅造を連れた二番目の兄(ヤクザの三兄弟がここらあたりを取り仕切っています)は、「俺たちを敵に回して、この街で生きていけると思うなよ」と捨て台詞を吐いて、飲み屋から出て行きます。コレを見て、成吉は大いに驚き、勝利に対して、「やったらめったら喧嘩をするな。俺たちみたいな余所者が東京で生活していくのは大変なんだ」などと言って、地元のルールに従うようたしなめます。しかしながら、その飲み屋を出た勝利は、ソコにいた二番目の兄を「田舎者で悪かったな」と殴り倒してしまいます。
こうした経緯があるところから、ヤクザ三兄弟が成吉のところに乗り込んで来るわけです。
(注4)というのも、ラストでエンディングの曲が流れるまでのところが、なかなか良く作り込まれていますから。
すなわち、成吉のサロンに車で戻る途中、エリ子の話(「もし人生をやり直せたらと思いません?」、「モット勉強して、学校へ行っていたら、別だったのに」)を聞くうちに、勝利は、彼女と二人でここをオサラバしようと思ったのでしょうか、その後で、ピストルで撃たれて虫の息のエリ子を車に乗せて運転しながら、思うようにならない世の中を打ち壊そうとするかのように、「ワォー」と何回も咆吼し、そしてエンディングの曲が実に格好良く流れてくるのです(パワー・イン・ザ・ワールド エレファントカシマシ 歌詞情報 - goo 音楽)。
★★★☆☆
象のロケット:東京プレイボーイクラブ