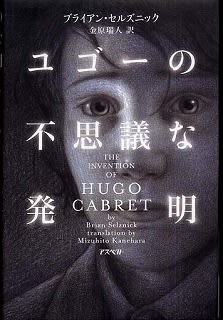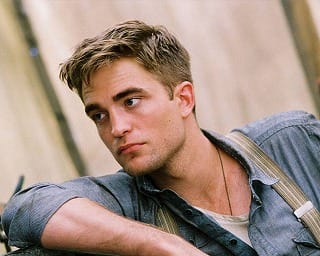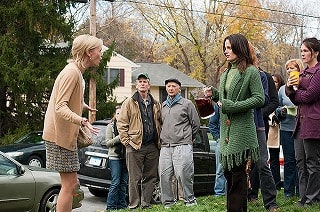『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』をTOHOシネマズ渋谷で見ました。
(1)クマネズミは、元来、伝記物は嫌いですが(取り上げる人物を美化するだけに終わってしまいますから)、この作品は、長年見続けてきているメリル・ストリープ(注1)がアカデミー賞主演女優賞(3回目!)を受けたということで、彼女を見ようと足を運んだ次第です。
そうしたところ、この作品における彼女の目を見張る演技には驚いてしまい、深く感動いたしました。
メリル・ストリープは現在62歳ですから、その25歳くらい上の老婦人のメイクをし、かつ演じるわけですが、とても演じているのが彼女とは思えないほど真に迫っているように思われました〔といって、その姿には何とも言えない気品が漂っていて、クマネズミの大嫌いな「ソックリさん」に堕していないのはさすがです(注2)〕。

さらに、本作は、通常の伝記物のように、幼少期から努力を重ね、遂には首相に上り詰め、そして引退する、といった成功譚を描く構成にはなっておりません。もちろん、数々のエピソードは描き出されはするものの通り一遍であり(注3)、終始、83歳の現在の時点にたちつつ、年老いて半ば認知症になっている女性(最近のことは忘れてしまっていても、過去のことは明瞭に覚えているようなのです)の視点から過去を振り返ります。
その際、すでに9年ほど前に亡くなった夫のデニス(ジム・ブロードベント)が幻覚となって彼女の周囲に出現し、彼女に話しかけます(注4)。

象徴的なのは本作の冒頭のシーンでしょう。警護の眼が離れている隙に、老いたマーガレット・サッチャーは、独りで外出してスーパーで牛乳を買ってくるのですが、戻ってきて夫と朝食を取ります。デニスがパンにバターを塗ると「too much butter」と注意しつつ、「今日は、牛乳が49ペンスと高かった」と報告するのです。そして、彼女が「節約しなくては」と言うと、夫は「車を売るとか、下宿人を置くとか」と答えますが、部屋の外で声がしてマーガレットがそちらの方に気を取られると、その隙に夫は消えてしまいます(注5)。
あるいは、こんなシーンがあります。
デニスの声がマーガレットに絶えず聞こえてくるものですから、ある時彼女は、家に置かれている音の出る器具のスイッチを全部入れ、なおかつそのボリュームを酷く上げてしまいます。こうすることでデニスの声が聞こえなくなると、マーガレットは、「私は正常」と呟きます。
そして、ラスト近くのシーンでマーガレットは、デニスの靴や服を黒いビニール袋にすべて放り込み、さらにトランクにも服などを入れて、「あなたのトランクに全部詰めたわ」と言うと、デニスはそのトランクを持ってドアから出て行ってしまいます。それを見たマーガレットは、慌てて「行かないで、私を独りぼっちにしないで」と懇願しますが、デニスは「大丈夫だよ、君は一人で生きていける」と言いつつ消え去ってしまいます(注6)。
要するに、登場人物や舞台となる家などの雰囲気は頗るリアルなタッチで描かれているのですが、構成は随分とファンタジック〔和製英語のようです(注7)〕なものとなっているわけです(注8)。
さらに、マーガレットには双子の子供がいて、娘キャロルは彼女の家によくやってきますが(注9)、頼りにしていた息子マイクの方は一家で南アフリカにいて、顔を出すことがありません。夫に死なれ息子にも見放された一人の老婦人の孤独な姿が執拗に描き出され、これではトテモ伝記物とはいえないのではと思いました。
本作は、マーガレット・サッチャーという超有名人の場を借りつつも(普通人を取り上げても物語になりませんから!)、現役から引退してかなりの日時が経過した人間が迎える有様(注10)をリアルかつファンタジックに描き出していて、クマネズミは、なかなか興味深く見終えることができました(注11)。
なお、本作の邦題は「鉄の女の涙」との副題が付いているところ(注12)、そしてデニスがトランクを手に提げて出て行ってしまうと、マーガレットの目から涙が流れ落ちますが、それはあの「鉄の女」と言われたサッチャー首相も家に戻れば普通の女だったという意味でのご大層な“涙”ではなく、単に夫ともう会えなくなってしまうことの寂しさからくる遺された妻の普通の“涙”ではないでしょうか?というのも、このときマーガレットは、首相を退いてから20年以上経過しているのですから。
(2)本作は、フーバーFBI長官を描いたクリント・イーストウッド監督の『J・エドガー』に類似しているといえるかもしれません。そこでも、フーバーFBI長官の事績を描くというよりもむしろ、その人間関係の方に焦点をあてているように思われましたし、それに、老齢のJ・エドガーが自叙伝を口述筆記させている時点から過去を振り返るという構成になっていましたから(注13)。
さらに、晩年になると、J・エドガーは、周囲の批判をものともせずに、従来の手法(政府要人の盗聴)に固執したところ、サッチャー首相も、与党内の根強い反対にもかかわらず人頭税などの政策遂行に邁進したがために辞任を余儀なくされます。
こうした映画の構成になっていることや、特にそれぞれの事績について映画で新しい解釈が提示されていないのも、もしかしたら、どちらも原作なしにいきなり脚本家が脚本を書き、それに従って映画が製作されているからではないかと思われます。
でも、『J・エドガー』では、エドガーを演じているディカプリオ(37歳)が前面に出てしまっている感じで、本作のように、メリル・ストリープが老いたマーガレットの後ろに隠れてしまうのとはレベルが違っている感じがしました(それは、二人の俳優としての年季とか力量の違いによるのかもしれません)(注14)。
なお、『J・エドガー』によれば、副長官のクライドが最後まで付き従っていたものの、J・エドガーは最後まで結婚しませんでした。本作におけるマーガレットも、結婚して子供はいましたが、愛する夫デニスに5年前に先立たれていますし、頼りにしていた息子は南アフリカに行ってしまいます。両作の主人公とも、家族の愛情という点では、寂しいものがあったといえるかもしれません。
(3)渡まち子氏は、「英国の経済を立て直しながら、格差社会を作った張本人。むしろ否定的なイメージが先行するサッチャーの政治的な立ち位置は、いずれ歴史が判断するだろうが、あらゆる困難に立ち向かった一人の女性の凛とした姿は、観る人すべての心に深く刻まれる」として70点をつけています。
他方、前田有一氏は、「すでに認知症になって表舞台に姿を見せない1人の女性に対し、その弱さを強調した物語化は、見ていていたたまれないものがあるし、個人的にはもっと政治家としての凄みを見たかった気がする」として45点しかつけていません。
なお、テーラー章子氏は、「鉄の女と呼ばれた元英国首相マーガレット・サッチャーをメリル・ストリープが演じた。声、発音、イントネーション、スピーチ、顔つき、歩き方やしぐさまで、全くそっくりで本人と見分けがつかない。これで、今年のアカデミー主演女優賞は決まりだ。ストリープが受賞するに違いない」として80点を付けています。
しかしながら、その映画評の大半を映画ではなくてサッチャー首相批判(そこから大きく現状批判まで発展します)に充てています。
例えば、サッチャーのような「保守派政治家が政権を取ると、いかに権力者、資本家、経営者が肥え太り、庶民が窮民に陥るかを絵に描いたように明確に見せてくれた首相は他に居ない」→「自由な市場に任せておけばすべての経済活動は解決するとし、「生産性に応じて報酬がもたらされる」と考える新自由主義は、2008年リーマン・ブラザーズの経営破綻が金融システム全体を崩壊させたように、理論的にも現実的にも破綻している」→「八方塞りの経済情勢のなかで、いまになって、やっぱりマーガレット・サッチャーが良かったみたいな、彼女のような強い指導力が再評価される流れが出てくるとしたら、それは間違いだ。彼女の時代を懐かしがるのは、余裕のある金融企業家や資本家だけで良い」などなど。
マア、映画を見て思い浮かんだことなら何を書いてもかまわないものの、こうした極めて政治色の強いプロパガンダめいた文章をこんな場で長々と書き記すことには問題があるのではと思われます。
それに、こうした日本でいえばいわゆる“小泉改革”批判は、現在マスコミや論断で一世風靡している感じですが、そんな右へ倣えの考え方をもってしては、到底現状の「八方塞りの経済情勢」を打破することが出来そうにもないことも明らかではないでしょうか?
(注1)最近では、『恋するベーカリー』、『ジュリー&ジュリア』、『ダウト』を見ています。
(注2)サッチャー首相とダンスをするレーガン大統領が登場しますが、短い時間でよかったと思います。
(注3)この点については、下記(3)で触れる前田有一氏が言うように、「イギリスの長い歴史の中で、サッチャー首相の統治時代は、稀に見るほど波乱万丈であった」のは確かでしょう。
例えば、フォークランド紛争(1982年)、IRAによる爆弾テロに遭遇(1984年)、ビッグバン(1986年)などなど。
とはいえ、これらの事柄に少しでも入り込もうとすれば、それぞれが一つの映画作品(まずは大部の研究書でしょうか)になってもおかしくないくらいの出来事ですから、全体を見通す際には本作のように通り一遍片のものとなっても、それはそれで仕方のないところでしょう。
(注4)幽霊のように出現する夫デニスですが、マーガレット以外には誰も見えないのですから、彼女の幻覚ではないかと思われます。たとえば、こうしたサイトの記事を見ると、認知症に幻覚が伴う場合がかなり見られるようです(ただ、劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「亡霊」とされていますが)。
(注5)マーガレットが一人で外出したのを見逃したことを警護の警察官同士で咎め立てしている声のようです(また、「薬で、1時間ほど頭がスッキリするんだ」などと言ったりもています)。
(注6)これでマーガレットの病気が治るわけでもなく(だいたい、デニスは靴を履いていないのです!)、その日のスケジュール(彼女の肖像画の除幕式)などすっかり忘れて、別の部屋に入っていきます(バッハの平均律曲集第1番が流れておしまいとなります)。
(注7)この点については、例えば、このサイトの記事を参照。
(注8)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「これは純粋に想像の産物です」と述べられています。
(注9)キャロル・サッチャーは、母親の行動について、こまごまとした注意をするものですから、マーガレットは嫌がっているようです。
冒頭シーンのあと、キャロルは「今日、外に出たの?一人で外に出ないでと言ったでしょ!」というと、マーガレットは、「牛乳を買うことぐらい出来る!あなたはいつもガミガミ言うだけ。他にやることないの?私はそんなことは言わなかった」と応じます。
また、キャロルは、マーガレットがスグに忘れてしまう現在の状況について、「マークは南アフリカよ、ママももう首相じゃない、そしてパパも亡くなった!」と言いますが、マーガレットは呆然としながらも、「あなたは疲れた顔をしている、もっとよく寝なくては」と答えます。
(注10)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「キャリアが終わって用済みにされ、老いに直面する私たちみんなの話でもある」と述べられています。
(注11)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「これが政治映画でないことはすぐにわかりました」と述べられていて、おそらくこの点が、映画におかまいなく自分の政治論を語ってしまうテーラー章子氏とは違って控えめ(?!)な下記(3)で触れる前田有一氏には不満だったのでしょう(大いに政治論を披歴すべく、手ぐすねひいて待ち構えていたに違いありません!)。
(注12)原題は『The Iron Lady』。
(注13)フーバー長官が亡くなったのは77歳で、本作のサッチャーが83歳とすれば、両者に5歳ほどの差があるものの、ほぼ同年齢のところから過去を振り返っているといえると思われます。
(注14)ディカプリオとストリープとは25歳ほどの開きがあります。
★★★★☆
象のロケット:マーガレット・サッチャー
(1)クマネズミは、元来、伝記物は嫌いですが(取り上げる人物を美化するだけに終わってしまいますから)、この作品は、長年見続けてきているメリル・ストリープ(注1)がアカデミー賞主演女優賞(3回目!)を受けたということで、彼女を見ようと足を運んだ次第です。
そうしたところ、この作品における彼女の目を見張る演技には驚いてしまい、深く感動いたしました。
メリル・ストリープは現在62歳ですから、その25歳くらい上の老婦人のメイクをし、かつ演じるわけですが、とても演じているのが彼女とは思えないほど真に迫っているように思われました〔といって、その姿には何とも言えない気品が漂っていて、クマネズミの大嫌いな「ソックリさん」に堕していないのはさすがです(注2)〕。

さらに、本作は、通常の伝記物のように、幼少期から努力を重ね、遂には首相に上り詰め、そして引退する、といった成功譚を描く構成にはなっておりません。もちろん、数々のエピソードは描き出されはするものの通り一遍であり(注3)、終始、83歳の現在の時点にたちつつ、年老いて半ば認知症になっている女性(最近のことは忘れてしまっていても、過去のことは明瞭に覚えているようなのです)の視点から過去を振り返ります。
その際、すでに9年ほど前に亡くなった夫のデニス(ジム・ブロードベント)が幻覚となって彼女の周囲に出現し、彼女に話しかけます(注4)。

象徴的なのは本作の冒頭のシーンでしょう。警護の眼が離れている隙に、老いたマーガレット・サッチャーは、独りで外出してスーパーで牛乳を買ってくるのですが、戻ってきて夫と朝食を取ります。デニスがパンにバターを塗ると「too much butter」と注意しつつ、「今日は、牛乳が49ペンスと高かった」と報告するのです。そして、彼女が「節約しなくては」と言うと、夫は「車を売るとか、下宿人を置くとか」と答えますが、部屋の外で声がしてマーガレットがそちらの方に気を取られると、その隙に夫は消えてしまいます(注5)。
あるいは、こんなシーンがあります。
デニスの声がマーガレットに絶えず聞こえてくるものですから、ある時彼女は、家に置かれている音の出る器具のスイッチを全部入れ、なおかつそのボリュームを酷く上げてしまいます。こうすることでデニスの声が聞こえなくなると、マーガレットは、「私は正常」と呟きます。
そして、ラスト近くのシーンでマーガレットは、デニスの靴や服を黒いビニール袋にすべて放り込み、さらにトランクにも服などを入れて、「あなたのトランクに全部詰めたわ」と言うと、デニスはそのトランクを持ってドアから出て行ってしまいます。それを見たマーガレットは、慌てて「行かないで、私を独りぼっちにしないで」と懇願しますが、デニスは「大丈夫だよ、君は一人で生きていける」と言いつつ消え去ってしまいます(注6)。
要するに、登場人物や舞台となる家などの雰囲気は頗るリアルなタッチで描かれているのですが、構成は随分とファンタジック〔和製英語のようです(注7)〕なものとなっているわけです(注8)。
さらに、マーガレットには双子の子供がいて、娘キャロルは彼女の家によくやってきますが(注9)、頼りにしていた息子マイクの方は一家で南アフリカにいて、顔を出すことがありません。夫に死なれ息子にも見放された一人の老婦人の孤独な姿が執拗に描き出され、これではトテモ伝記物とはいえないのではと思いました。
本作は、マーガレット・サッチャーという超有名人の場を借りつつも(普通人を取り上げても物語になりませんから!)、現役から引退してかなりの日時が経過した人間が迎える有様(注10)をリアルかつファンタジックに描き出していて、クマネズミは、なかなか興味深く見終えることができました(注11)。
なお、本作の邦題は「鉄の女の涙」との副題が付いているところ(注12)、そしてデニスがトランクを手に提げて出て行ってしまうと、マーガレットの目から涙が流れ落ちますが、それはあの「鉄の女」と言われたサッチャー首相も家に戻れば普通の女だったという意味でのご大層な“涙”ではなく、単に夫ともう会えなくなってしまうことの寂しさからくる遺された妻の普通の“涙”ではないでしょうか?というのも、このときマーガレットは、首相を退いてから20年以上経過しているのですから。
(2)本作は、フーバーFBI長官を描いたクリント・イーストウッド監督の『J・エドガー』に類似しているといえるかもしれません。そこでも、フーバーFBI長官の事績を描くというよりもむしろ、その人間関係の方に焦点をあてているように思われましたし、それに、老齢のJ・エドガーが自叙伝を口述筆記させている時点から過去を振り返るという構成になっていましたから(注13)。
さらに、晩年になると、J・エドガーは、周囲の批判をものともせずに、従来の手法(政府要人の盗聴)に固執したところ、サッチャー首相も、与党内の根強い反対にもかかわらず人頭税などの政策遂行に邁進したがために辞任を余儀なくされます。
こうした映画の構成になっていることや、特にそれぞれの事績について映画で新しい解釈が提示されていないのも、もしかしたら、どちらも原作なしにいきなり脚本家が脚本を書き、それに従って映画が製作されているからではないかと思われます。
でも、『J・エドガー』では、エドガーを演じているディカプリオ(37歳)が前面に出てしまっている感じで、本作のように、メリル・ストリープが老いたマーガレットの後ろに隠れてしまうのとはレベルが違っている感じがしました(それは、二人の俳優としての年季とか力量の違いによるのかもしれません)(注14)。
なお、『J・エドガー』によれば、副長官のクライドが最後まで付き従っていたものの、J・エドガーは最後まで結婚しませんでした。本作におけるマーガレットも、結婚して子供はいましたが、愛する夫デニスに5年前に先立たれていますし、頼りにしていた息子は南アフリカに行ってしまいます。両作の主人公とも、家族の愛情という点では、寂しいものがあったといえるかもしれません。
(3)渡まち子氏は、「英国の経済を立て直しながら、格差社会を作った張本人。むしろ否定的なイメージが先行するサッチャーの政治的な立ち位置は、いずれ歴史が判断するだろうが、あらゆる困難に立ち向かった一人の女性の凛とした姿は、観る人すべての心に深く刻まれる」として70点をつけています。
他方、前田有一氏は、「すでに認知症になって表舞台に姿を見せない1人の女性に対し、その弱さを強調した物語化は、見ていていたたまれないものがあるし、個人的にはもっと政治家としての凄みを見たかった気がする」として45点しかつけていません。
なお、テーラー章子氏は、「鉄の女と呼ばれた元英国首相マーガレット・サッチャーをメリル・ストリープが演じた。声、発音、イントネーション、スピーチ、顔つき、歩き方やしぐさまで、全くそっくりで本人と見分けがつかない。これで、今年のアカデミー主演女優賞は決まりだ。ストリープが受賞するに違いない」として80点を付けています。
しかしながら、その映画評の大半を映画ではなくてサッチャー首相批判(そこから大きく現状批判まで発展します)に充てています。
例えば、サッチャーのような「保守派政治家が政権を取ると、いかに権力者、資本家、経営者が肥え太り、庶民が窮民に陥るかを絵に描いたように明確に見せてくれた首相は他に居ない」→「自由な市場に任せておけばすべての経済活動は解決するとし、「生産性に応じて報酬がもたらされる」と考える新自由主義は、2008年リーマン・ブラザーズの経営破綻が金融システム全体を崩壊させたように、理論的にも現実的にも破綻している」→「八方塞りの経済情勢のなかで、いまになって、やっぱりマーガレット・サッチャーが良かったみたいな、彼女のような強い指導力が再評価される流れが出てくるとしたら、それは間違いだ。彼女の時代を懐かしがるのは、余裕のある金融企業家や資本家だけで良い」などなど。
マア、映画を見て思い浮かんだことなら何を書いてもかまわないものの、こうした極めて政治色の強いプロパガンダめいた文章をこんな場で長々と書き記すことには問題があるのではと思われます。
それに、こうした日本でいえばいわゆる“小泉改革”批判は、現在マスコミや論断で一世風靡している感じですが、そんな右へ倣えの考え方をもってしては、到底現状の「八方塞りの経済情勢」を打破することが出来そうにもないことも明らかではないでしょうか?
(注1)最近では、『恋するベーカリー』、『ジュリー&ジュリア』、『ダウト』を見ています。
(注2)サッチャー首相とダンスをするレーガン大統領が登場しますが、短い時間でよかったと思います。
(注3)この点については、下記(3)で触れる前田有一氏が言うように、「イギリスの長い歴史の中で、サッチャー首相の統治時代は、稀に見るほど波乱万丈であった」のは確かでしょう。
例えば、フォークランド紛争(1982年)、IRAによる爆弾テロに遭遇(1984年)、ビッグバン(1986年)などなど。
とはいえ、これらの事柄に少しでも入り込もうとすれば、それぞれが一つの映画作品(まずは大部の研究書でしょうか)になってもおかしくないくらいの出来事ですから、全体を見通す際には本作のように通り一遍片のものとなっても、それはそれで仕方のないところでしょう。
(注4)幽霊のように出現する夫デニスですが、マーガレット以外には誰も見えないのですから、彼女の幻覚ではないかと思われます。たとえば、こうしたサイトの記事を見ると、認知症に幻覚が伴う場合がかなり見られるようです(ただ、劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「亡霊」とされていますが)。
(注5)マーガレットが一人で外出したのを見逃したことを警護の警察官同士で咎め立てしている声のようです(また、「薬で、1時間ほど頭がスッキリするんだ」などと言ったりもています)。
(注6)これでマーガレットの病気が治るわけでもなく(だいたい、デニスは靴を履いていないのです!)、その日のスケジュール(彼女の肖像画の除幕式)などすっかり忘れて、別の部屋に入っていきます(バッハの平均律曲集第1番が流れておしまいとなります)。
(注7)この点については、例えば、このサイトの記事を参照。
(注8)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「これは純粋に想像の産物です」と述べられています。
(注9)キャロル・サッチャーは、母親の行動について、こまごまとした注意をするものですから、マーガレットは嫌がっているようです。
冒頭シーンのあと、キャロルは「今日、外に出たの?一人で外に出ないでと言ったでしょ!」というと、マーガレットは、「牛乳を買うことぐらい出来る!あなたはいつもガミガミ言うだけ。他にやることないの?私はそんなことは言わなかった」と応じます。
また、キャロルは、マーガレットがスグに忘れてしまう現在の状況について、「マークは南アフリカよ、ママももう首相じゃない、そしてパパも亡くなった!」と言いますが、マーガレットは呆然としながらも、「あなたは疲れた顔をしている、もっとよく寝なくては」と答えます。
(注10)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「キャリアが終わって用済みにされ、老いに直面する私たちみんなの話でもある」と述べられています。
(注11)劇場用パンフレット掲載のフィリダ・ロイド監督インタビュー記事では、「これが政治映画でないことはすぐにわかりました」と述べられていて、おそらくこの点が、映画におかまいなく自分の政治論を語ってしまうテーラー章子氏とは違って控えめ(?!)な下記(3)で触れる前田有一氏には不満だったのでしょう(大いに政治論を披歴すべく、手ぐすねひいて待ち構えていたに違いありません!)。
(注12)原題は『The Iron Lady』。
(注13)フーバー長官が亡くなったのは77歳で、本作のサッチャーが83歳とすれば、両者に5歳ほどの差があるものの、ほぼ同年齢のところから過去を振り返っているといえると思われます。
(注14)ディカプリオとストリープとは25歳ほどの開きがあります。
★★★★☆
象のロケット:マーガレット・サッチャー