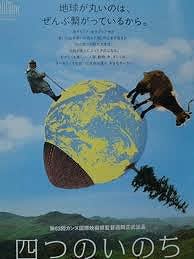『ブラック・スワン』をTOHOシネマズ六本木ヒルズで見ました。
(1)本作品で披露される、ナタリー・ポートマンの渾身の演技を見るだけでも、映画館に行く価値があると思いました。
ただ、映し出される映像が随分と錯綜した印象を観客に与えるものの、始めてプリマドンナを射止めたバレリーナの心の揺れを描くという物語自体はそれほど複雑なものではなく、その展開の仕方にはむしろ“あざとさ”が窺える感じでした。
前半部分において、バレリーナの主人公・ニナ(ナタリー・ポートマン)を極度の「おぼこ娘」として描いているのも〔その原因は描かれてはいませんが、あるいは母親(バーバラ・ハーシー)の存在が問題なのかもしれません〕、後半部分で女性として開花するのを印象付けるため、という物語構成がすぐにミエミエになりますし、それが黒鳥の踊りの大成功をもたらすだろうという展開の先行きも、観客には容易に推測がつきます。

こうなるのも、一つには、演出家のトマ(ヴァンサン・カッセル)の描き方が単純だからなのかもしれません。彼は、ナナの代役のリリー(ミラ・クニス)とか引退するベス(ウィノナ・ライダー)のことをあれだけ褒めていながら、いきなり説明もなしに、「白鳥の湖」のプリマにニナを選んでしまい、その後もその選択を変更しようとはしないのですから、逆に彼のニナに対する期待の大きさが透けて見えてしまいます。

要すれば、ニナの女としての開花と黒鳥の大舞台との時期を合わせようと、トマはいろいろ策を弄したということでしょう。そのためにトマは、ニナには厳しいことを言い続け(それも、女となる必要があると言うだけで、実際には体を求めませんでした)、もしかしたらニナのポストをできるだけ脅かすように行動するよう、リリーに言い含めたりもしたのではないでしょうか?
ただ、トマとしても、ニナがギリギリに追い込まれて、ついには誤って自分を傷つけてしまうところまでは予測できなかったのだ、と思います。彼がニナの深い傷を見て慌てふためくのはそのためでしょう。
ここまでくると、この映画についてのもう一つの問題点も明らかになってくると思われます。
すなわち、ダンサーが素晴らしい踊りを見せることと、扮する役柄と身体的に同じになることとが、あたかも連動しているように描かれているのは疑問ではないでしょうか?どうしてニナの手足が黒鳥のようになることが(あるいは、そのように見えることが)、彼女が素晴らしいダンスをしていることに繋がるのか、傷ついた自分があたかも黒鳥そのものになったかのように感じてラストで笑顔をみせることになるのか、よく理解できないところです。
こうなるのも、演出家トマが舞台に持ち込んだことの結果なのですから、この点でもトマの描き方に問題があると言えそうです。実生活と舞台とを密接に結びつけようとする演出をこの舞台に持ち込んでいるトマは、前世紀の古色蒼然としたリアリズムに基づいた演出思想を今だに持ち続けている三流どころではないでしょうか(19世紀末に作曲された「白鳥の湖」を現在上演することの意味合いが、トマにあっては少しも考えられてはいないのではないでしょうか)?
なお、この映画については、ラストが確定的ではない点が様々に議論されているようです。すべて夢だったと考える方もいるようですが、クマネズミとしては、自分でそうするつもりはなかったものの、死にゆく白鳥とまさに同じ状態になったというので、笑顔を見せたのではないか、ただそれ以降ニナがどうなるのかは映画の視野の外であって、あのまま死んでしまうのか、そうではなく無事に生還してバレリーナとして大成するのか、などなど様々な可能性があるとしても、最早どうでもいいことでは、と思ったりしています。
でも、こんなふうに決めつけずに、むしろ様々な解釈を許すように開かれたラストになっているところが、かえってこの映画の幅を拡大しているとみるべきではないか、とも考えているところです。
この映画を制作したアロノフスキー監督は、この映画を『レスラー』の姉妹編と考えているようですが(劇場用パンフレットによります)、そうならば分からないわけでもありません。
なにしろ、その映画のラストシーンでは、心臓病の手術をしたばかりの主人公のレスラー(ミッキー・ローク)が、リングの四囲に張られているロープの上から因縁の相手レスラーにむかってダイビング・ジャンプする様が描かれているのですから!
おそらくは、そのレベルで「白鳥の湖」を捉えていることから、こうした映画作りになったのではないか、とも思えるところです(例えば、この映画はニナの心の揺れを描き出すのが主眼ですから当然のこととは言え、バレエの良さは、プリマの踊りもさることながら、むしろ群舞にあると思われるところ、この映画では、専らナタリー・ポートマンしかスポットライトが当たっていません!)。
ナタリー・ポートマンは、最近では『マイ・ブラザー』とか『ニューヨーク、アイラブユー』で見かけましたが、この映画ではほとんど出ずっぱりで、まるで彼女の“ワンマンショー”のような印象を受けます(下記のテイラー章子氏が指摘している点ですが)。
とはいえ、長期間トレーニングを積んで、ぜい肉を落とし、あれだけの踊りを披露するのですから、アカデミー賞主演女優賞に輝いたのも当然でしょう。
(2)“ブラック・スワン”というと、この映画が出現するまでは、2007年以降の世界金融危機を予言した書として高く評価されたナシーム・ニコラス・タレブの著書『ブラック・スワン』(邦訳:ダイヤモンド社、2009年)の方が、クマネズミにとっては馴染みがありました。
池田信夫氏のブログの書評記事(2007年6月26日)においては、「ふつう自然科学や経済学で確率を考える場合、ほとんど正規分布を仮定している。しかし実際に世界を動かしているのは、そういう伝統的な確率論で予測できない極端な出来事――Black Swanである」と述べられており、さらには、「いわばメタレベルで人々の予想を裏切る現象がBlack Swanである。ここでは母集団が未知なので、その確率分布もわからない。圧倒的多数の出来事はごくまれにしか起こらないので、その分布は非常に長いロングテール(ベキ分布)になる」とか、「ではBlack Swanを予測する理論はあるのだろうか? それは「予測不可能な現象」という定義によってありえない」とも述べられています。
要すれば、その著書では、人知の及ばない予測不可能なものが“ブラック・スワン”とされているようです(注)。
それでは、映画の描く「黒鳥」はどうでしょうか?

一方で、演出家トマは、むしろ十分コントロール可能なものとして「黒鳥」を把握しているようであり、ですからニナを意図的に煽りたてて、自分が望む「黒鳥」に変身してもらおうと様々に手を打っているように思われます。
ですが、他方のニナは、わけのわからない予測不可能な「黒鳥」になんとかなってみようと、わけのわからないまま練習に明け暮れしているかの如くです。
その結果がラストシーンではないでしょうか?コントロールしえないものに変身するには、自分の身体と精神とをすべて捧げ尽くさなくてはトテモ不可能だった、というのが、ニナがラストで見せた笑顔の意味だったのでは、と思えるところです。
(注)望月衛氏による訳本『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社、2009年)は“積ん読”状態なので、ここでは池田信夫氏の書評から引用しましたが、同訳本の冒頭には、「黒い白鳥」の特徴が次のようにまとめられています。「普通は起こらないこと、とても大きな衝撃があること、そして(事前ではなく)事後には予測が可能であること」(「上」P.4)。
(3)映画評論家は、総じて好意的のようです。
福本次郎氏は、「やがて心の闇と官能の境地にたどりついたニナのパフォーマンスは、身震いするほどの美しさを纏っていく。そんな、アートに人生を捧げた者だけが立てる高みを映画は見事に描き切っていた」として60点をつけています。
前田有一氏は、「この作品を、「超一流アーティストの誕生過程」を描くドラマと(第一に)見る。その恐るべき生みの苦しみ、才能の覚醒に至るまでを、映画史上有数のリアリティとともに描いた大傑作である」として95点をつけています。
渡まち子氏は、「スタジオや楽屋にある鏡が、無数のニナを具現化していく演出が効果的で素晴らしい。クライマックスの舞台では、文字通り、黒鳥と化すニナに、見ているこちらも鳥肌がたった」、「作品を支えるのは何と言っても9キロも減量し過酷なバレエのトレーニングに耐えて熱演したナタリー・ポートマンの存在だろう」として85点をつけています。
ただ、テイラー章子氏は、ナタリー・ポートマンが「いないシーンなど皆無と言うほど 彼女が出ずくめのフィルム。一人芝居と言っても良い。音響も音楽よりも彼女の息遣いだけがサウンドになっている時が嫌に多かった。それでスリラーとかミステリー効果を狙ったのだろう」とし、さらに、この映画に「共感できるところは、ひとつもない。またこのストーリーとニューヨークシテイーバレエ団とがマッチしない。10年前のキエフバレエ団なら合うだろうか」と述べて60点をつけています。
★★★☆☆
象のロケット:ブラック・スワン
(1)本作品で披露される、ナタリー・ポートマンの渾身の演技を見るだけでも、映画館に行く価値があると思いました。
ただ、映し出される映像が随分と錯綜した印象を観客に与えるものの、始めてプリマドンナを射止めたバレリーナの心の揺れを描くという物語自体はそれほど複雑なものではなく、その展開の仕方にはむしろ“あざとさ”が窺える感じでした。
前半部分において、バレリーナの主人公・ニナ(ナタリー・ポートマン)を極度の「おぼこ娘」として描いているのも〔その原因は描かれてはいませんが、あるいは母親(バーバラ・ハーシー)の存在が問題なのかもしれません〕、後半部分で女性として開花するのを印象付けるため、という物語構成がすぐにミエミエになりますし、それが黒鳥の踊りの大成功をもたらすだろうという展開の先行きも、観客には容易に推測がつきます。

こうなるのも、一つには、演出家のトマ(ヴァンサン・カッセル)の描き方が単純だからなのかもしれません。彼は、ナナの代役のリリー(ミラ・クニス)とか引退するベス(ウィノナ・ライダー)のことをあれだけ褒めていながら、いきなり説明もなしに、「白鳥の湖」のプリマにニナを選んでしまい、その後もその選択を変更しようとはしないのですから、逆に彼のニナに対する期待の大きさが透けて見えてしまいます。

要すれば、ニナの女としての開花と黒鳥の大舞台との時期を合わせようと、トマはいろいろ策を弄したということでしょう。そのためにトマは、ニナには厳しいことを言い続け(それも、女となる必要があると言うだけで、実際には体を求めませんでした)、もしかしたらニナのポストをできるだけ脅かすように行動するよう、リリーに言い含めたりもしたのではないでしょうか?
ただ、トマとしても、ニナがギリギリに追い込まれて、ついには誤って自分を傷つけてしまうところまでは予測できなかったのだ、と思います。彼がニナの深い傷を見て慌てふためくのはそのためでしょう。
ここまでくると、この映画についてのもう一つの問題点も明らかになってくると思われます。
すなわち、ダンサーが素晴らしい踊りを見せることと、扮する役柄と身体的に同じになることとが、あたかも連動しているように描かれているのは疑問ではないでしょうか?どうしてニナの手足が黒鳥のようになることが(あるいは、そのように見えることが)、彼女が素晴らしいダンスをしていることに繋がるのか、傷ついた自分があたかも黒鳥そのものになったかのように感じてラストで笑顔をみせることになるのか、よく理解できないところです。
こうなるのも、演出家トマが舞台に持ち込んだことの結果なのですから、この点でもトマの描き方に問題があると言えそうです。実生活と舞台とを密接に結びつけようとする演出をこの舞台に持ち込んでいるトマは、前世紀の古色蒼然としたリアリズムに基づいた演出思想を今だに持ち続けている三流どころではないでしょうか(19世紀末に作曲された「白鳥の湖」を現在上演することの意味合いが、トマにあっては少しも考えられてはいないのではないでしょうか)?
なお、この映画については、ラストが確定的ではない点が様々に議論されているようです。すべて夢だったと考える方もいるようですが、クマネズミとしては、自分でそうするつもりはなかったものの、死にゆく白鳥とまさに同じ状態になったというので、笑顔を見せたのではないか、ただそれ以降ニナがどうなるのかは映画の視野の外であって、あのまま死んでしまうのか、そうではなく無事に生還してバレリーナとして大成するのか、などなど様々な可能性があるとしても、最早どうでもいいことでは、と思ったりしています。
でも、こんなふうに決めつけずに、むしろ様々な解釈を許すように開かれたラストになっているところが、かえってこの映画の幅を拡大しているとみるべきではないか、とも考えているところです。
この映画を制作したアロノフスキー監督は、この映画を『レスラー』の姉妹編と考えているようですが(劇場用パンフレットによります)、そうならば分からないわけでもありません。
なにしろ、その映画のラストシーンでは、心臓病の手術をしたばかりの主人公のレスラー(ミッキー・ローク)が、リングの四囲に張られているロープの上から因縁の相手レスラーにむかってダイビング・ジャンプする様が描かれているのですから!
おそらくは、そのレベルで「白鳥の湖」を捉えていることから、こうした映画作りになったのではないか、とも思えるところです(例えば、この映画はニナの心の揺れを描き出すのが主眼ですから当然のこととは言え、バレエの良さは、プリマの踊りもさることながら、むしろ群舞にあると思われるところ、この映画では、専らナタリー・ポートマンしかスポットライトが当たっていません!)。
ナタリー・ポートマンは、最近では『マイ・ブラザー』とか『ニューヨーク、アイラブユー』で見かけましたが、この映画ではほとんど出ずっぱりで、まるで彼女の“ワンマンショー”のような印象を受けます(下記のテイラー章子氏が指摘している点ですが)。
とはいえ、長期間トレーニングを積んで、ぜい肉を落とし、あれだけの踊りを披露するのですから、アカデミー賞主演女優賞に輝いたのも当然でしょう。
(2)“ブラック・スワン”というと、この映画が出現するまでは、2007年以降の世界金融危機を予言した書として高く評価されたナシーム・ニコラス・タレブの著書『ブラック・スワン』(邦訳:ダイヤモンド社、2009年)の方が、クマネズミにとっては馴染みがありました。
池田信夫氏のブログの書評記事(2007年6月26日)においては、「ふつう自然科学や経済学で確率を考える場合、ほとんど正規分布を仮定している。しかし実際に世界を動かしているのは、そういう伝統的な確率論で予測できない極端な出来事――Black Swanである」と述べられており、さらには、「いわばメタレベルで人々の予想を裏切る現象がBlack Swanである。ここでは母集団が未知なので、その確率分布もわからない。圧倒的多数の出来事はごくまれにしか起こらないので、その分布は非常に長いロングテール(ベキ分布)になる」とか、「ではBlack Swanを予測する理論はあるのだろうか? それは「予測不可能な現象」という定義によってありえない」とも述べられています。
要すれば、その著書では、人知の及ばない予測不可能なものが“ブラック・スワン”とされているようです(注)。
それでは、映画の描く「黒鳥」はどうでしょうか?

一方で、演出家トマは、むしろ十分コントロール可能なものとして「黒鳥」を把握しているようであり、ですからニナを意図的に煽りたてて、自分が望む「黒鳥」に変身してもらおうと様々に手を打っているように思われます。
ですが、他方のニナは、わけのわからない予測不可能な「黒鳥」になんとかなってみようと、わけのわからないまま練習に明け暮れしているかの如くです。
その結果がラストシーンではないでしょうか?コントロールしえないものに変身するには、自分の身体と精神とをすべて捧げ尽くさなくてはトテモ不可能だった、というのが、ニナがラストで見せた笑顔の意味だったのでは、と思えるところです。
(注)望月衛氏による訳本『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社、2009年)は“積ん読”状態なので、ここでは池田信夫氏の書評から引用しましたが、同訳本の冒頭には、「黒い白鳥」の特徴が次のようにまとめられています。「普通は起こらないこと、とても大きな衝撃があること、そして(事前ではなく)事後には予測が可能であること」(「上」P.4)。
(3)映画評論家は、総じて好意的のようです。
福本次郎氏は、「やがて心の闇と官能の境地にたどりついたニナのパフォーマンスは、身震いするほどの美しさを纏っていく。そんな、アートに人生を捧げた者だけが立てる高みを映画は見事に描き切っていた」として60点をつけています。
前田有一氏は、「この作品を、「超一流アーティストの誕生過程」を描くドラマと(第一に)見る。その恐るべき生みの苦しみ、才能の覚醒に至るまでを、映画史上有数のリアリティとともに描いた大傑作である」として95点をつけています。
渡まち子氏は、「スタジオや楽屋にある鏡が、無数のニナを具現化していく演出が効果的で素晴らしい。クライマックスの舞台では、文字通り、黒鳥と化すニナに、見ているこちらも鳥肌がたった」、「作品を支えるのは何と言っても9キロも減量し過酷なバレエのトレーニングに耐えて熱演したナタリー・ポートマンの存在だろう」として85点をつけています。
ただ、テイラー章子氏は、ナタリー・ポートマンが「いないシーンなど皆無と言うほど 彼女が出ずくめのフィルム。一人芝居と言っても良い。音響も音楽よりも彼女の息遣いだけがサウンドになっている時が嫌に多かった。それでスリラーとかミステリー効果を狙ったのだろう」とし、さらに、この映画に「共感できるところは、ひとつもない。またこのストーリーとニューヨークシテイーバレエ団とがマッチしない。10年前のキエフバレエ団なら合うだろうか」と述べて60点をつけています。
★★★☆☆
象のロケット:ブラック・スワン