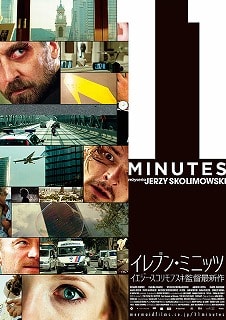『怒り』をTOHOシネマズ渋谷で見ました。
(1)同じ原作者の小説を同じ監督が手掛けた『悪人』(2010年)がなかなか良かったので、本作もと思い映画館に行ってきました。
本作(注1)の冒頭は、空中から見た街(八王子)の光景。蝉の声が高まる中、カメラは次第に一軒の家に近づきます。なんと、その家の浴室では人が殺されているのです。一体(女性)は、浴槽の中に、もう一体(男性)はその外に。その家に住む夫婦が殺されたようです。
八王子署の刑事が、血の付いた包丁を見つけ、またドア(注2)に書かれた「怒」の文字を見て「これ、ガイシャの血かな」などと言ったりします。
場面は変わって、洋平(渡辺謙)は、新宿の歌舞伎町で、NPOの保護センターの男と会います。その男は、洋平の娘の愛子(宮崎あおい)について、「ウチの職員が発見した時には、ギリギリの状態でした。彼女は、客の要求をどんなものでも聞いてしまうので、おもちゃみたいに扱われ、壊れてしまっています」と話します。
そして、洋平は、風俗店のベッドで横になっている愛子を見つけます。
愛子は、目を開けて洋平を認めると、「お父ちゃん」と言います。

2人は千葉の家に戻ることに。
列車の中で、洋平が「晩飯どうする?寿司でもとるか?」と訊くと、愛子は「お父ちゃんのオニギリがいい」と答えるので、洋平は「そんなもんでいいのか?」と驚きます。
また、愛子は耳にしていたイヤホンの一つを、「これ、前に言っていた東方神起」と言いながら洋平に渡します。
そんな愛子は、漁協で働く田代(松山ケンイチ)に出会います。

場面が変わって、東京にあるクラブに設けられているプールの周りで、ゲイたちがワイワイ騒いでいます。
その中に優馬(妻夫木聡)がいます。仲間が「この後、新宿に」と誘いますが、優馬は「今日、俺、いいわ。残業が続いていて、家でゆっくりしたい」と断ります。
続いて、ホスピスの病室。優馬の母親(原日出子)がベッドで目を覚まします。そして、「いつきたの?」と訊くので、優馬は「今さっき、15分前かな」と答え、さらに母親が「今、温泉の夢を見ていた。秋田かな、思い出せない」と言うので、優馬は「また行けばいいよ」と応じます。
そんな優馬は、ある日、クラブで直人(綾野剛)に出会います。

更に場面が変わって、沖縄の離島で暮らすようになった泉(広瀬すず)は、クラスメートの辰哉(作久本宝)が操縦するボートに乗って、無人島に向かいます。
島に着くと2人は上陸し、泉が「島の中、見て回ってもいい?」と言うので、辰哉は「いいけど、俺は、あっちで昼寝する」と答えます。泉が「一緒に行かないんだ」と言うと、辰哉は「行ってもいいけど、一人でブラブラしたいのかと思って」と答えます。
そんな泉は、その無人島で田中(森山未來)と出会います。

東京・八王子で殺人事件があった後、千葉、東京、沖縄の3箇所で、それぞれの物語が動き出しますが、さあ、この後どんな展開になるのでしょうか、………?
本作は、八王子で起きた夫婦惨殺事件を巡るもの。容疑者に酷似する3人の男がそれぞれ織りなす3つの物語から構成されています。編集の冴えと、3人の男を演ずる俳優のみならず、彼らを取り巻く人物を演じる俳優たちの堅実で素晴らしい演技によって、3つの物語相互に何らつながりはないものの、見る方は、全体としてまとまりのある一つの物語として受け取ることになります。色々問題点はあると思いますが、制作者側の意気込みを強く感じさせる作品だと思いました。
(以下は、本作がサスペンス物であるにもかかわらず、ネタバレしていますので、未見の方はご注意ください)
(2)本作においては、テレビの未解決事件を取り上げる特別番組「逃亡犯を追え」で八王子の殺人事件が取り上げられ(注3)、容疑者・山神の整形後の写真などが画面に映し出されます。
その顔写真に、田代や直人、田中の3人の顔が酷似するところから、3つのバラバラに展開する物語(千葉編、東京編、沖縄編)が、見る方にはつながりがある一つの物語のように思えてきます。こんなところは、映画ならではの効果と思われます(注4)。
さらに、千葉編における渡辺謙、宮崎あおい、そして松山ケンイチ、東京編における妻夫木聡と綾野剛、沖縄編における森山未來、広瀬すず、そして作久本宝が、それぞれ各パートで熱演しており、その熱気が他のパートにも波及して、全体がつながりのある作品のように見えてくる感じがします。
モット言えば、千葉編、東京編、それに沖縄編のそれぞれのシーンが、大層効果的に編集され巧みに交互につなぎ合わされていることも、全体がなかなか緊迫感溢れる作品に仕上がっているように思いました(注5)。
とは言え、よくわからない点もあるように思います。
特に、タイトルの「怒り」です。
確かに、冒頭の八王子の事件では、ドアに「怒」の血文字が書かれ、沖縄の無人島の廃墟の壁にも「怒」の文字がかかれていますから、タイトルが「怒り」とされていることもわからないわけではありません。
でも、それを書いた者がなぜその文字を使ったのかということになると、あまり釈然としません。
八王子の事件の容疑者・山神については、同じ職場にいた男(水澤紳吾)が「山神は、その家の主婦から冷たい麦茶を出され、同情されたことに腹を立てて殺した」と証言しています。でも、そうだとしたら、そんなことで「怒」の血文字を書くのでしょうか?それも、ことさらに大きな文字で。容疑者・山神は、一体誰に何をアピールしているのでしょうか?
他方、沖縄の無人島の「怒」の文字については、あるいは沖縄に置かれている米軍基地に対する「怒」なのかも知れず、それならわからないこともありません。
でも、そのことから本作のタイトルを「怒り」とすると、本作はかなり政治的意図を持った作品と受け取られかねないように思われます。それに、田中がそんな政治的な行動をするようにも、映画の中では描かれていません。
そうではなく、泉が受けた理不尽な暴力に対する「怒り」なのかもしれません。
それはそれで理解できるかもしれません。ただ、本作を見ていると、泉が、いくら内地から来て沖縄の実情を知らないとしても、いくら元気いっぱいの女子高生としても(注6)、あの位の年齢にしてはあまりにも無警戒過ぎて、配慮がなさすぎるように思えてしまいます(注7)。
そして、田中は、泉が受けた暴力を見ていて知っているのです(注8)。にもかかわらず、「怒」とはよくわからない感じがします。
まあ、田中は、サイコパスとして、衝動的にいろいろなものに「怒り」の感情をぶつける人間なのかもしれません(注9)。ただ、そうだとしたら、タイトルを「怒り」とするのは、どんな意味があるのでしょう?
あるいは、千葉編とか東京編にも「怒り」を見出すことができるのでしょうか?
クマネズミには、本作全般にわたって見出せるのは、「怒り」よりもむしろ「信」の方ではないかと思えました。
愛子は田代を信用しきれずに警察に通報してしまいますし、優馬は直人を信用できずに手放してしまいます(注10)。また、辰哉は信用していた田中に大きく裏切られてしまいます。
ただ、もしかしたら、近しい人を信用し続けることができなかった自分に対する「怒り」、あるいは信用を裏切った相手に対する「怒り」というところから、本作のタイトルが付けられているのかもしれませんが。
(3)渡まち子氏は、「「悪人」でタッグを組んだ原作者の吉田修一と、李相日監督が放つ「怒り」は、3つの物語を通して、人を愛すること、信じることの意味を問いかける」作品であり、「見る側にも力を要求するヘビーな映画だが、間違いなく見る価値がある力作ドラマである」として70点をつけています。
村山匡一郎氏は、「これは構成の映画といえる。冒頭の殺人事件の真犯人が誰かというサスペンスに支えられた流れの中で、事件と無関係の2つの物語をいかに関連あるように見せるかが肝要である。1つの物語の音声が別の物語に重ねられ、各物語が信/不信のテーマに巧みに収斂していく様は見事である」として★4つ(「見逃せない」)をつけています。
りんたいこ氏は、「俳優たちから従来とは違う表情を引き出し、三つの独立した話を違和感なく一つにまとめあげた李監督の手腕に、改めて感服した」と述べています。
(注1)監督・脚本は、『許されざる者』の李相日。
原作は、吉田修一著『怒り』(中公文庫)。
原作は、完全なフィクションとはいえ、リンゼイ・アン・ホーカー殺害事件を踏まえているのでしょう。
出演者の内、最近では、渡辺謙は『GODZILLA ゴジラ』、宮崎あおいと高畑充希は『バンクーバーの朝日』、松山ケンイチは『の・ようなもの のようなもの』、妻夫木聡は『殿、利息でござる!』、綾野剛とピエール瀧は『日本で一番悪い奴ら』、広瀬すずは『ちはやふる 上の句』、森山未來は『人類資金』、三浦貴大は『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』、原日出子は『リップヴァンウィンクルの花嫁』、愛子の従姉妹の明日香役の池脇千鶴は『きみはいい子』で、それぞれ見ました。
(注2)劇場用パンフレットの「Production Notes」の「千葉」では、「ドアに殴り書きされた「怒」の血文字」とありますが、「美術」の都築雄二氏は、「八王子の殺人現場の残されていたのは白い壁に血文字の赤い「怒」でした」と述べています。「ドア」か「壁」か、いずれなのでしょう?ちなみに、原作小説では「この凶行の場となった廊下に血文字が残されていた」(文庫版(上)P.8)とされていて、「ドア」とも「壁」ともわかりません。
(注3)TVの特番を見ながら、八王子署の刑事(ピエール瀧)は、「1年も逃げおおせている」「視聴率が高いといいが」などと言い、もうひとりの刑事(三浦貴大)も、「新宿2丁目で目撃情報があったからと言って、新宿に潜伏しているとは限らないのでは?」などと言っています。
(注4)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事において、「美術」の都築雄二氏は、「指名手配写真を謎解きの道具にするのではなく、視覚的にストーリーを語るための映画的方法論のひとつとして提示しています」と述べています(具体的には、指名手配の写真を各シーンごとに差し替えている―例えば、千葉編では松山ケンイチ似の写真を使う―とのこと)。
(注5)ただ、冒頭の八王子の殺人事件の場面では、犯人が裸で家の中を動き回ったりするシーンが挿入されていますが、その姿から3人の男の中で誰が犯人なのかある程度推測がついてしまうおそれがあるように思います。
(注6)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事において、李監督は、「彼女(広瀬すず)が秀でているのは、その熱量なんですね」と述べています。
(注7)辰哉と行った無人島では独りで島内を探検しますし、その際に田中に出会っても無警戒に言葉を交わします。さらには、那覇の暗い夜の街を、辰哉の後をどこまでも追いかけてしまい、その結果、大変な目に遭うことになるのです。
(注8)さらには、田中は、「逃げずに最後までやれよ米兵」などという文字を壁に書きつけていますし、辰哉にも、「俺、結構、最初から見ていた。なのに、オヤジがポリースと叫んだ。逃げないで、最後までやれよ」と喋るのです。
(注9)田中は、しばらくは、辰哉の両親が営む民宿の手伝いを大人しくしていますが、突如として、客の荷物を大層ぞんざいに扱ったり、さらには、厨房の中をめちゃくちゃに破壊したりします。
(注10)優馬は、直人が喫茶店で女性(高畑充希)と一緒にいたことを詰り、その結果直人は優馬の前から姿を消してしまいます。ただ、その女性は、後で優馬に会った時に、直人と同じ施設で育ち、自分たち二人は兄妹のような関係だったこと、さらに、直人が心臓病の持病で亡くなったことまで話すのです。これを聞いた優馬は、強い後悔の念に苛まされます。
★★★☆☆☆
象のロケット:怒り
(1)同じ原作者の小説を同じ監督が手掛けた『悪人』(2010年)がなかなか良かったので、本作もと思い映画館に行ってきました。
本作(注1)の冒頭は、空中から見た街(八王子)の光景。蝉の声が高まる中、カメラは次第に一軒の家に近づきます。なんと、その家の浴室では人が殺されているのです。一体(女性)は、浴槽の中に、もう一体(男性)はその外に。その家に住む夫婦が殺されたようです。
八王子署の刑事が、血の付いた包丁を見つけ、またドア(注2)に書かれた「怒」の文字を見て「これ、ガイシャの血かな」などと言ったりします。
場面は変わって、洋平(渡辺謙)は、新宿の歌舞伎町で、NPOの保護センターの男と会います。その男は、洋平の娘の愛子(宮崎あおい)について、「ウチの職員が発見した時には、ギリギリの状態でした。彼女は、客の要求をどんなものでも聞いてしまうので、おもちゃみたいに扱われ、壊れてしまっています」と話します。
そして、洋平は、風俗店のベッドで横になっている愛子を見つけます。
愛子は、目を開けて洋平を認めると、「お父ちゃん」と言います。

2人は千葉の家に戻ることに。
列車の中で、洋平が「晩飯どうする?寿司でもとるか?」と訊くと、愛子は「お父ちゃんのオニギリがいい」と答えるので、洋平は「そんなもんでいいのか?」と驚きます。
また、愛子は耳にしていたイヤホンの一つを、「これ、前に言っていた東方神起」と言いながら洋平に渡します。
そんな愛子は、漁協で働く田代(松山ケンイチ)に出会います。

場面が変わって、東京にあるクラブに設けられているプールの周りで、ゲイたちがワイワイ騒いでいます。
その中に優馬(妻夫木聡)がいます。仲間が「この後、新宿に」と誘いますが、優馬は「今日、俺、いいわ。残業が続いていて、家でゆっくりしたい」と断ります。
続いて、ホスピスの病室。優馬の母親(原日出子)がベッドで目を覚まします。そして、「いつきたの?」と訊くので、優馬は「今さっき、15分前かな」と答え、さらに母親が「今、温泉の夢を見ていた。秋田かな、思い出せない」と言うので、優馬は「また行けばいいよ」と応じます。
そんな優馬は、ある日、クラブで直人(綾野剛)に出会います。

更に場面が変わって、沖縄の離島で暮らすようになった泉(広瀬すず)は、クラスメートの辰哉(作久本宝)が操縦するボートに乗って、無人島に向かいます。
島に着くと2人は上陸し、泉が「島の中、見て回ってもいい?」と言うので、辰哉は「いいけど、俺は、あっちで昼寝する」と答えます。泉が「一緒に行かないんだ」と言うと、辰哉は「行ってもいいけど、一人でブラブラしたいのかと思って」と答えます。
そんな泉は、その無人島で田中(森山未來)と出会います。

東京・八王子で殺人事件があった後、千葉、東京、沖縄の3箇所で、それぞれの物語が動き出しますが、さあ、この後どんな展開になるのでしょうか、………?
本作は、八王子で起きた夫婦惨殺事件を巡るもの。容疑者に酷似する3人の男がそれぞれ織りなす3つの物語から構成されています。編集の冴えと、3人の男を演ずる俳優のみならず、彼らを取り巻く人物を演じる俳優たちの堅実で素晴らしい演技によって、3つの物語相互に何らつながりはないものの、見る方は、全体としてまとまりのある一つの物語として受け取ることになります。色々問題点はあると思いますが、制作者側の意気込みを強く感じさせる作品だと思いました。
(以下は、本作がサスペンス物であるにもかかわらず、ネタバレしていますので、未見の方はご注意ください)
(2)本作においては、テレビの未解決事件を取り上げる特別番組「逃亡犯を追え」で八王子の殺人事件が取り上げられ(注3)、容疑者・山神の整形後の写真などが画面に映し出されます。
その顔写真に、田代や直人、田中の3人の顔が酷似するところから、3つのバラバラに展開する物語(千葉編、東京編、沖縄編)が、見る方にはつながりがある一つの物語のように思えてきます。こんなところは、映画ならではの効果と思われます(注4)。
さらに、千葉編における渡辺謙、宮崎あおい、そして松山ケンイチ、東京編における妻夫木聡と綾野剛、沖縄編における森山未來、広瀬すず、そして作久本宝が、それぞれ各パートで熱演しており、その熱気が他のパートにも波及して、全体がつながりのある作品のように見えてくる感じがします。
モット言えば、千葉編、東京編、それに沖縄編のそれぞれのシーンが、大層効果的に編集され巧みに交互につなぎ合わされていることも、全体がなかなか緊迫感溢れる作品に仕上がっているように思いました(注5)。
とは言え、よくわからない点もあるように思います。
特に、タイトルの「怒り」です。
確かに、冒頭の八王子の事件では、ドアに「怒」の血文字が書かれ、沖縄の無人島の廃墟の壁にも「怒」の文字がかかれていますから、タイトルが「怒り」とされていることもわからないわけではありません。
でも、それを書いた者がなぜその文字を使ったのかということになると、あまり釈然としません。
八王子の事件の容疑者・山神については、同じ職場にいた男(水澤紳吾)が「山神は、その家の主婦から冷たい麦茶を出され、同情されたことに腹を立てて殺した」と証言しています。でも、そうだとしたら、そんなことで「怒」の血文字を書くのでしょうか?それも、ことさらに大きな文字で。容疑者・山神は、一体誰に何をアピールしているのでしょうか?
他方、沖縄の無人島の「怒」の文字については、あるいは沖縄に置かれている米軍基地に対する「怒」なのかも知れず、それならわからないこともありません。
でも、そのことから本作のタイトルを「怒り」とすると、本作はかなり政治的意図を持った作品と受け取られかねないように思われます。それに、田中がそんな政治的な行動をするようにも、映画の中では描かれていません。
そうではなく、泉が受けた理不尽な暴力に対する「怒り」なのかもしれません。
それはそれで理解できるかもしれません。ただ、本作を見ていると、泉が、いくら内地から来て沖縄の実情を知らないとしても、いくら元気いっぱいの女子高生としても(注6)、あの位の年齢にしてはあまりにも無警戒過ぎて、配慮がなさすぎるように思えてしまいます(注7)。
そして、田中は、泉が受けた暴力を見ていて知っているのです(注8)。にもかかわらず、「怒」とはよくわからない感じがします。
まあ、田中は、サイコパスとして、衝動的にいろいろなものに「怒り」の感情をぶつける人間なのかもしれません(注9)。ただ、そうだとしたら、タイトルを「怒り」とするのは、どんな意味があるのでしょう?
あるいは、千葉編とか東京編にも「怒り」を見出すことができるのでしょうか?
クマネズミには、本作全般にわたって見出せるのは、「怒り」よりもむしろ「信」の方ではないかと思えました。
愛子は田代を信用しきれずに警察に通報してしまいますし、優馬は直人を信用できずに手放してしまいます(注10)。また、辰哉は信用していた田中に大きく裏切られてしまいます。
ただ、もしかしたら、近しい人を信用し続けることができなかった自分に対する「怒り」、あるいは信用を裏切った相手に対する「怒り」というところから、本作のタイトルが付けられているのかもしれませんが。
(3)渡まち子氏は、「「悪人」でタッグを組んだ原作者の吉田修一と、李相日監督が放つ「怒り」は、3つの物語を通して、人を愛すること、信じることの意味を問いかける」作品であり、「見る側にも力を要求するヘビーな映画だが、間違いなく見る価値がある力作ドラマである」として70点をつけています。
村山匡一郎氏は、「これは構成の映画といえる。冒頭の殺人事件の真犯人が誰かというサスペンスに支えられた流れの中で、事件と無関係の2つの物語をいかに関連あるように見せるかが肝要である。1つの物語の音声が別の物語に重ねられ、各物語が信/不信のテーマに巧みに収斂していく様は見事である」として★4つ(「見逃せない」)をつけています。
りんたいこ氏は、「俳優たちから従来とは違う表情を引き出し、三つの独立した話を違和感なく一つにまとめあげた李監督の手腕に、改めて感服した」と述べています。
(注1)監督・脚本は、『許されざる者』の李相日。
原作は、吉田修一著『怒り』(中公文庫)。
原作は、完全なフィクションとはいえ、リンゼイ・アン・ホーカー殺害事件を踏まえているのでしょう。
出演者の内、最近では、渡辺謙は『GODZILLA ゴジラ』、宮崎あおいと高畑充希は『バンクーバーの朝日』、松山ケンイチは『の・ようなもの のようなもの』、妻夫木聡は『殿、利息でござる!』、綾野剛とピエール瀧は『日本で一番悪い奴ら』、広瀬すずは『ちはやふる 上の句』、森山未來は『人類資金』、三浦貴大は『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』、原日出子は『リップヴァンウィンクルの花嫁』、愛子の従姉妹の明日香役の池脇千鶴は『きみはいい子』で、それぞれ見ました。
(注2)劇場用パンフレットの「Production Notes」の「千葉」では、「ドアに殴り書きされた「怒」の血文字」とありますが、「美術」の都築雄二氏は、「八王子の殺人現場の残されていたのは白い壁に血文字の赤い「怒」でした」と述べています。「ドア」か「壁」か、いずれなのでしょう?ちなみに、原作小説では「この凶行の場となった廊下に血文字が残されていた」(文庫版(上)P.8)とされていて、「ドア」とも「壁」ともわかりません。
(注3)TVの特番を見ながら、八王子署の刑事(ピエール瀧)は、「1年も逃げおおせている」「視聴率が高いといいが」などと言い、もうひとりの刑事(三浦貴大)も、「新宿2丁目で目撃情報があったからと言って、新宿に潜伏しているとは限らないのでは?」などと言っています。
(注4)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事において、「美術」の都築雄二氏は、「指名手配写真を謎解きの道具にするのではなく、視覚的にストーリーを語るための映画的方法論のひとつとして提示しています」と述べています(具体的には、指名手配の写真を各シーンごとに差し替えている―例えば、千葉編では松山ケンイチ似の写真を使う―とのこと)。
(注5)ただ、冒頭の八王子の殺人事件の場面では、犯人が裸で家の中を動き回ったりするシーンが挿入されていますが、その姿から3人の男の中で誰が犯人なのかある程度推測がついてしまうおそれがあるように思います。
(注6)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事において、李監督は、「彼女(広瀬すず)が秀でているのは、その熱量なんですね」と述べています。
(注7)辰哉と行った無人島では独りで島内を探検しますし、その際に田中に出会っても無警戒に言葉を交わします。さらには、那覇の暗い夜の街を、辰哉の後をどこまでも追いかけてしまい、その結果、大変な目に遭うことになるのです。
(注8)さらには、田中は、「逃げずに最後までやれよ米兵」などという文字を壁に書きつけていますし、辰哉にも、「俺、結構、最初から見ていた。なのに、オヤジがポリースと叫んだ。逃げないで、最後までやれよ」と喋るのです。
(注9)田中は、しばらくは、辰哉の両親が営む民宿の手伝いを大人しくしていますが、突如として、客の荷物を大層ぞんざいに扱ったり、さらには、厨房の中をめちゃくちゃに破壊したりします。
(注10)優馬は、直人が喫茶店で女性(高畑充希)と一緒にいたことを詰り、その結果直人は優馬の前から姿を消してしまいます。ただ、その女性は、後で優馬に会った時に、直人と同じ施設で育ち、自分たち二人は兄妹のような関係だったこと、さらに、直人が心臓病の持病で亡くなったことまで話すのです。これを聞いた優馬は、強い後悔の念に苛まされます。
★★★☆☆☆
象のロケット:怒り