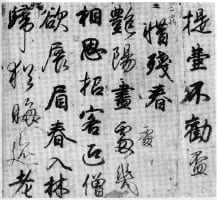東京都現代美術館で「岡崎乾二郎展」(MOTコレクション特集展示)が開催されているというので見に行ってきました(4月11日まで)。
きっかけは、「ART TOUCH 絵画と映画と小説」というブログの記事で、安積桂氏が、この展示覧会で展示されている作品「あかさかみつけ」などについて、「小学生の図画工作の展示だ」と酷評していることで興味を惹かれたからです。
安積氏は、「図工の先生が、あらかじめ製作方法を説明して生徒に作らせ、面白いのとつまらないのを捨てて、平凡な作品を選んで並べれば、こんな展示になるだろう。並べてみると、それなりにおもしろい展示になっているのは、その平凡さの背後に反美術的態度がうかがえるからだ」とまで述べています。
そこまで言うのであれば、実際にはどんな作品なのだろうと確かめてみたくなってしまいました(注1)。
まず、「あかさかみつけ」は、会場入ってすぐの部屋の壁に8点ほど取り付けられています。

確かに、紙を切りぬいたようなもので(樹脂板でできているようです)、いわれてみれば「小学生の図画工作」といった雰囲気がうかがわれます。
安積桂氏が言うように、「『あかさかみつけ』は絵画と彫刻の合いの子だ。オブジェでありながら、台の上に置かれるのではなく、絵画のように壁に掛けてあ」って、「一枚の板の切り起こしが、もとの一枚の板にもどそうとして、、実と虚の面がズレていたり、表面のはずが裏面の色になっていたりして、ちぐはぐなイリュージョンに似た錯覚が生じている」が、「展示された作品をすなおに見れば、けっきょくはちょっと面白い図画工作」なのかもしれません。
といって、一つ一つの作品の切れ込みは、トテモ小中学生の手には負えない独創的なものだとは思いましたが。
それに続く部屋には、今回の特集展示のもう一つの目玉と言える2枚組の大作絵画が3つほど展示されています。


こちらについても、安積桂氏は、「似たような色や形で、アクションでもなくドリッピングでもなく、ブラッシュ・ストロークでも線描でもなく、ただパレット・ナイフ(?)で塗りつけたようで、どれも同じような「絵具で汚したキャンバス」にしか見えない。イリュージョンのない退屈な四角い事物である」と酷評しますが、こちらの方は作品からかなりの面白さを感じました。
むろん、こちらは素人ですから、あるいは「知覚心理学的な錯視現象」かもしれず、もしくは「作品の外部にあるもの」によっているのかもしれませんが、なんだか伊藤若冲が現代に蘇って「動植綵絵」を描いたら、ひょっとしてこんな感じになるのでは、と思わせるものがありました(単なる妄想に過ぎませんが)。

ですから、朝日新聞の大西若人記者の「コントロールされた色彩の増殖が、モダニズムの白い大空間と響き合い、浮遊感を味わうほどに心地よい」という感想(朝日新聞2月10日夕刊)も、あながち的外れとは言えないのではないかと思いました。
ところで、安積桂氏のブログ記事には、「会田誠は山口晃とのふたり展『アートで候。』(上野の森美術館)に出展した『浅田批判』(岡崎作品のパロディ)で揶揄した」とあり、何のことかと思って、その注に従って以前の記事にあたってみますと、「「アートで候」展の二階、「山愚痴屋・澱エンナーレ2007」 のコーナーにあった会田誠の浅田彰批判の作品が面白かった」とあります。

昔のことなのですっかり忘れていましたが、そういえばこの2007年の「アートで候」展に行ったことがあるな、カタログも買った覚えがあるなと思いだし、本棚の奥からそれを引っ張り出して見てみました。ところが、それらしいものは掲載されている様子がありません。
また、その後に出版された作品集『MONUMENT FOR NOTHING』(グラフィック社、2007年)にも記載がありません。
あるいは違うのかしらと思っていましたら、今週号(4月8日)の『週刊文春』の「著者は語る/アート界の異端児による知性と諧謔に満ちた初エッセイ集」の記事で紹介されている『カリコリせんとや生まれけむ』(幻冬舎、2010.2)において、なんとこの作品のことが触れられているではありませんか!

「そこで展示した最新作の中には、作品集に収めることが間に合わなかったものもいくつかあった」(P.26)。
なんだ単にそういうことなのか、というわけです。
ただ、会田誠氏は、「あの作品は、一見するとそういう論争的なものを志向しているようでありながら、全くしていない。一般的な美術品と同じく、ただ鑑賞してもらうことを目的にしている」と述べているので(P.29)、安積桂氏のように「『浅田批判』(岡崎作品のパロディ)で揶揄」と簡単に言い切れないかもしれません(注2)。
といっても、同書の先の方で、「不思議なくらい、笑っちゃうくらい、僕、岡崎さんや浅田さんの考えていることが、全く理解できないんです」、「正直言って現代日本のモダニストって僕にとって、存在に無理がありすぎって思っちゃいます」(P.38)と述べているところからすれば、実際には「揶揄」しているとしか考えられないところですが!
なにはともあれ、日本の現代美術の中心的な存在になっているアーティストの作品に触れることが出来たということで、高揚した気持ちになったことは確かです。
(注1)安積桂氏は、これ以前にも岡崎市の作品を批判しています。すなわち、2008年4月11日の記事には、「会田誠の《浅田批判》は岡崎乾二郎のパロディなのだが、その岡崎の作品を『わたしいまめまいしたわ』展(東京国立近代美術館)で見たけれど、案の定つまらん絵」とあります。
この展覧会にも行きましたが、その時は河原温氏の作品に専ら引き寄せられてしまって、あまり印象に残りませんでした。
(注2)会田誠氏のこの作品が問題となったのは、絵そのものが岡崎氏に類似しているばかりか、タイトルが、「美術に限っていえば、浅田彰は下らないものを誉めそやし、大切なものを貶め、日本の美術界をさんざん停滞させた責任を、いつ、どのようなかたちでとるのだろうか。」となっていて、岡崎氏張りに長い上に中身が挑戦的だ、といったことからでしょう。
きっかけは、「ART TOUCH 絵画と映画と小説」というブログの記事で、安積桂氏が、この展示覧会で展示されている作品「あかさかみつけ」などについて、「小学生の図画工作の展示だ」と酷評していることで興味を惹かれたからです。
安積氏は、「図工の先生が、あらかじめ製作方法を説明して生徒に作らせ、面白いのとつまらないのを捨てて、平凡な作品を選んで並べれば、こんな展示になるだろう。並べてみると、それなりにおもしろい展示になっているのは、その平凡さの背後に反美術的態度がうかがえるからだ」とまで述べています。
そこまで言うのであれば、実際にはどんな作品なのだろうと確かめてみたくなってしまいました(注1)。
まず、「あかさかみつけ」は、会場入ってすぐの部屋の壁に8点ほど取り付けられています。

確かに、紙を切りぬいたようなもので(樹脂板でできているようです)、いわれてみれば「小学生の図画工作」といった雰囲気がうかがわれます。
安積桂氏が言うように、「『あかさかみつけ』は絵画と彫刻の合いの子だ。オブジェでありながら、台の上に置かれるのではなく、絵画のように壁に掛けてあ」って、「一枚の板の切り起こしが、もとの一枚の板にもどそうとして、、実と虚の面がズレていたり、表面のはずが裏面の色になっていたりして、ちぐはぐなイリュージョンに似た錯覚が生じている」が、「展示された作品をすなおに見れば、けっきょくはちょっと面白い図画工作」なのかもしれません。
といって、一つ一つの作品の切れ込みは、トテモ小中学生の手には負えない独創的なものだとは思いましたが。
それに続く部屋には、今回の特集展示のもう一つの目玉と言える2枚組の大作絵画が3つほど展示されています。


こちらについても、安積桂氏は、「似たような色や形で、アクションでもなくドリッピングでもなく、ブラッシュ・ストロークでも線描でもなく、ただパレット・ナイフ(?)で塗りつけたようで、どれも同じような「絵具で汚したキャンバス」にしか見えない。イリュージョンのない退屈な四角い事物である」と酷評しますが、こちらの方は作品からかなりの面白さを感じました。
むろん、こちらは素人ですから、あるいは「知覚心理学的な錯視現象」かもしれず、もしくは「作品の外部にあるもの」によっているのかもしれませんが、なんだか伊藤若冲が現代に蘇って「動植綵絵」を描いたら、ひょっとしてこんな感じになるのでは、と思わせるものがありました(単なる妄想に過ぎませんが)。

ですから、朝日新聞の大西若人記者の「コントロールされた色彩の増殖が、モダニズムの白い大空間と響き合い、浮遊感を味わうほどに心地よい」という感想(朝日新聞2月10日夕刊)も、あながち的外れとは言えないのではないかと思いました。
ところで、安積桂氏のブログ記事には、「会田誠は山口晃とのふたり展『アートで候。』(上野の森美術館)に出展した『浅田批判』(岡崎作品のパロディ)で揶揄した」とあり、何のことかと思って、その注に従って以前の記事にあたってみますと、「「アートで候」展の二階、「山愚痴屋・澱エンナーレ2007」 のコーナーにあった会田誠の浅田彰批判の作品が面白かった」とあります。

昔のことなのですっかり忘れていましたが、そういえばこの2007年の「アートで候」展に行ったことがあるな、カタログも買った覚えがあるなと思いだし、本棚の奥からそれを引っ張り出して見てみました。ところが、それらしいものは掲載されている様子がありません。
また、その後に出版された作品集『MONUMENT FOR NOTHING』(グラフィック社、2007年)にも記載がありません。
あるいは違うのかしらと思っていましたら、今週号(4月8日)の『週刊文春』の「著者は語る/アート界の異端児による知性と諧謔に満ちた初エッセイ集」の記事で紹介されている『カリコリせんとや生まれけむ』(幻冬舎、2010.2)において、なんとこの作品のことが触れられているではありませんか!

「そこで展示した最新作の中には、作品集に収めることが間に合わなかったものもいくつかあった」(P.26)。
なんだ単にそういうことなのか、というわけです。
ただ、会田誠氏は、「あの作品は、一見するとそういう論争的なものを志向しているようでありながら、全くしていない。一般的な美術品と同じく、ただ鑑賞してもらうことを目的にしている」と述べているので(P.29)、安積桂氏のように「『浅田批判』(岡崎作品のパロディ)で揶揄」と簡単に言い切れないかもしれません(注2)。
といっても、同書の先の方で、「不思議なくらい、笑っちゃうくらい、僕、岡崎さんや浅田さんの考えていることが、全く理解できないんです」、「正直言って現代日本のモダニストって僕にとって、存在に無理がありすぎって思っちゃいます」(P.38)と述べているところからすれば、実際には「揶揄」しているとしか考えられないところですが!
なにはともあれ、日本の現代美術の中心的な存在になっているアーティストの作品に触れることが出来たということで、高揚した気持ちになったことは確かです。
(注1)安積桂氏は、これ以前にも岡崎市の作品を批判しています。すなわち、2008年4月11日の記事には、「会田誠の《浅田批判》は岡崎乾二郎のパロディなのだが、その岡崎の作品を『わたしいまめまいしたわ』展(東京国立近代美術館)で見たけれど、案の定つまらん絵」とあります。
この展覧会にも行きましたが、その時は河原温氏の作品に専ら引き寄せられてしまって、あまり印象に残りませんでした。
(注2)会田誠氏のこの作品が問題となったのは、絵そのものが岡崎氏に類似しているばかりか、タイトルが、「美術に限っていえば、浅田彰は下らないものを誉めそやし、大切なものを貶め、日本の美術界をさんざん停滞させた責任を、いつ、どのようなかたちでとるのだろうか。」となっていて、岡崎氏張りに長い上に中身が挑戦的だ、といったことからでしょう。