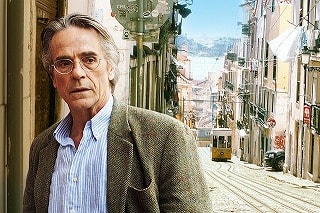『グレース・オブ・モナコ』をTOHOシネマズ渋谷で見ました。
(1)『ペーパーボーイ―真夏の引力』や『レイルウェイ 運命の旅路』で好演したニコール・キッドマンが出演するというので映画館に行ってきました。
本作(注1)の最初の方では映画の撮影風景が映し出され、クランクアップしたのでしょう、コートを着たグレース・ケリー(ニコール・キッドマン)に花束が渡され、皆が拍手をします。
それから、当時のニュースフィルムで、彼女が客船でモナコに向かうところや、車で宮殿に入っていくところが映し出されます(注2)。
次いで、1961年12月となり、ハリウッドのヒッチコック監督(ロジャー・アシュトン=グリフィス)が宮殿を案内されますが、侍女のマッジ(パーカー・ポージー)から「くれぐれもプリンセスと言わないように」と釘を差されます。
丁度、グレースが少女たちに賞状を授与している最中ながら、彼女はヒッチコックを見かけると「ヒッチ」と大声をあげます。
ヒッチコックは、グレースに映画『マーニー』の出演依頼に訪れたのですが、彼女の顔を見て「不幸に見える、やつれた顔だ」とつぶやき、さらに「今でも君はアーチストだということを忘れるな」と言います(注3)。
他方で、レーニエ大公(ティム・ロス)は、大臣や顧問的存在のオナシス(ロバート・リンゼイ)らと議論をするグレースに対して、「ここはアメリカじゃないのだから、思ったことをスグに口にするな。黙っていてくれ」と叱りますが、彼女の方は、「子供に対し、自分の意見を言えと教えているのに」と不満を持ちます。
そんな時に、モナコとフランスとの間に課税問題が持ち上がります(注4)。

さあ、レーニエ大公はどう対応するでしょうか、この問題でグレースが果たした役割とは、………?
無論、実在のグレース・ケリーの美貌とは比べようがないものの、主演のニコール・キッドマンの美しさも比類ないものがあり、その点では問題ないと思います。とはいえ、民間人が王室に入った時の大変さが映画で描かれても(注5)、日本人にとり随分とおなじみであり、余り新鮮さがありません。それに、映画の副題になっている「公妃の切り札」なるものも、持ち上げ過ぎの感があります(注6)。総じて、こうした作品になぜニコール・キッドマンが出演したのかと首を傾げたくなってしまいます。
(2)本作は、サスペンス的要素(注7)も盛り込まれていますが、全体としては、ハリウッドの大スターだったグレースのモナコでの暮らしぶりといった観点から描かれているように思われます。
なにより、映画の最初に描かれるクランクアップの場面は、本作のラストでも映し出されます。
さらには、グレースは、大公とは別のベッドに入り、そこでヒッチコックが置いていった『マーニー』の脚本を読みますし、鏡の前で脚本を読みながら演技の練習もしています(注8)。
また、デリエール伯爵(デレク・ジャコビ)から宮殿の作法を学びますが、その際伯爵は「役を演じればいい」ことを強調します(注9)。

こんなことから、本作は、“公妃”としてよりもむしろ“女優”としてのグレース・ケリーに焦点を当てているのでしょうが、そうであるならば、なにもド・ゴール大統領そっくりさんを映画に登場させることなど二の次にして、そのグレースを“女優”のニコール・キッドマンが更に演じているという観点に立った映画作りもありうるのでは、などといい加減なことを思ったりしました。
(3)渡まち子氏は、「公妃をつらい立場ではなく、演じがいのある大役と割り切ってからの生き生きとした表情が、魅力的だ。全編を彩る優雅な衣装にも注目したい」として60点を付けています。
前田有一氏は、「伝記映画とは、その本人が出演した映画や作品より面白いものを作るくらいの覚悟がなければうまくいかない。グレース・ケリーのカリスマに頼っているだけではダメだ」として55点を付けています。
(注1)本作の監督は、『エディット・ピアフ~愛の讃歌~』(2007年)のオリヴィエ・ダアン。
ちなみに、本作はれっきとしたハリウッド映画と思っていたらフランス映画なのですね(うかつなことに、この記事を見るまでは気が付きませんでした!)。
なお、本作は、その冒頭で「実話によるフィクション」との字幕が流れ、様々のフィクションが紛れ込んでいると思いますから、グレース・ケリーの伝記映画というよりも、単なる娯楽作品と受け止めたほうがいいのではと思います。
(注2)1956年に彼女は、モナコ公国の大公レーニエ3世と結婚。
(注3)なお、ヒッチコックが「大公はどこ?」と尋ねると、グレースは、「公務が忙しくて、顔を合わせていない」と答えます。こんなところにも、結婚6年目のレーニエ大公とグレースの結婚生活ぶりが伺われます。
(注4)本作によれば、1962年に、アルジェリア戦争で肥大化する戦費を調達するために、フランスのド・ゴール大統領はモナコに対し企業課税するよう(その収入の一部をフランスに支払うよう)要請し、それが退けられるとモナコに対して経済封鎖を行いました。
本作によれば、モナコはカジノによる収入しかなくその財政は大層逼迫していたようですから、フランスの要請は渡に船のように思われるところ、レーニエ大公は、何故か執拗に反対します(課税権について他国から介入されれば、モナコの独立性が脅かされると思ったのでしょうか)。
現在、このサイトの記事に従えば、所得税について、モナコの住民は、一部のフランス国籍の人を除き、所得には税金がかかりませんし、通常の法人には税金はかかりません。
ただし、隣のフランスとの軋轢の結果 、1963年に関税協定を結び、フランスと同様の付加価値税(消費税)、関税が課されます(なお、この記事からすると、フランスとモナコの紛争は付加価値税を巡ってのものなのかもしれません←このサイトの記事にも同様のことが記載されています)。
(注5)例えば、モナコの上流階級の女性たちは、舞踏会には興味を示すものの、グレースが関心を示す地味な活動には消極的です。グレースが、彼女たちを病院に案内して汚れている実情を見せても、簡単な改装に頷いてはくれません。レーニエ大公からも、伯爵夫人の機嫌を損ねないように、とストップがかかってしまいます(実際には、病院の改装は実現するのですが)。
(注6)国際赤十字の舞踏会でのグレースの演説はなかなかの内容とはいえ、それを耳にしたド・ゴール大統領が、自分のとった措置を翻すことなど常識的には考えられません(だいたい、舞踏会にド・ゴール大統領がわざわざ出席するのでしょうか?)。
この舞踏会は、マリア・カラス(パス・ベガ)が歌うシーンがあったりして、画面としては一番の盛り上がりが見られるシーンながら、ストーリーとしては随分ちゃちな手を用いてしまったなとクマネズミには思えました。
(注7)グレースの『マーニー』出演話は、レーニエ大公も「君が責任をもってやるなら」と承認して、彼女のハリウッド復帰が決まったものの、時期が悪いために発表は控えられました(発表文は金庫にしまわれます)。ところが、別件でグレースが記者に取り囲まれた時に、記者の方から映画出演のことを持ちだされ、宮殿内に、秘密情報を漏らして大公とグレースの仲を悪化させようと企むスパイが潜んでいるらしいことがわかります。一体誰なのでしょうか、………?
(注8)グレースは、ことさらに、「もう堪えられない、死んでやる」という台詞を大声で繰り返したりします。
(注9)グレースが頼りにしているタッカー神父(フランク・ランジェラ)も、「あなたは、人生最高の役を演じるためにモナコにやってきたはず」と言います。
ただ、これらのこと(役を演じること)は、この拙エントリの「(3)ロ)」で、「平田氏は、ある講義の中で「大人は様々な役割を演じながら生きています」とか、「仮面の総体が人格なんです。私たちは演じる生き物なんです」と述べます」と申し上げたように、そしてこの拙エントリの「注8」で、「鈴木先生が、「演劇を真剣に学ぶことは有意義だと思う」、「俺は教師を演じている」「おのおのが役割を演じて成り立っている部分もある」などと教室で語ったりします」と書きましたように、ことさらめいた問題でもないように思われます。
★★★☆☆☆
象のロケット:グレース・オブ・モナコ
(1)『ペーパーボーイ―真夏の引力』や『レイルウェイ 運命の旅路』で好演したニコール・キッドマンが出演するというので映画館に行ってきました。
本作(注1)の最初の方では映画の撮影風景が映し出され、クランクアップしたのでしょう、コートを着たグレース・ケリー(ニコール・キッドマン)に花束が渡され、皆が拍手をします。
それから、当時のニュースフィルムで、彼女が客船でモナコに向かうところや、車で宮殿に入っていくところが映し出されます(注2)。
次いで、1961年12月となり、ハリウッドのヒッチコック監督(ロジャー・アシュトン=グリフィス)が宮殿を案内されますが、侍女のマッジ(パーカー・ポージー)から「くれぐれもプリンセスと言わないように」と釘を差されます。
丁度、グレースが少女たちに賞状を授与している最中ながら、彼女はヒッチコックを見かけると「ヒッチ」と大声をあげます。
ヒッチコックは、グレースに映画『マーニー』の出演依頼に訪れたのですが、彼女の顔を見て「不幸に見える、やつれた顔だ」とつぶやき、さらに「今でも君はアーチストだということを忘れるな」と言います(注3)。
他方で、レーニエ大公(ティム・ロス)は、大臣や顧問的存在のオナシス(ロバート・リンゼイ)らと議論をするグレースに対して、「ここはアメリカじゃないのだから、思ったことをスグに口にするな。黙っていてくれ」と叱りますが、彼女の方は、「子供に対し、自分の意見を言えと教えているのに」と不満を持ちます。
そんな時に、モナコとフランスとの間に課税問題が持ち上がります(注4)。

さあ、レーニエ大公はどう対応するでしょうか、この問題でグレースが果たした役割とは、………?
無論、実在のグレース・ケリーの美貌とは比べようがないものの、主演のニコール・キッドマンの美しさも比類ないものがあり、その点では問題ないと思います。とはいえ、民間人が王室に入った時の大変さが映画で描かれても(注5)、日本人にとり随分とおなじみであり、余り新鮮さがありません。それに、映画の副題になっている「公妃の切り札」なるものも、持ち上げ過ぎの感があります(注6)。総じて、こうした作品になぜニコール・キッドマンが出演したのかと首を傾げたくなってしまいます。
(2)本作は、サスペンス的要素(注7)も盛り込まれていますが、全体としては、ハリウッドの大スターだったグレースのモナコでの暮らしぶりといった観点から描かれているように思われます。
なにより、映画の最初に描かれるクランクアップの場面は、本作のラストでも映し出されます。
さらには、グレースは、大公とは別のベッドに入り、そこでヒッチコックが置いていった『マーニー』の脚本を読みますし、鏡の前で脚本を読みながら演技の練習もしています(注8)。
また、デリエール伯爵(デレク・ジャコビ)から宮殿の作法を学びますが、その際伯爵は「役を演じればいい」ことを強調します(注9)。

こんなことから、本作は、“公妃”としてよりもむしろ“女優”としてのグレース・ケリーに焦点を当てているのでしょうが、そうであるならば、なにもド・ゴール大統領そっくりさんを映画に登場させることなど二の次にして、そのグレースを“女優”のニコール・キッドマンが更に演じているという観点に立った映画作りもありうるのでは、などといい加減なことを思ったりしました。
(3)渡まち子氏は、「公妃をつらい立場ではなく、演じがいのある大役と割り切ってからの生き生きとした表情が、魅力的だ。全編を彩る優雅な衣装にも注目したい」として60点を付けています。
前田有一氏は、「伝記映画とは、その本人が出演した映画や作品より面白いものを作るくらいの覚悟がなければうまくいかない。グレース・ケリーのカリスマに頼っているだけではダメだ」として55点を付けています。
(注1)本作の監督は、『エディット・ピアフ~愛の讃歌~』(2007年)のオリヴィエ・ダアン。
ちなみに、本作はれっきとしたハリウッド映画と思っていたらフランス映画なのですね(うかつなことに、この記事を見るまでは気が付きませんでした!)。
なお、本作は、その冒頭で「実話によるフィクション」との字幕が流れ、様々のフィクションが紛れ込んでいると思いますから、グレース・ケリーの伝記映画というよりも、単なる娯楽作品と受け止めたほうがいいのではと思います。
(注2)1956年に彼女は、モナコ公国の大公レーニエ3世と結婚。
(注3)なお、ヒッチコックが「大公はどこ?」と尋ねると、グレースは、「公務が忙しくて、顔を合わせていない」と答えます。こんなところにも、結婚6年目のレーニエ大公とグレースの結婚生活ぶりが伺われます。
(注4)本作によれば、1962年に、アルジェリア戦争で肥大化する戦費を調達するために、フランスのド・ゴール大統領はモナコに対し企業課税するよう(その収入の一部をフランスに支払うよう)要請し、それが退けられるとモナコに対して経済封鎖を行いました。
本作によれば、モナコはカジノによる収入しかなくその財政は大層逼迫していたようですから、フランスの要請は渡に船のように思われるところ、レーニエ大公は、何故か執拗に反対します(課税権について他国から介入されれば、モナコの独立性が脅かされると思ったのでしょうか)。
現在、このサイトの記事に従えば、所得税について、モナコの住民は、一部のフランス国籍の人を除き、所得には税金がかかりませんし、通常の法人には税金はかかりません。
ただし、隣のフランスとの軋轢の結果 、1963年に関税協定を結び、フランスと同様の付加価値税(消費税)、関税が課されます(なお、この記事からすると、フランスとモナコの紛争は付加価値税を巡ってのものなのかもしれません←このサイトの記事にも同様のことが記載されています)。
(注5)例えば、モナコの上流階級の女性たちは、舞踏会には興味を示すものの、グレースが関心を示す地味な活動には消極的です。グレースが、彼女たちを病院に案内して汚れている実情を見せても、簡単な改装に頷いてはくれません。レーニエ大公からも、伯爵夫人の機嫌を損ねないように、とストップがかかってしまいます(実際には、病院の改装は実現するのですが)。
(注6)国際赤十字の舞踏会でのグレースの演説はなかなかの内容とはいえ、それを耳にしたド・ゴール大統領が、自分のとった措置を翻すことなど常識的には考えられません(だいたい、舞踏会にド・ゴール大統領がわざわざ出席するのでしょうか?)。
この舞踏会は、マリア・カラス(パス・ベガ)が歌うシーンがあったりして、画面としては一番の盛り上がりが見られるシーンながら、ストーリーとしては随分ちゃちな手を用いてしまったなとクマネズミには思えました。
(注7)グレースの『マーニー』出演話は、レーニエ大公も「君が責任をもってやるなら」と承認して、彼女のハリウッド復帰が決まったものの、時期が悪いために発表は控えられました(発表文は金庫にしまわれます)。ところが、別件でグレースが記者に取り囲まれた時に、記者の方から映画出演のことを持ちだされ、宮殿内に、秘密情報を漏らして大公とグレースの仲を悪化させようと企むスパイが潜んでいるらしいことがわかります。一体誰なのでしょうか、………?
(注8)グレースは、ことさらに、「もう堪えられない、死んでやる」という台詞を大声で繰り返したりします。
(注9)グレースが頼りにしているタッカー神父(フランク・ランジェラ)も、「あなたは、人生最高の役を演じるためにモナコにやってきたはず」と言います。
ただ、これらのこと(役を演じること)は、この拙エントリの「(3)ロ)」で、「平田氏は、ある講義の中で「大人は様々な役割を演じながら生きています」とか、「仮面の総体が人格なんです。私たちは演じる生き物なんです」と述べます」と申し上げたように、そしてこの拙エントリの「注8」で、「鈴木先生が、「演劇を真剣に学ぶことは有意義だと思う」、「俺は教師を演じている」「おのおのが役割を演じて成り立っている部分もある」などと教室で語ったりします」と書きましたように、ことさらめいた問題でもないように思われます。
★★★☆☆☆
象のロケット:グレース・オブ・モナコ