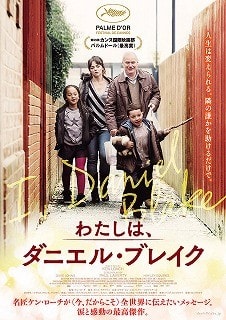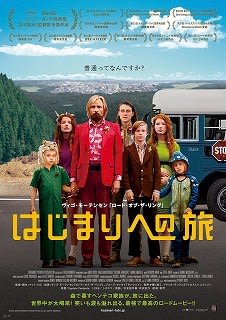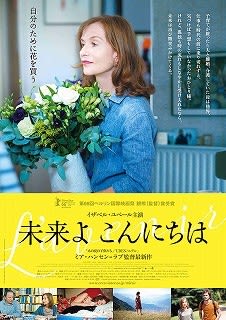『午後8時の訪問者』を新宿武蔵野館で見ました。
(1)『ロルナの祈り』や『少年と自転車』で印象深かったダルデンヌ兄弟の作品ということで映画館に行ってきました〔補注〕。
本作(注1)の冒頭は、都市郊外にある小さな診療所の診察室(注2)。
主人公の女医・ジェニー(アデル・エネル)が、患者の背中に聴診器を当てて診ています(注3)。研修医のジュリアン(オリヴィエ・ボノー)も聴診器を当て、「肺気腫では?」と言います。
ジェニーは、再度聴診器を当てて、「気管支炎による喘息かも」「レントゲンを見ましょう」と言うと、患者は「明日、撮りに行きます」と答えます。
そこへ、「大変です」と女が診察室に入って来たので、ジェニーらが慌てて待合室に行くと、彼女の子供が発作を起こして床に倒れており、体を震えさせたり、硬直させたりします。
ジェニーはジュリアンに「早く診察を」と言うのですが、彼はボーッと立ってその有様を見ているだけ。仕方なくジェニーが、子供に向かって「イリアス、大丈夫よ!」「声が聞こえる?」と叫び、母親も呼びかけをします。しばらくすると、子供は「ママ」と言って目を開けます。
再び診察室。時間は夜8時過ぎです。
ジェニーとジュリアンは、昼間に行った診察の整理などをしています。
ジェニーがジュリアンに「新薬申請の書類はどうなった?」と尋ねると、ジュリアンは無反応です。それで、ジェニーが「私と話さないの?」とイラつくと、やっとジュリアンは「書きました」と答えます。次に、「X線の写しは送ったの?」と訊くと、今度は「送りました」とすぐに答えます。
ジェニーはジュリアンに、「あなたは研修医よね」、「患者の状態にいちいち驚いてはダメ」、「診断する際には、自分の感情を抑えなさい」などと諭します(注4)。
そこに、電話がかかってきます(注5)。

それから、入口のインターホンのブザーが鳴ります。
ジュリアンが出ようとすると、ジェニーは「出なくていい」「診療時間も過ぎているし」「今頃来る方が勝手」と言って制します(注6)。
ジュリアンは、なおも「急患なのかも」と言うのですが、ジェニーは「だったら、もっとベルを押すわ」と頑なに判断を変えません(注7)。ジュリアンが不服そうにその場を離れると、ジェニーは「なんのつもり?理由を言って」と怒ります。
これが、本作で描かれることになる事件の発端なのですが、さあ、どんな物語が待ち構えているのでしょうか、………?
本作は、時間外診療を拒んだことで殺されたのかもしれない黒人の少女を巡る物語。主人公の若い女医は、診療所のドアを開けなかったことで深い罪悪感にとらわれて、その少女の身元を尋ね回ったりして探偵的な役割を果たすとともに、他方で、何となく“下町の赤ひげ先生”的な感じをも醸し出していて、全体的にとても地味な作品ながら、物語の展開はまずまず面白く、最後まで飽きさせません。
(2)ジェニーが診療所のドアを開けさせなかった翌日、警察がやってきて、診療所の近くで身元不明の少女(“La fille inconnue”)の遺体が発見されたと告げます。警察はジェニーに、監視カメラの画像を見せますが、そこでは、診療所のインターホンを押している少女の姿が捉えてられていました。ジェニーは、罪悪感から、携帯に取り込んだ画像を見せながら、知っている者がいないか聞き回ります。
ところで、主人公のジェニーは、この事件があった頃は、当該診療所のアブラン医師(イヴ・ラレク)が病気で入院したために、その代わりとしてそこに勤務していたに過ぎませんでした。
彼女は、しばらくしたら大きな病院で勤務することになっていて、その病院では歓迎パーティーが開催され(まさに殺人事件の起きた当日の夜)、また彼女に用意されている部屋が病院内にあることもわかります。
ですが、ジェニーは、この事件があったこともあり、さらには、アブラン医師が診療所から身を引こうとしていることを知って、自分が診療所を引き継ぐとアブラン医師に申し出ます。

アブラン医師は、「嬉しいけれど、ここは保険診療の多いところだよ」などと忠告しますし、さらには、行くことが決まっていた大病院の医師も翻意を促します(注8)。ですが、ジェニーはその決意を変えません。
実際のところ、映画を見ていると、この診療所にやってくる患者の身なりは決して良くなく、支払いが大丈夫なのか見ていても心配になるほどです(注9)。
ただ、ジェニーには、大病院では見られないような濃密な人間関係がここにあると思えたに違いありません。
元々ジェニーは、黒人少女の殺人に自分が直接関わっているわけではないにもかかわらず(注10)、「あの時、ドアを開けてさえいれば、殺されずに済んだだのでは?」という思いに深く囚われてしまうほど生真面目な性格です(注11)。
彼女が、大病院よりもこの診療所の方を選ぶのは、そうした性格によるところも大きいのではと思えます。
こんなこともあり、さらには、診療所で次から次へと訪れる患者にテキパキと対応するジェニーの姿を見れば、黒澤明監督の『赤ひげ』(1965年)を思い出す人も多いでしょう。
本作のアブラン医師とジェニーとの関係は、あるいは、同作の“赤ひげ”(注12:三船敏郎)と保本登(注13:加山雄三)との関係になぞらえられるかもしれません。
でも、本作におけるアブラン医師の登場時間はごく僅かであり、むしろジェニーと研修医・ジュリアンとの関係に置き換えた方がいいかもしれません。
そのジュリアンですが、医師になるのを諦めて田舎に帰ってしまいます。
生真面目なジェニーは、ジュリアンがそうするのは、自分が彼に厳しく当たったからだと考え、何とか戻るように説得しますが、ジュリアンは「それが理由ではない」と言って、復帰を拒否します。
ところが、ジェニーが、田舎の祖父の元にいるというジュリアンを尋ねていくと、ジュリアンも胸襟を開いて、どうして医師になるのを諦めたのか色々話をします(注14)。
後日、ジュリアンから電話が入り、再度医師を目指すとのこと。
こんなところを見ると、まだまだ経験年数などが大層不足しているとはいえ、若さ故にいろいろ仕出かす保本を教え諭す“赤ひげ”のイメ―ジが、ジェニーにも幾分かは重なってくるようにも思えるところです。
とはいえ、ジェニーのように、誰に対しても一本気で生真面目に対処し続けると、体がいくつあっても足らなくなって、早晩倒れてしまうのではないのか、と映画の中の話にしても心配になってきます。“赤ひげ”になるのは、もう少し年季を積んで、診察などに緩急と言ったものが付けられるようになってからでも遅くはないような気もするのですが(注15)。
それに、ジェニーはまだ若くて美貌なのですから、周囲の男性は放っておかないのではないでしょうか?特に、研修医のジュリアンとは年齢も近いはずで、狭い診療所で一緒に働いてもいるのです。性的なものをお互いに意識してもよさそうですが、映画からはそうしたことは微塵も感じられません。あくまでも、先生と生徒という関係での付き合いにすぎないように見えます。
監督のタルデンヌ兄弟は、意図的にそのように描いているようですが(注16)、少しくらいは配慮があってしかるべきでは、とも思いました。
それはともかく、黒人の少女を殺したのは一体誰なのでしょうか?
でも、本作はサスペンス映画ですから、本作を見てのお楽しみにしておきましょう。
(3)渡まち子氏は、「償いの旅をするジェニー自身にも、医者として、人間として、心の変化が訪れるストーリーが秀逸だ。ヒロインを演じる仏の人気女優アデル・エネルの、繊細で寂しげな、それでいて強い意志を感じる表情が忘れがたい」として75点を付けています。
村山匡一郎氏は、「真相が判明するラストは秀逸である。長回し撮影を駆使して浮かび上がってくるのは、ジェニーを含めた人々の、少女の死をめぐって生じる罪悪感であり、良心の呵責である。そこから現代社会に生きることの倫理観が浮き彫りになる」として★4つ(「見逃せない」)を付けています。
秦早穂子氏は、「開けないドア。開けてしまうドア。期せずして正反対の問題も暗示され、注目したい。今日ほど、世界の人たちが、ドア一枚の内と外、危険に晒され、揺れ動く時代はないのだから」と述べています。
毎日新聞の高橋諭治氏は、「外傷を手当てし、脈拍を測り、体の不自由な患者に寄り添う。そうした細かな描写を積み重ね、誠実で腕もいいが不器用な面もあるジェニーが、少女をめぐる真実と自分の進むべき道を見いだしていくさまを描く。その手並みの鮮やかさ、そして深い余韻を残すラストは必見」と述べています。
(注1)監督・脚本は、ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ。
原題は「La fille inconnue」(The Unknown Girl)。
出演者の内、アデル・エネル(以前はアデル・ハネルと表記)は『黒いスーツを来た男』、ジェレミー・レニエは『少年と自転車』で見ました。
(注2)ジェニーは、しばしば窓を開けてタバコを吸いますが、窓の下は高速道路であり、その向こうには大きな川が見えます。
後の話からすると、映画の舞台となっているのは、ベルーギーのリエージュでしょう。
(注3)この冒頭のシーンはじっくりと映し出されますが、この記事に掲載されている監督インタビューにおいて、リュック・ダルデンヌ氏は、「最初のシーンが、この映画において重要な点を物語っていて、彼女は"耳"なのです。だからこそ、アデル・エネルを選んだのです。みんなの耳になれる人」と述べています。
(注4)医者になるのを諦めて田舎に戻ろうと準備をしているジュリアンのところに行って、ジェニーは、「調べたらイリアスは、脳腫瘍でもてんかんでもなかった」、「あなたは、良い医者になれる」と言います。
(注5)ジェニーを歓迎して大病院で催されるパーティー(本文の(2)で触れています)の件で。
(注6)ジェニーが警察に話したところによると、診療所の診療時間は午後7時までで、インターホンのブザーが鳴ったのは、それよりも1時間後だったとのこと。
(注7)あとで、ジェニーはジュリアンに、「あの時、私もドアを開けたかった」、「でも開けさせなかったのは、あなたに、力関係を見せつけようと思ったから」と話します。
(注8)大病院のリガ医師(ファブリツィオ・ロンジォーネ)は、23人の候補の中からジェニーを選んだだけに、いろいろジェニーを説得します(「後任の募集は1週間待つから」などと言って)。
(注9)例えば、パスポートを見せたくないという理由で病院に行くのを拒んで傷が化膿してしまった患者が、通訳らしき男を連れて駆け込んできたり、診断書を偽造してくれと頼みに来る非常識なカップルも登場します(むろん、ジェニーは断ります)。
(注10)アブラン医師も、「ドアは開けるべきだった」、「けれど、殺したのは君じゃない」とジェニーに言います。
(注11)さらにジェニーは、殺された少女の葬儀こそ逃してしまいましたが、葬られているのが無縁塚と聞いて、10年分の埋葬料を支払います(およそ5万円:身元が判明したら、家族が遺骨の引き取りに来るだろうから、とジェニーは考えたようです←映画では、後になると身元が判明します)。
(注12)小石川養生所の所長で通称“赤ひげ”と呼ばれている新出去定。
(注13)長崎帰りの若い蘭学医。
“赤ひげ”の方は、伝統的な漢方医でしょう。
(注14)ジェニーが、「5年も勉強したのだから、医師になれる」、「研修も1週間残っているだけ」と言うと、ジュリアンは自分のことを話し出します。「発作で震えるあのイリアス少年は、父に殴られた僕だった。近くの医師は、それを見抜けなかった」、「父のことは考えたくなかった」、「それが医師を諦めた理由だった」などと。
(注15)上記「注3」で触れているこの記事に掲載されている監督インタビューにおいて、ジャン=ピエール・ダルデンヌ氏は、「2014年の6月に、偶然、アデル・エネルと会ったのです。……それまでは、医師を40歳くらいに設定していたのです」と述べています。
(注16)劇場用パンフレット掲載の監督インタビュー記事において、ジャン=ピエール・ダルデンヌ氏は、「ジェニーの詳細を伝えることにこだわる必要はないと思いました。脚本の草稿段階では、彼女の私生活にも触れていたのですが、そうした要素は不要に思えたのです」と述べています。
〔補注〕本作を見た後で、ダルデンヌ兄弟の監督作品『サンドラの週末』(2014年)をDVDで見ました。
ある零細企業で、社長の提案によって、病気休職していたサンドラ(マリオン・コティヤール)の復職を認めるのか、それとも臨時ボーナスの1000ユーロを受け取るかについて従業員投票が行われることになり、サンドラは復職したいので、16人の従業員に復職を認めてくれるよう、週末の2日をかけて一人一人に説得に回るというお話。
うつ病上がりのサンドラにとっては実に厳しい状況ながらも、夫(ファブリツィオ・ロンジョーネ)に励まされたりして、各人の家を回ります。賛成してくれる人もいれば、内情の苦しさを言い訳にして反対する者もいます。そのたびに、サンドラの感情が大きく揺れ動きます。さあ、投票の結果はどうなるのか、というところで見る者の興味を惹きつけます。
ただ、1000ユーロ(およそ12万円)が大金とされるのだろうかとか、元々こんな選択をわざわざ社長が従業員投票に任せるのだろうか、など疑問が湧いてしまい、この物語はファンタジーなのだろうなとも思ったりしてしまいます。
まあ、素のマリオン・コティヤールを見ることが出来、人々に善意がないわけではないことや、サンドラが次に向けて前に踏み出そうとする姿勢が描かれていることで良しとすべきなのでしょう。
なお、サンドラが、従業員の一人一人を訪ね歩く姿は、本作のジェニーが、殺された黒人の少女の身元を求めて、周囲を訪ね歩く姿を思い起こさせます(なんだか、日本のお役所などで見られるという“根回し”に似ているかもしれませんが)。
★★★☆☆☆
象のロケット:午後8時の訪問者
(1)『ロルナの祈り』や『少年と自転車』で印象深かったダルデンヌ兄弟の作品ということで映画館に行ってきました〔補注〕。
本作(注1)の冒頭は、都市郊外にある小さな診療所の診察室(注2)。
主人公の女医・ジェニー(アデル・エネル)が、患者の背中に聴診器を当てて診ています(注3)。研修医のジュリアン(オリヴィエ・ボノー)も聴診器を当て、「肺気腫では?」と言います。
ジェニーは、再度聴診器を当てて、「気管支炎による喘息かも」「レントゲンを見ましょう」と言うと、患者は「明日、撮りに行きます」と答えます。
そこへ、「大変です」と女が診察室に入って来たので、ジェニーらが慌てて待合室に行くと、彼女の子供が発作を起こして床に倒れており、体を震えさせたり、硬直させたりします。
ジェニーはジュリアンに「早く診察を」と言うのですが、彼はボーッと立ってその有様を見ているだけ。仕方なくジェニーが、子供に向かって「イリアス、大丈夫よ!」「声が聞こえる?」と叫び、母親も呼びかけをします。しばらくすると、子供は「ママ」と言って目を開けます。
再び診察室。時間は夜8時過ぎです。
ジェニーとジュリアンは、昼間に行った診察の整理などをしています。
ジェニーがジュリアンに「新薬申請の書類はどうなった?」と尋ねると、ジュリアンは無反応です。それで、ジェニーが「私と話さないの?」とイラつくと、やっとジュリアンは「書きました」と答えます。次に、「X線の写しは送ったの?」と訊くと、今度は「送りました」とすぐに答えます。
ジェニーはジュリアンに、「あなたは研修医よね」、「患者の状態にいちいち驚いてはダメ」、「診断する際には、自分の感情を抑えなさい」などと諭します(注4)。
そこに、電話がかかってきます(注5)。

それから、入口のインターホンのブザーが鳴ります。
ジュリアンが出ようとすると、ジェニーは「出なくていい」「診療時間も過ぎているし」「今頃来る方が勝手」と言って制します(注6)。
ジュリアンは、なおも「急患なのかも」と言うのですが、ジェニーは「だったら、もっとベルを押すわ」と頑なに判断を変えません(注7)。ジュリアンが不服そうにその場を離れると、ジェニーは「なんのつもり?理由を言って」と怒ります。
これが、本作で描かれることになる事件の発端なのですが、さあ、どんな物語が待ち構えているのでしょうか、………?
本作は、時間外診療を拒んだことで殺されたのかもしれない黒人の少女を巡る物語。主人公の若い女医は、診療所のドアを開けなかったことで深い罪悪感にとらわれて、その少女の身元を尋ね回ったりして探偵的な役割を果たすとともに、他方で、何となく“下町の赤ひげ先生”的な感じをも醸し出していて、全体的にとても地味な作品ながら、物語の展開はまずまず面白く、最後まで飽きさせません。
(2)ジェニーが診療所のドアを開けさせなかった翌日、警察がやってきて、診療所の近くで身元不明の少女(“La fille inconnue”)の遺体が発見されたと告げます。警察はジェニーに、監視カメラの画像を見せますが、そこでは、診療所のインターホンを押している少女の姿が捉えてられていました。ジェニーは、罪悪感から、携帯に取り込んだ画像を見せながら、知っている者がいないか聞き回ります。
ところで、主人公のジェニーは、この事件があった頃は、当該診療所のアブラン医師(イヴ・ラレク)が病気で入院したために、その代わりとしてそこに勤務していたに過ぎませんでした。
彼女は、しばらくしたら大きな病院で勤務することになっていて、その病院では歓迎パーティーが開催され(まさに殺人事件の起きた当日の夜)、また彼女に用意されている部屋が病院内にあることもわかります。
ですが、ジェニーは、この事件があったこともあり、さらには、アブラン医師が診療所から身を引こうとしていることを知って、自分が診療所を引き継ぐとアブラン医師に申し出ます。

アブラン医師は、「嬉しいけれど、ここは保険診療の多いところだよ」などと忠告しますし、さらには、行くことが決まっていた大病院の医師も翻意を促します(注8)。ですが、ジェニーはその決意を変えません。
実際のところ、映画を見ていると、この診療所にやってくる患者の身なりは決して良くなく、支払いが大丈夫なのか見ていても心配になるほどです(注9)。
ただ、ジェニーには、大病院では見られないような濃密な人間関係がここにあると思えたに違いありません。
元々ジェニーは、黒人少女の殺人に自分が直接関わっているわけではないにもかかわらず(注10)、「あの時、ドアを開けてさえいれば、殺されずに済んだだのでは?」という思いに深く囚われてしまうほど生真面目な性格です(注11)。
彼女が、大病院よりもこの診療所の方を選ぶのは、そうした性格によるところも大きいのではと思えます。
こんなこともあり、さらには、診療所で次から次へと訪れる患者にテキパキと対応するジェニーの姿を見れば、黒澤明監督の『赤ひげ』(1965年)を思い出す人も多いでしょう。
本作のアブラン医師とジェニーとの関係は、あるいは、同作の“赤ひげ”(注12:三船敏郎)と保本登(注13:加山雄三)との関係になぞらえられるかもしれません。
でも、本作におけるアブラン医師の登場時間はごく僅かであり、むしろジェニーと研修医・ジュリアンとの関係に置き換えた方がいいかもしれません。
そのジュリアンですが、医師になるのを諦めて田舎に帰ってしまいます。
生真面目なジェニーは、ジュリアンがそうするのは、自分が彼に厳しく当たったからだと考え、何とか戻るように説得しますが、ジュリアンは「それが理由ではない」と言って、復帰を拒否します。
ところが、ジェニーが、田舎の祖父の元にいるというジュリアンを尋ねていくと、ジュリアンも胸襟を開いて、どうして医師になるのを諦めたのか色々話をします(注14)。
後日、ジュリアンから電話が入り、再度医師を目指すとのこと。
こんなところを見ると、まだまだ経験年数などが大層不足しているとはいえ、若さ故にいろいろ仕出かす保本を教え諭す“赤ひげ”のイメ―ジが、ジェニーにも幾分かは重なってくるようにも思えるところです。
とはいえ、ジェニーのように、誰に対しても一本気で生真面目に対処し続けると、体がいくつあっても足らなくなって、早晩倒れてしまうのではないのか、と映画の中の話にしても心配になってきます。“赤ひげ”になるのは、もう少し年季を積んで、診察などに緩急と言ったものが付けられるようになってからでも遅くはないような気もするのですが(注15)。
それに、ジェニーはまだ若くて美貌なのですから、周囲の男性は放っておかないのではないでしょうか?特に、研修医のジュリアンとは年齢も近いはずで、狭い診療所で一緒に働いてもいるのです。性的なものをお互いに意識してもよさそうですが、映画からはそうしたことは微塵も感じられません。あくまでも、先生と生徒という関係での付き合いにすぎないように見えます。
監督のタルデンヌ兄弟は、意図的にそのように描いているようですが(注16)、少しくらいは配慮があってしかるべきでは、とも思いました。
それはともかく、黒人の少女を殺したのは一体誰なのでしょうか?
でも、本作はサスペンス映画ですから、本作を見てのお楽しみにしておきましょう。
(3)渡まち子氏は、「償いの旅をするジェニー自身にも、医者として、人間として、心の変化が訪れるストーリーが秀逸だ。ヒロインを演じる仏の人気女優アデル・エネルの、繊細で寂しげな、それでいて強い意志を感じる表情が忘れがたい」として75点を付けています。
村山匡一郎氏は、「真相が判明するラストは秀逸である。長回し撮影を駆使して浮かび上がってくるのは、ジェニーを含めた人々の、少女の死をめぐって生じる罪悪感であり、良心の呵責である。そこから現代社会に生きることの倫理観が浮き彫りになる」として★4つ(「見逃せない」)を付けています。
秦早穂子氏は、「開けないドア。開けてしまうドア。期せずして正反対の問題も暗示され、注目したい。今日ほど、世界の人たちが、ドア一枚の内と外、危険に晒され、揺れ動く時代はないのだから」と述べています。
毎日新聞の高橋諭治氏は、「外傷を手当てし、脈拍を測り、体の不自由な患者に寄り添う。そうした細かな描写を積み重ね、誠実で腕もいいが不器用な面もあるジェニーが、少女をめぐる真実と自分の進むべき道を見いだしていくさまを描く。その手並みの鮮やかさ、そして深い余韻を残すラストは必見」と述べています。
(注1)監督・脚本は、ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ。
原題は「La fille inconnue」(The Unknown Girl)。
出演者の内、アデル・エネル(以前はアデル・ハネルと表記)は『黒いスーツを来た男』、ジェレミー・レニエは『少年と自転車』で見ました。
(注2)ジェニーは、しばしば窓を開けてタバコを吸いますが、窓の下は高速道路であり、その向こうには大きな川が見えます。
後の話からすると、映画の舞台となっているのは、ベルーギーのリエージュでしょう。
(注3)この冒頭のシーンはじっくりと映し出されますが、この記事に掲載されている監督インタビューにおいて、リュック・ダルデンヌ氏は、「最初のシーンが、この映画において重要な点を物語っていて、彼女は"耳"なのです。だからこそ、アデル・エネルを選んだのです。みんなの耳になれる人」と述べています。
(注4)医者になるのを諦めて田舎に戻ろうと準備をしているジュリアンのところに行って、ジェニーは、「調べたらイリアスは、脳腫瘍でもてんかんでもなかった」、「あなたは、良い医者になれる」と言います。
(注5)ジェニーを歓迎して大病院で催されるパーティー(本文の(2)で触れています)の件で。
(注6)ジェニーが警察に話したところによると、診療所の診療時間は午後7時までで、インターホンのブザーが鳴ったのは、それよりも1時間後だったとのこと。
(注7)あとで、ジェニーはジュリアンに、「あの時、私もドアを開けたかった」、「でも開けさせなかったのは、あなたに、力関係を見せつけようと思ったから」と話します。
(注8)大病院のリガ医師(ファブリツィオ・ロンジォーネ)は、23人の候補の中からジェニーを選んだだけに、いろいろジェニーを説得します(「後任の募集は1週間待つから」などと言って)。
(注9)例えば、パスポートを見せたくないという理由で病院に行くのを拒んで傷が化膿してしまった患者が、通訳らしき男を連れて駆け込んできたり、診断書を偽造してくれと頼みに来る非常識なカップルも登場します(むろん、ジェニーは断ります)。
(注10)アブラン医師も、「ドアは開けるべきだった」、「けれど、殺したのは君じゃない」とジェニーに言います。
(注11)さらにジェニーは、殺された少女の葬儀こそ逃してしまいましたが、葬られているのが無縁塚と聞いて、10年分の埋葬料を支払います(およそ5万円:身元が判明したら、家族が遺骨の引き取りに来るだろうから、とジェニーは考えたようです←映画では、後になると身元が判明します)。
(注12)小石川養生所の所長で通称“赤ひげ”と呼ばれている新出去定。
(注13)長崎帰りの若い蘭学医。
“赤ひげ”の方は、伝統的な漢方医でしょう。
(注14)ジェニーが、「5年も勉強したのだから、医師になれる」、「研修も1週間残っているだけ」と言うと、ジュリアンは自分のことを話し出します。「発作で震えるあのイリアス少年は、父に殴られた僕だった。近くの医師は、それを見抜けなかった」、「父のことは考えたくなかった」、「それが医師を諦めた理由だった」などと。
(注15)上記「注3」で触れているこの記事に掲載されている監督インタビューにおいて、ジャン=ピエール・ダルデンヌ氏は、「2014年の6月に、偶然、アデル・エネルと会ったのです。……それまでは、医師を40歳くらいに設定していたのです」と述べています。
(注16)劇場用パンフレット掲載の監督インタビュー記事において、ジャン=ピエール・ダルデンヌ氏は、「ジェニーの詳細を伝えることにこだわる必要はないと思いました。脚本の草稿段階では、彼女の私生活にも触れていたのですが、そうした要素は不要に思えたのです」と述べています。
〔補注〕本作を見た後で、ダルデンヌ兄弟の監督作品『サンドラの週末』(2014年)をDVDで見ました。
ある零細企業で、社長の提案によって、病気休職していたサンドラ(マリオン・コティヤール)の復職を認めるのか、それとも臨時ボーナスの1000ユーロを受け取るかについて従業員投票が行われることになり、サンドラは復職したいので、16人の従業員に復職を認めてくれるよう、週末の2日をかけて一人一人に説得に回るというお話。
うつ病上がりのサンドラにとっては実に厳しい状況ながらも、夫(ファブリツィオ・ロンジョーネ)に励まされたりして、各人の家を回ります。賛成してくれる人もいれば、内情の苦しさを言い訳にして反対する者もいます。そのたびに、サンドラの感情が大きく揺れ動きます。さあ、投票の結果はどうなるのか、というところで見る者の興味を惹きつけます。
ただ、1000ユーロ(およそ12万円)が大金とされるのだろうかとか、元々こんな選択をわざわざ社長が従業員投票に任せるのだろうか、など疑問が湧いてしまい、この物語はファンタジーなのだろうなとも思ったりしてしまいます。
まあ、素のマリオン・コティヤールを見ることが出来、人々に善意がないわけではないことや、サンドラが次に向けて前に踏み出そうとする姿勢が描かれていることで良しとすべきなのでしょう。
なお、サンドラが、従業員の一人一人を訪ね歩く姿は、本作のジェニーが、殺された黒人の少女の身元を求めて、周囲を訪ね歩く姿を思い起こさせます(なんだか、日本のお役所などで見られるという“根回し”に似ているかもしれませんが)。
★★★☆☆☆
象のロケット:午後8時の訪問者