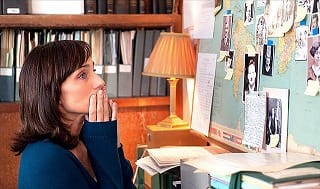『サラの鍵』を銀座テアトルシネマで見ました。
(1)この映画は、以前見た『黄色い星の子供たち』で描かれたのと全く同様の事件(注1)を取り扱った作品で、そちらがかなり実録ベースであるのに対して、こちらはフィクション仕立てになっています(注2)。
そして、そちらは、当時のユダヤ人の視点に立ちながら、検挙されたユダヤ人が一旦「屋内競輪場(ヴェル・ディヴ)」に集められ、そこからフランス国内の収容所に移されて、ついにはドイツやポーランドの絶滅収容所に送られるところまでが映し出されますが、こちらは、現在の時点で展開される物語の中で、同じ事柄が描かれています。
すなわち、ジャーナリストのジュリア(クリスティン・スコット・トーマス)〔元はアメリカ人ですが、もう長いことパリで生活しています〕は、この事件に関するレポートを雑誌に掲載すべく取材しているうちに、とんでもないことが分かってきます。というのも、内部を大改装して自分たち家族がこれから住もうとしているアパートは、実は、この事件で検挙されたユダヤ人が居住していたものだったのです(ユダヤ人が立ち退いて空き室になったものを、昔、彼女の義理の祖父母が取得したという訳です)。
さらには、まさにその部屋で、この事件にまつわる忌まわしい出来事があったこともわかってきます。すなわち、1942年の事件に際して、その部屋に住んでいたサラ(メリュジーヌ・マヤンス)という少女が、ユダヤ人を検挙すべくフランス警察が押し入ってきた際に、弟ミシェルを逃れさせようと、納戸に入れて外から鍵を掛けてしまったのです(注3)。

サラは、「屋内競輪場(ヴェル・ディヴ)」を経由して地方の収容所に送られたものの、納戸に閉じ込めたままになってしまった弟のことばかりが気懸りで、やっとのことでそこを脱出して(注4)、パリのアパートに立ち戻り、それまで大事に握りしめていた鍵を使って納戸を開くのですが、……。
ジュリアは、その後のサラの行方を追い求めて、フィレンツェからニューヨークまで足を延ばします。
その間、なかなか身ごもらなかった彼女が2番目の子供を妊娠するも、夫のベルトランは、今更子供は欲しくないと言い出して(注5)、夫婦の間に大きな溝が出来てしまったり、過去の忌まわしい出来事をほじくり返そうとするジュリアに対して、義父とか、アメリカに渡ったサラにできた息子ウィリアムなどが強い不快感を示したりします。
映画を見るまでは、そして初めのうちは、『黄色い星野子供たち』と同じように、強制収容所のことが専ら描かれるのかな、と思っていましたが、現代に生きるジュリアが主人公だとわかってくると、映画の複雑な構成にも引きつけられて(注6)、久し振りに質の高い文芸作品を見たな(注7)、という充実した気分になりました。
主演のクリスティン・スコット・トーマスは、昨年公開された『ずっとあなたを愛してる』や『ノーウェアボーイ』で大変印象に残る演技を披露したところですが、本作においても、まさに彼女ならではの存在感のある瞠目の演技を披露しています。

(2)本作は、様々なレベルで読むことが出来ると思います。
例えば、いうまでもなく、1942年の「ヴェル・ディヴ事件」という観点から(ただこれは、『黄色い星の子供たち』でかなり描かれています)。
中心的には、ジュリアの生き方(アメリカ人が、「ヴェル・ディヴ事件」を通してユダヤ人問題に触れてどのように変わっていくか、など)。
あるいは、ジュリアとベルトラン(それに娘のゾーイ)の家族という観点。
または、過去の真実の追求ということ(注8)。
それに、サラの生きざま(注9)、などなど。
ただここでは、少し趣向を変えて、本作において重要な役割を果たしていると思われる「鍵」について少しばかり見てみましょう。
一つは、むろん、サラが弟を閉じ込めた納戸の「鍵」です。弟は自分の言うことを聞くから、自分で納戸を開けて出てきはしない、それでは大変なことになると思い、フランス国内の収容所に送られたサラは、「鍵」を使って納戸を開けることだけを考え詰めます。要すれば、開くために使われる「鍵」といっていいでしょう。
ところが、ジュリアの義理の父親は、ジュリアらがこれから住もうとしている家は1942年に祖父母が取得したものであること、さらにはサラが戻ってきて納戸を開けたことまで知っているにもかかわらず、それをずっと黙ってきたのです。その上、その事実をジュリアが明るみに出そうとすることに対して、義父は強く非難したりします。ここでは、過去を封じ込めるために、想像上の「鍵」が使われているといえるのではないでしょうか?
さらに、本作とは離れますが、もう一つの「鍵」の使い方もあるようです。
谷崎潤一郎の小説『鍵』においては、夫と妻が、それぞれ付けている日記を抽出などの隠し場所に隠していて、それに「鍵」をかけているのですが、その鍵の在り処をお互いに知っていて、隠してある日記はお互いに盗み見られていることがお互いに分かっている、という設定にされた上で、それぞれの日記がほぼ交互に掲載されていきます(注10)。
つまり、この小説における「鍵」は、かかっているようでいて、実はかかってはいない感じなのです(注11)。
なお、アメリカに渡ったサラが産んだウィリアムは、当初は、「鍵」をかけてしまっておく過去など何も持っていなかったにもかかわらず、ジュリアに母親がユダヤ人であると告げられると、鍵をかけておくべき過去があたかもあったかのような態度に出て、ジュリアを激しく拒絶します。これは、鍵のもう一つの使い方(なかった鍵を新たに作り出す、とでもいったらいいのでしょうか)といえるかもしれません(注12)。
(3)渡まち子氏は、「この物語は、ホロコーストを過去の“点”ではなく、現代へと続く線、あるいは面としてとらえることで、命は次世代に引き継がれ、未来への希望が生まれることを教えてくれる。ラストシーン、娘の名を聞かれたジュリアが答える場面では、胸いっぱいにあたたかい感動が広がった」として70点を付けています。
また、粉川哲夫氏は、ジュリアが、「謎を追い、パリから生まれ故郷のブルックリン、さらにはフィレンツェまで動くのは、一見「探偵ドラマ」風だが、それは、交互に描かれる古い時代のシーンとのたくみなバランスのなかで単なるエンターテインメントに堕すことをまぬがれる。収容所からからくも逃れ、生き延びたサラという少女の悲痛なドラマは、そのままならお涙頂戴のドラマになりかねないが、交互に挿入されるジュリアの「現在」(2009年とそれ以後)によって「異 化」され、内省的な静溢さをもたらしている」と、★を5つ付けています。
(注1)1942年に、パリのユダヤ人を一斉検挙した「ヴェル・ディヴ事件」のこと。1995年になって、当時のシラク大統領がその事実を公式に認めて、犠牲者に謝罪しました
(注2)本作は、タチアナ・ド・ロネの同名の小説(邦訳は高見浩訳で新潮社から)を映画化したものです。
(注3)劇場用パンフレットのProduction Notes には、「ブレネール監督とジョンクールが共同で手掛けた脚本は小説に忠実」ながら、「警察が来たとき、サラの弟は自ら納戸に隠れる」が、「映画では、サラが彼に隠れるように言う」、とあります。
確かに、原作小説では、警察が踏み込んできたとき、「僕、秘密の場所にいくよ」とミシェルは「ささやき」、「だめー」「一緒にいくのよ。こなきゃだめ」とサラは「せっつ」きます。サラは、「弟をつかまえようとし」ますが、ミッシェルは、「寝室の壁の裏に設けられた、奥行きのある納戸の中にもぐりこ」みます。「そこはいつも2人が隠れんぼをして遊ぶ場所」でした。そして、ミッシェルは、「怖くない。鍵をかけてくれれば、絶対につかまらないよ、ぼく」と言うのです。サラは、「外部の人間には、この壁の裏に納戸があるなどと見抜けないはずだ。弟はここにいたほうが安全だ。間違いない」、「あとで、きょうのうちに帰宅が許されたら、もどってきて弟を出しやればいいのだ」と思います(邦訳P.16~P.17)。
(注4)『黄色い星の子供たち』でも、少年ジョーがもう一人の少年と収容所を脱出するのですが、その作品では、途中経過が省かれて(裕福な家の養子となった、と説明されますが)、いきなり戦後となって、メラニー・ロラン扮する看護士がジョンと再会する場面となります。
これに対して、本作では、サラは友達と一緒に収容所を脱出しますが(『黄色い星の子供たち』と同じように、収容所の周囲は、背の高い草が一面に生えている草原なのです)、そこからサラが、自分のアパートに戻るまでが詳しく描き出されています。

すなわち、サラは、一度は追い出された農家で何とか匿われた上(もう一人の友人は、ジフテリアに罹って死んでしまいますが)、男の子に変装してパリに戻って、元の家に入り込みます。その後は、またその農家で働きますが、戦後暫くして、家出をしてしまいます。
(注5)夫のベルトランは、一人娘のゾーイが10代になっていることだし、アパートも整いつつあるし、それに年老いた父親になりたくない、といった理由で、ジュリアが子供を産むことに強く反対し続けます。
(注6)映画は、「1942年の最初の小麦がペタン元帥に送られました」との文字映像から始まり、フランス警察がサラたちの住むアパートに乗り込んで来る場面となり、ついで、ジュリアが勤務する雑誌社の編集会議のシーン、そして1942年の「冬季競輪場」へという具合に、当時と今とが煩雑に入り組んで映し出されます。
(注7)例えば、ジュリアの一家の一人娘ゾーイは、多感な時期で(14歳)、ジュリアが何も説明しないで各地を飛び回っていることなどに批判的ですし、また今頃自分に妹ができることも釈然としない感じです。ジュリアが出産後夫と別れてニューヨークで生活するときも同行するものの、やはり父親のいるパリの方がいいと言い出す始末。といった具合に、登場人物一人一人に複雑な性格が与えられているのです。
なお、ゾーイが父親とPC電話で話していると、その最中に、父親の方の画面に、彼が一緒に暮らしているらしい女性が一時現れたりするのです。
(注8)サラがアメリカで産んだウィリアム(エイダン・クイン)は、生まれてスグにカトリックの洗礼を受けたこともあって、自分がユダヤ人であることを知らずに大人になりました。ですから、当初ジュリアから母親のサラのことを聞いた時は、酷いショックを受け、その事実を受け入れることを拒絶します。

ですが、その後、病に伏せる父親から、母親サラの真実の姿を知らされ(「彼女は私が人生の中で出会った女性の中で一番美しい」などと語ります)、また遺品なども手渡されます(手渡されたノートから、例の「鍵」が出てきます)。
それで、ジュリアがニューヨークに移り住んで再会した時には、ウィリアムの態度は一変しています。ジュリアが、「自分の態度は傲慢だった」と述べると、ウィリアムの方も、「あなたのおかげで、父も落ち着いて死んだ」と述べたりします。
さらに、ジュリアが、生まれた娘をサラと名付けたと言うと、ウィリアムは泣き崩れてしまいます(こうした姿から、ジュリアとウィリアムとが結婚するに至るのではと考えられもしますが、ただジュリアは、ウィリアムに対し、「そろそろパリに戻ろうと考えている、ゾーイがニューヨークは嫌いというもので」と言うことなどからすると、そこまでには至らないのではと考えられるところです)。
(注9)サラ(シャーロット・ポートレル)は、車の事故で亡くなりますが、ウィリアムの父親(すなわちサラの夫)によれば、それは事故ではなく自殺だったとのこと。鬱状態となっていて、クスリやアルコールに溺れていたようです。
なお、劇場用パンフレットのProduction Notesには、「ブレネール監督とジョンクールは、小説では描かれなかった“大人になったサラ”のキャラクターを作り上げた」と述べられています。
確かに、原作小説では、サラを匿ってくれた農夫の孫の話として、「フランスとちがってホロコーストと無関係だったところにいきたい」と言って、「サラは1952年の末にフランスを出国した」とあったり(邦訳P.279)、「母の死は自殺だった」とウィリアムが述べるくらいがせいぜいのところです(邦訳P.375)。

(注10)妻の日記には、例えば、「私は勿論夫が日記をつけていることも、その日記帳をあの小机の抽出に入れて鍵をかけていることも、そしてその鍵を時としては書棚のいろいろな書物の間に、時としては床の絨毯の下に隠していることも、とうの昔から知っている」(P.14)と記載されている一方で、夫の日記には「妻ガコノ日記帳ヲ盗ミ読ミシテイルコトハ殆ド疑イナイ」と書かれているのです(新潮文庫P.33)。
また、夫の日記にも、「ヤッパリ推察通リダッタ。妻ハ日記ツケテイタノダ」、「今日彼女ガ映画ヲ見ニ出カケタ間ニ茶ノ間ヲ探シテ、容易ニ探リアテルコトヲ得タ」(新潮文庫P.56~P.57)と書かれています。
(注11)この小説は、これまで都合4回映画化されています〔Wikipediaのこの項目を参照。ただし、3番目の作品について、若松孝二は監督ではなくプロデューサー(監督は木俣尭喬)〕。
そこで、有名な第1番目(1959年)の市川昆監督のものをDVDで見てみましたが、映画自体は素晴らしい作品ながら、なんとそこでは「日記」も「鍵」も登場せずに、小説では脇役でしかない木村の話として、それもサスペンス物として描かれているのです。
なお、「鍵」について、3番目の作品(1983年)においては、このHPによれば、「この映画で言う「鍵」は日記帳の鍵ではなく、主人公の書斎にある金庫の鍵です。金庫の中には、妻との房事を事細かに綴った日記帳、怪しげな精力剤のアンプルと注射器、妻の裸体を撮るのに使うポラロイドカメラなどが入っている」とのことです。
(注12)なお、3月上旬の公開されるマーティン・スコセッシ監督の『ヒューゴの不思議な発明』の予告編を見ると、「ハート型の鍵」が重要な働きをするようで、また楽しみが一つ増えました。
★★★★☆
象のロケット:サラの鍵
(1)この映画は、以前見た『黄色い星の子供たち』で描かれたのと全く同様の事件(注1)を取り扱った作品で、そちらがかなり実録ベースであるのに対して、こちらはフィクション仕立てになっています(注2)。
そして、そちらは、当時のユダヤ人の視点に立ちながら、検挙されたユダヤ人が一旦「屋内競輪場(ヴェル・ディヴ)」に集められ、そこからフランス国内の収容所に移されて、ついにはドイツやポーランドの絶滅収容所に送られるところまでが映し出されますが、こちらは、現在の時点で展開される物語の中で、同じ事柄が描かれています。
すなわち、ジャーナリストのジュリア(クリスティン・スコット・トーマス)〔元はアメリカ人ですが、もう長いことパリで生活しています〕は、この事件に関するレポートを雑誌に掲載すべく取材しているうちに、とんでもないことが分かってきます。というのも、内部を大改装して自分たち家族がこれから住もうとしているアパートは、実は、この事件で検挙されたユダヤ人が居住していたものだったのです(ユダヤ人が立ち退いて空き室になったものを、昔、彼女の義理の祖父母が取得したという訳です)。
さらには、まさにその部屋で、この事件にまつわる忌まわしい出来事があったこともわかってきます。すなわち、1942年の事件に際して、その部屋に住んでいたサラ(メリュジーヌ・マヤンス)という少女が、ユダヤ人を検挙すべくフランス警察が押し入ってきた際に、弟ミシェルを逃れさせようと、納戸に入れて外から鍵を掛けてしまったのです(注3)。

サラは、「屋内競輪場(ヴェル・ディヴ)」を経由して地方の収容所に送られたものの、納戸に閉じ込めたままになってしまった弟のことばかりが気懸りで、やっとのことでそこを脱出して(注4)、パリのアパートに立ち戻り、それまで大事に握りしめていた鍵を使って納戸を開くのですが、……。
ジュリアは、その後のサラの行方を追い求めて、フィレンツェからニューヨークまで足を延ばします。
その間、なかなか身ごもらなかった彼女が2番目の子供を妊娠するも、夫のベルトランは、今更子供は欲しくないと言い出して(注5)、夫婦の間に大きな溝が出来てしまったり、過去の忌まわしい出来事をほじくり返そうとするジュリアに対して、義父とか、アメリカに渡ったサラにできた息子ウィリアムなどが強い不快感を示したりします。
映画を見るまでは、そして初めのうちは、『黄色い星野子供たち』と同じように、強制収容所のことが専ら描かれるのかな、と思っていましたが、現代に生きるジュリアが主人公だとわかってくると、映画の複雑な構成にも引きつけられて(注6)、久し振りに質の高い文芸作品を見たな(注7)、という充実した気分になりました。
主演のクリスティン・スコット・トーマスは、昨年公開された『ずっとあなたを愛してる』や『ノーウェアボーイ』で大変印象に残る演技を披露したところですが、本作においても、まさに彼女ならではの存在感のある瞠目の演技を披露しています。

(2)本作は、様々なレベルで読むことが出来ると思います。
例えば、いうまでもなく、1942年の「ヴェル・ディヴ事件」という観点から(ただこれは、『黄色い星の子供たち』でかなり描かれています)。
中心的には、ジュリアの生き方(アメリカ人が、「ヴェル・ディヴ事件」を通してユダヤ人問題に触れてどのように変わっていくか、など)。
あるいは、ジュリアとベルトラン(それに娘のゾーイ)の家族という観点。
または、過去の真実の追求ということ(注8)。
それに、サラの生きざま(注9)、などなど。
ただここでは、少し趣向を変えて、本作において重要な役割を果たしていると思われる「鍵」について少しばかり見てみましょう。
一つは、むろん、サラが弟を閉じ込めた納戸の「鍵」です。弟は自分の言うことを聞くから、自分で納戸を開けて出てきはしない、それでは大変なことになると思い、フランス国内の収容所に送られたサラは、「鍵」を使って納戸を開けることだけを考え詰めます。要すれば、開くために使われる「鍵」といっていいでしょう。
ところが、ジュリアの義理の父親は、ジュリアらがこれから住もうとしている家は1942年に祖父母が取得したものであること、さらにはサラが戻ってきて納戸を開けたことまで知っているにもかかわらず、それをずっと黙ってきたのです。その上、その事実をジュリアが明るみに出そうとすることに対して、義父は強く非難したりします。ここでは、過去を封じ込めるために、想像上の「鍵」が使われているといえるのではないでしょうか?
さらに、本作とは離れますが、もう一つの「鍵」の使い方もあるようです。
谷崎潤一郎の小説『鍵』においては、夫と妻が、それぞれ付けている日記を抽出などの隠し場所に隠していて、それに「鍵」をかけているのですが、その鍵の在り処をお互いに知っていて、隠してある日記はお互いに盗み見られていることがお互いに分かっている、という設定にされた上で、それぞれの日記がほぼ交互に掲載されていきます(注10)。
つまり、この小説における「鍵」は、かかっているようでいて、実はかかってはいない感じなのです(注11)。
なお、アメリカに渡ったサラが産んだウィリアムは、当初は、「鍵」をかけてしまっておく過去など何も持っていなかったにもかかわらず、ジュリアに母親がユダヤ人であると告げられると、鍵をかけておくべき過去があたかもあったかのような態度に出て、ジュリアを激しく拒絶します。これは、鍵のもう一つの使い方(なかった鍵を新たに作り出す、とでもいったらいいのでしょうか)といえるかもしれません(注12)。
(3)渡まち子氏は、「この物語は、ホロコーストを過去の“点”ではなく、現代へと続く線、あるいは面としてとらえることで、命は次世代に引き継がれ、未来への希望が生まれることを教えてくれる。ラストシーン、娘の名を聞かれたジュリアが答える場面では、胸いっぱいにあたたかい感動が広がった」として70点を付けています。
また、粉川哲夫氏は、ジュリアが、「謎を追い、パリから生まれ故郷のブルックリン、さらにはフィレンツェまで動くのは、一見「探偵ドラマ」風だが、それは、交互に描かれる古い時代のシーンとのたくみなバランスのなかで単なるエンターテインメントに堕すことをまぬがれる。収容所からからくも逃れ、生き延びたサラという少女の悲痛なドラマは、そのままならお涙頂戴のドラマになりかねないが、交互に挿入されるジュリアの「現在」(2009年とそれ以後)によって「異 化」され、内省的な静溢さをもたらしている」と、★を5つ付けています。
(注1)1942年に、パリのユダヤ人を一斉検挙した「ヴェル・ディヴ事件」のこと。1995年になって、当時のシラク大統領がその事実を公式に認めて、犠牲者に謝罪しました
(注2)本作は、タチアナ・ド・ロネの同名の小説(邦訳は高見浩訳で新潮社から)を映画化したものです。
(注3)劇場用パンフレットのProduction Notes には、「ブレネール監督とジョンクールが共同で手掛けた脚本は小説に忠実」ながら、「警察が来たとき、サラの弟は自ら納戸に隠れる」が、「映画では、サラが彼に隠れるように言う」、とあります。
確かに、原作小説では、警察が踏み込んできたとき、「僕、秘密の場所にいくよ」とミシェルは「ささやき」、「だめー」「一緒にいくのよ。こなきゃだめ」とサラは「せっつ」きます。サラは、「弟をつかまえようとし」ますが、ミッシェルは、「寝室の壁の裏に設けられた、奥行きのある納戸の中にもぐりこ」みます。「そこはいつも2人が隠れんぼをして遊ぶ場所」でした。そして、ミッシェルは、「怖くない。鍵をかけてくれれば、絶対につかまらないよ、ぼく」と言うのです。サラは、「外部の人間には、この壁の裏に納戸があるなどと見抜けないはずだ。弟はここにいたほうが安全だ。間違いない」、「あとで、きょうのうちに帰宅が許されたら、もどってきて弟を出しやればいいのだ」と思います(邦訳P.16~P.17)。
(注4)『黄色い星の子供たち』でも、少年ジョーがもう一人の少年と収容所を脱出するのですが、その作品では、途中経過が省かれて(裕福な家の養子となった、と説明されますが)、いきなり戦後となって、メラニー・ロラン扮する看護士がジョンと再会する場面となります。
これに対して、本作では、サラは友達と一緒に収容所を脱出しますが(『黄色い星の子供たち』と同じように、収容所の周囲は、背の高い草が一面に生えている草原なのです)、そこからサラが、自分のアパートに戻るまでが詳しく描き出されています。

すなわち、サラは、一度は追い出された農家で何とか匿われた上(もう一人の友人は、ジフテリアに罹って死んでしまいますが)、男の子に変装してパリに戻って、元の家に入り込みます。その後は、またその農家で働きますが、戦後暫くして、家出をしてしまいます。
(注5)夫のベルトランは、一人娘のゾーイが10代になっていることだし、アパートも整いつつあるし、それに年老いた父親になりたくない、といった理由で、ジュリアが子供を産むことに強く反対し続けます。
(注6)映画は、「1942年の最初の小麦がペタン元帥に送られました」との文字映像から始まり、フランス警察がサラたちの住むアパートに乗り込んで来る場面となり、ついで、ジュリアが勤務する雑誌社の編集会議のシーン、そして1942年の「冬季競輪場」へという具合に、当時と今とが煩雑に入り組んで映し出されます。
(注7)例えば、ジュリアの一家の一人娘ゾーイは、多感な時期で(14歳)、ジュリアが何も説明しないで各地を飛び回っていることなどに批判的ですし、また今頃自分に妹ができることも釈然としない感じです。ジュリアが出産後夫と別れてニューヨークで生活するときも同行するものの、やはり父親のいるパリの方がいいと言い出す始末。といった具合に、登場人物一人一人に複雑な性格が与えられているのです。
なお、ゾーイが父親とPC電話で話していると、その最中に、父親の方の画面に、彼が一緒に暮らしているらしい女性が一時現れたりするのです。
(注8)サラがアメリカで産んだウィリアム(エイダン・クイン)は、生まれてスグにカトリックの洗礼を受けたこともあって、自分がユダヤ人であることを知らずに大人になりました。ですから、当初ジュリアから母親のサラのことを聞いた時は、酷いショックを受け、その事実を受け入れることを拒絶します。

ですが、その後、病に伏せる父親から、母親サラの真実の姿を知らされ(「彼女は私が人生の中で出会った女性の中で一番美しい」などと語ります)、また遺品なども手渡されます(手渡されたノートから、例の「鍵」が出てきます)。
それで、ジュリアがニューヨークに移り住んで再会した時には、ウィリアムの態度は一変しています。ジュリアが、「自分の態度は傲慢だった」と述べると、ウィリアムの方も、「あなたのおかげで、父も落ち着いて死んだ」と述べたりします。
さらに、ジュリアが、生まれた娘をサラと名付けたと言うと、ウィリアムは泣き崩れてしまいます(こうした姿から、ジュリアとウィリアムとが結婚するに至るのではと考えられもしますが、ただジュリアは、ウィリアムに対し、「そろそろパリに戻ろうと考えている、ゾーイがニューヨークは嫌いというもので」と言うことなどからすると、そこまでには至らないのではと考えられるところです)。
(注9)サラ(シャーロット・ポートレル)は、車の事故で亡くなりますが、ウィリアムの父親(すなわちサラの夫)によれば、それは事故ではなく自殺だったとのこと。鬱状態となっていて、クスリやアルコールに溺れていたようです。
なお、劇場用パンフレットのProduction Notesには、「ブレネール監督とジョンクールは、小説では描かれなかった“大人になったサラ”のキャラクターを作り上げた」と述べられています。
確かに、原作小説では、サラを匿ってくれた農夫の孫の話として、「フランスとちがってホロコーストと無関係だったところにいきたい」と言って、「サラは1952年の末にフランスを出国した」とあったり(邦訳P.279)、「母の死は自殺だった」とウィリアムが述べるくらいがせいぜいのところです(邦訳P.375)。

(注10)妻の日記には、例えば、「私は勿論夫が日記をつけていることも、その日記帳をあの小机の抽出に入れて鍵をかけていることも、そしてその鍵を時としては書棚のいろいろな書物の間に、時としては床の絨毯の下に隠していることも、とうの昔から知っている」(P.14)と記載されている一方で、夫の日記には「妻ガコノ日記帳ヲ盗ミ読ミシテイルコトハ殆ド疑イナイ」と書かれているのです(新潮文庫P.33)。
また、夫の日記にも、「ヤッパリ推察通リダッタ。妻ハ日記ツケテイタノダ」、「今日彼女ガ映画ヲ見ニ出カケタ間ニ茶ノ間ヲ探シテ、容易ニ探リアテルコトヲ得タ」(新潮文庫P.56~P.57)と書かれています。
(注11)この小説は、これまで都合4回映画化されています〔Wikipediaのこの項目を参照。ただし、3番目の作品について、若松孝二は監督ではなくプロデューサー(監督は木俣尭喬)〕。
そこで、有名な第1番目(1959年)の市川昆監督のものをDVDで見てみましたが、映画自体は素晴らしい作品ながら、なんとそこでは「日記」も「鍵」も登場せずに、小説では脇役でしかない木村の話として、それもサスペンス物として描かれているのです。
なお、「鍵」について、3番目の作品(1983年)においては、このHPによれば、「この映画で言う「鍵」は日記帳の鍵ではなく、主人公の書斎にある金庫の鍵です。金庫の中には、妻との房事を事細かに綴った日記帳、怪しげな精力剤のアンプルと注射器、妻の裸体を撮るのに使うポラロイドカメラなどが入っている」とのことです。
(注12)なお、3月上旬の公開されるマーティン・スコセッシ監督の『ヒューゴの不思議な発明』の予告編を見ると、「ハート型の鍵」が重要な働きをするようで、また楽しみが一つ増えました。
★★★★☆
象のロケット:サラの鍵