
(1)前回のエントリでは映画『幻肢』を取り上げましたが、同エントリの「(2)」で触れた「幻肢」(あるいは幻影肢、もしくは幻像肢)の現象について考察したのが、著名なフランス哲学者のメルロ=ポンティです(注1)。
(2)彼は、主著とされる『知覚の現象学』(注2)において、件の「幻肢」につき、だいたいこんなことを述べています(注3)。
・「幻肢」は、生理学によっても心理学によっても説明できない現象である(注4)。
・「幻肢」は、我々は「世界内存在」である(我々は、ある環境の内にしっかりとつなぎとめられている)、という視角から見てはじめて了解できる現象である。
つまり、手足の切断を認めまいとするのは、今までどおりの自分の世界に立ち向かおうとしていることであり、「腕のみがなしうるところのあらゆる行動の可能性を今もなお所持しているということである」(注5)。
・要すれば、「幻肢」の現象は、(「私の」という)人称的な「現実の身体」の層によっていわば「抑圧」されている(「ひと」という)非人称的な「習慣的身体」の層が、顔をのぞかせ、一時的に「現実の身体」につきまとう、ということであろう(注6)。
(3)さて最近、渋谷の大型書店を覗いてみたところ、なんとまさにこのメルロ=ポンティと、さらには同じくフランスの哲学者ジル・ドゥルーズ(注7)とを主題的に取り扱っている新刊本『経験と出来事 メルロ=ポンティとドゥルーズにおける身体の哲学』(小林徹著 水声社)が、哲学・現代思想コーナーに陳列してあるではありませんか!
普段から至極ミーハーなクマネズミは、これも何かの縁と思い、本文が350ページに及ぶ分厚さにもかかわらず、早速目を通すことにしてみました。
とはいえ、本書は、ただでさえ難しいメルロ=ポンティのみならず、独特の言い回し(注8)などで素人のアクセスを困難なものにしているドゥルーズまでも取り上げているために(注9)、読む側に一層の負担を強いるものになっています。
それに、元々本書は、新進気鋭の哲学者である著者の小林徹氏(注10)が、留学先のパリ第一大学に提出した博士論文の「翻訳改訂版」であって(注11)、高度に専門的な著作。哲学方面の専門的な訓練を受けたことがないクマネズミにとって、到底歯が立つようなシロモノではありません。あえなく途中で挫折してしまいました。
それでも、ネズミ特有の前歯を使ってところどころ強引に齧ったところから本書の全体の構想を少しだけ推測してみると、次のようになるかもしれません。すなわち、
メルロ=ポンティとドゥルーズの哲学の間には随分と大きな溝がある〔第1部:「それぞれ独自の身体概念を打ちたて、それを刷新し続ける」(P.18)〕。
でも、二人の依って立つところを定めてその溝を明確化すると、逆に二つの哲学が交叉する点も見えてくる〔第2部:「そこにはいつも一つの同じ〈身体〉が留まっている」(同)〕。
そして、この交叉するから絵画とか映画といった視覚芸術を眺めると、現代思想の要のところが見えてくる〔第3部:「現代的な思考に相応しい身体概念(〈身体〉)の在り処を指し示す」(同)〕。
ただ、そんな青写真をいくら描いてみても、持ち合わせの貧弱な素人がその中に入り込むことは困難を極めます。
思うに、本書がクマネズミにとり難解なのは、勿論、専門書だからということが第一ですが、それだけでなく、類書に見られない姿勢で書かれていることも大いに与っている気がします。
すなわち、本書の場合、「序論」の冒頭で「透明に、偏りなく。これが本書を貫く主要なモチーフであるある」(P.13)と述べられているように、メルロ=ポンティとドゥルーズの著作に限りなく寄り添いながら、その間から垣間見えてくるものを探し出す著者の作業がスリリングに進められているのが特色的でしょう。
ただそんなことをすれば、何しろ「彼らの間には、少なくとも公式には討論も対話も行われなかった」のですから(P.15)、著者の作業が困難を極めたものになるのは当然でしょうし、読む側にも忍耐が求められます。
それでも、読者は、彼らの哲学を解説する著作を読む場合のように単なる知識を取得するだけに終わるということはまったくありませんし、また彼らの哲学を踏み台にして自説を展開する著作のようないかがわしさを感じることもないでしょう。むしろ、著者に導かれつつ、「ある哲学的言説の純粋な展開に身を置くこと」(P.13)によって、読者も自ずと一緒に哲学せざるを得なくなるものと思います。
(4)もしかしたら、こういった大層専門的な著作を素人が読む場合には、行きつ戻りつしながら時間をかけなければならないにしても、どんなことでもかまいませんから何か取っ掛かりとなる点があれば、前に進み易いかもしれません。
例えば、上で問題にした「幻肢」は、本書とどのように関連してくるでしょうか?
メルロ=ポンティは、上で見たように、「幻肢」の現象は生理学によっても心理学によっても説明できない現象であるとしていますが、その際、生理学は経験主義に基づくものとし、心理学を主知主義に依っているとしていますから(注12)、結局のところは、経験主義と主知主義のいずれをも認めていないことになるでしょう。
そしてこのことは、本書の第1部第1章で述べられている文章、すなわち、「ここに、科学的思考の経験主義と、観念論的哲学の主知主義に対するメルロ=ポンティの二重の闘いが存する」とか、「「経験主義も主知主義も、知覚的世界が織り成している複雑な構造についての、抽象的な二つの見方にすぎない」といった文章(いずれもP.38)に接続されるのではないかと考えられます。
また、例えば、本書の第1部第2章では、「われわれは、いわば他人の身体の内部に住み着くことによって、そして同時に私自身の身体にその所作を住み着かせることによって、その「意味」を知るのである。このような相互身体的交流に、個人的なものにせよ集団的なものにせよ、「意識」や「意図」が介入する余地はないだろう」(P.49)と述べられていますが、その文章は、ちょうどその頃DVDで見た『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』(1997年)(注13)を想起させました。
というのも、その作品のラストでは、ショーン(ロビン・ウィリアムズ)はウィル(マット・デイモン)をセラピストとして診るのですが、最後には、言葉なしに突然二人が抱きあうことによって、黙って、ショーンはインド・中国に旅立ち、ウィルもカリフォルニアに行った恋人に会いに行くことになるのです。
要すれば、ショーンは、既存の理論でウィルを一方的に診断・治療しようとするのではなく、真剣に話し合っていくうちに、相手の心も開いていきますが、自分の心も知らず知らずと変わってしまうのです(ショーンはウィルに対して、こうすべきだああした方がいいなどとは決して言いません)。
著者が本書で書いているのとは次元が違うことを申し上げているかもしれませんが、「相互身体的交流」という言葉に興味が惹かれたところです。
更に言えば、拙ブログでは、本書の第3部第2章「スタイルの発生」で取り上げられているパウル・クレーについて、このエントリでほんの少々ながら触れましたし、また、このエントリで取り扱っているフランシス・ベーコンは、本書の第3部第5章「絵画の力」で議論されています。
もっと言えば、第3部第6章「運動と時間―二つの映画論」は、拙ブログ全体にかかわるテーマを取り扱っています。
〔追記:本項に関連したことをこの拙エントリで書きましたので、そちらをもご覧になっていただければ幸いです〕
(5)こんなあれこれがわかってくると、本書に対する興味がまた一段と沸き起こってきて、どうやらこの秋冬は再度本書と格闘するハメになりそうです。
その際にクマネズミにとり救いとなるのは、大層明晰で淀みなく流れるような文章によって本書全体が綴られていることです(注14)。近頃目にすることが珍しいこうした素晴らしい文章を味わうのもまた無上の愉しみとなるでしょう。
みなさんも、興味を持たれたら、どうぞ一度書店で本書を手にとってご覧になられては如何でしょうか(注15)?
(注1)拙ブログでは、以前、このエントリでメルロ=ポンティに触れたことがあります。

なお、「幻肢」の問題を取り上げた哲学者はメルロ=ポンティだけでなく、古くはデカルトがいます(その『哲学原理』において、いわば生理学的な説明を行っています:例えば、このサイトの記事を参照)。
(注2)中島盛夫訳(法政大学出版局、1982年刊)。なお、以下の『知覚の現象学』からの引用は、すべてこの邦訳によっています。
(注3)ここらあたりの記述は、木田元著『メルロ=ポンティの思想』(岩波書店、1984年)の「Ⅲ-3」に依っています。
なお、ここでの要約では、あまりにも簡略にすぎるかもしれません。
例えば、中山元氏のこのエッセイ(「幻影肢の問題性 『知覚の現象学』を読む(四)」)が参考になるのではないでしょうか。
(注4)「(幻像肢は、)生理学的説明も心理学的説明も、また両者の混合による説明も受けつけないのである」(『知覚の現象学』P.147)。
『知覚の現象学』では、さらに次のように述べられています。
「コカインによる麻酔も幻像肢を消滅させることはできない。肢体を切断されていない場合でも、脳髄の障害につづいて幻像肢体が現れることがある」(P.141)。むしろ、「この現象は実際に、「心的」な決定因子に依存している」のだ(P.141)。しかしながら、「いかなる心理学的説明も、脳髄に向かう感覚導体の切断が幻像肢を消失せしめるという事実(脳に通じる求心性の神経を切断すれば「幻肢」は消えてしまうということ)を、無視することは許されない」(P.142)。従って、「心的決定因子と生理的条件とが、どのように噛み合うかを理解しなくてはならない」のだ(P.142)。
ちなみに、映画『幻肢』の劇場用パンフレット掲載の原作者・島田荘司氏のエッセイ「『幻肢』への想い」では、「幻肢」について、「これは簡単に言うと、前頭葉の運動野が筋肉に向かって出した命令を、四肢の断端付近が、存在しない筋肉が命令通りの運動を成したとする偽の情報を戻すことによって、小脳と前頭葉をだますという現象です」と説明されていますが、生理学的な説明といえるでしょう。
更にそこでは、「これは、四肢の喪失という絶望が、その個体の生存に危機をもたらしかねないような深刻な局面においては、保身のため、脳が喪失部位の幻を見せる、ととらえることも可能です」とも説明されていますが、心理学的な説明といえるでしょう。
(注5)『知覚の現象学』P.149。
(注6)映画『幻肢』で描き出される遥(谷村美月)の「幽霊」についても、自動車事故によって雅人(吉木遼)の無意識の中に「抑圧」された遥の姿が、雅人がTMSを受けることによって次第に雅人の現実の世界に現れ出てきたもの、というように解釈できるかもしれません。
この場合、「幻肢」が患者本人しか認められないのと同じように、映画における遥の「幽霊」も、雅人によってしか見ることができません。
ただ、一般に言われる「幽霊」にはそのような制限があるとはされていませんから、「幻肢」現象から「幽霊」を説明しようとする雅人の仮説(前回エントリの「注6」を参照)の一般性には疑問がもたれるところです。
なお、前記の「注4」で触れたエッセイにおいて島田氏は、「子供や恋人など、その個体にとって自身の四肢と同等の重要さを持つ外部の存在が失われた際、脳はこの「幻肢」のプロセスを利用して、そうした他者の姿を見せ、生存のための前頭葉をだまそうとする、それが幽霊なのだ、ととらえることもできます」と述べているところ、この説明では、「幻肢」と同様に幽霊はいつでも見えている必要があることになります。ですが、映画において遥の幽霊が現れるのは、雅人がTMSを受けた際に限られているのです。
(注7)拙ブログでは、以前、このエントリの(2)とか、このエントリの「注2」や「注10」でドゥルーズにほんの少々触れたことがあります。
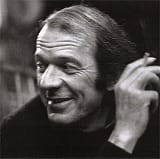
(注8)本書においても、「アイオン」、「クロノス」、「器官なき身体」などといった用語が用いられています。
(注9)本書の「参考文献」で取り上げられていますが、昨年から本年にかけてドゥルーズを取り上げている著作が次々と刊行されています〔例えば、千葉雅也著『動きすぎてはいけない―ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社):なお、同氏については、このエントリで取り上げています〕。
(注10)本書の奥付にある略歴によれば、1975年生まれ。
(注11)本書の「あとがき」によります。
(注12)『知覚の現象学』では、例えば、「知覚の生理学は、一定の受容器から発し一定の伝達器を経て、これもまた特殊化した記録係に達する解剖学的な道程を、最初から仮定してかかる」と述べられ(P.35)、合わせて「経験主義は、われわれの知覚内容を、感覚器官に作用する刺激の物理-科学的性質によって改めて定義し、怒りや苦痛を、宗教や都市を、近くできないものと見なすのである」と述べられていることからすれば(P.61)、生理学が経験主義に基づいているとメルロ=ポンティがみなしていることは明らかのように思われます。
他方で、「知覚を「解釈」と見なす理論―こういう心理学者たちの主知主義―は、じじつ経験主義の相手方にすぎない」と述べられています(P.81)。
(注13)映画全体のストーリーについては、例えばこちらをご覧ください。

なお、このDVDを見たのは、その頃映画館で見た『プロミスト・ランド』と同じ監督(ガス・ヴァン・サント)・主演(マット・デイモン)の作品だからです。
(注14)これは訳文にも及んでいます。
例えば、『知覚の現象学』の「序文」からの引用ですが、中島盛夫氏の訳が「知覚は世界に関する一つの科学ではない。それは一つの行為ですらない。つまり熟慮を経た上での態度の決定ではない。知覚は、その上にあらゆる行為が浮かびあがる背景であり、行為はこれを前提としている」(P.7)となっているところ、本書では「知覚は世界についての科学ではない。それは行為や断定的な態度決定ですらない。それはあらゆる行為がその上に浮かび上がっている背景なのであり、それらが前提しているものなのである」(P.30)と訳されています。
ほぼ同一内容の文章ながら、後者の方にクマネズミはメルロ=ポンティの畳み掛けるような息遣いを感じるところです。
(注15)本書の装幀も、森麗子氏(例えば、このサイトの記事が参考になります)の「地図」を使ったセンス溢れるものとなっています(装幀は、atelier fusain氏)。
(2)彼は、主著とされる『知覚の現象学』(注2)において、件の「幻肢」につき、だいたいこんなことを述べています(注3)。
・「幻肢」は、生理学によっても心理学によっても説明できない現象である(注4)。
・「幻肢」は、我々は「世界内存在」である(我々は、ある環境の内にしっかりとつなぎとめられている)、という視角から見てはじめて了解できる現象である。
つまり、手足の切断を認めまいとするのは、今までどおりの自分の世界に立ち向かおうとしていることであり、「腕のみがなしうるところのあらゆる行動の可能性を今もなお所持しているということである」(注5)。
・要すれば、「幻肢」の現象は、(「私の」という)人称的な「現実の身体」の層によっていわば「抑圧」されている(「ひと」という)非人称的な「習慣的身体」の層が、顔をのぞかせ、一時的に「現実の身体」につきまとう、ということであろう(注6)。
(3)さて最近、渋谷の大型書店を覗いてみたところ、なんとまさにこのメルロ=ポンティと、さらには同じくフランスの哲学者ジル・ドゥルーズ(注7)とを主題的に取り扱っている新刊本『経験と出来事 メルロ=ポンティとドゥルーズにおける身体の哲学』(小林徹著 水声社)が、哲学・現代思想コーナーに陳列してあるではありませんか!
普段から至極ミーハーなクマネズミは、これも何かの縁と思い、本文が350ページに及ぶ分厚さにもかかわらず、早速目を通すことにしてみました。
とはいえ、本書は、ただでさえ難しいメルロ=ポンティのみならず、独特の言い回し(注8)などで素人のアクセスを困難なものにしているドゥルーズまでも取り上げているために(注9)、読む側に一層の負担を強いるものになっています。
それに、元々本書は、新進気鋭の哲学者である著者の小林徹氏(注10)が、留学先のパリ第一大学に提出した博士論文の「翻訳改訂版」であって(注11)、高度に専門的な著作。哲学方面の専門的な訓練を受けたことがないクマネズミにとって、到底歯が立つようなシロモノではありません。あえなく途中で挫折してしまいました。
それでも、ネズミ特有の前歯を使ってところどころ強引に齧ったところから本書の全体の構想を少しだけ推測してみると、次のようになるかもしれません。すなわち、
メルロ=ポンティとドゥルーズの哲学の間には随分と大きな溝がある〔第1部:「それぞれ独自の身体概念を打ちたて、それを刷新し続ける」(P.18)〕。
でも、二人の依って立つところを定めてその溝を明確化すると、逆に二つの哲学が交叉する点も見えてくる〔第2部:「そこにはいつも一つの同じ〈身体〉が留まっている」(同)〕。
そして、この交叉するから絵画とか映画といった視覚芸術を眺めると、現代思想の要のところが見えてくる〔第3部:「現代的な思考に相応しい身体概念(〈身体〉)の在り処を指し示す」(同)〕。
ただ、そんな青写真をいくら描いてみても、持ち合わせの貧弱な素人がその中に入り込むことは困難を極めます。
思うに、本書がクマネズミにとり難解なのは、勿論、専門書だからということが第一ですが、それだけでなく、類書に見られない姿勢で書かれていることも大いに与っている気がします。
すなわち、本書の場合、「序論」の冒頭で「透明に、偏りなく。これが本書を貫く主要なモチーフであるある」(P.13)と述べられているように、メルロ=ポンティとドゥルーズの著作に限りなく寄り添いながら、その間から垣間見えてくるものを探し出す著者の作業がスリリングに進められているのが特色的でしょう。
ただそんなことをすれば、何しろ「彼らの間には、少なくとも公式には討論も対話も行われなかった」のですから(P.15)、著者の作業が困難を極めたものになるのは当然でしょうし、読む側にも忍耐が求められます。
それでも、読者は、彼らの哲学を解説する著作を読む場合のように単なる知識を取得するだけに終わるということはまったくありませんし、また彼らの哲学を踏み台にして自説を展開する著作のようないかがわしさを感じることもないでしょう。むしろ、著者に導かれつつ、「ある哲学的言説の純粋な展開に身を置くこと」(P.13)によって、読者も自ずと一緒に哲学せざるを得なくなるものと思います。
(4)もしかしたら、こういった大層専門的な著作を素人が読む場合には、行きつ戻りつしながら時間をかけなければならないにしても、どんなことでもかまいませんから何か取っ掛かりとなる点があれば、前に進み易いかもしれません。
例えば、上で問題にした「幻肢」は、本書とどのように関連してくるでしょうか?
メルロ=ポンティは、上で見たように、「幻肢」の現象は生理学によっても心理学によっても説明できない現象であるとしていますが、その際、生理学は経験主義に基づくものとし、心理学を主知主義に依っているとしていますから(注12)、結局のところは、経験主義と主知主義のいずれをも認めていないことになるでしょう。
そしてこのことは、本書の第1部第1章で述べられている文章、すなわち、「ここに、科学的思考の経験主義と、観念論的哲学の主知主義に対するメルロ=ポンティの二重の闘いが存する」とか、「「経験主義も主知主義も、知覚的世界が織り成している複雑な構造についての、抽象的な二つの見方にすぎない」といった文章(いずれもP.38)に接続されるのではないかと考えられます。
また、例えば、本書の第1部第2章では、「われわれは、いわば他人の身体の内部に住み着くことによって、そして同時に私自身の身体にその所作を住み着かせることによって、その「意味」を知るのである。このような相互身体的交流に、個人的なものにせよ集団的なものにせよ、「意識」や「意図」が介入する余地はないだろう」(P.49)と述べられていますが、その文章は、ちょうどその頃DVDで見た『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』(1997年)(注13)を想起させました。
というのも、その作品のラストでは、ショーン(ロビン・ウィリアムズ)はウィル(マット・デイモン)をセラピストとして診るのですが、最後には、言葉なしに突然二人が抱きあうことによって、黙って、ショーンはインド・中国に旅立ち、ウィルもカリフォルニアに行った恋人に会いに行くことになるのです。
要すれば、ショーンは、既存の理論でウィルを一方的に診断・治療しようとするのではなく、真剣に話し合っていくうちに、相手の心も開いていきますが、自分の心も知らず知らずと変わってしまうのです(ショーンはウィルに対して、こうすべきだああした方がいいなどとは決して言いません)。
著者が本書で書いているのとは次元が違うことを申し上げているかもしれませんが、「相互身体的交流」という言葉に興味が惹かれたところです。
更に言えば、拙ブログでは、本書の第3部第2章「スタイルの発生」で取り上げられているパウル・クレーについて、このエントリでほんの少々ながら触れましたし、また、このエントリで取り扱っているフランシス・ベーコンは、本書の第3部第5章「絵画の力」で議論されています。
もっと言えば、第3部第6章「運動と時間―二つの映画論」は、拙ブログ全体にかかわるテーマを取り扱っています。
〔追記:本項に関連したことをこの拙エントリで書きましたので、そちらをもご覧になっていただければ幸いです〕
(5)こんなあれこれがわかってくると、本書に対する興味がまた一段と沸き起こってきて、どうやらこの秋冬は再度本書と格闘するハメになりそうです。
その際にクマネズミにとり救いとなるのは、大層明晰で淀みなく流れるような文章によって本書全体が綴られていることです(注14)。近頃目にすることが珍しいこうした素晴らしい文章を味わうのもまた無上の愉しみとなるでしょう。
みなさんも、興味を持たれたら、どうぞ一度書店で本書を手にとってご覧になられては如何でしょうか(注15)?
(注1)拙ブログでは、以前、このエントリでメルロ=ポンティに触れたことがあります。

なお、「幻肢」の問題を取り上げた哲学者はメルロ=ポンティだけでなく、古くはデカルトがいます(その『哲学原理』において、いわば生理学的な説明を行っています:例えば、このサイトの記事を参照)。
(注2)中島盛夫訳(法政大学出版局、1982年刊)。なお、以下の『知覚の現象学』からの引用は、すべてこの邦訳によっています。
(注3)ここらあたりの記述は、木田元著『メルロ=ポンティの思想』(岩波書店、1984年)の「Ⅲ-3」に依っています。
なお、ここでの要約では、あまりにも簡略にすぎるかもしれません。
例えば、中山元氏のこのエッセイ(「幻影肢の問題性 『知覚の現象学』を読む(四)」)が参考になるのではないでしょうか。
(注4)「(幻像肢は、)生理学的説明も心理学的説明も、また両者の混合による説明も受けつけないのである」(『知覚の現象学』P.147)。
『知覚の現象学』では、さらに次のように述べられています。
「コカインによる麻酔も幻像肢を消滅させることはできない。肢体を切断されていない場合でも、脳髄の障害につづいて幻像肢体が現れることがある」(P.141)。むしろ、「この現象は実際に、「心的」な決定因子に依存している」のだ(P.141)。しかしながら、「いかなる心理学的説明も、脳髄に向かう感覚導体の切断が幻像肢を消失せしめるという事実(脳に通じる求心性の神経を切断すれば「幻肢」は消えてしまうということ)を、無視することは許されない」(P.142)。従って、「心的決定因子と生理的条件とが、どのように噛み合うかを理解しなくてはならない」のだ(P.142)。
ちなみに、映画『幻肢』の劇場用パンフレット掲載の原作者・島田荘司氏のエッセイ「『幻肢』への想い」では、「幻肢」について、「これは簡単に言うと、前頭葉の運動野が筋肉に向かって出した命令を、四肢の断端付近が、存在しない筋肉が命令通りの運動を成したとする偽の情報を戻すことによって、小脳と前頭葉をだますという現象です」と説明されていますが、生理学的な説明といえるでしょう。
更にそこでは、「これは、四肢の喪失という絶望が、その個体の生存に危機をもたらしかねないような深刻な局面においては、保身のため、脳が喪失部位の幻を見せる、ととらえることも可能です」とも説明されていますが、心理学的な説明といえるでしょう。
(注5)『知覚の現象学』P.149。
(注6)映画『幻肢』で描き出される遥(谷村美月)の「幽霊」についても、自動車事故によって雅人(吉木遼)の無意識の中に「抑圧」された遥の姿が、雅人がTMSを受けることによって次第に雅人の現実の世界に現れ出てきたもの、というように解釈できるかもしれません。
この場合、「幻肢」が患者本人しか認められないのと同じように、映画における遥の「幽霊」も、雅人によってしか見ることができません。
ただ、一般に言われる「幽霊」にはそのような制限があるとはされていませんから、「幻肢」現象から「幽霊」を説明しようとする雅人の仮説(前回エントリの「注6」を参照)の一般性には疑問がもたれるところです。
なお、前記の「注4」で触れたエッセイにおいて島田氏は、「子供や恋人など、その個体にとって自身の四肢と同等の重要さを持つ外部の存在が失われた際、脳はこの「幻肢」のプロセスを利用して、そうした他者の姿を見せ、生存のための前頭葉をだまそうとする、それが幽霊なのだ、ととらえることもできます」と述べているところ、この説明では、「幻肢」と同様に幽霊はいつでも見えている必要があることになります。ですが、映画において遥の幽霊が現れるのは、雅人がTMSを受けた際に限られているのです。
(注7)拙ブログでは、以前、このエントリの(2)とか、このエントリの「注2」や「注10」でドゥルーズにほんの少々触れたことがあります。
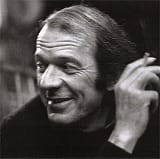
(注8)本書においても、「アイオン」、「クロノス」、「器官なき身体」などといった用語が用いられています。
(注9)本書の「参考文献」で取り上げられていますが、昨年から本年にかけてドゥルーズを取り上げている著作が次々と刊行されています〔例えば、千葉雅也著『動きすぎてはいけない―ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社):なお、同氏については、このエントリで取り上げています〕。
(注10)本書の奥付にある略歴によれば、1975年生まれ。
(注11)本書の「あとがき」によります。
(注12)『知覚の現象学』では、例えば、「知覚の生理学は、一定の受容器から発し一定の伝達器を経て、これもまた特殊化した記録係に達する解剖学的な道程を、最初から仮定してかかる」と述べられ(P.35)、合わせて「経験主義は、われわれの知覚内容を、感覚器官に作用する刺激の物理-科学的性質によって改めて定義し、怒りや苦痛を、宗教や都市を、近くできないものと見なすのである」と述べられていることからすれば(P.61)、生理学が経験主義に基づいているとメルロ=ポンティがみなしていることは明らかのように思われます。
他方で、「知覚を「解釈」と見なす理論―こういう心理学者たちの主知主義―は、じじつ経験主義の相手方にすぎない」と述べられています(P.81)。
(注13)映画全体のストーリーについては、例えばこちらをご覧ください。

なお、このDVDを見たのは、その頃映画館で見た『プロミスト・ランド』と同じ監督(ガス・ヴァン・サント)・主演(マット・デイモン)の作品だからです。
(注14)これは訳文にも及んでいます。
例えば、『知覚の現象学』の「序文」からの引用ですが、中島盛夫氏の訳が「知覚は世界に関する一つの科学ではない。それは一つの行為ですらない。つまり熟慮を経た上での態度の決定ではない。知覚は、その上にあらゆる行為が浮かびあがる背景であり、行為はこれを前提としている」(P.7)となっているところ、本書では「知覚は世界についての科学ではない。それは行為や断定的な態度決定ですらない。それはあらゆる行為がその上に浮かび上がっている背景なのであり、それらが前提しているものなのである」(P.30)と訳されています。
ほぼ同一内容の文章ながら、後者の方にクマネズミはメルロ=ポンティの畳み掛けるような息遣いを感じるところです。
(注15)本書の装幀も、森麗子氏(例えば、このサイトの記事が参考になります)の「地図」を使ったセンス溢れるものとなっています(装幀は、atelier fusain氏)。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます