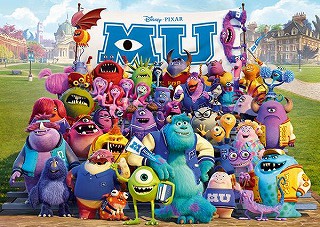『モンスターズ・ユニバーシティ』の3D・吹替版を吉祥寺オデヲンで見ました。
(1)本作は、『モンスターズ・インク』(2001年)の前日譚。
前作ではサリーとマイクというモンスターがモンスターズ株式会社(Monsters Inc.)で働いていましたが、本作ではその二人がモンスターズ・ユニバーシティ(Monsters Univ.)の学生となって、そこのトップである「怖がらせ学部」(School of Scaring)に入り、様々な出来事の末、結局は退学させられて同社に入社することになるというお話です。

一番大きな出来事は、同大学伝統の「怖がらせ大会」(The Scare Games)。
期末試験を台無しにしてしまい、学長に、「怖がらせ学部」に向いていないと宣告され追放されてしまったマイクとサリーは、学長と掛け合って、その大会で優勝すれば元の学部に戻してもらえることになります(ただし、「負ければ大学を辞めてもらいます」と言われてしまうのですが)。
そこで、二人は「OK」(ウーズマ・カッパ:注1)というサークルに入って、6名のモンスターから成るチームを結成します。
ただ、マイク一人やる気があるものの、「OK」の他のメンバーは、実力のあるサリーを除いて落ちこぼればかり。
ですが、他のチームが失格したりしたためなんとか「OK」は生き残り、最後に、最強のチームである「RΩR」(ロアー・オメガ・ロアー:注2)と対決することに(注3)。
さあ、「OK」は勝ち抜くことができるでしょうか、……?
アニメですから当然のことながら、モンスターといっても皆、実にユーモラスな存在でちっとも怖くはありません。となると、外見はともかく、本作で描かれるモンスターの行動は人間とまるで同じようにみえ、わざわざこうした作品に仕立てる意味がどこにあるのか、といささか疑問に思えてきます(注4)。それでも、実にカラフルな画像が映し出され、それも3Dですから、おのずと映画の中に引き込まれてしまうのですが。
(2)まったくどうでもいいことながら、モンスター達がこの大学(注5)で学ぶ意味は奈辺にあるのでしょう?
だいたい、入学が認められる「モンスター」にはどんなものが含まれるのでしょう(日本の大学のような厳しい入学試験はないのかもしれないものの、受験資格は問われるでしょう)?
公式サイトの最初のページなどで見られるモンスターたちの集合写真からすると、ゴジラのような怪獣とか、日本の各種の「お化け」といった妖怪は入っていないようですから、いわゆる怪物に資格が与えられているのかもしれません。
でも、それらの線引きはどうなっているのでしょう?
あるいは、外国籍のものの留学は、この大学では認められていないのでしょうか(注6)?
もともと、モンスターズ・インクやモンスターズ・ユニバーシティのあるモンスター・シティ自体が、かなり閉鎖的な都市なのかもしれません(TPPの対象として開放するとしたら、こういうところから手を付けていったらどうでしょう)。
また、この大学のトップの学部が「怖がらせ学部」だとしたら(注7)、大学で教える学問のトップは「人間をいかに怖がらせるか」に関するものでしょう。
でも、「怖がらせる」〔あるいは「怖がる」(be scared:注8)〕というような、酷く主観的で、人により、地域により、民族によって違い、決して普遍的なものではないことについて、モンスターたちは大学でいったい何を学ぶというのでしょうか?
確かに、実際の人間世界では美術大学とか音楽大学などが設けられており、“芸術”というわけのわからないことがらが教えられているのですから、「怖がらせる」ことについても学問が成立するのかもしれません。
とはいえ、その場合の学問としては、「美術」における美術史や色彩理論だったり、「音楽」における音楽史や音楽理論だったりするように、「怖がらせる」ことに関する歴史とか理論ということになるでしょう。
そうだとしたら、本作においては、「怖がらせ学部」にマイクは不適とされていますが(注9)、むしろ話は逆で、ナイト教授の講義のみならず、関係の著作をいろいろ読破して自分のものにしているマイクこそが、優秀な大学生として学長に表彰されるべきなのではないでしょうか(注10)?

なお、このアニメを見に来ている幼い子供たちに、モンスター・ユニバーシティに設けられている学部とかサークル組織などについて、どの程度理解できるのか〔日本の大学の部とかサークルとも違うようですから(注11)、正直、クマネズミには分かりません〕、やや疑問に思えます。
それはともかく、モンスターの教育という観点はかなり興味をそそります。
でも、アレッ、モンスターって子どもから大人に成長するものなの?
そもそも、誰がモンスターを産むのでしょう?モンスターに性別があるのかしら(注12)?
そういえば、大学時代で最重要事項の一つの恋愛は、本作ではどこへ行ってしまったのでしょう?
(3)渡まち子氏は、「夢をあきらめない大切さを描いてきたディズニー/ピクサー作品だが、この前日譚では、理想と現実のギャップを知る苦味とともに、叶わない夢を希望に変える自分探しのマジックがテーマになっているところが新しい。そんなストーリーには現代社会の閉塞感をうっすらと感じてしまうのだが、絵の具箱をひっくり返したようなカラフルなビジュアルが、堅苦しいことを忘れさせ、楽しませてくれた」として60点をつけています。
(注1)Oozma Kappa(Kappaはギリシア語)。
(注2)Roar Omega Roar(Omegaはギリシア語)。
(注3)「怖がらせ大会」の決勝戦では、余りに熱心に勝負に挑んでいるマイクを見て、サリーがマイクを勝たせようと不正な小細工をしてしまい、それでマイクは「RΩR」のキャプテンに勝つことができます。でも、サリーは、どうしてそんな小細工を施すことができたのでしょうか?その情報を彼はどこから仕入れたのでしょう。「RΩR」の方はなぜその情報を同じように事前に取得できなかったのでしょう?
なお、マイクはその不正を知って、トロフィーを学長に返還すると同時に、自分の実力を大学の外で試してみようと考え、大事件を引き起こしてしまいます。
(注4)製作者たちは、「劇場用パンフレット」を見ると、本作についていろいろ語っています。
例えば、監督・ストーリー・脚本のダン・スキャンロン氏は、「「人生は思い描いたようには進まない」というテーマを前面に打ち出しました」と述べ、製作のコーリー・レイ氏は、「「自分が何者であるのかを探究する」ことを物語の核にしました」と言っています。
でも、そうしたありきたりの人生訓話めいた事柄を知ることは、逆に本作を見る上で妨げになるのかもしれません。
「怖がらせ大会」での不正行為を知って、マイクが獲得したトロフィーを学長に変換するところからは(上記「注3」参照)、ジョージ・ワシントンばりの教訓を得ることが出来るでしょうし(映画『フライト』における機長ウィトカーの告白!)、そんなつまらないことより何より、本作の色彩の素晴らしさとか3Dを堪能してもかまわないのではないかと思います。
(注5)ユニバーシティですから総合大学です(「劇場用パンフレット」によれば、同大学には、「怖がらせ学部」の他に、「工学部」、「教養及びモンスター学部」、「理学部」、「経営学部」の5つの学部が設けられています)。
(注6)もしかしたら、モンスター・ワールドの日本支部のようなところに、モンスター・ユニバーシティの分校が設けられているのかもしれません。
というよりか、日本の「お化け屋敷」の方がその元祖とは考えられないでしょうか(なにしろ、「天保元年(1830)」に遡るというのですから!)?
そこには様々の怪物や妖怪などが参集し、日々、入場する人間に悲鳴を上げさせるべく知恵を凝らしているのですから〔いくらでも悲鳴ボンベ(scream canister)を作ることができるでしょう!〕!
さらに言えば、本作に登場するマイクですが、彼は、霊長類ヒト科傘お化け属に分類されるべき存在ではないでしょうか(サリーは、霊長類ヒト科雪男属)?
(注7)モンスターの本質が「人間を怖がらせること」にあるから「怖がらせ学部」がトップだとすると、日本において医学部が偏差値からするとトップになっているのは、人間の本質をどう見ていることになるのでしょうか?
(注8)この記事を参照。
(注9)マイクは学長から、「勉強しても身に付かないものがある。もともとあなたは怖くない」と言われてしまいます。ですが、そうだとしたらこの大学の存在意味はどこにあるのでしょうか?
(注10)ここで問題になるのは、実技に関することでしょう。
いくら理論面で優秀でも、実践が伴わなければダメだという考え方があります。
マイクの場合、どう頑張っても人間の子供を怖がらせることはできません。でも、理論を身に着けていれば、サリーのような才能のあるモンスターを使って、より怖がらせることができます(本作のラストの方では、そのやり方で人を思い切り怖がらせて、エネルギーを生み出し、人間の世界からモンスター・ワールドに戻ってくることができました)。
大学の使命は、実践よりもむしろ理論の確立にあるのではないでしょうか?
実践の方は、在野の職業的な専門家に託した方がいい結果が現れるのではないかと思えるところです。
でも、日本では、ごく僅かの例外を除いて、音大を出ていないプロの音楽家とか美大を卒業していないプロの画家はうまく育っていないようです。
(注11)例えば、このサイトの記事とかこの記事が参考になるでしょう。
(注12)本作に登場する学長(ドラゴンに似たモンスター)とか、「怖がらせ大会」に出場するサークル「PINK」(Python Nu Kappa)の所属するものは、女性のモンスターのようですが?
★★★☆☆
象のロケット:モンスターズ・ユニバーシティ
(1)本作は、『モンスターズ・インク』(2001年)の前日譚。
前作ではサリーとマイクというモンスターがモンスターズ株式会社(Monsters Inc.)で働いていましたが、本作ではその二人がモンスターズ・ユニバーシティ(Monsters Univ.)の学生となって、そこのトップである「怖がらせ学部」(School of Scaring)に入り、様々な出来事の末、結局は退学させられて同社に入社することになるというお話です。

一番大きな出来事は、同大学伝統の「怖がらせ大会」(The Scare Games)。
期末試験を台無しにしてしまい、学長に、「怖がらせ学部」に向いていないと宣告され追放されてしまったマイクとサリーは、学長と掛け合って、その大会で優勝すれば元の学部に戻してもらえることになります(ただし、「負ければ大学を辞めてもらいます」と言われてしまうのですが)。
そこで、二人は「OK」(ウーズマ・カッパ:注1)というサークルに入って、6名のモンスターから成るチームを結成します。
ただ、マイク一人やる気があるものの、「OK」の他のメンバーは、実力のあるサリーを除いて落ちこぼればかり。
ですが、他のチームが失格したりしたためなんとか「OK」は生き残り、最後に、最強のチームである「RΩR」(ロアー・オメガ・ロアー:注2)と対決することに(注3)。
さあ、「OK」は勝ち抜くことができるでしょうか、……?
アニメですから当然のことながら、モンスターといっても皆、実にユーモラスな存在でちっとも怖くはありません。となると、外見はともかく、本作で描かれるモンスターの行動は人間とまるで同じようにみえ、わざわざこうした作品に仕立てる意味がどこにあるのか、といささか疑問に思えてきます(注4)。それでも、実にカラフルな画像が映し出され、それも3Dですから、おのずと映画の中に引き込まれてしまうのですが。
(2)まったくどうでもいいことながら、モンスター達がこの大学(注5)で学ぶ意味は奈辺にあるのでしょう?
だいたい、入学が認められる「モンスター」にはどんなものが含まれるのでしょう(日本の大学のような厳しい入学試験はないのかもしれないものの、受験資格は問われるでしょう)?
公式サイトの最初のページなどで見られるモンスターたちの集合写真からすると、ゴジラのような怪獣とか、日本の各種の「お化け」といった妖怪は入っていないようですから、いわゆる怪物に資格が与えられているのかもしれません。
でも、それらの線引きはどうなっているのでしょう?
あるいは、外国籍のものの留学は、この大学では認められていないのでしょうか(注6)?
もともと、モンスターズ・インクやモンスターズ・ユニバーシティのあるモンスター・シティ自体が、かなり閉鎖的な都市なのかもしれません(TPPの対象として開放するとしたら、こういうところから手を付けていったらどうでしょう)。
また、この大学のトップの学部が「怖がらせ学部」だとしたら(注7)、大学で教える学問のトップは「人間をいかに怖がらせるか」に関するものでしょう。
でも、「怖がらせる」〔あるいは「怖がる」(be scared:注8)〕というような、酷く主観的で、人により、地域により、民族によって違い、決して普遍的なものではないことについて、モンスターたちは大学でいったい何を学ぶというのでしょうか?
確かに、実際の人間世界では美術大学とか音楽大学などが設けられており、“芸術”というわけのわからないことがらが教えられているのですから、「怖がらせる」ことについても学問が成立するのかもしれません。
とはいえ、その場合の学問としては、「美術」における美術史や色彩理論だったり、「音楽」における音楽史や音楽理論だったりするように、「怖がらせる」ことに関する歴史とか理論ということになるでしょう。
そうだとしたら、本作においては、「怖がらせ学部」にマイクは不適とされていますが(注9)、むしろ話は逆で、ナイト教授の講義のみならず、関係の著作をいろいろ読破して自分のものにしているマイクこそが、優秀な大学生として学長に表彰されるべきなのではないでしょうか(注10)?

なお、このアニメを見に来ている幼い子供たちに、モンスター・ユニバーシティに設けられている学部とかサークル組織などについて、どの程度理解できるのか〔日本の大学の部とかサークルとも違うようですから(注11)、正直、クマネズミには分かりません〕、やや疑問に思えます。
それはともかく、モンスターの教育という観点はかなり興味をそそります。
でも、アレッ、モンスターって子どもから大人に成長するものなの?
そもそも、誰がモンスターを産むのでしょう?モンスターに性別があるのかしら(注12)?
そういえば、大学時代で最重要事項の一つの恋愛は、本作ではどこへ行ってしまったのでしょう?
(3)渡まち子氏は、「夢をあきらめない大切さを描いてきたディズニー/ピクサー作品だが、この前日譚では、理想と現実のギャップを知る苦味とともに、叶わない夢を希望に変える自分探しのマジックがテーマになっているところが新しい。そんなストーリーには現代社会の閉塞感をうっすらと感じてしまうのだが、絵の具箱をひっくり返したようなカラフルなビジュアルが、堅苦しいことを忘れさせ、楽しませてくれた」として60点をつけています。
(注1)Oozma Kappa(Kappaはギリシア語)。
(注2)Roar Omega Roar(Omegaはギリシア語)。
(注3)「怖がらせ大会」の決勝戦では、余りに熱心に勝負に挑んでいるマイクを見て、サリーがマイクを勝たせようと不正な小細工をしてしまい、それでマイクは「RΩR」のキャプテンに勝つことができます。でも、サリーは、どうしてそんな小細工を施すことができたのでしょうか?その情報を彼はどこから仕入れたのでしょう。「RΩR」の方はなぜその情報を同じように事前に取得できなかったのでしょう?
なお、マイクはその不正を知って、トロフィーを学長に返還すると同時に、自分の実力を大学の外で試してみようと考え、大事件を引き起こしてしまいます。
(注4)製作者たちは、「劇場用パンフレット」を見ると、本作についていろいろ語っています。
例えば、監督・ストーリー・脚本のダン・スキャンロン氏は、「「人生は思い描いたようには進まない」というテーマを前面に打ち出しました」と述べ、製作のコーリー・レイ氏は、「「自分が何者であるのかを探究する」ことを物語の核にしました」と言っています。
でも、そうしたありきたりの人生訓話めいた事柄を知ることは、逆に本作を見る上で妨げになるのかもしれません。
「怖がらせ大会」での不正行為を知って、マイクが獲得したトロフィーを学長に変換するところからは(上記「注3」参照)、ジョージ・ワシントンばりの教訓を得ることが出来るでしょうし(映画『フライト』における機長ウィトカーの告白!)、そんなつまらないことより何より、本作の色彩の素晴らしさとか3Dを堪能してもかまわないのではないかと思います。
(注5)ユニバーシティですから総合大学です(「劇場用パンフレット」によれば、同大学には、「怖がらせ学部」の他に、「工学部」、「教養及びモンスター学部」、「理学部」、「経営学部」の5つの学部が設けられています)。
(注6)もしかしたら、モンスター・ワールドの日本支部のようなところに、モンスター・ユニバーシティの分校が設けられているのかもしれません。
というよりか、日本の「お化け屋敷」の方がその元祖とは考えられないでしょうか(なにしろ、「天保元年(1830)」に遡るというのですから!)?
そこには様々の怪物や妖怪などが参集し、日々、入場する人間に悲鳴を上げさせるべく知恵を凝らしているのですから〔いくらでも悲鳴ボンベ(scream canister)を作ることができるでしょう!〕!
さらに言えば、本作に登場するマイクですが、彼は、霊長類ヒト科傘お化け属に分類されるべき存在ではないでしょうか(サリーは、霊長類ヒト科雪男属)?
(注7)モンスターの本質が「人間を怖がらせること」にあるから「怖がらせ学部」がトップだとすると、日本において医学部が偏差値からするとトップになっているのは、人間の本質をどう見ていることになるのでしょうか?
(注8)この記事を参照。
(注9)マイクは学長から、「勉強しても身に付かないものがある。もともとあなたは怖くない」と言われてしまいます。ですが、そうだとしたらこの大学の存在意味はどこにあるのでしょうか?
(注10)ここで問題になるのは、実技に関することでしょう。
いくら理論面で優秀でも、実践が伴わなければダメだという考え方があります。
マイクの場合、どう頑張っても人間の子供を怖がらせることはできません。でも、理論を身に着けていれば、サリーのような才能のあるモンスターを使って、より怖がらせることができます(本作のラストの方では、そのやり方で人を思い切り怖がらせて、エネルギーを生み出し、人間の世界からモンスター・ワールドに戻ってくることができました)。
大学の使命は、実践よりもむしろ理論の確立にあるのではないでしょうか?
実践の方は、在野の職業的な専門家に託した方がいい結果が現れるのではないかと思えるところです。
でも、日本では、ごく僅かの例外を除いて、音大を出ていないプロの音楽家とか美大を卒業していないプロの画家はうまく育っていないようです。
(注11)例えば、このサイトの記事とかこの記事が参考になるでしょう。
(注12)本作に登場する学長(ドラゴンに似たモンスター)とか、「怖がらせ大会」に出場するサークル「PINK」(Python Nu Kappa)の所属するものは、女性のモンスターのようですが?
★★★☆☆
象のロケット:モンスターズ・ユニバーシティ