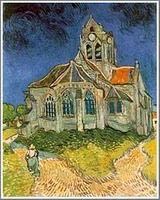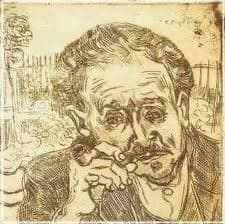近年稀に見る長さの映画だということに興味をひかれて、少し前になりますが、『ヘヴンズ ストーリー』を渋谷のユーロスペースで見てきました。
(1)長時間映画と言えば、クマネズミにとっては、『ユリイカ』(青山真治監督、2000年)の217分とか、『愛のむきだし』(園子温監督、2009年)の237分、『沈まぬ太陽』(若松節朗監督、2009年)の202分などですが、この映画はそれらをもはるかに超える278分の長さです。
途中に休憩をはさむため、特段腰が痛くなることもなく見終わることができました。
とはいえ、映画にずっと惹きつけられたから、というわけでもありません。見終わって感想を取りまとめようとしても、ばらばらな印象が頭に残っているだけで、とてもうまく書けそうにありません(マア印象が散漫になってしまう点が、長時間作品の問題点といえばいえるかもしれないとはいえ、単なる言い訳にしかならないでしょう)。
以下は、備忘録的に思いついたことだけを簡単に書いておこうと思います。
この映画でクマネズミが興味を惹かれた話は、3つあります。
一つ目は、祖父の家に行っている間に家族を殺されて孤児になってしまった少女・サト(寉岡萌希)の話。

二つ目は、警察官でありながら、副業として、依頼によって見ず知らずの他人を殺してしまう復讐代行男・カイジマ(村上淳)の話。
三つ目は、刑務所から出所した男・ミツオ(忍成修吾)と若年性認知症の女・恭子(山崎ハコ)の話。

これらを全体として統合する役目を与えられているのが、最初と真ん中と最後に描かれる人形による踊りでしょう。
これだけですと、これら3つの話は、それぞれ独立しているようにみえるでしょう。
ですが、お互いに相当入り組んだ関係が設定されているのです(なにより、これらの話は、それぞれが独立して描かれているのではありません)。
ただ、二つ目の話は、現実性が乏しく感情移入しにくいものながら、それだけでまとまっているようにも見えます。動物園でカイジマが男を射殺する話は、他の物語と何も関係しませんし、とりわけ、この二つ目の物語には佐藤浩市が登場しますから、何か彼がはかばかしい活躍をして映画全体の中心になるのかなと思いきや、さんざんカイジマをてこずらせはするものの、最後はいともアッサリと射殺されてしまうのです。
とはいえ、この佐藤浩一が殺される場所は、閉山となって見捨てられた社宅アパートの屋上なのですが、ここは三番目の話において、重要な舞台となるのです。
また、一つ目の話の末尾で、港から出て行く船をサトが見送りますが、そこにはカイジマの愛人が現れ、あろうことか殺されたはずのカイジマまでも出現するのです!というのも、港でサトが見送っているのは、カイジマの一人息子なのですから。
という具合に、二つ目の話も、他の話とレベルは低いものの有機的につながっています。
とすれば、一つ目の話と三つ目の話のつながりは、もっと強いはずと簡単に推測できましょう。なんといっても、一つ目の話に登場する男・トモキ(長谷川朝晴)が、サトの唆しによって、平和な暮らしを投げうち、ついには刑務所から出所した男・ミツオを殺そうとし、結局は両者とも死ぬ破目になるのですから。
それも、トモキが若年性認知症の女を殺したからという理由で。

特に、なぜサトがトモキをそそのかすと言えば、同じように家族を殺されたトモキが、記者会見の席で、18歳であるために無期懲役になった犯人の少年を“絶対に殺してやる”と明言していたにもかかわらず、暫くしたら別の女性と家庭を営んでいたからです。
どうやら、サトの生き甲斐は、トモキがミツオを殺す事にあったかのようです(というのも、サトの家族を殺した犯人はすぐに自殺してしまっていたので、復讐しようにも不可能だったからです)。
こうみてくると、この映画は、3つの話から構成されていると言っても、お互いに有機的に絡み合っていて、その絡みの始まりの始まりが、サトの家族が理由もなく殺されてしまったことにあるだろうことがわかってきます。
としたら、一方でその事件の関係者が皆死んだりして片がついてしまい、他方で新しく子供も生まれ、全体としては、これでひとまず決着したのかと思ったところ、最後の人形の踊りからは、まだ決して何も終わってはいないという厳しい事態のようにも見えてきます。
等身大の人形を背後で操っていた人間が、サトの殺された家族であることが露わになるものの、サトが、その両親たちと一緒に再会を喜んでも、続いて彼らの世界に入ろうとすると、かたくなに拒まれ、彼らは自分たちの世界に舞い戻ってしまうのです。
こういった作品から、家族の崩壊と再生、さらには死と生などというように、何か統一的なメッセージを掴みだそうとしても、仕方がないのではと思います。むしろそんな風にまとめてしまったら、わざわざ278分もの長い時間、この映画に付き合ったことの意味が消えてしまうのではないでしょうか?むしろ、『愛のむきだし』でもそうですが、このまま放っておいて、別の映画を見た折になど、そう言えばこれはあの場面に通じるところがあるな、あの場面が意味するところはあるいはこんなことかもしれない、などと思い返すことの方に価値があるのではないかと思います(言うまでもなく、メッセージを抽出できないことの言い訳、開き直りです)。
(2)この長い映画を見ながら、なんとなくではありますが、冒頭で触れました『ユリイカ』を思い出してしまいました。

極めて大雑把ながら、類似する点をいくつか感じるからです。例えば、
・両作品とも、現実に起きた事件が物語の発端に置かれています。『ユリイカ』が、西鉄バスジャック事件(2000年5月)を下敷きにしているのに対応して(注1)、『ヘヴンズ ストーリー』は光市母子殺害事件(1999年4月)を下敷きにしているようです(ただ、サトの家族が殺される事件ではなく、トモキの家族がミツオによって殺される方ですが)。
・両作品とも、冒頭の殺人事件の後も、物語が展開するに従って、次々と人が殺されていきます。『ユリイカ』では、主人公達の周囲で次々に連続殺人事件が起きますし、『ヘヴンズ ストーリー』でも、殺人請負人・カイジマまで登場します!
・両作品とも、少女が大きな役割を果たします。『ユリイカ』では田村梢(宮崎あおい)、『ヘヴンズ ストーリー』ではサト(寉岡萌希)。
・両作品とも自然の描写が印象的です。『ユリイカ』では、ラストで、阿蘇の大観峰が、空中からの撮影で実に雄大に捉えられていますし、『ヘヴンズ ストーリー』でも、岩手の松尾鉱山跡の廃墟については、雪と緑の時期との2度にわたって広大な景色が描き出されています。
単なる印象に過ぎませんが、『ユリイカ』は、酷い事件に巻き込まれた運転手(役所広司)や兄妹(宮崎将と宮崎あおい)らが、なんとかして被った傷から立ち直ろうとする様子が詳細に描き出されていますが、他方『ヘヴンズ ストーリー』では、サトにそそのかされたトモキはミツオ共々死んでしまいますし、ラスト近くでカイジマが資金援助していた女に子どもが産まれるという明るい面はあるものの、未来に希望が見えるわけにはいかない感じです。
これも、酷く大づかみに言えば、それぞれの映画が制作された時代の差と言いうるのかもしれません。
以上のことから、酷く個人的な感想になってしまいますが、この『ヘヴンズ ストーリー』は、大好きな『ユリイカ』を10年後に瀬々敬久監督(注2)が渾身の力で解釈し直した作品とも考えられ、仮にソウだとすれば(そうでなくとも)、クマネズミは酷く興味を惹かれ、高く評価したくなってしまいます!
(注1)実際には、下記のコメントで指摘されているように、映画『ユリイカ』の公開は2000年1月でした。クマネズミは、なぜか逆に思い込んでいたようです。
(注2)瀬々敬久監督の作品レビューについては、2011年1月12日の記事をご覧ください。
(3)この映画の公式サイトには評論家等のレビューが掲載されています。
秦早穂子氏は、「題名の<ヘヴン>は既存の宗教と同意義ではないが、死者は生きる者を見守り、生者は死んだ人を思う。再会の場としての共通点はあろう。復讐を超え、肉親の死を受け入れるサト18歳。成長し、初めて前を見る。決して、決して、すぐの答えなどないが、これからが出発。独自の世界観に、深い暗示がある」と述べています(10月6日朝日新聞)。
恩田泰子氏は、「瀬々監督は、これまでにも現実に着想を得て、殺し、殺される者たちを描いてきた。今回は、楽園からこぼれ落ちてしまった人間たちの愛と憎しみの物語を重層的に描くことで、誰もが殺人事件の当事者になるやもしれぬ理不尽な私たちの世界を丸ごととらえてみせる。ただ、絶望では終わらない。地べたをはいずり回った後、女たちはもう一度生をつないでいく。そして、作品は普遍性を獲得する」と述べています(10月1日 読売新聞)。
★★★★☆
(1)長時間映画と言えば、クマネズミにとっては、『ユリイカ』(青山真治監督、2000年)の217分とか、『愛のむきだし』(園子温監督、2009年)の237分、『沈まぬ太陽』(若松節朗監督、2009年)の202分などですが、この映画はそれらをもはるかに超える278分の長さです。
途中に休憩をはさむため、特段腰が痛くなることもなく見終わることができました。
とはいえ、映画にずっと惹きつけられたから、というわけでもありません。見終わって感想を取りまとめようとしても、ばらばらな印象が頭に残っているだけで、とてもうまく書けそうにありません(マア印象が散漫になってしまう点が、長時間作品の問題点といえばいえるかもしれないとはいえ、単なる言い訳にしかならないでしょう)。
以下は、備忘録的に思いついたことだけを簡単に書いておこうと思います。
この映画でクマネズミが興味を惹かれた話は、3つあります。
一つ目は、祖父の家に行っている間に家族を殺されて孤児になってしまった少女・サト(寉岡萌希)の話。

二つ目は、警察官でありながら、副業として、依頼によって見ず知らずの他人を殺してしまう復讐代行男・カイジマ(村上淳)の話。
三つ目は、刑務所から出所した男・ミツオ(忍成修吾)と若年性認知症の女・恭子(山崎ハコ)の話。

これらを全体として統合する役目を与えられているのが、最初と真ん中と最後に描かれる人形による踊りでしょう。
これだけですと、これら3つの話は、それぞれ独立しているようにみえるでしょう。
ですが、お互いに相当入り組んだ関係が設定されているのです(なにより、これらの話は、それぞれが独立して描かれているのではありません)。
ただ、二つ目の話は、現実性が乏しく感情移入しにくいものながら、それだけでまとまっているようにも見えます。動物園でカイジマが男を射殺する話は、他の物語と何も関係しませんし、とりわけ、この二つ目の物語には佐藤浩市が登場しますから、何か彼がはかばかしい活躍をして映画全体の中心になるのかなと思いきや、さんざんカイジマをてこずらせはするものの、最後はいともアッサリと射殺されてしまうのです。
とはいえ、この佐藤浩一が殺される場所は、閉山となって見捨てられた社宅アパートの屋上なのですが、ここは三番目の話において、重要な舞台となるのです。
また、一つ目の話の末尾で、港から出て行く船をサトが見送りますが、そこにはカイジマの愛人が現れ、あろうことか殺されたはずのカイジマまでも出現するのです!というのも、港でサトが見送っているのは、カイジマの一人息子なのですから。
という具合に、二つ目の話も、他の話とレベルは低いものの有機的につながっています。
とすれば、一つ目の話と三つ目の話のつながりは、もっと強いはずと簡単に推測できましょう。なんといっても、一つ目の話に登場する男・トモキ(長谷川朝晴)が、サトの唆しによって、平和な暮らしを投げうち、ついには刑務所から出所した男・ミツオを殺そうとし、結局は両者とも死ぬ破目になるのですから。
それも、トモキが若年性認知症の女を殺したからという理由で。

特に、なぜサトがトモキをそそのかすと言えば、同じように家族を殺されたトモキが、記者会見の席で、18歳であるために無期懲役になった犯人の少年を“絶対に殺してやる”と明言していたにもかかわらず、暫くしたら別の女性と家庭を営んでいたからです。
どうやら、サトの生き甲斐は、トモキがミツオを殺す事にあったかのようです(というのも、サトの家族を殺した犯人はすぐに自殺してしまっていたので、復讐しようにも不可能だったからです)。
こうみてくると、この映画は、3つの話から構成されていると言っても、お互いに有機的に絡み合っていて、その絡みの始まりの始まりが、サトの家族が理由もなく殺されてしまったことにあるだろうことがわかってきます。
としたら、一方でその事件の関係者が皆死んだりして片がついてしまい、他方で新しく子供も生まれ、全体としては、これでひとまず決着したのかと思ったところ、最後の人形の踊りからは、まだ決して何も終わってはいないという厳しい事態のようにも見えてきます。
等身大の人形を背後で操っていた人間が、サトの殺された家族であることが露わになるものの、サトが、その両親たちと一緒に再会を喜んでも、続いて彼らの世界に入ろうとすると、かたくなに拒まれ、彼らは自分たちの世界に舞い戻ってしまうのです。
こういった作品から、家族の崩壊と再生、さらには死と生などというように、何か統一的なメッセージを掴みだそうとしても、仕方がないのではと思います。むしろそんな風にまとめてしまったら、わざわざ278分もの長い時間、この映画に付き合ったことの意味が消えてしまうのではないでしょうか?むしろ、『愛のむきだし』でもそうですが、このまま放っておいて、別の映画を見た折になど、そう言えばこれはあの場面に通じるところがあるな、あの場面が意味するところはあるいはこんなことかもしれない、などと思い返すことの方に価値があるのではないかと思います(言うまでもなく、メッセージを抽出できないことの言い訳、開き直りです)。
(2)この長い映画を見ながら、なんとなくではありますが、冒頭で触れました『ユリイカ』を思い出してしまいました。

極めて大雑把ながら、類似する点をいくつか感じるからです。例えば、
・両作品とも、現実に起きた事件が物語の発端に置かれています。『ユリイカ』が、西鉄バスジャック事件(2000年5月)を下敷きにしているのに対応して(注1)、『ヘヴンズ ストーリー』は光市母子殺害事件(1999年4月)を下敷きにしているようです(ただ、サトの家族が殺される事件ではなく、トモキの家族がミツオによって殺される方ですが)。
・両作品とも、冒頭の殺人事件の後も、物語が展開するに従って、次々と人が殺されていきます。『ユリイカ』では、主人公達の周囲で次々に連続殺人事件が起きますし、『ヘヴンズ ストーリー』でも、殺人請負人・カイジマまで登場します!
・両作品とも、少女が大きな役割を果たします。『ユリイカ』では田村梢(宮崎あおい)、『ヘヴンズ ストーリー』ではサト(寉岡萌希)。
・両作品とも自然の描写が印象的です。『ユリイカ』では、ラストで、阿蘇の大観峰が、空中からの撮影で実に雄大に捉えられていますし、『ヘヴンズ ストーリー』でも、岩手の松尾鉱山跡の廃墟については、雪と緑の時期との2度にわたって広大な景色が描き出されています。
単なる印象に過ぎませんが、『ユリイカ』は、酷い事件に巻き込まれた運転手(役所広司)や兄妹(宮崎将と宮崎あおい)らが、なんとかして被った傷から立ち直ろうとする様子が詳細に描き出されていますが、他方『ヘヴンズ ストーリー』では、サトにそそのかされたトモキはミツオ共々死んでしまいますし、ラスト近くでカイジマが資金援助していた女に子どもが産まれるという明るい面はあるものの、未来に希望が見えるわけにはいかない感じです。
これも、酷く大づかみに言えば、それぞれの映画が制作された時代の差と言いうるのかもしれません。
以上のことから、酷く個人的な感想になってしまいますが、この『ヘヴンズ ストーリー』は、大好きな『ユリイカ』を10年後に瀬々敬久監督(注2)が渾身の力で解釈し直した作品とも考えられ、仮にソウだとすれば(そうでなくとも)、クマネズミは酷く興味を惹かれ、高く評価したくなってしまいます!
(注1)実際には、下記のコメントで指摘されているように、映画『ユリイカ』の公開は2000年1月でした。クマネズミは、なぜか逆に思い込んでいたようです。
(注2)瀬々敬久監督の作品レビューについては、2011年1月12日の記事をご覧ください。
(3)この映画の公式サイトには評論家等のレビューが掲載されています。
秦早穂子氏は、「題名の<ヘヴン>は既存の宗教と同意義ではないが、死者は生きる者を見守り、生者は死んだ人を思う。再会の場としての共通点はあろう。復讐を超え、肉親の死を受け入れるサト18歳。成長し、初めて前を見る。決して、決して、すぐの答えなどないが、これからが出発。独自の世界観に、深い暗示がある」と述べています(10月6日朝日新聞)。
恩田泰子氏は、「瀬々監督は、これまでにも現実に着想を得て、殺し、殺される者たちを描いてきた。今回は、楽園からこぼれ落ちてしまった人間たちの愛と憎しみの物語を重層的に描くことで、誰もが殺人事件の当事者になるやもしれぬ理不尽な私たちの世界を丸ごととらえてみせる。ただ、絶望では終わらない。地べたをはいずり回った後、女たちはもう一度生をつないでいく。そして、作品は普遍性を獲得する」と述べています(10月1日 読売新聞)。
★★★★☆