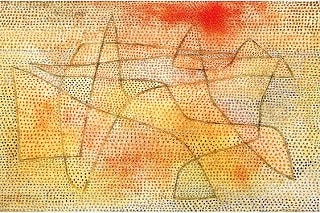『ミステリーズ運命のリスボン』を銀座シネスイッチで見ました。
(1)ブラジルの旧宗主国であるポルトガルの映画と聞いて、それなら見てみようと思ったわけですが、全部で4時間半近くの大長編(注1)。ただ、全編・後編に分けて上映され、別々に見ることができるとされていましたので、トータルでは100円ほど高くなるものの(続けて見れば一人2,500円)、二日に分けて映画館に足を運びました。
とはいえ、入り具合は惨憺たる有様。クマネズミが行った時は、二日とも観客が5,6人ほど。ポルトガルの映画で、かつ大長編と聞いて、皆が二の足を踏んだのでしょう!
ですが、フランスでは1年にも及ぶロングランで、その他の国々でも評判は上々とのこと。やっぱり、ヨーロッパと日本とでは国情が異なるようです。
物語の舞台は、19世紀前半のポルトガル王国。
まずは、修道院内の学校にいる少年ジョアンが登場します。

ジョアンは、クラスメートとの喧嘩で気を失って倒れていて、その間、自分に関係すると思われる人物群の幻を夢見ています。一体彼らは何者なのかが、これからの長い物語の中で解き明かされることになるでしょう(注2)。
最初は、実の母親・アンジェラ(注3)。

彼女は、以前愛する男がいて妊娠していたにもかかわらず、父親に結婚を認めてもらえず(注4)、別の男と無理やり結婚させられたのです。
結婚前に密かに生まれた子供がジョアンで、修道院のデイニス神父が匿っていましたが、彼女は、そのことを知った夫に、8年間も館に軟禁状態にありました。
あるとき、彼女の夫の留守を知った神父は、彼女を館から連れ出して、14歳になったジョアンに会わせます。二人はしばらく神父の元で一緒の生活をするものの、結局彼女は、修道院に入ってしまいます。
実は、母親・アンジェラの父親は、横暴な貴族で、母親の愛人とその子・ジョアンを殺してしまうように殺し屋を雇っていました。愛人は、殺し屋が放った銃弾が原因で死んでしまいますし(注5)、殺し屋にさらわれたジョアンも、すんでのところで殺されるところでしたが、デイニス神父が大金を支払って上手く救出します。
その殺し屋が、しばらくすると、そのとき得た大金を元手に事業に成功したのか(注6)、大富豪・アルベルトとして社交界に登場します。

ただ、パリ時代につきあっていた女・エリーズが、自分を袖にしてプライドを深く傷つけられたとして、復讐すべく何度も刺客を彼の元に送ってきます。

ひょんな偶然で、大きくなったジョアン(今ではペドロとされます)もその刺客の一人となって、大富豪・アルベルトと決闘する羽目に。

さあ、この結末は、……?
本作は、非常に沢山の人物が登場し、後編冒頭からはデイニス神父の方に焦点があわせられたりするなど(注7)、物語の作りは、上で酷くはしょって申し上げたものよりずっと複雑ですが、それが、ポルトガルの貴族の豪華な生活と、修道院の清貧な生活との対比の中で、さらには人形劇を使ったりして(注8)、実に上手く描き出されていると思いました。
(2)この長い映画については様々な視点から語ることができるでしょうが、例えば、主人公の一人ジョアンが成長していく際に出会った二人の典型的な女性(貞淑なアンジェラと奔放なエリーズ)の物語と見なすことも、あるいはできるのではと思われます。
アンジェラは、14歳のジョアンと会った後、暫くして夫が病気で亡くなると、夫が残した遺産を受け取ろうともせずに女子修道院に入ってしまいます。
夫は、妻に子供がいることが分かると、彼女を館の部屋の中に閉じ込めるだけでなく、ポルトガルの社交界に彼女が身元の悪い女なことを言い触らしたり、愛人(注9)までもうけて館に連れ込んだりもするのです。
でも、死ぬ間際に残した手紙で、夫がアンジェラに対する深い愛を告白したことを知ると、アンジェラは、夫の遺産を受け取らない一方で、自分は修道院に入ってしまうのです(注10)。
もう一方のエリーズですが、貴族の夫の後、パリの社交界で随分と淫蕩な生活を送っていて、なかでも大富豪のアルベルトをいたく気に入ります。
ですが、アルベルトは、契約を交わしてごくわずかだけつきあうと、契約に従って大金を支払った後は、彼女が会おうとやってきても追い払ってしまうのでした(注11)。
それで、エリーズは、自尊心を深く傷つけられて、なんとしても彼を殺そうとします(注12)。
そんなときに、エリーズが住む邸宅の隣に住む貴族の友人として、ペドロはエリーズと出会うことになり、一目でエリーズに魅入られてしまいます。
それで、ペドロは、エリーズに唆されてアルベルトと決闘することになるのですが、逆にアルベルトの説得を受けて、その無意味なことを知り、放浪の旅に出ることに。
こんな両極端の女性を知ることになったペドロ(昔のジョアン)のその後の女性遍歴は、さぞや面白いものとなるでしょうが、残念ながら映画では描かれず、観客の方で想像するしか仕方がありません。
(3)中条省平氏は、「多くの登場人物が交錯する迷宮のように複雑な物語が、最後にはパズルの断片のようにぴたりと嵌まりあい、人間と運命の不可思議を結晶させる。正統的な物語の力と、巧緻な映像の面白さが見事に結びついた傑作である」と述べています。
また、川口敦子氏も、「筋の起伏にのみ込まれつつふと気づくと長まわしのキャメラの優雅な動きの中、幽かに揺れたりゆがんだりしているフレームの周辺部、微妙に遠近が誇張された人物配置と、映像美のそこここに奇妙がぼこぼこと蠢いている。そんな実験性。その妙味。筋を先取りするように登場してくる少年の紙製の人形劇に、はたまた彼の死の床の夢に総てを収斂させるのかと、答えの出ない謎を仕掛けてほくそ笑む鬼才、そのスリリングな挑発に乗ってみたい」と述べています。
(注1)上映時間266分ですから、2年前に見た瀬々敬久監督の『ヘヴンズストーリー』(278分)よりわずかに短いだけです。
(注2)映画のラストでも、別途に横たわって気が遠くなったペドロの周りに同じような幻が見えることになります。
(注3)むしろ、サンタ・バルバラ伯爵夫人と言うべきかもしれませんが、煩瑣になるので、以下では他の登場人物も含めて、できるだけ簡便に記すことといたします。
(注4)父親のモンテゼロス侯爵は、アンジェラが次女のため財産を持たないことから、財力のある男のもとへと嫁がせようと考えていたところ、求婚の申し出にやってきた男ペドロ・ダ・シルヴァが財産を持っていないために(嫡出子ながら庶子扱いされていました)、その申し出を拒絶します。
(注5)実は、愛人のペドロ・ダ・シルヴァは、鉄砲で撃たれた後、デイニス神父の修道院にやってきて助けを求めるものの、暫くして息を引き取ります。
(注6)ポルトガルの社交界で色々の噂が飛び交う中には、アルベルトは、ブラジルで奴隷貿易に従事したことで富を築いた、というものがあります。
アルベルトとブラジルとの関係は深いようで、気に行ったオペラ歌劇団を丸ごと買い取ってブラジルに持って行こうとしたりします。
(注7)アンジェラの夫がある修道院で息を引き取る際には、知らせを受けたデイニス神父もその修道院に駆け付けるのですが、そこで立ち会った修道士の一人が、実は、54年前に別れたデイニス神父の父親だったのです。

彼は、友人付き合いをしていた伯爵の夫人を愛してしまい、伯爵が留守をした隙に、夫人と一緒に駆け落ちをして、最後はベネチアまで辿りつき、そこで生まれたのがデイニス神父。
ただ、夫人は体質のせいでデイニス神父を生むのと引き換えに死んでしまいます。
そこで、彼の方は修道院に入ることにし、デイニス神父をローマにいた従弟に預けます。
その次に預けられたモンフォール家では、その家のブノワと兄弟同然に育てられます(なお、ブノワの娘がエリーズだとされています)。
その後様々な経緯があって、神父になっているというわけです。
(注8)映画の節目では、人形劇の舞台が映し出されます。
この舞台は、小さく折り畳んで鞄の中に入れることができ、ペドロがあちこち放浪しているときも、いつもそばに持ち歩いているようです。
ただ、不思議なのは、それを操る人などいないのに自然に動き出しますし、また背景に人の顔が現れたりするのです(鏡になっていて、舞台を見ている人の顔が映るのかもしれません)。
(注9)驚いたことに、大富豪のアルベルトは、この愛人・エウジェニアと結婚するのです。
(注10)その後ポルトガルでコレラが流行すると、彼女はそれに罹って死んでしまい共同墓地に葬られます。その跡を探しにペドロが歩いていると、気が触れて盲目となって乞食に落ちぶれたアンジェラの父親のモンテゼロス侯爵に出会います。
(注11)エリーズは、一週間続けてアルベルトの元にやってきて、「本気になったから、金は返す」と言ったとのこと。
(注12)エリーズがアルベルトも元に送り込んだ刺客の中には、彼女の双子の弟まで入っていて、これは事故に近いのですが、エリーズの弟はアルベルトに殺されてしまうのです。そのことも、エリーズの復讐心を一層燃え立たせています。
★★★★☆
象のロケット:ミステリーズ 運命のリスボン
(1)ブラジルの旧宗主国であるポルトガルの映画と聞いて、それなら見てみようと思ったわけですが、全部で4時間半近くの大長編(注1)。ただ、全編・後編に分けて上映され、別々に見ることができるとされていましたので、トータルでは100円ほど高くなるものの(続けて見れば一人2,500円)、二日に分けて映画館に足を運びました。
とはいえ、入り具合は惨憺たる有様。クマネズミが行った時は、二日とも観客が5,6人ほど。ポルトガルの映画で、かつ大長編と聞いて、皆が二の足を踏んだのでしょう!
ですが、フランスでは1年にも及ぶロングランで、その他の国々でも評判は上々とのこと。やっぱり、ヨーロッパと日本とでは国情が異なるようです。
物語の舞台は、19世紀前半のポルトガル王国。
まずは、修道院内の学校にいる少年ジョアンが登場します。

ジョアンは、クラスメートとの喧嘩で気を失って倒れていて、その間、自分に関係すると思われる人物群の幻を夢見ています。一体彼らは何者なのかが、これからの長い物語の中で解き明かされることになるでしょう(注2)。
最初は、実の母親・アンジェラ(注3)。

彼女は、以前愛する男がいて妊娠していたにもかかわらず、父親に結婚を認めてもらえず(注4)、別の男と無理やり結婚させられたのです。
結婚前に密かに生まれた子供がジョアンで、修道院のデイニス神父が匿っていましたが、彼女は、そのことを知った夫に、8年間も館に軟禁状態にありました。
あるとき、彼女の夫の留守を知った神父は、彼女を館から連れ出して、14歳になったジョアンに会わせます。二人はしばらく神父の元で一緒の生活をするものの、結局彼女は、修道院に入ってしまいます。
実は、母親・アンジェラの父親は、横暴な貴族で、母親の愛人とその子・ジョアンを殺してしまうように殺し屋を雇っていました。愛人は、殺し屋が放った銃弾が原因で死んでしまいますし(注5)、殺し屋にさらわれたジョアンも、すんでのところで殺されるところでしたが、デイニス神父が大金を支払って上手く救出します。
その殺し屋が、しばらくすると、そのとき得た大金を元手に事業に成功したのか(注6)、大富豪・アルベルトとして社交界に登場します。

ただ、パリ時代につきあっていた女・エリーズが、自分を袖にしてプライドを深く傷つけられたとして、復讐すべく何度も刺客を彼の元に送ってきます。

ひょんな偶然で、大きくなったジョアン(今ではペドロとされます)もその刺客の一人となって、大富豪・アルベルトと決闘する羽目に。

さあ、この結末は、……?
本作は、非常に沢山の人物が登場し、後編冒頭からはデイニス神父の方に焦点があわせられたりするなど(注7)、物語の作りは、上で酷くはしょって申し上げたものよりずっと複雑ですが、それが、ポルトガルの貴族の豪華な生活と、修道院の清貧な生活との対比の中で、さらには人形劇を使ったりして(注8)、実に上手く描き出されていると思いました。
(2)この長い映画については様々な視点から語ることができるでしょうが、例えば、主人公の一人ジョアンが成長していく際に出会った二人の典型的な女性(貞淑なアンジェラと奔放なエリーズ)の物語と見なすことも、あるいはできるのではと思われます。
アンジェラは、14歳のジョアンと会った後、暫くして夫が病気で亡くなると、夫が残した遺産を受け取ろうともせずに女子修道院に入ってしまいます。
夫は、妻に子供がいることが分かると、彼女を館の部屋の中に閉じ込めるだけでなく、ポルトガルの社交界に彼女が身元の悪い女なことを言い触らしたり、愛人(注9)までもうけて館に連れ込んだりもするのです。
でも、死ぬ間際に残した手紙で、夫がアンジェラに対する深い愛を告白したことを知ると、アンジェラは、夫の遺産を受け取らない一方で、自分は修道院に入ってしまうのです(注10)。
もう一方のエリーズですが、貴族の夫の後、パリの社交界で随分と淫蕩な生活を送っていて、なかでも大富豪のアルベルトをいたく気に入ります。
ですが、アルベルトは、契約を交わしてごくわずかだけつきあうと、契約に従って大金を支払った後は、彼女が会おうとやってきても追い払ってしまうのでした(注11)。
それで、エリーズは、自尊心を深く傷つけられて、なんとしても彼を殺そうとします(注12)。
そんなときに、エリーズが住む邸宅の隣に住む貴族の友人として、ペドロはエリーズと出会うことになり、一目でエリーズに魅入られてしまいます。
それで、ペドロは、エリーズに唆されてアルベルトと決闘することになるのですが、逆にアルベルトの説得を受けて、その無意味なことを知り、放浪の旅に出ることに。
こんな両極端の女性を知ることになったペドロ(昔のジョアン)のその後の女性遍歴は、さぞや面白いものとなるでしょうが、残念ながら映画では描かれず、観客の方で想像するしか仕方がありません。
(3)中条省平氏は、「多くの登場人物が交錯する迷宮のように複雑な物語が、最後にはパズルの断片のようにぴたりと嵌まりあい、人間と運命の不可思議を結晶させる。正統的な物語の力と、巧緻な映像の面白さが見事に結びついた傑作である」と述べています。
また、川口敦子氏も、「筋の起伏にのみ込まれつつふと気づくと長まわしのキャメラの優雅な動きの中、幽かに揺れたりゆがんだりしているフレームの周辺部、微妙に遠近が誇張された人物配置と、映像美のそこここに奇妙がぼこぼこと蠢いている。そんな実験性。その妙味。筋を先取りするように登場してくる少年の紙製の人形劇に、はたまた彼の死の床の夢に総てを収斂させるのかと、答えの出ない謎を仕掛けてほくそ笑む鬼才、そのスリリングな挑発に乗ってみたい」と述べています。
(注1)上映時間266分ですから、2年前に見た瀬々敬久監督の『ヘヴンズストーリー』(278分)よりわずかに短いだけです。
(注2)映画のラストでも、別途に横たわって気が遠くなったペドロの周りに同じような幻が見えることになります。
(注3)むしろ、サンタ・バルバラ伯爵夫人と言うべきかもしれませんが、煩瑣になるので、以下では他の登場人物も含めて、できるだけ簡便に記すことといたします。
(注4)父親のモンテゼロス侯爵は、アンジェラが次女のため財産を持たないことから、財力のある男のもとへと嫁がせようと考えていたところ、求婚の申し出にやってきた男ペドロ・ダ・シルヴァが財産を持っていないために(嫡出子ながら庶子扱いされていました)、その申し出を拒絶します。
(注5)実は、愛人のペドロ・ダ・シルヴァは、鉄砲で撃たれた後、デイニス神父の修道院にやってきて助けを求めるものの、暫くして息を引き取ります。
(注6)ポルトガルの社交界で色々の噂が飛び交う中には、アルベルトは、ブラジルで奴隷貿易に従事したことで富を築いた、というものがあります。
アルベルトとブラジルとの関係は深いようで、気に行ったオペラ歌劇団を丸ごと買い取ってブラジルに持って行こうとしたりします。
(注7)アンジェラの夫がある修道院で息を引き取る際には、知らせを受けたデイニス神父もその修道院に駆け付けるのですが、そこで立ち会った修道士の一人が、実は、54年前に別れたデイニス神父の父親だったのです。

彼は、友人付き合いをしていた伯爵の夫人を愛してしまい、伯爵が留守をした隙に、夫人と一緒に駆け落ちをして、最後はベネチアまで辿りつき、そこで生まれたのがデイニス神父。
ただ、夫人は体質のせいでデイニス神父を生むのと引き換えに死んでしまいます。
そこで、彼の方は修道院に入ることにし、デイニス神父をローマにいた従弟に預けます。
その次に預けられたモンフォール家では、その家のブノワと兄弟同然に育てられます(なお、ブノワの娘がエリーズだとされています)。
その後様々な経緯があって、神父になっているというわけです。
(注8)映画の節目では、人形劇の舞台が映し出されます。
この舞台は、小さく折り畳んで鞄の中に入れることができ、ペドロがあちこち放浪しているときも、いつもそばに持ち歩いているようです。
ただ、不思議なのは、それを操る人などいないのに自然に動き出しますし、また背景に人の顔が現れたりするのです(鏡になっていて、舞台を見ている人の顔が映るのかもしれません)。
(注9)驚いたことに、大富豪のアルベルトは、この愛人・エウジェニアと結婚するのです。
(注10)その後ポルトガルでコレラが流行すると、彼女はそれに罹って死んでしまい共同墓地に葬られます。その跡を探しにペドロが歩いていると、気が触れて盲目となって乞食に落ちぶれたアンジェラの父親のモンテゼロス侯爵に出会います。
(注11)エリーズは、一週間続けてアルベルトの元にやってきて、「本気になったから、金は返す」と言ったとのこと。
(注12)エリーズがアルベルトも元に送り込んだ刺客の中には、彼女の双子の弟まで入っていて、これは事故に近いのですが、エリーズの弟はアルベルトに殺されてしまうのです。そのことも、エリーズの復讐心を一層燃え立たせています。
★★★★☆
象のロケット:ミステリーズ 運命のリスボン