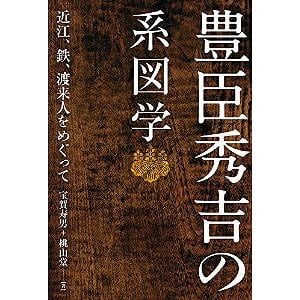(1)昨年末映画『黄金のアデーレ 名画の帰還』を見た後、同作についてエントリを書いた際に、ニューヨーク近代美術館(MOMA)のサイトを調べたことがありますが(注1)、最近そのサイトを眺めていましたら、ちょうど今、同館では「Jackson Pollock: A Collection Survey, 1934–1954」展が開催されていることがわかりました(5月1日まで)。

ジャクソン・ポロックは60年ほど前に亡くなっているとはいえ、このところ、こうした展覧会が開かれるばかりでなく(注2)、その作品がスマホ・ケースとかTシャツの柄に使われたりもしていて(注3)、決して過去の芸術家とはなっていないようです。
(2)そんなジャクソン・ポロックですが、今年のはじめに刊行されたアルフォンソ・リンギス著『変形する身体』(小林徹訳:水声社、2016.1)でも、「カドリーユ」(注4)という章(注5)で彼について言及されているのです。
本書について少しばかり説明すると、冒頭で「本書で私たちが研究するのは、現代社会において、ときに噴出する古代的な欲求や振る舞いと、それが獲得している諸形式である」と述べられた上で、3番目の「カドリーユ」の章では、「芸術というハイカルチャーには、自然淘汰よりも、性淘汰(注6)を通じた進化が見られる」とされ、その進化の様子が取り扱われます(本書P.11)。
もう少し詳しく申し上げれば、まず、「性淘汰の方はしばしば、華麗な色彩や、装飾的なとさかとか、枝角とか、たてがみとか、尻尾とか、騒々しく目立つような儀式的ディスプレイ(注7)などを促進させる」と述べられた後(本書P.48)、「そうした解剖学上の精妙さやディスプレイ行動がもたらすコストと利益を見極めること」が必要だとして(本書P.49)、様々の事例が記述されます(注8)。
その行き着く先のこととして、「オス(あるいはメス)が、もっぱら自分の装飾やディスプレイによって性的パートナーを引きつける」のではなく、「オスの贈り物は、……むしろメスにとって単純に魅力的なもの」である場合が見られるが、この場合、「しばしばオスは派手な装飾を身にまとっていない」(P.58)。すなわち、「オスがメスのために競争するとき、彼らはもはや自分の身体を改造したり、飾り立てたりするのではなく、……物品の蒐集を行うようにな」り、「古物や絵画などのコレクションをディスプレイすることによって、男性の誘引力は強化される」ことになる、と述べられます(本書P.59)。
つまり、「実際にパフォーマンスする者から切り離され」た「(絵画などの)飾り」を巨額の資金によって獲得した男たちが、女を引き付ける「誘引力」も獲得することになる、ということでしょう。
ところが、こうした「進化を転覆させ」たのがジャクソン・ポロックだとリンギス氏は主張します。

ここで本書の分析がユニークなのは、著者が、ポロックが制作した作品には目もくれずに(注9)、彼が絵を描く際に行うパフォーマンスの方に専ら関心を向けている点でしょう。
本書によれば、「ポロックは、競技場(アリーナ)に捕らわれた一人の画家であり、そこで行われる創作活動は、儀式化されてはいるが依然として爆発的なものであった。何枚もの広大な画布が、額縁の内側に収容された物体であることをやめ、環境と化した。それらはまた、存在している事物を独立的に描写するための構成的空間であることをやめた」とされ、「芸術家とその対象との分離が、転覆されつつあった。芸術の主題が、いよいよ自分自身の制作過程になった」というわけです(本書P.60)。
要すれば、オスが、再び中世の騎士のように自分自身で行動するようになった、ということではないかと思われます(注10)。
それまでの「進化を転覆」してしまうこのような結果をもたらしたのは、本書によれば、「ポロックに関するナムスの写真とファルケンベルクの映像」があったからこそとされています〔前者についてはこのサイトで、後者についてはこのサイトで映像を見ることが出来ます(注11)〕。
すなわち、「ナムスの写真とファルケンベルクの映像は、ポロックの絵画活動が、そこにいない者に向けられたダンスであることを明らかにした」のです(本書P.60)。
リンギス氏の分析は、このあとの「カドリーユ」の章において、キジオライチョウとかアオアズマヤマドリといった鳥類が行う実に興味深いパフォーマンスに向いますが(注12)、長くなるのでこのへんでやめておきましょう。
(3)ところで、リンギス氏の『Body Transformations. Evolutions and Atavisms in Culture』を翻訳して『変形する身体』として刊行した小林徹氏は、拙ブログのこのエントリの(3)で紹介しましたように、1年半ほど前、浩瀚な『経験と出来事』(水声社)を著したフランス哲学の専門家です。
そんな人類学者ではない哲学研究者が、どうして叢書「人類学の転回」に含まれる本の翻訳に携わったのか、一見すると不思議な感じがします。
ですが、本書の「「メキシコのヴァルハラで」―訳者あとがき」において述べられているように、原著者のアルフォンソ・リンギス氏は、「アメリカ合衆国の哲学者であり、メルロ・ポンティ、レヴィナス、ピエール・クロソウスキーの英語翻訳者」なのです(注13)。
であれば、メルロ=ポンティの研究者である小林氏が本書を翻訳するのは、まさにうってつけと言えるでしょう(注14)。
現に、同じ「訳者あとがき」では、「身体とは何か。リンギスはそれを、モリス・メルロ=ポンティの『知覚の現象学』に(暗黙のうちに)依拠しつつ、準視覚的な「身体イメージ」と言い換える」などと述べられていますが(注15)、まさに訳者ならではと思います。
それに、先に取り上げた拙ブログのエントリの(5)や「注14」で触れたように、小林氏の言葉に対する感覚は大層優れているところ、その点は本書でも遺憾なく発揮されています。
このエントリで引用している箇所からもある程度おわかり願えると思いますが、翻訳本にありがちな、生硬で、主語と述語が酷く離れていて何度も読み直さないと意味を汲み取れない文章、といったものにお目にかかることはありません。書かれている内容自体が難解で簡単に読み飛ばせない箇所もあるとはいえ、大部分のページでは、実にリズミカルで明晰な文章が綴られていて、どんどん読み進むことが出来ます。
(4)本書によれば、ジャクソン・ポロックがなしたことは、1970年あたりに出現した女性のパフォーマンス・アーティストに変質した形で引き継がれていくことになります(注16)。
とはいえ、冒頭で申し上げたように、今でもスマホ・ケースのカバーとかTシャツにポロックの図柄が使われていることをかんがみると、そうしたものを飛び越えて、むしろ、現代人の“身体の変形”に直接的に寄与しているのではないか、とも思えてしまいます。
そんないい加減なことはさておいて、このエントリでは非常に興味深い『変形する身体』のごくごく一部しか紹介できませんでしたので、ぜひ皆さんも、本書を書店で手に取られて全体をご覧になっていただきたいと思います。本書を起点にしながら、さまざまなことについて思いを巡らすようになることは間違いありませんから。
(注1)『黄金のアデーレ 名画の帰還』についての拙エントリの「注3」で触れているように、MOMAは、映画で中心的に取り上げられた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ』(1907年)の姉妹作『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ』を所蔵しています。
(注2)例えば、日本では、2012年に『生誕100年 ジャクソン・ポロック展』が開催されています。
(注3)スマホ・ケースについては、例えばこちらを。

また、この記事(2015.7.29)においては、「マストバイ!買うべきユニクロTシャツ3選」の一つに「SPRZ NYグラフィックT(ジャクソン・ポロック・半袖)」が挙げられています。

(注4)Wikipediaのこの記事によれば、カドリーユとは「4組の男女のカップルがスクエア(四角)になって踊る歴史的ダンス」(このダンスでは「絶えずパートナーが入れ替わる」ため、性淘汰を取り扱う章のタイトルに使われたのでは、と思います)。
(注5)本書の中で一番長大な章となっています。
(注6)Wikipediaのこの記事では、性淘汰とは「異性をめぐる競争を通じて起きる進化のこと」とされています(ただし、その記事では、「性淘汰は通常は自然淘汰とは別のメカニズムとして論じられる」とはいえ、「広義には性淘汰は自然淘汰に含められる」と記載されています)。
(注7)Wikipediaのこの記事では、ディスプレイとは、鳥類の生態について、「求愛や威嚇などの際、音や動作・姿勢などで誇示する行為」とされています。
(注8)主に取り扱われているのは、中世ヨーロッパの騎士のディスプレイ行動です。
例えば、「性別間の激しい競争は、事実上の一夫多妻制とあいまって、騎士たちの猛々しい活力、攻撃的な気性、芝居じみた衣裳、そして手の込んだ仕方で特殊化されたディスプレイといったものを進化させる結果となった」と述べられています(本書P.56)。
(注9)制作された作品の方面から見たら、彼の絵は非常な高値で市場で取り引きされているのですから(例えば、この記事を参照)、事態は以前とあまり変わりがないように思えます。
(注10)「パトロンや蒐集家に色気をもたらすという芸術的オブジェの社会的・性的な機能が、パフォーマーとしての芸術家に転移したのである」(本書P.62)。
(注11)後者の動画は、ハンス・ナムス(あるいはネイムス)とポール・ファルケンベルクの共同制作によっているようです(このサイトの動画では、約10分のうち3分強にわたって字幕が付けられています)。
なお、この動画は、BBCが制作したドキュメンタリー映画『ポロック その愛と死』(2006年)の中でもかなりの部分が使われています。

(同作の大部分は、ポロックを取り巻く人々の証言から成り立っています。興味深いのは、ポロックが1956年に交通事故死した際に、同じ車に乗っていた愛人のルース・クリグマン は生き残り、この作品に出演して証言している点でしょう)。
また、ポロックは、劇映画『ポロック 2人だけのアトリエ』(2000年)において取り上げられています。

この作品は、監督・脚本・主演のエド・ハリス(同作でアカデミー賞主演男優賞にノミネート)によって制作され、ポロックの妻リー・クラズナーを演じたマーシャ・ゲイ・ハーデン(『マジック・イン・ムーンライト』)が、その演技でアカデミー助演女優賞を受賞しています。また、ポロックの愛人のルース・クリグマンをジェニファー・コネリー(『ノア 約束の舟』)が演じています(なお、同作については、前田有一氏の映画評があります)。
ちなみに、『ポロック その愛と死』の中でルース・クリグマンは、「(劇映画の)ポロックは、マーロン・ブランドに演じて欲しかった。二人は、自由奔放で天才的で気取らないところがそっくりだから」などと述べています。
(注12)例えば、キジオライチョウ(sage-grouse)について「2月下旬から3月上旬にかけて、雄鶏たちは伝統的な儀式が行われる競技場に集まる」云々と書かれています(本書P.67以降)。

また、アオアズマヤマドリ(bowerbird)についても、オスは「東屋(あずまや)」を作り、その入り口の前に「さまざまな物品のコレクションをディスプレイする」、「それは、青いオウムの羽毛であったり青い花々であったり、………青いボタンであったりする」(本書P.75)と述べられています。

〔こうした文章だけではなかなか動的なイメージがつかめないところ、前者についてはこのサイトの動画で、後者についてはこのサイトの動画で、ある程度把握できるように思われます〕。
あるいは、キジライチョウとアオアズマヤマドリとは、人間界の中世騎士と大実業家とに対応しているのかもしれません。
(注13)Wikipediaのこの記事でも、「彼(アルフォンソ・リンギス)の博士論文は、……フランスの現象学者モーリス・メルロ=ポンティとサルトルについての議論をテーマにしたものだった。アメリカに帰国後、……たちまちにしてメルロ=ポンティやレヴィナスの翻訳者として名声を博するようになる」と記載されています。
(注14)拙エントリの(4)で触れましたように、小林氏の『経験と出来事』の第3部第5章「絵画の力」は、ジル・ドゥルーズのフランシス・ベーコン論に触れています。
その際小林氏は、同書の目的に従って、「(絵画に関する)メルロ=ポンティの議論とドゥルーズの議論とを接合」(同書P.315)させる方向で叙述を進めているところ、フランシス・ベーコンについてドゥルーズは、最近新訳が出された『フランシス・ベーコン 感覚の論理学』(宇野邦一訳、河出書房新社:2016.2)の「第12章図表(ダイアグラム)」の中で、次のような点から、ここで取り上げているポロックを対置させています。
すなわち、「画家のそれぞれの違いは、この非具象的なカオスをいかに抱擁するか、来るべき絵画の秩序を、この秩序とカオスとの関係をいかに評価するかによって生じる」と述べた上で、「この点に関しておそらく三つの方向が区別できるだろう」として、一つの方向は、モンドリアンやカンディンスキーらの「抽象絵画」であり、もう一つの方向は、ポロックらの「抽象表現主義あるいはアンフォルメル芸術」だとしています(同書P.140)。
ただし、ドゥルーズは、ポロックの出来上がった画だけを見ているのではなく、「アクション・ペインティング、絵のまわりの、あるいはむしろ絵の中の、画家の「熱狂的ダンス」、絵は画架の上に広げられるのではなく、広げないまま床の上に釘付けされる」といった点も忘れてはいません(同書P.142)。
また、ドゥルーズによれば、フランシス・ベーコンは、それらのいずれの方向にも進まず第3の道を歩んだとしていますが(フランシス・ベーコンについては、この拙エントリを参照してください)。
(注15)まさに、本書がポロックを取り扱っている箇所で「身体イメージ」という用語が使われています〔「姿勢維持的図式は、「身体イメージ」を発散しているのだ」(本書P.61)〕。
(注16)本書によれば、そうした女性のパフォーマンス・アーティストの一人オルラン(例えば、この記事を参照)は、「メジャーな芸術作品を自分の顔に彫りつけることを試み」ているが(本書P.62)、それは「新しい種類の男性を選別し、新しい騎士集団を召喚する」とされます(本書P.65)。

ジャクソン・ポロックは60年ほど前に亡くなっているとはいえ、このところ、こうした展覧会が開かれるばかりでなく(注2)、その作品がスマホ・ケースとかTシャツの柄に使われたりもしていて(注3)、決して過去の芸術家とはなっていないようです。
(2)そんなジャクソン・ポロックですが、今年のはじめに刊行されたアルフォンソ・リンギス著『変形する身体』(小林徹訳:水声社、2016.1)でも、「カドリーユ」(注4)という章(注5)で彼について言及されているのです。
本書について少しばかり説明すると、冒頭で「本書で私たちが研究するのは、現代社会において、ときに噴出する古代的な欲求や振る舞いと、それが獲得している諸形式である」と述べられた上で、3番目の「カドリーユ」の章では、「芸術というハイカルチャーには、自然淘汰よりも、性淘汰(注6)を通じた進化が見られる」とされ、その進化の様子が取り扱われます(本書P.11)。
もう少し詳しく申し上げれば、まず、「性淘汰の方はしばしば、華麗な色彩や、装飾的なとさかとか、枝角とか、たてがみとか、尻尾とか、騒々しく目立つような儀式的ディスプレイ(注7)などを促進させる」と述べられた後(本書P.48)、「そうした解剖学上の精妙さやディスプレイ行動がもたらすコストと利益を見極めること」が必要だとして(本書P.49)、様々の事例が記述されます(注8)。
その行き着く先のこととして、「オス(あるいはメス)が、もっぱら自分の装飾やディスプレイによって性的パートナーを引きつける」のではなく、「オスの贈り物は、……むしろメスにとって単純に魅力的なもの」である場合が見られるが、この場合、「しばしばオスは派手な装飾を身にまとっていない」(P.58)。すなわち、「オスがメスのために競争するとき、彼らはもはや自分の身体を改造したり、飾り立てたりするのではなく、……物品の蒐集を行うようにな」り、「古物や絵画などのコレクションをディスプレイすることによって、男性の誘引力は強化される」ことになる、と述べられます(本書P.59)。
つまり、「実際にパフォーマンスする者から切り離され」た「(絵画などの)飾り」を巨額の資金によって獲得した男たちが、女を引き付ける「誘引力」も獲得することになる、ということでしょう。
ところが、こうした「進化を転覆させ」たのがジャクソン・ポロックだとリンギス氏は主張します。

ここで本書の分析がユニークなのは、著者が、ポロックが制作した作品には目もくれずに(注9)、彼が絵を描く際に行うパフォーマンスの方に専ら関心を向けている点でしょう。
本書によれば、「ポロックは、競技場(アリーナ)に捕らわれた一人の画家であり、そこで行われる創作活動は、儀式化されてはいるが依然として爆発的なものであった。何枚もの広大な画布が、額縁の内側に収容された物体であることをやめ、環境と化した。それらはまた、存在している事物を独立的に描写するための構成的空間であることをやめた」とされ、「芸術家とその対象との分離が、転覆されつつあった。芸術の主題が、いよいよ自分自身の制作過程になった」というわけです(本書P.60)。
要すれば、オスが、再び中世の騎士のように自分自身で行動するようになった、ということではないかと思われます(注10)。
それまでの「進化を転覆」してしまうこのような結果をもたらしたのは、本書によれば、「ポロックに関するナムスの写真とファルケンベルクの映像」があったからこそとされています〔前者についてはこのサイトで、後者についてはこのサイトで映像を見ることが出来ます(注11)〕。
すなわち、「ナムスの写真とファルケンベルクの映像は、ポロックの絵画活動が、そこにいない者に向けられたダンスであることを明らかにした」のです(本書P.60)。
リンギス氏の分析は、このあとの「カドリーユ」の章において、キジオライチョウとかアオアズマヤマドリといった鳥類が行う実に興味深いパフォーマンスに向いますが(注12)、長くなるのでこのへんでやめておきましょう。
(3)ところで、リンギス氏の『Body Transformations. Evolutions and Atavisms in Culture』を翻訳して『変形する身体』として刊行した小林徹氏は、拙ブログのこのエントリの(3)で紹介しましたように、1年半ほど前、浩瀚な『経験と出来事』(水声社)を著したフランス哲学の専門家です。
そんな人類学者ではない哲学研究者が、どうして叢書「人類学の転回」に含まれる本の翻訳に携わったのか、一見すると不思議な感じがします。
ですが、本書の「「メキシコのヴァルハラで」―訳者あとがき」において述べられているように、原著者のアルフォンソ・リンギス氏は、「アメリカ合衆国の哲学者であり、メルロ・ポンティ、レヴィナス、ピエール・クロソウスキーの英語翻訳者」なのです(注13)。
であれば、メルロ=ポンティの研究者である小林氏が本書を翻訳するのは、まさにうってつけと言えるでしょう(注14)。
現に、同じ「訳者あとがき」では、「身体とは何か。リンギスはそれを、モリス・メルロ=ポンティの『知覚の現象学』に(暗黙のうちに)依拠しつつ、準視覚的な「身体イメージ」と言い換える」などと述べられていますが(注15)、まさに訳者ならではと思います。
それに、先に取り上げた拙ブログのエントリの(5)や「注14」で触れたように、小林氏の言葉に対する感覚は大層優れているところ、その点は本書でも遺憾なく発揮されています。
このエントリで引用している箇所からもある程度おわかり願えると思いますが、翻訳本にありがちな、生硬で、主語と述語が酷く離れていて何度も読み直さないと意味を汲み取れない文章、といったものにお目にかかることはありません。書かれている内容自体が難解で簡単に読み飛ばせない箇所もあるとはいえ、大部分のページでは、実にリズミカルで明晰な文章が綴られていて、どんどん読み進むことが出来ます。
(4)本書によれば、ジャクソン・ポロックがなしたことは、1970年あたりに出現した女性のパフォーマンス・アーティストに変質した形で引き継がれていくことになります(注16)。
とはいえ、冒頭で申し上げたように、今でもスマホ・ケースのカバーとかTシャツにポロックの図柄が使われていることをかんがみると、そうしたものを飛び越えて、むしろ、現代人の“身体の変形”に直接的に寄与しているのではないか、とも思えてしまいます。
そんないい加減なことはさておいて、このエントリでは非常に興味深い『変形する身体』のごくごく一部しか紹介できませんでしたので、ぜひ皆さんも、本書を書店で手に取られて全体をご覧になっていただきたいと思います。本書を起点にしながら、さまざまなことについて思いを巡らすようになることは間違いありませんから。
(注1)『黄金のアデーレ 名画の帰還』についての拙エントリの「注3」で触れているように、MOMAは、映画で中心的に取り上げられた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ』(1907年)の姉妹作『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ』を所蔵しています。
(注2)例えば、日本では、2012年に『生誕100年 ジャクソン・ポロック展』が開催されています。
(注3)スマホ・ケースについては、例えばこちらを。

また、この記事(2015.7.29)においては、「マストバイ!買うべきユニクロTシャツ3選」の一つに「SPRZ NYグラフィックT(ジャクソン・ポロック・半袖)」が挙げられています。

(注4)Wikipediaのこの記事によれば、カドリーユとは「4組の男女のカップルがスクエア(四角)になって踊る歴史的ダンス」(このダンスでは「絶えずパートナーが入れ替わる」ため、性淘汰を取り扱う章のタイトルに使われたのでは、と思います)。
(注5)本書の中で一番長大な章となっています。
(注6)Wikipediaのこの記事では、性淘汰とは「異性をめぐる競争を通じて起きる進化のこと」とされています(ただし、その記事では、「性淘汰は通常は自然淘汰とは別のメカニズムとして論じられる」とはいえ、「広義には性淘汰は自然淘汰に含められる」と記載されています)。
(注7)Wikipediaのこの記事では、ディスプレイとは、鳥類の生態について、「求愛や威嚇などの際、音や動作・姿勢などで誇示する行為」とされています。
(注8)主に取り扱われているのは、中世ヨーロッパの騎士のディスプレイ行動です。
例えば、「性別間の激しい競争は、事実上の一夫多妻制とあいまって、騎士たちの猛々しい活力、攻撃的な気性、芝居じみた衣裳、そして手の込んだ仕方で特殊化されたディスプレイといったものを進化させる結果となった」と述べられています(本書P.56)。
(注9)制作された作品の方面から見たら、彼の絵は非常な高値で市場で取り引きされているのですから(例えば、この記事を参照)、事態は以前とあまり変わりがないように思えます。
(注10)「パトロンや蒐集家に色気をもたらすという芸術的オブジェの社会的・性的な機能が、パフォーマーとしての芸術家に転移したのである」(本書P.62)。
(注11)後者の動画は、ハンス・ナムス(あるいはネイムス)とポール・ファルケンベルクの共同制作によっているようです(このサイトの動画では、約10分のうち3分強にわたって字幕が付けられています)。
なお、この動画は、BBCが制作したドキュメンタリー映画『ポロック その愛と死』(2006年)の中でもかなりの部分が使われています。

(同作の大部分は、ポロックを取り巻く人々の証言から成り立っています。興味深いのは、ポロックが1956年に交通事故死した際に、同じ車に乗っていた愛人のルース・クリグマン は生き残り、この作品に出演して証言している点でしょう)。
また、ポロックは、劇映画『ポロック 2人だけのアトリエ』(2000年)において取り上げられています。

この作品は、監督・脚本・主演のエド・ハリス(同作でアカデミー賞主演男優賞にノミネート)によって制作され、ポロックの妻リー・クラズナーを演じたマーシャ・ゲイ・ハーデン(『マジック・イン・ムーンライト』)が、その演技でアカデミー助演女優賞を受賞しています。また、ポロックの愛人のルース・クリグマンをジェニファー・コネリー(『ノア 約束の舟』)が演じています(なお、同作については、前田有一氏の映画評があります)。
ちなみに、『ポロック その愛と死』の中でルース・クリグマンは、「(劇映画の)ポロックは、マーロン・ブランドに演じて欲しかった。二人は、自由奔放で天才的で気取らないところがそっくりだから」などと述べています。
(注12)例えば、キジオライチョウ(sage-grouse)について「2月下旬から3月上旬にかけて、雄鶏たちは伝統的な儀式が行われる競技場に集まる」云々と書かれています(本書P.67以降)。

また、アオアズマヤマドリ(bowerbird)についても、オスは「東屋(あずまや)」を作り、その入り口の前に「さまざまな物品のコレクションをディスプレイする」、「それは、青いオウムの羽毛であったり青い花々であったり、………青いボタンであったりする」(本書P.75)と述べられています。

〔こうした文章だけではなかなか動的なイメージがつかめないところ、前者についてはこのサイトの動画で、後者についてはこのサイトの動画で、ある程度把握できるように思われます〕。
あるいは、キジライチョウとアオアズマヤマドリとは、人間界の中世騎士と大実業家とに対応しているのかもしれません。
(注13)Wikipediaのこの記事でも、「彼(アルフォンソ・リンギス)の博士論文は、……フランスの現象学者モーリス・メルロ=ポンティとサルトルについての議論をテーマにしたものだった。アメリカに帰国後、……たちまちにしてメルロ=ポンティやレヴィナスの翻訳者として名声を博するようになる」と記載されています。
(注14)拙エントリの(4)で触れましたように、小林氏の『経験と出来事』の第3部第5章「絵画の力」は、ジル・ドゥルーズのフランシス・ベーコン論に触れています。
その際小林氏は、同書の目的に従って、「(絵画に関する)メルロ=ポンティの議論とドゥルーズの議論とを接合」(同書P.315)させる方向で叙述を進めているところ、フランシス・ベーコンについてドゥルーズは、最近新訳が出された『フランシス・ベーコン 感覚の論理学』(宇野邦一訳、河出書房新社:2016.2)の「第12章図表(ダイアグラム)」の中で、次のような点から、ここで取り上げているポロックを対置させています。
すなわち、「画家のそれぞれの違いは、この非具象的なカオスをいかに抱擁するか、来るべき絵画の秩序を、この秩序とカオスとの関係をいかに評価するかによって生じる」と述べた上で、「この点に関しておそらく三つの方向が区別できるだろう」として、一つの方向は、モンドリアンやカンディンスキーらの「抽象絵画」であり、もう一つの方向は、ポロックらの「抽象表現主義あるいはアンフォルメル芸術」だとしています(同書P.140)。
ただし、ドゥルーズは、ポロックの出来上がった画だけを見ているのではなく、「アクション・ペインティング、絵のまわりの、あるいはむしろ絵の中の、画家の「熱狂的ダンス」、絵は画架の上に広げられるのではなく、広げないまま床の上に釘付けされる」といった点も忘れてはいません(同書P.142)。
また、ドゥルーズによれば、フランシス・ベーコンは、それらのいずれの方向にも進まず第3の道を歩んだとしていますが(フランシス・ベーコンについては、この拙エントリを参照してください)。
(注15)まさに、本書がポロックを取り扱っている箇所で「身体イメージ」という用語が使われています〔「姿勢維持的図式は、「身体イメージ」を発散しているのだ」(本書P.61)〕。
(注16)本書によれば、そうした女性のパフォーマンス・アーティストの一人オルラン(例えば、この記事を参照)は、「メジャーな芸術作品を自分の顔に彫りつけることを試み」ているが(本書P.62)、それは「新しい種類の男性を選別し、新しい騎士集団を召喚する」とされます(本書P.65)。