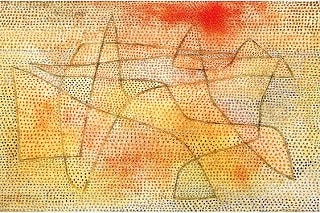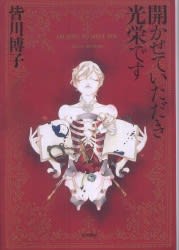江戸東京博物館で開催されている「川村清雄展」に行ってきました。
最近刊行された画家の山口晃氏の『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012.11)(注)の最後の章「やがてかなしき明治画壇」のそのまた最後の節に「西洋絵画の破壊者―川村清雄」とあって、川村清雄が取り上げられているところ、丁度折良くその大回顧展が開催されていたので足を運びました。
実のところ、川村清雄については、『江戸城明渡の帰途(勝海舟江戸開城図)』をチラと見たことがあるくらいで、名前も定かではありませんでした。

ですから、山口氏の著書に、雪舟とか若冲、暁斎などと並んで彼の名前が記載されているのを見て、とても奇異に思いました。
でも、その著書に、徳川歴代の肖像画について、「西洋画の奥行き表現を大胆に壊しながらも、全く異質な空間を現出させる。そのために油彩の描法を崩す。単純に言うと、こういう事が清雄の絵では起こっています」と述べられていて(P.249)、展覧会で展示されている絵を見てみると、よく分からないながらも、納得できる部分もあります(下記は『徳川慶喜像』)。

要すれば、「清雄がした事は、単純に両者(東洋と西洋)の技術を一つの画面の中に混ぜ合わせたと云う、一般的な意味での融合ではない」ということなのでしょう(P.247)(注)。
なお、本展覧会については、美術評論家の高階秀爾氏が、毎日新聞の「目は語る・アート逍遙」欄の記事において、「清雄の全貌を示す代表的絵画作品約100点と、主として川村家に残された多くの歴史資料100点あまりを揃えた贅沢な内容の催しである」と述べています(注)。
(注)同書については、拙ブログの本年11月20日付エントリの「注6」においても若干触れております。
(注)本展覧会カタログの関東に掲載された同氏による特別寄稿「歴史の中の川村清雄」には、「川村清雄は、日本近代絵画の歴史の上で、決して孤高の画家ではなく、むしろ当時の国際的芸術環境のなかに身を置いてそこからたっぷりと養分を摂取して独自の芸術を成熟させ、その活動を通じて近代絵画の発展に大きな役割を果たした画家と位置づけるべき存在なのである」と述べられています(P.12)。
なお、同エッセイによれば、「川村清雄の成し遂げた画業を改めて見直し、その正当な位置を恢復しようという機運がようやく明らかになって来たのは、1970年代の末頃からであ」り、「この再評価の動きに大きな役割果たしたのは川村清衛氏(清雄の長男)であ」って、高階氏はその「清衛氏の知遇を得」たとのこと。
(注)東洋と西洋の絵画の「融合」に関しては、京大准教授の高階絵里加氏による論考「フランスへ渡った日本―川村清雄の《建国》について―」においては、特に晩年に川村清雄によって描かれフランスのオルセー美術館に収められている『建国』(1929年)について、「写実的な個々のモティーフをある秩序に従って構成・配置し、ひとつの思想や理念を表現するという西洋正統派のやり方は、画中のあらゆる要素が絵の主題にむすびつく《建国》にも、はっきりとあらわれている」、「主題とモティーフそのものに加えて、金地背景、浅い空間、画面の縁によるモティーフの切り取り、画中に措かれていない太陽を暗示的に表す手法などは、日本ないし東洋美術の手法に範を取っている」、「描写における写実性と理想にもとづく構築性という西欧美術の伝統と、装飾性、暗示性と明るく軽快な構成という日本美術の伝統とが、ここでは計算しつくされた意匠のうちに結びついている」などと述べられています(P.12~P.13)。
そして、「画伯は、東洋的なものと西洋的なものとを、それぞれの特質を消すことなくして、ある種の遠い幻影のうちに融合しました」と述べるコレージュ・ド・フランス教授シルヴァン・レヴィの受贈式演説に対して、高階氏は「この言葉は十分に納得のゆくものである」と記しているところです(P.13)。

クマネズミとしても、ごく単純に、下記の『梅と椿の静物』のような随分と日本画的なものと、『波』のような西洋画的なものを「融合」すると『建国』ができあがるのでは、などと考えてみたくなってしまいます。


ただ、同論考においても、「背景は装飾的に塗りつぶされているが、鶏の足の部分に見える影などから、地面は奥行きのある空間としてある程度意識されていることがわかる」とあり(P.8)、山口氏に近い見解も見られるところです。
どうやら何回も川村清雄の絵画を見てみる必要がありそうです。
なお、同論考のことは、山口氏の著書で知りました(P.242)。
最近刊行された画家の山口晃氏の『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012.11)(注)の最後の章「やがてかなしき明治画壇」のそのまた最後の節に「西洋絵画の破壊者―川村清雄」とあって、川村清雄が取り上げられているところ、丁度折良くその大回顧展が開催されていたので足を運びました。
実のところ、川村清雄については、『江戸城明渡の帰途(勝海舟江戸開城図)』をチラと見たことがあるくらいで、名前も定かではありませんでした。

ですから、山口氏の著書に、雪舟とか若冲、暁斎などと並んで彼の名前が記載されているのを見て、とても奇異に思いました。
でも、その著書に、徳川歴代の肖像画について、「西洋画の奥行き表現を大胆に壊しながらも、全く異質な空間を現出させる。そのために油彩の描法を崩す。単純に言うと、こういう事が清雄の絵では起こっています」と述べられていて(P.249)、展覧会で展示されている絵を見てみると、よく分からないながらも、納得できる部分もあります(下記は『徳川慶喜像』)。

要すれば、「清雄がした事は、単純に両者(東洋と西洋)の技術を一つの画面の中に混ぜ合わせたと云う、一般的な意味での融合ではない」ということなのでしょう(P.247)(注)。
なお、本展覧会については、美術評論家の高階秀爾氏が、毎日新聞の「目は語る・アート逍遙」欄の記事において、「清雄の全貌を示す代表的絵画作品約100点と、主として川村家に残された多くの歴史資料100点あまりを揃えた贅沢な内容の催しである」と述べています(注)。
(注)同書については、拙ブログの本年11月20日付エントリの「注6」においても若干触れております。
(注)本展覧会カタログの関東に掲載された同氏による特別寄稿「歴史の中の川村清雄」には、「川村清雄は、日本近代絵画の歴史の上で、決して孤高の画家ではなく、むしろ当時の国際的芸術環境のなかに身を置いてそこからたっぷりと養分を摂取して独自の芸術を成熟させ、その活動を通じて近代絵画の発展に大きな役割を果たした画家と位置づけるべき存在なのである」と述べられています(P.12)。
なお、同エッセイによれば、「川村清雄の成し遂げた画業を改めて見直し、その正当な位置を恢復しようという機運がようやく明らかになって来たのは、1970年代の末頃からであ」り、「この再評価の動きに大きな役割果たしたのは川村清衛氏(清雄の長男)であ」って、高階氏はその「清衛氏の知遇を得」たとのこと。
(注)東洋と西洋の絵画の「融合」に関しては、京大准教授の高階絵里加氏による論考「フランスへ渡った日本―川村清雄の《建国》について―」においては、特に晩年に川村清雄によって描かれフランスのオルセー美術館に収められている『建国』(1929年)について、「写実的な個々のモティーフをある秩序に従って構成・配置し、ひとつの思想や理念を表現するという西洋正統派のやり方は、画中のあらゆる要素が絵の主題にむすびつく《建国》にも、はっきりとあらわれている」、「主題とモティーフそのものに加えて、金地背景、浅い空間、画面の縁によるモティーフの切り取り、画中に措かれていない太陽を暗示的に表す手法などは、日本ないし東洋美術の手法に範を取っている」、「描写における写実性と理想にもとづく構築性という西欧美術の伝統と、装飾性、暗示性と明るく軽快な構成という日本美術の伝統とが、ここでは計算しつくされた意匠のうちに結びついている」などと述べられています(P.12~P.13)。
そして、「画伯は、東洋的なものと西洋的なものとを、それぞれの特質を消すことなくして、ある種の遠い幻影のうちに融合しました」と述べるコレージュ・ド・フランス教授シルヴァン・レヴィの受贈式演説に対して、高階氏は「この言葉は十分に納得のゆくものである」と記しているところです(P.13)。

クマネズミとしても、ごく単純に、下記の『梅と椿の静物』のような随分と日本画的なものと、『波』のような西洋画的なものを「融合」すると『建国』ができあがるのでは、などと考えてみたくなってしまいます。


ただ、同論考においても、「背景は装飾的に塗りつぶされているが、鶏の足の部分に見える影などから、地面は奥行きのある空間としてある程度意識されていることがわかる」とあり(P.8)、山口氏に近い見解も見られるところです。
どうやら何回も川村清雄の絵画を見てみる必要がありそうです。
なお、同論考のことは、山口氏の著書で知りました(P.242)。