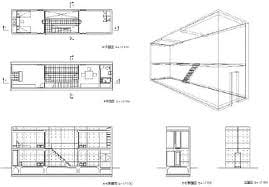『週刊文春』(10月21日号)の阿川佐和子のインタビューに、主役の大沢たかおが登場して、面白そうな内容のように思えたこともあって、『桜田門外ノ変』を渋谷TOEIで見てきました。
(1)ただ、映画を見てまで歴史の勉強をしようと思わないクマネズミとしては、見に行くべきではなかったかもしれません。
見ながら、一体全体、どうしてこんなに単調で型どおりのことを長々と映画にして観客に見せようとするのだろうかと思って、退屈してしまいました。
むろん、このような描き方になるのは原作の吉村氏の小説によるところが大きいのでしょう。
ですが、他方では、映画化に当たりご当地の茨城県下の団体の全面的な協力があったということで、関係者があちこちにいるのでしょう、登場人物の皆が皆、杓子定規で当たり前と思えることばかり口にして、人の裏側がほとんど描かれないというのに首をかしげたくなります(NHKの大河ドラマが面白くないのも、同じような理由から、登場人物に常識を超えたところが感じられないせいだと思われます←なにしろ、大河ドラマの舞台となれば、当該地域の観光収入が確実に伸びるとされていますから、当該地域にかかわる歴史上の人物を、ちょっとでもおかしい感じでは描けないのでしょう!)(注)。
それに、敵役になるはずの井伊大老(伊武雅人)も、襲撃されてまでも駕籠の中で「このままで日本はどうなるのだ」と天下国家の行く末を憂える始末です(板垣退助ばりに!)。
問題点を探せば、さらにいくつでも見つかるでしょう。たとえば、
・最初と最後に、桜田門の現在の光景が映し出されますが、観客に向かって、“皆さんは知らないと思いますが、今から100年以上昔に、ここでこんなことがあったのですよ”、と先生が生徒に教えているかのようで、目をそむけたくなりました〔もちろん、このシーンから、現代の政治状況に対する無言の批判といったメッセージを読み取ることは可能でしょうが、そんなのは児戯に等しいと言えるでしょう〕。
・大沢たかお演じる関鉄之介ですが、鳥取藩一の剣の使い手を、他人の剣を使いながらも倒してしまうほどの腕前ながら、そしてピストルを持っていながら、井伊大老襲撃に際して、何もしないで見守っているだけとは、襲撃グループのトップとはいえ、割り切れなさを感じました。
・これも史実であって言ってみても仕方ないのかもしれませんが、井伊大老一行の襲撃に際して、水戸浪士達が、隠れた場所から三々五々飛び出して襲うというのならまだしも、そうではなく、道端に全員が展開していて、ある程度行列が通り過ぎるのをやり過ごしてから斬りかかるというのも、本当なのかしらと思ってしまいます(江戸城の周辺を警固しているはずの幕府側の武士等が、一人もいなかったのでしょうか?水戸浪士を探し出して捕縛することに関しては、あれほど徹底して遂行できるにもかかわらず?)。
・それに、彦根藩邸のすぐそばで襲撃があったにもかかわらず、彦根藩からの応援部隊の到着がかなり遅れたように見えるのも奇妙です(雪のため、物音があまりしなかったようですし、襲撃にかかった時間もごく短かったようですが)。
・金子孫二郎(柄本明)以下が奉行から斬首を言い渡されるシーンがありますが、皆同じにもかかわらず、どうして一人一人個別に描かねばならないのかよく理解できません(要するに、製作者側としては、水戸藩関係者全員についてその消息を描いてみたかったのでしょう。ですが、そんなものを見せられる観客としては、酷く退屈なところです)。
・この映画では、関鉄之介に焦点を当て、その愛人の消息まで触れているところ、妻(長谷川京子)と息子(加藤清史郎)とはどうなったのでしょうか?
なお、加藤清史郎は、この映画の性格からすると全くのミスキャストとしか思えません(なにしろ、あのCMにおける姿がダブってしまいますから!)。
たとえば、当時水戸藩内にあったという天狗党と諸正党との血なまぐさい対立抗争の中で、この「桜田門外の変」を描いてみたらどうなのでしょうか?
あるいは、居丈高で独裁的な傾向を強める井伊大老を排除する動きが、幕閣の中や彦根藩の中にあって、水戸浪士襲撃の確報は、前日に幕閣や彦根藩に伝達されたにもかかわらず、大老にきちんと上げられる前に握り潰され、その結果、桜田門外は全くの真空地帯となってしまって、容易に襲撃は成功するものの、水戸浪士たちは結局使い捨てにされてしまった、などといったストーリーは考えられなかったでしょうか〔映画では、井伊大老に襲撃情報が届けられますが、単なる投げ文だったため無視されます。また、京都で3,000人が挙兵するとの薩摩藩の約束が反故にされて、水戸浪士の襲撃の意義が減殺されてしまいますが、これは当初から仕組まれていたわけではなく、予想外の情勢変化によるものでしょう〕?
なにはともあれ、私には、『十三人の刺客』や『大奥』の方が、製作者のアイデアがふんだんに盛り込まれていて、ズッと面白い映画ではないかと思えました〔ノンフィクション物であっても、様々な解釈をぶつけることは可能なはずですから〕。
(注)にもかかわらず、粉川哲夫氏によれば、「この映画では、「水戸」というローカリティは、全く重視されていない。それは、薩摩弁まがいや関西弁まがいは聞かれるが、茨城弁に関しては、その気配さえも聞こえないという点にあらわれている。茨城弁というのは、同じ関東でもこうも違うのかと思われるくらい、特徴がある。たとえば、「い」と「え」の発音の混在、しり上がりの発音等である。だから、いまでも、茨城出身の人は、すぐわかる」とのこと。
(2)ところで、映画評論家諸氏は、下記の(3)でおわかりのように、桜田門外における水戸浪士の襲撃の場面が冒頭近くに置かれていることを高く評価しているところ、様々のブログでは、やはりラスト近くにすべきだとの意見が多いように見受けられます。
たとえば、「LOVE Cinemas 調布」のKLYさんは、「「桜田門外の変」を描きたいのならば、通常の時系列に乗せつつ、鉄之介たち藩士の日頃に密着し、彼らの尊王攘夷思想の発端であるとか、藩主斉昭が彼らに及ぼした影響、世の尊皇攘夷の流れの中で彼らがその中心にいたことなどを描いた上で、最後に襲撃を成功させるというオーソドックスな描き方が一番良かったのだと思」うと述べていますし、「masalaの辛口映画館」のマサラ0517さんは、「本作の場合はちゃんと時系列通りに物語を描き、何故実行犯達がこの様な襲撃事件を起こしたのかを観客にキッチリと説明した上で襲撃事件を描くべきである」と述べています。
この映画が依拠した原作はどうかと言えば、新潮文庫版の下巻P.100~P.133に襲撃の模様が描かれています。すなわち、全体の真ん中よりやや後の方といったところでしょうか。
どうも様々な考え方があるようです。
ただ、クマネズミには、この映画のタイトルが『桜田門外ノ変』となっている以上、やはりクライマックスを水戸浪士の襲撃とすべきであり、としたらそのシーンはラスト近くに置く方が全体の構成から言ってみても座りがいいのではと思えます〔まあ、この作品は、原作の下巻を映画化したのだと言ってしまえば、この点を余り云々しても意味はないかもしれませんが〕。
もし、この映画のように、“それからの浪士達”を専ら描くというのであれば、それなりのタイトルとすべきではなかったでしょうか?
(3)また、この作品は、最近見たばかりの『十三人の刺客』と類似する点が多いように見受けられます。
すなわち、
・時代としては、どちらも江戸後期。すなわち、『十三人の刺客』の場合、弘化元年(1844年)とされ、『桜田門外ノ変』は、安政7年(1860年)が中心。
・どちらの作品でも、襲撃側は、相手側のトップ、それも将軍の弟であったり幕府の大老であったりと、トップ中のトップの首を取ることが目的。
・どちらも襲撃側の人数が少ない。すなわち、『十三人の刺客』の場合13人であり、『桜田門外ノ変』では18人。
・逆に、どちらも防御側の人数はかなり多い。すなわち、『十三人の刺客』の場合300人(オリジナル作品では53人)であり、『桜田門外ノ変』では約60人。
・襲撃側の作戦は実際には相当違っているとはいえ、どちらも少人数で効率よく目的を達しようとする精神では同じ〔『十三人の刺客』の場合、大勢の防御側の侍をいくつもの小グループに分断した上で殲滅していく作戦 、他方『桜田門外ノ変』では、まず行列の先頭を襲い、それに防御側の侍が集中して駕籠の警固が手薄になったところで本来の目的を果たすという作戦〕。
・どちらの防御側も、ある程度襲撃を予期していたとはいえ、実際には思いもかけないところで襲われ、人数が多いにもかかわらずトップを守りきることができなかった。
・どちらであっても、襲撃側も防御側もその大半が命を落としている。『十三人の刺客』の場合、襲撃側で生き残ったのは2人(漫画では8人)、防御側も大半がやられている。また『桜田門外ノ変』では、襲撃側で生き残ったのは2人、防御側の大半は、その場でなくとも、その後様々な形で命を落としている。
同じ時期に公開されたフィクション映画とノンフィクション映画とが、偶然とはいえこうまで類似する点が多いというのは、非常に興味深いことだと思います(と言っても、2つの映画において、襲撃の場面の位置づけがまるで異なっているのも事実ですが)。
なお、12月に公開される『最後の忠臣蔵』において、仮に四十七士による吉良邸討入りが描かれるとすれば(何の情報も持ち合わせてはいません)、時期を同じくして3つもの作品で集団暗殺劇(それも、時の権力者の首を取ることを大目的とする)が取り上げられることになります。
そこに何らかの政治的・社会的なな意味合いを嗅ぎ取るべきなのかもしれないものの、いずれも単なる娯楽映画に過ぎないものですし、クマネズミの手に余ることもあり、他日を期すことといたしましょう。
(4)映画評論家は、総じてこの作品には好意的です。
前田有一氏は、「時代にマッチしたテーマ性、役者たちの名演、重厚な桜田門のセットをはじめとする美術のレベルの高さ、そしてストーリー構成の斬新さにより私は本作品をオススメの筆頭にあげる。最後に挙げた構成の巧みさとは、一言でいえばクライマックスの暗殺事件を映画の冒頭に持ってきたことを指す。エンターテイメント大作を任せられる数少ない日本の巨匠、佐藤純彌監督の手腕は今回冴えに冴え、この構成によって物語の感動、せつなさが大いに強調された」として75点を、
渡まち子氏は、「映画は、襲撃をクライマックスにしないことで、事件を美化せず、大きくうねった時代の流れの中で先を見据えることの難しさを丁寧に描いた。物語序盤で早々と訪れる桜田門外ノ変の場面が、個よりも集団を意識した混沌としたバトルになっているのがリアルだ」等として60点を、
それぞれ与えています。
さらに、前田有一氏は、同じ論評の中で、次のように述べています。「昔の日本には、気持ちのいい奴らがたくさん生きていた。政治に携わる者たちも本気で国の未来を憂い、自分の立場なりに最善を尽くそうとしていた──。 たとえ脚色による錯覚、ファンタジーであったとしても、そんな気持ちをしばし味わうのは悪いものではない」。
ですが、もうそろそろこうした司馬遼太郎の小説的な歴史観から卒業すべきではないでしょうか?
★★☆☆☆
象のロケット:桜田門外ノ変
(1)ただ、映画を見てまで歴史の勉強をしようと思わないクマネズミとしては、見に行くべきではなかったかもしれません。
見ながら、一体全体、どうしてこんなに単調で型どおりのことを長々と映画にして観客に見せようとするのだろうかと思って、退屈してしまいました。
むろん、このような描き方になるのは原作の吉村氏の小説によるところが大きいのでしょう。
ですが、他方では、映画化に当たりご当地の茨城県下の団体の全面的な協力があったということで、関係者があちこちにいるのでしょう、登場人物の皆が皆、杓子定規で当たり前と思えることばかり口にして、人の裏側がほとんど描かれないというのに首をかしげたくなります(NHKの大河ドラマが面白くないのも、同じような理由から、登場人物に常識を超えたところが感じられないせいだと思われます←なにしろ、大河ドラマの舞台となれば、当該地域の観光収入が確実に伸びるとされていますから、当該地域にかかわる歴史上の人物を、ちょっとでもおかしい感じでは描けないのでしょう!)(注)。
それに、敵役になるはずの井伊大老(伊武雅人)も、襲撃されてまでも駕籠の中で「このままで日本はどうなるのだ」と天下国家の行く末を憂える始末です(板垣退助ばりに!)。
問題点を探せば、さらにいくつでも見つかるでしょう。たとえば、
・最初と最後に、桜田門の現在の光景が映し出されますが、観客に向かって、“皆さんは知らないと思いますが、今から100年以上昔に、ここでこんなことがあったのですよ”、と先生が生徒に教えているかのようで、目をそむけたくなりました〔もちろん、このシーンから、現代の政治状況に対する無言の批判といったメッセージを読み取ることは可能でしょうが、そんなのは児戯に等しいと言えるでしょう〕。
・大沢たかお演じる関鉄之介ですが、鳥取藩一の剣の使い手を、他人の剣を使いながらも倒してしまうほどの腕前ながら、そしてピストルを持っていながら、井伊大老襲撃に際して、何もしないで見守っているだけとは、襲撃グループのトップとはいえ、割り切れなさを感じました。
・これも史実であって言ってみても仕方ないのかもしれませんが、井伊大老一行の襲撃に際して、水戸浪士達が、隠れた場所から三々五々飛び出して襲うというのならまだしも、そうではなく、道端に全員が展開していて、ある程度行列が通り過ぎるのをやり過ごしてから斬りかかるというのも、本当なのかしらと思ってしまいます(江戸城の周辺を警固しているはずの幕府側の武士等が、一人もいなかったのでしょうか?水戸浪士を探し出して捕縛することに関しては、あれほど徹底して遂行できるにもかかわらず?)。
・それに、彦根藩邸のすぐそばで襲撃があったにもかかわらず、彦根藩からの応援部隊の到着がかなり遅れたように見えるのも奇妙です(雪のため、物音があまりしなかったようですし、襲撃にかかった時間もごく短かったようですが)。
・金子孫二郎(柄本明)以下が奉行から斬首を言い渡されるシーンがありますが、皆同じにもかかわらず、どうして一人一人個別に描かねばならないのかよく理解できません(要するに、製作者側としては、水戸藩関係者全員についてその消息を描いてみたかったのでしょう。ですが、そんなものを見せられる観客としては、酷く退屈なところです)。
・この映画では、関鉄之介に焦点を当て、その愛人の消息まで触れているところ、妻(長谷川京子)と息子(加藤清史郎)とはどうなったのでしょうか?
なお、加藤清史郎は、この映画の性格からすると全くのミスキャストとしか思えません(なにしろ、あのCMにおける姿がダブってしまいますから!)。
たとえば、当時水戸藩内にあったという天狗党と諸正党との血なまぐさい対立抗争の中で、この「桜田門外の変」を描いてみたらどうなのでしょうか?
あるいは、居丈高で独裁的な傾向を強める井伊大老を排除する動きが、幕閣の中や彦根藩の中にあって、水戸浪士襲撃の確報は、前日に幕閣や彦根藩に伝達されたにもかかわらず、大老にきちんと上げられる前に握り潰され、その結果、桜田門外は全くの真空地帯となってしまって、容易に襲撃は成功するものの、水戸浪士たちは結局使い捨てにされてしまった、などといったストーリーは考えられなかったでしょうか〔映画では、井伊大老に襲撃情報が届けられますが、単なる投げ文だったため無視されます。また、京都で3,000人が挙兵するとの薩摩藩の約束が反故にされて、水戸浪士の襲撃の意義が減殺されてしまいますが、これは当初から仕組まれていたわけではなく、予想外の情勢変化によるものでしょう〕?
なにはともあれ、私には、『十三人の刺客』や『大奥』の方が、製作者のアイデアがふんだんに盛り込まれていて、ズッと面白い映画ではないかと思えました〔ノンフィクション物であっても、様々な解釈をぶつけることは可能なはずですから〕。
(注)にもかかわらず、粉川哲夫氏によれば、「この映画では、「水戸」というローカリティは、全く重視されていない。それは、薩摩弁まがいや関西弁まがいは聞かれるが、茨城弁に関しては、その気配さえも聞こえないという点にあらわれている。茨城弁というのは、同じ関東でもこうも違うのかと思われるくらい、特徴がある。たとえば、「い」と「え」の発音の混在、しり上がりの発音等である。だから、いまでも、茨城出身の人は、すぐわかる」とのこと。
(2)ところで、映画評論家諸氏は、下記の(3)でおわかりのように、桜田門外における水戸浪士の襲撃の場面が冒頭近くに置かれていることを高く評価しているところ、様々のブログでは、やはりラスト近くにすべきだとの意見が多いように見受けられます。
たとえば、「LOVE Cinemas 調布」のKLYさんは、「「桜田門外の変」を描きたいのならば、通常の時系列に乗せつつ、鉄之介たち藩士の日頃に密着し、彼らの尊王攘夷思想の発端であるとか、藩主斉昭が彼らに及ぼした影響、世の尊皇攘夷の流れの中で彼らがその中心にいたことなどを描いた上で、最後に襲撃を成功させるというオーソドックスな描き方が一番良かったのだと思」うと述べていますし、「masalaの辛口映画館」のマサラ0517さんは、「本作の場合はちゃんと時系列通りに物語を描き、何故実行犯達がこの様な襲撃事件を起こしたのかを観客にキッチリと説明した上で襲撃事件を描くべきである」と述べています。
この映画が依拠した原作はどうかと言えば、新潮文庫版の下巻P.100~P.133に襲撃の模様が描かれています。すなわち、全体の真ん中よりやや後の方といったところでしょうか。
どうも様々な考え方があるようです。
ただ、クマネズミには、この映画のタイトルが『桜田門外ノ変』となっている以上、やはりクライマックスを水戸浪士の襲撃とすべきであり、としたらそのシーンはラスト近くに置く方が全体の構成から言ってみても座りがいいのではと思えます〔まあ、この作品は、原作の下巻を映画化したのだと言ってしまえば、この点を余り云々しても意味はないかもしれませんが〕。
もし、この映画のように、“それからの浪士達”を専ら描くというのであれば、それなりのタイトルとすべきではなかったでしょうか?
(3)また、この作品は、最近見たばかりの『十三人の刺客』と類似する点が多いように見受けられます。
すなわち、
・時代としては、どちらも江戸後期。すなわち、『十三人の刺客』の場合、弘化元年(1844年)とされ、『桜田門外ノ変』は、安政7年(1860年)が中心。
・どちらの作品でも、襲撃側は、相手側のトップ、それも将軍の弟であったり幕府の大老であったりと、トップ中のトップの首を取ることが目的。
・どちらも襲撃側の人数が少ない。すなわち、『十三人の刺客』の場合13人であり、『桜田門外ノ変』では18人。
・逆に、どちらも防御側の人数はかなり多い。すなわち、『十三人の刺客』の場合300人(オリジナル作品では53人)であり、『桜田門外ノ変』では約60人。
・襲撃側の作戦は実際には相当違っているとはいえ、どちらも少人数で効率よく目的を達しようとする精神では同じ〔『十三人の刺客』の場合、大勢の防御側の侍をいくつもの小グループに分断した上で殲滅していく作戦 、他方『桜田門外ノ変』では、まず行列の先頭を襲い、それに防御側の侍が集中して駕籠の警固が手薄になったところで本来の目的を果たすという作戦〕。
・どちらの防御側も、ある程度襲撃を予期していたとはいえ、実際には思いもかけないところで襲われ、人数が多いにもかかわらずトップを守りきることができなかった。
・どちらであっても、襲撃側も防御側もその大半が命を落としている。『十三人の刺客』の場合、襲撃側で生き残ったのは2人(漫画では8人)、防御側も大半がやられている。また『桜田門外ノ変』では、襲撃側で生き残ったのは2人、防御側の大半は、その場でなくとも、その後様々な形で命を落としている。
同じ時期に公開されたフィクション映画とノンフィクション映画とが、偶然とはいえこうまで類似する点が多いというのは、非常に興味深いことだと思います(と言っても、2つの映画において、襲撃の場面の位置づけがまるで異なっているのも事実ですが)。
なお、12月に公開される『最後の忠臣蔵』において、仮に四十七士による吉良邸討入りが描かれるとすれば(何の情報も持ち合わせてはいません)、時期を同じくして3つもの作品で集団暗殺劇(それも、時の権力者の首を取ることを大目的とする)が取り上げられることになります。
そこに何らかの政治的・社会的なな意味合いを嗅ぎ取るべきなのかもしれないものの、いずれも単なる娯楽映画に過ぎないものですし、クマネズミの手に余ることもあり、他日を期すことといたしましょう。
(4)映画評論家は、総じてこの作品には好意的です。
前田有一氏は、「時代にマッチしたテーマ性、役者たちの名演、重厚な桜田門のセットをはじめとする美術のレベルの高さ、そしてストーリー構成の斬新さにより私は本作品をオススメの筆頭にあげる。最後に挙げた構成の巧みさとは、一言でいえばクライマックスの暗殺事件を映画の冒頭に持ってきたことを指す。エンターテイメント大作を任せられる数少ない日本の巨匠、佐藤純彌監督の手腕は今回冴えに冴え、この構成によって物語の感動、せつなさが大いに強調された」として75点を、
渡まち子氏は、「映画は、襲撃をクライマックスにしないことで、事件を美化せず、大きくうねった時代の流れの中で先を見据えることの難しさを丁寧に描いた。物語序盤で早々と訪れる桜田門外ノ変の場面が、個よりも集団を意識した混沌としたバトルになっているのがリアルだ」等として60点を、
それぞれ与えています。
さらに、前田有一氏は、同じ論評の中で、次のように述べています。「昔の日本には、気持ちのいい奴らがたくさん生きていた。政治に携わる者たちも本気で国の未来を憂い、自分の立場なりに最善を尽くそうとしていた──。 たとえ脚色による錯覚、ファンタジーであったとしても、そんな気持ちをしばし味わうのは悪いものではない」。
ですが、もうそろそろこうした司馬遼太郎の小説的な歴史観から卒業すべきではないでしょうか?
★★☆☆☆
象のロケット:桜田門外ノ変