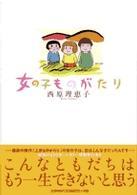「キャデラック・レコード」を恵比寿ガーデン・シネマで見ました。
精神科医・樺沢氏によるメルマガ「シカゴ発 映画の精神分析」第342号(9月2日)に、「音楽映画としても非常に完成度が高いので、社会的なテーマを抜きにしても、純粋に音楽に感動し、物語に共感できる」とあり、「私の場合、映画が終わってから、3分くらい涙が止まらなかった」とまで述べられていたこともあって見にいってきました。
実際にこの映画を見てみると、50年~60年代にかけてブルースからロックへアメリカ音楽が拡大していった時代を、それに大きく貢献したひとつのレーベル(「チェス・レコード」)を核にジックリと描きだしていて、私のようにこの方面に疎くとも、次々に演奏される曲を聴いているだけでジーンときてしまいます。どの歌も実によくできているのです。
こうした素晴らしい映画にも関わらず、福本次郎氏は、「映画は彼らの歌声をじっくりと聴かすというサービスはせず、主人公・レナードを中心とする人々の酒と女とドラッグにおぼれる日々ばかりを描写する」などと至極ピントとのはずれた批評をしています(40点)。
尤も、「ラジオのDJがくわえタバコのままマイクに向かってしゃべったり、ミュージシャンがところ構わず平気でタバコを吸っている。まだ、健康意識が低く、タバコの害などまったく問題にされなかった世の中とはいえ、見ているだけで気分が悪くなる映像だ」とも述べていて、そんな本筋と無関係の些細なことが気になるくらいですから、福本氏はこうした映画に全然向いていないようです。それなら見なければいいのに!
この映画に関する批評としては、次の渡まち子氏のものが私に一番近い感じがします(70点)。
いろいろ問題点はあるにせよ、「そんな不満をシビレるほど素晴らしい音楽がすべて吹き飛ばす。特にエタ・ジェイムズを演じるビヨンセの熱唱は心を揺さぶるもので、名曲「At Last」を聴くだけでもこの映画を見る価値があるというものだ。個人的にお勧めは、劇中で涙をためて歌う「All I Could Do Was Cry」。何度聴いても泣けてくる」。
問題があるとすれば、渡まち子氏が、「人種にこだわらないレナードの価値観や背景も、ほとんど分からない」というように、主人公レナード・チェスがさまざまの場面で何を考えているのか、映画からはいまいち読み取り難いという点なのかもしれません。
というのも、この映画は、レナード・チェスの伝記映画ではなく、むしろチェス・レコードというレコード会社についての話をメインに据えているからでしょう。冒頭いきなり黒人のギタリストのマディ・ウォーターズが南部の農場で働きながら歌っている場面となり、その彼がシカゴの街頭で歌っているところをレナード・チェスが見出して、チェス・レコードを立ち上げて、云々と映画は進み、ラスト近くでレナード・チェスがレコード会社を手放して死んでしまっても、その会社自体は存続して、云々と映画はしばらく続きます。
主人公のレナード・チェスの思いなど描くつもりはないのでしょう。
ただこの点は、樺沢氏のメルマガで補えます。
すなわち、同氏によれば、この映画の舞台である「シカゴという土地は、人種差別が非常に少ない土地柄であ」って、その理由は、「シカゴがほぼマイノリティで構成される街」だからとのこと。
同氏が示している最近の統計によれば、合計 283万人の住民のうち、
・白人系 42.0% 119万人
ポーランド系 7.3 % 21万人 (全米1位)
アイルランド系 6.6 % 19万人 (全米1位)
・黒人系 36.8 % 106万人 (全米2位)
要すれば、シカゴは、アメリカのマジョリティである「WASPと呼ばれる、アングロサクソン系プロテスタント」の割合が低く、カトリックや黒人といった「マイノリティーが大きな力を持っているという、アメリカでも非常にユニークな街」だとのことです(注)。
そのうえで、樺沢氏は、この映画のポイントは、主人公である「レナード・チェスが白人であるということ」であり、ポーランド系移民の「白人であるチェスが、全く人種的な偏見を持たず、素晴らしい音楽は素晴らしい、黒人も白人も関係なく多くの人に伝わるはずだ、という信念のもと、身を粉にして黒人シンガーの売り出しに命をかける点」だとしています。
なるほど、こうした背景があるのであれば、レナード・チェスが、黒人のギタリストのマディ・ウォーターズに「自分は偏見を持っていない」と簡単に肩ひじ張らずに明言するのもよく理解できます。
このレナード・チェスを演ずるのは、『戦場のピアニスト』の主役でアカデミー賞主演男優賞を獲得したエイドリアン・ブロディで、その映画ではナチス将校の前でベートーヴェンのピアノソナタを演奏する場面が印象的でした。他にDVDで『ダージリン急行』を見たことがあります。いかにもポーランド系ユダヤ人といった感じで、独特の雰囲気を持つ俳優です。
なお、タイトルにある「キャデラック」は、大ヒットを飛ばしたミュージシャンにレナード・チェスが買い与えたものですが、それが成功のシンボルとなっているところがアメリカの黄金時代なのだな、今からすればまさに隔世の感があるな(GMの経営破綻!)、日本だったらこんな場合には車ではなく一戸建ての家を買い与えるのかもしれないな、などと思ったりしました。
(注)黒人初の米国大統領オバマ氏がシカゴ出身だということも、こうした背景があると樺沢氏は述べています。すなわち、オバマ氏は、大統領になる前は上院議員でしたが、「黒人の上院議員は米史上、6人しか輩出されていない」ようで、そういう点からして、「アメリカ初の黒人大統領がアメリカでも人種的偏見が非常に少ない街「シカゴ」から生まれたことに、私はある種の必然性を感じる」と述べています。
精神科医・樺沢氏によるメルマガ「シカゴ発 映画の精神分析」第342号(9月2日)に、「音楽映画としても非常に完成度が高いので、社会的なテーマを抜きにしても、純粋に音楽に感動し、物語に共感できる」とあり、「私の場合、映画が終わってから、3分くらい涙が止まらなかった」とまで述べられていたこともあって見にいってきました。
実際にこの映画を見てみると、50年~60年代にかけてブルースからロックへアメリカ音楽が拡大していった時代を、それに大きく貢献したひとつのレーベル(「チェス・レコード」)を核にジックリと描きだしていて、私のようにこの方面に疎くとも、次々に演奏される曲を聴いているだけでジーンときてしまいます。どの歌も実によくできているのです。
こうした素晴らしい映画にも関わらず、福本次郎氏は、「映画は彼らの歌声をじっくりと聴かすというサービスはせず、主人公・レナードを中心とする人々の酒と女とドラッグにおぼれる日々ばかりを描写する」などと至極ピントとのはずれた批評をしています(40点)。
尤も、「ラジオのDJがくわえタバコのままマイクに向かってしゃべったり、ミュージシャンがところ構わず平気でタバコを吸っている。まだ、健康意識が低く、タバコの害などまったく問題にされなかった世の中とはいえ、見ているだけで気分が悪くなる映像だ」とも述べていて、そんな本筋と無関係の些細なことが気になるくらいですから、福本氏はこうした映画に全然向いていないようです。それなら見なければいいのに!
この映画に関する批評としては、次の渡まち子氏のものが私に一番近い感じがします(70点)。
いろいろ問題点はあるにせよ、「そんな不満をシビレるほど素晴らしい音楽がすべて吹き飛ばす。特にエタ・ジェイムズを演じるビヨンセの熱唱は心を揺さぶるもので、名曲「At Last」を聴くだけでもこの映画を見る価値があるというものだ。個人的にお勧めは、劇中で涙をためて歌う「All I Could Do Was Cry」。何度聴いても泣けてくる」。
問題があるとすれば、渡まち子氏が、「人種にこだわらないレナードの価値観や背景も、ほとんど分からない」というように、主人公レナード・チェスがさまざまの場面で何を考えているのか、映画からはいまいち読み取り難いという点なのかもしれません。
というのも、この映画は、レナード・チェスの伝記映画ではなく、むしろチェス・レコードというレコード会社についての話をメインに据えているからでしょう。冒頭いきなり黒人のギタリストのマディ・ウォーターズが南部の農場で働きながら歌っている場面となり、その彼がシカゴの街頭で歌っているところをレナード・チェスが見出して、チェス・レコードを立ち上げて、云々と映画は進み、ラスト近くでレナード・チェスがレコード会社を手放して死んでしまっても、その会社自体は存続して、云々と映画はしばらく続きます。
主人公のレナード・チェスの思いなど描くつもりはないのでしょう。
ただこの点は、樺沢氏のメルマガで補えます。
すなわち、同氏によれば、この映画の舞台である「シカゴという土地は、人種差別が非常に少ない土地柄であ」って、その理由は、「シカゴがほぼマイノリティで構成される街」だからとのこと。
同氏が示している最近の統計によれば、合計 283万人の住民のうち、
・白人系 42.0% 119万人
ポーランド系 7.3 % 21万人 (全米1位)
アイルランド系 6.6 % 19万人 (全米1位)
・黒人系 36.8 % 106万人 (全米2位)
要すれば、シカゴは、アメリカのマジョリティである「WASPと呼ばれる、アングロサクソン系プロテスタント」の割合が低く、カトリックや黒人といった「マイノリティーが大きな力を持っているという、アメリカでも非常にユニークな街」だとのことです(注)。
そのうえで、樺沢氏は、この映画のポイントは、主人公である「レナード・チェスが白人であるということ」であり、ポーランド系移民の「白人であるチェスが、全く人種的な偏見を持たず、素晴らしい音楽は素晴らしい、黒人も白人も関係なく多くの人に伝わるはずだ、という信念のもと、身を粉にして黒人シンガーの売り出しに命をかける点」だとしています。
なるほど、こうした背景があるのであれば、レナード・チェスが、黒人のギタリストのマディ・ウォーターズに「自分は偏見を持っていない」と簡単に肩ひじ張らずに明言するのもよく理解できます。
このレナード・チェスを演ずるのは、『戦場のピアニスト』の主役でアカデミー賞主演男優賞を獲得したエイドリアン・ブロディで、その映画ではナチス将校の前でベートーヴェンのピアノソナタを演奏する場面が印象的でした。他にDVDで『ダージリン急行』を見たことがあります。いかにもポーランド系ユダヤ人といった感じで、独特の雰囲気を持つ俳優です。
なお、タイトルにある「キャデラック」は、大ヒットを飛ばしたミュージシャンにレナード・チェスが買い与えたものですが、それが成功のシンボルとなっているところがアメリカの黄金時代なのだな、今からすればまさに隔世の感があるな(GMの経営破綻!)、日本だったらこんな場合には車ではなく一戸建ての家を買い与えるのかもしれないな、などと思ったりしました。
(注)黒人初の米国大統領オバマ氏がシカゴ出身だということも、こうした背景があると樺沢氏は述べています。すなわち、オバマ氏は、大統領になる前は上院議員でしたが、「黒人の上院議員は米史上、6人しか輩出されていない」ようで、そういう点からして、「アメリカ初の黒人大統領がアメリカでも人種的偏見が非常に少ない街「シカゴ」から生まれたことに、私はある種の必然性を感じる」と述べています。