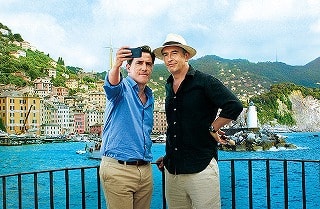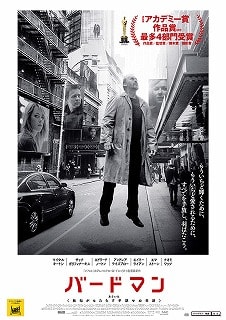『Zアイランド』を新宿の角川シネマで見ました。
(1)哀川翔(注1)の芸能生活30周年記念作品(注2)を品川ヒロシ(注3)が制作したということで(注4)、映画館に行ってきました。
本作(注5)の冒頭では、宗形組組長(哀川翔)らが高級クラブから出てきたところを、敵対する竹下組の反町(木村祐一)らに襲われ、無傷だった武史(鶴見辰吾)は、反町らに復讐するものの警察に捕まり、刑務所に。
次いで時点は10年後。
10年前に、銃で数発撃たれただけでなく短刀で刺されもした宗形ながら、今ではカタギとなって、かつての仲間とともに運送業を営んでいます。
そこに、刑務所から武史が戻ってきて、世話になっているはずの娘の日向(山本舞香)を探します。ですが、日向は家出をしたとのこと。
それで、宗形や武史らは、日向が行ったという銭荷島(注6)に向かいます。
他方で、反町らの竹下組の者も、クスリを持ち逃げした吉田(宮川大輔)を捕まえるべく、銭荷島に。
ところが、その銭荷島では大変な事態が持ち上がっているのです。
さあ、それはどんなことなのでしょうか、………?
本作での哀川翔は、今はカタギの生活をしている元親分。出所してきた子分の娘が家出したため皆で探しに行くと、娘が行った先の島ではゾンビが出没。全体として、ゾンビ物(注7)とヤクザ物とが一体化した映画の中で、哀川翔は、ゾンビばかりか、親分時代の抗争相手だったヤクザらをも縦横になぎ倒すという無敵の活躍振りを見せます(注8)。
(2)哀川翔は、ゼブラーマンや昆虫探偵を演じるのも構わないとはいえ、やはり本領はヤクザ物にあり、『25 NJYU-GO』では専らピストルが使われましたが(注9)、本作では、日本刀を振り回したりハーレーダヴィットソンに乗ったりするのですから、格好良さが倍加されます。

対するゾンビですが、銭荷島でゾンビ第1号となる吉田に扮する宮川大輔が秀逸です。
NTVの「世界の果てまでイッテQ!」で披露される“お祭り男”宮川大輔ならではの凄さで(注10)、映画を盛り上げます。

それに、宗形とラストで相まみえる反町役の木村祐一も、アクションシーンは初めてとのことながら(注11)なかなかの貫禄であり、今後こうした方面での活躍も期待されます。

本作は、登場人物たちが皆次々と「絶海の孤島」(注12)のはずの銭荷島に集まってしまうなどという超ご都合主義的なところ(注13)が見られるとはいえ、本作の主眼がヤクザとゾンビの対決にあるのですから、そんなことはどうでもよく、数多いアクションシーンを愉しめばいいのでしょう。
(3)渡まち子氏は、「孤島を舞台にヤクザたちが謎の感染者と戦う和製ゾンビ映画「Zアイランド」。群像劇、クロスオーバーのジャンルものとしてよくまとまっている」として65点をつけています。
前田有一氏は、「品川ヒロシ監督の「Zアイランド」は、なるほど、映画好きの監督らしいよく研究された娯楽映画であった」として70点をつけています。
(注1)最近見た哀川翔出演作については、本ブログのこのエントリの(3)をご覧ください。
(注2)本作もそうですが、「東映Vシネマ25周年記念」の『25 NJYU-GO』(2014年)とか、「映画デビュー25周年」の『ゼブラーマン―ゼブラシティの逆襲―』(2010年)、「主演作100本目」の『ゼブラーマン』(2003年)という具合に(ちなみに、本作は、哀川翔の「111本」目の主演映画)、哀川翔の映画には、節目を表すキャッチコピーがしばしば付けられます。
(注3)品川ヒロシの監督作品は、『ドロップ』(2009年)、『漫才ギャング』(2011年)、そして『サンブンノイチ』(2014年)を見ました。
(注4)本作は、劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事で哀川翔が述べているところによれば、映画『サンブンノイチ』に出演した折、彼が、「俺の30周年映画を取ってくれよ」と「軽いノリ」で頼んだところ、品川監督も、「分かりました。すぐやります」と受けてやりたい放題のことを詰め込んだ脚本を書いて云々という経緯を持っています。
なお、こうした経緯については、本ブログのこのエントリの「注8」で若干ながら触れています。
また、この記事によれば、続編の準備も図られているようです。
(注5)本作の監督・脚本は品川ヒロシ。
上映時間は109分。
(注6)その島は、以前、武史と桜(鈴木砂羽)と娘の日向とで家族旅行をしたことがある思い出の島。
なお、タイトルの「Zアイランド」は、「銭荷島→Zeni-island→Zアイランド」ということと、「Zombieの島」という意味があるのでしょう。
(注7)これまでゾンビ物は余り見ませんでしたが、最近では『ワールド・ウォーZ』を見ました。
なお、本作の医師のしげる(風間俊介)は、「ウィルス型のゾンビは速いが、薬品型のゾンビは遅い」などと薀蓄を垂れますが、確かに、『ワールド・ウォーZ』のゾンビはウィルス感染で数が急増し、なおかつものすごい速さで走りますから、あるいはあたっているのでしょう。
(注8)出演者の内、鶴見辰吾は『バンクーバーの朝日』、木村祐一は『ジャッジ!』、風間俊介は『鈴木先生』、銭荷島駐在の警察官役の窪塚洋介は『TOKYO TRIBE』、竹下組の中で反町に対立する木山に扮する中野英雄は『謝罪の王様』、竹下組組長役の小沢仁志は『25 NJYU-GO』で、それぞれ見ました。
(注9)『25 NJYU-GO』では刑事に扮しているとはいえ、温水洋一が横領した金を奪い取ろうとする悪徳刑事なのですから、ヤクザ物の変形ではないかと思います。
(注10)なにしろ、ものすごい速さで、自転車に乗って逃げる医師のしげるを追いかけたりするのですから!この点からすると、ゾンビの吉田はウィルス型と言えそうですが、映画では薬品を飲むことでゾンビになっています(劇場用パンフレットの「PRODUCTION NOTES」では「ハイブリッドゾンビ」とされています。)。
(注11)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事で哀川翔が述べています(問13の答)。
(注12)本作の公式サイトの「Introduction」に、「絶海の孤島を舞台にした、後戻りなしの超絶アクション・エンタテインメント」とあります。
(注13)例えば、吉田がなぜそんな「絶海の孤島」くんだりまで出向いたのかが不明ですし〔一応、愛人の恵(篠原ゆき子)の故郷とされていますが〕、また宗形は10年前の襲撃で足の神経をやられているはずにもかかわらず、大体において普通の歩き方をしていたりします。
★★★★☆☆
象のロケット:Zアイランド
(1)哀川翔(注1)の芸能生活30周年記念作品(注2)を品川ヒロシ(注3)が制作したということで(注4)、映画館に行ってきました。
本作(注5)の冒頭では、宗形組組長(哀川翔)らが高級クラブから出てきたところを、敵対する竹下組の反町(木村祐一)らに襲われ、無傷だった武史(鶴見辰吾)は、反町らに復讐するものの警察に捕まり、刑務所に。
次いで時点は10年後。
10年前に、銃で数発撃たれただけでなく短刀で刺されもした宗形ながら、今ではカタギとなって、かつての仲間とともに運送業を営んでいます。
そこに、刑務所から武史が戻ってきて、世話になっているはずの娘の日向(山本舞香)を探します。ですが、日向は家出をしたとのこと。
それで、宗形や武史らは、日向が行ったという銭荷島(注6)に向かいます。
他方で、反町らの竹下組の者も、クスリを持ち逃げした吉田(宮川大輔)を捕まえるべく、銭荷島に。
ところが、その銭荷島では大変な事態が持ち上がっているのです。
さあ、それはどんなことなのでしょうか、………?
本作での哀川翔は、今はカタギの生活をしている元親分。出所してきた子分の娘が家出したため皆で探しに行くと、娘が行った先の島ではゾンビが出没。全体として、ゾンビ物(注7)とヤクザ物とが一体化した映画の中で、哀川翔は、ゾンビばかりか、親分時代の抗争相手だったヤクザらをも縦横になぎ倒すという無敵の活躍振りを見せます(注8)。
(2)哀川翔は、ゼブラーマンや昆虫探偵を演じるのも構わないとはいえ、やはり本領はヤクザ物にあり、『25 NJYU-GO』では専らピストルが使われましたが(注9)、本作では、日本刀を振り回したりハーレーダヴィットソンに乗ったりするのですから、格好良さが倍加されます。

対するゾンビですが、銭荷島でゾンビ第1号となる吉田に扮する宮川大輔が秀逸です。
NTVの「世界の果てまでイッテQ!」で披露される“お祭り男”宮川大輔ならではの凄さで(注10)、映画を盛り上げます。

それに、宗形とラストで相まみえる反町役の木村祐一も、アクションシーンは初めてとのことながら(注11)なかなかの貫禄であり、今後こうした方面での活躍も期待されます。

本作は、登場人物たちが皆次々と「絶海の孤島」(注12)のはずの銭荷島に集まってしまうなどという超ご都合主義的なところ(注13)が見られるとはいえ、本作の主眼がヤクザとゾンビの対決にあるのですから、そんなことはどうでもよく、数多いアクションシーンを愉しめばいいのでしょう。
(3)渡まち子氏は、「孤島を舞台にヤクザたちが謎の感染者と戦う和製ゾンビ映画「Zアイランド」。群像劇、クロスオーバーのジャンルものとしてよくまとまっている」として65点をつけています。
前田有一氏は、「品川ヒロシ監督の「Zアイランド」は、なるほど、映画好きの監督らしいよく研究された娯楽映画であった」として70点をつけています。
(注1)最近見た哀川翔出演作については、本ブログのこのエントリの(3)をご覧ください。
(注2)本作もそうですが、「東映Vシネマ25周年記念」の『25 NJYU-GO』(2014年)とか、「映画デビュー25周年」の『ゼブラーマン―ゼブラシティの逆襲―』(2010年)、「主演作100本目」の『ゼブラーマン』(2003年)という具合に(ちなみに、本作は、哀川翔の「111本」目の主演映画)、哀川翔の映画には、節目を表すキャッチコピーがしばしば付けられます。
(注3)品川ヒロシの監督作品は、『ドロップ』(2009年)、『漫才ギャング』(2011年)、そして『サンブンノイチ』(2014年)を見ました。
(注4)本作は、劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事で哀川翔が述べているところによれば、映画『サンブンノイチ』に出演した折、彼が、「俺の30周年映画を取ってくれよ」と「軽いノリ」で頼んだところ、品川監督も、「分かりました。すぐやります」と受けてやりたい放題のことを詰め込んだ脚本を書いて云々という経緯を持っています。
なお、こうした経緯については、本ブログのこのエントリの「注8」で若干ながら触れています。
また、この記事によれば、続編の準備も図られているようです。
(注5)本作の監督・脚本は品川ヒロシ。
上映時間は109分。
(注6)その島は、以前、武史と桜(鈴木砂羽)と娘の日向とで家族旅行をしたことがある思い出の島。
なお、タイトルの「Zアイランド」は、「銭荷島→Zeni-island→Zアイランド」ということと、「Zombieの島」という意味があるのでしょう。
(注7)これまでゾンビ物は余り見ませんでしたが、最近では『ワールド・ウォーZ』を見ました。
なお、本作の医師のしげる(風間俊介)は、「ウィルス型のゾンビは速いが、薬品型のゾンビは遅い」などと薀蓄を垂れますが、確かに、『ワールド・ウォーZ』のゾンビはウィルス感染で数が急増し、なおかつものすごい速さで走りますから、あるいはあたっているのでしょう。
(注8)出演者の内、鶴見辰吾は『バンクーバーの朝日』、木村祐一は『ジャッジ!』、風間俊介は『鈴木先生』、銭荷島駐在の警察官役の窪塚洋介は『TOKYO TRIBE』、竹下組の中で反町に対立する木山に扮する中野英雄は『謝罪の王様』、竹下組組長役の小沢仁志は『25 NJYU-GO』で、それぞれ見ました。
(注9)『25 NJYU-GO』では刑事に扮しているとはいえ、温水洋一が横領した金を奪い取ろうとする悪徳刑事なのですから、ヤクザ物の変形ではないかと思います。
(注10)なにしろ、ものすごい速さで、自転車に乗って逃げる医師のしげるを追いかけたりするのですから!この点からすると、ゾンビの吉田はウィルス型と言えそうですが、映画では薬品を飲むことでゾンビになっています(劇場用パンフレットの「PRODUCTION NOTES」では「ハイブリッドゾンビ」とされています。)。
(注11)劇場用パンフレット掲載のインタビュー記事で哀川翔が述べています(問13の答)。
(注12)本作の公式サイトの「Introduction」に、「絶海の孤島を舞台にした、後戻りなしの超絶アクション・エンタテインメント」とあります。
(注13)例えば、吉田がなぜそんな「絶海の孤島」くんだりまで出向いたのかが不明ですし〔一応、愛人の恵(篠原ゆき子)の故郷とされていますが〕、また宗形は10年前の襲撃で足の神経をやられているはずにもかかわらず、大体において普通の歩き方をしていたりします。
★★★★☆☆
象のロケット:Zアイランド