横浜美術館で開催されている「松井冬子展」(~3月18日)に行ってきました。
松井冬子氏については、このブログでも何度か取り上げていますが(注1)、公立美術館における初めての大規模個展ということで、注目されます。
(1)冒頭に掲げましたのは、『世界中の子と友達になれる』(2002年)で(注2)、雑誌の対談において松井氏は、タイトルの由来につき、「子供の頃、本心でそう感じた瞬間があって。でも大人になったいまそれは妄想であると気づきました。それゆえ狂気と希望が入り交じる、私の琴線にふれる言葉になりました」と述べています(注3)。
(2)下図は『浄相の持続』(2004年)で、同展覧会では、「第7章九相図」のコーナーで展示されています(注4)。

この作品は、腹部を開いているところから、「腑分図:第七頸椎」とか「解剖 仔牛」などの作品が展示されている「第5章腑分」にも通じているように思われます(注5)。
となると、2011年の「このミステリーがすごい」で3位だった皆川博子氏の『開かせていただき光栄です』(早川書房、2011.7)を読み終わったばかりなので、そのシンクロ性に驚きました。
というのも、素晴らしい出来栄えの同ミステリー(とても80歳を越える作者が描いたものとは思えません!)は、舞台が18世紀のロンドン、解剖を専らにする外科医ダニエルの解剖教室(注6)で、四肢を切断された少年と顔を潰された男の死体が見つかったという事件を追って行くもので、「特別附録」として「解剖ソング」まで巻末に付けられているほど解剖についての話が満載なのですから(注7)。
さて、同展のカタログによれば、「松井冬子は、人間というものは開いたら内臓が出てくるものなのだから、それは現実であり事実であって、臓物を描くことは真実を見つめることと同義だとい」っているとのこと(P.125)。
ここには、どこまでも真実を求めることが正しいのだ、という作者の姿勢がうかがわれます(注8)。
でも、映画『サラの鍵』で登場人物の一人が言っているように、真実を追求することは本当に正しいことなのか、そのまま静かに放っておくことも必要な場合もあるのではないか、とも思われるところですが(無論、『サラの鍵』の主人公は、ジャーナリストとしてどこまでも真実を追い求めて行くのですが)。
(注1)「医学と芸術展」についてのエントリ(2010年1月7日)で『無傷の標本』(2009年)を、映画『ステキな金縛り』に関するエントリ(2011年11月12日)で『夜盲症』(2005年)を取り上げています。
(注2)朝日新聞2月8日夕刊の展覧会紹介記事によれば、東京芸大の卒業制作であり、松井氏は「プロとしての第1歩」と位置付けているようです(この絵については、何枚もの下図も同時に展示されていますが、同氏によれば、「イメージがしっかりあって練っている、その過程を理解してほしかった」とのこと)。
なお、なおこの作品は、次のジョットの『聖フランチェスコの小鳥への説教』を思い起こさせます。

(注3)『美術手帖』本年2月号(美術出版社)。
(注4)松井氏によれば、「九相図」は、鎌倉時代にあった「九相詩絵巻」からヒントを得ているところ、新しい「九相図」を描くべく、9つの自殺の要因を一つずつ描いていこうとしていて、この『浄相の持続』は「復讐」(「親とか恋人とか、周囲の人を攻撃する。最後の復讐という意味合いの自殺」)とのこと〔「注3」の雑誌のP.48~P.49〕。
同作品の脇に作者によって付けられた解説には、次のように記されています。
「「私はこんなに立派な子宮をもっている」という攻撃的な態度は、自傷行為の原因となる防衛目的から発現した破壊的衝動である。私はこの女に対し自己投影し同一視している。また彼女の周りに咲く花々も、彼女に同調するように切断し、雌しべをみせびらかしている。私はこの作品に共感し、同調しうるであろう女性達に向けて作品を制作した。同調に関しての優れた能力は、卵をつくる、分身をつくる、という子宮を持つ者の強い特権であるからだ。」
こうした作者の姿勢を巡って、精神科医の斎藤環氏は、「確かに男性にはこの作品を正確に理解することが難しい。なぜか、男性にはどうしても、横たわって内臓をさらけ出している女性の姿を「屍体」と見てしまうからだ」、しかし、「女性ほどではないにせよ、男性にとっても「シンクロ」が可能になる」ポイントはある、それは「まなざし」だ、云々と述べています〔「注3」の雑誌に掲載されている論文「松井冬子論 ジェンダーとアートの新しい回路」〕。
(注5)「腑分」というと、『解体新書』を思い出させますが、同書の「解剖絵図を一人で担当した」のが、秋田蘭画を代表する画家の一人の小田野直武であることなどについては、昨年5月5日のエントリの末尾及び「注5」を参照して下さい。
(注6)実は、解剖教室を所有するのは、兄のロバート・バートン(「ロバート・バートンが教室を開設するまでは、ロンドンにおいては、医学生であっても屍体に触れる機会はほとんどなかった」)で、弟のダニエル・バートンが外科医として手伝うようになってから、「ロバートは社会的地位の高い内科医の資格を得、上流社会の仲間入りをした。ダニエルのような外科医は、数段低くみられている」とのことです(『開かせていただき光栄です』P.14)。
(注7)佳嶋氏による『開かせていただき光栄です』のBook Cover Illustrationは、「解剖」をイメージしたものになっています。
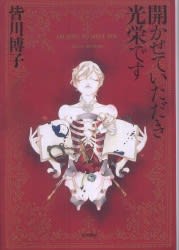
(注8)ここでいう「真実」とは何かということが問題となるかも知れませんが、それはサテ置いて、映画『麒麟の翼』に登場する加賀刑事も、「真実を避けるから殺人事件が起きてしまったのだ」と語ります。
松井冬子氏については、このブログでも何度か取り上げていますが(注1)、公立美術館における初めての大規模個展ということで、注目されます。
(1)冒頭に掲げましたのは、『世界中の子と友達になれる』(2002年)で(注2)、雑誌の対談において松井氏は、タイトルの由来につき、「子供の頃、本心でそう感じた瞬間があって。でも大人になったいまそれは妄想であると気づきました。それゆえ狂気と希望が入り交じる、私の琴線にふれる言葉になりました」と述べています(注3)。
(2)下図は『浄相の持続』(2004年)で、同展覧会では、「第7章九相図」のコーナーで展示されています(注4)。

この作品は、腹部を開いているところから、「腑分図:第七頸椎」とか「解剖 仔牛」などの作品が展示されている「第5章腑分」にも通じているように思われます(注5)。
となると、2011年の「このミステリーがすごい」で3位だった皆川博子氏の『開かせていただき光栄です』(早川書房、2011.7)を読み終わったばかりなので、そのシンクロ性に驚きました。
というのも、素晴らしい出来栄えの同ミステリー(とても80歳を越える作者が描いたものとは思えません!)は、舞台が18世紀のロンドン、解剖を専らにする外科医ダニエルの解剖教室(注6)で、四肢を切断された少年と顔を潰された男の死体が見つかったという事件を追って行くもので、「特別附録」として「解剖ソング」まで巻末に付けられているほど解剖についての話が満載なのですから(注7)。
さて、同展のカタログによれば、「松井冬子は、人間というものは開いたら内臓が出てくるものなのだから、それは現実であり事実であって、臓物を描くことは真実を見つめることと同義だとい」っているとのこと(P.125)。
ここには、どこまでも真実を求めることが正しいのだ、という作者の姿勢がうかがわれます(注8)。
でも、映画『サラの鍵』で登場人物の一人が言っているように、真実を追求することは本当に正しいことなのか、そのまま静かに放っておくことも必要な場合もあるのではないか、とも思われるところですが(無論、『サラの鍵』の主人公は、ジャーナリストとしてどこまでも真実を追い求めて行くのですが)。
(注1)「医学と芸術展」についてのエントリ(2010年1月7日)で『無傷の標本』(2009年)を、映画『ステキな金縛り』に関するエントリ(2011年11月12日)で『夜盲症』(2005年)を取り上げています。
(注2)朝日新聞2月8日夕刊の展覧会紹介記事によれば、東京芸大の卒業制作であり、松井氏は「プロとしての第1歩」と位置付けているようです(この絵については、何枚もの下図も同時に展示されていますが、同氏によれば、「イメージがしっかりあって練っている、その過程を理解してほしかった」とのこと)。
なお、なおこの作品は、次のジョットの『聖フランチェスコの小鳥への説教』を思い起こさせます。

(注3)『美術手帖』本年2月号(美術出版社)。
(注4)松井氏によれば、「九相図」は、鎌倉時代にあった「九相詩絵巻」からヒントを得ているところ、新しい「九相図」を描くべく、9つの自殺の要因を一つずつ描いていこうとしていて、この『浄相の持続』は「復讐」(「親とか恋人とか、周囲の人を攻撃する。最後の復讐という意味合いの自殺」)とのこと〔「注3」の雑誌のP.48~P.49〕。
同作品の脇に作者によって付けられた解説には、次のように記されています。
「「私はこんなに立派な子宮をもっている」という攻撃的な態度は、自傷行為の原因となる防衛目的から発現した破壊的衝動である。私はこの女に対し自己投影し同一視している。また彼女の周りに咲く花々も、彼女に同調するように切断し、雌しべをみせびらかしている。私はこの作品に共感し、同調しうるであろう女性達に向けて作品を制作した。同調に関しての優れた能力は、卵をつくる、分身をつくる、という子宮を持つ者の強い特権であるからだ。」
こうした作者の姿勢を巡って、精神科医の斎藤環氏は、「確かに男性にはこの作品を正確に理解することが難しい。なぜか、男性にはどうしても、横たわって内臓をさらけ出している女性の姿を「屍体」と見てしまうからだ」、しかし、「女性ほどではないにせよ、男性にとっても「シンクロ」が可能になる」ポイントはある、それは「まなざし」だ、云々と述べています〔「注3」の雑誌に掲載されている論文「松井冬子論 ジェンダーとアートの新しい回路」〕。
(注5)「腑分」というと、『解体新書』を思い出させますが、同書の「解剖絵図を一人で担当した」のが、秋田蘭画を代表する画家の一人の小田野直武であることなどについては、昨年5月5日のエントリの末尾及び「注5」を参照して下さい。
(注6)実は、解剖教室を所有するのは、兄のロバート・バートン(「ロバート・バートンが教室を開設するまでは、ロンドンにおいては、医学生であっても屍体に触れる機会はほとんどなかった」)で、弟のダニエル・バートンが外科医として手伝うようになってから、「ロバートは社会的地位の高い内科医の資格を得、上流社会の仲間入りをした。ダニエルのような外科医は、数段低くみられている」とのことです(『開かせていただき光栄です』P.14)。
(注7)佳嶋氏による『開かせていただき光栄です』のBook Cover Illustrationは、「解剖」をイメージしたものになっています。
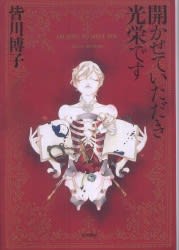
(注8)ここでいう「真実」とは何かということが問題となるかも知れませんが、それはサテ置いて、映画『麒麟の翼』に登場する加賀刑事も、「真実を避けるから殺人事件が起きてしまったのだ」と語ります。










