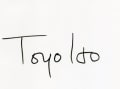あるフランス映画を見ようと思って出かけたところが、狙った時間帯には上映されていないことがわかり、それなら別のフランス映画を見ようということになって、『華麗なるアリバイ』を渋谷のル・シネマで見てきました。
(1)邦題を見て、この映画はいわゆる“アリバイ崩し”物かもしれないと思い、それも「華麗なる(grand)」というわけですから、ポアロ探偵も酷くてこずるのではと大層期待させます(アガサ・クリスティの原作によっていることが前もってわかりましたから)。
ですが、実はそんなことは全然ありません。まず、期待したポアロ探偵はいっさい現れず、代わりに登場するのは風采の上がらない刑事であり、別段彼がこの事件を解決するわけでもありません(ラスト近くで、犯人らが一つの家に集まるのを見ていながら、何の手も打たないボンクラなのです!)。
また、犯人と目された人のアリバイが映画の中で重要な争点となるわけではなく、従って“アリバイ崩し”がなされているわけでもありません。
一番犯人らしいのが、殺された精神科医ピエールの妻のクレール。なにしろ、遺体のそばでピストルを持ってしゃがみこんでいたのですから!
そこで、彼女は警察に連行されますが、彼女が申し立てたアリバイが成立したからというわけではなく、単に使われたピストルと彼女が手にしていたピストルが違っていたという理由から、結局釈放されてしまいます。
それに彼女は、事件の舞台となった屋敷を所有する上院議員の妻と一緒にキノコ狩りに行っていたとされますが、なぜ上院議員の妻と別れて遺体のそばにいたのかという点については、映画では何ら問題にされません!銃声を聞いて飛んで行ったというのであれば、上院議員の妻も同行したのではないでしょうか?ここでは当初から「アリバイ」など問題視されてはいないのです。
そこで、クレールでないとしたら犯人と目されるのが小説家フィリップ。というのも、酷いアルコール依存症で、飲んだ時の記憶が全くなくなってしまうことから、特に第2の殺人事件(ピエールの昔の愛人レアが殺されます)について自分の無実を証拠立てられないという点が問題となります。
とはいえ、これでは身を守ってくれる「アリバイ」自体がまったく存在しないわけで、そんなものを「華麗なるアリバイ」とは言えますまい。
それに彼には、最初の殺人事件についても、特に第2の殺人事件については、十分な動機がこの映画からはうかがえません〔最初の犠牲者ピエールに対しては、自分が愛する女性エステルが愛する男性だということで嫉妬はするでしょうが、だからといってまさか殺してしまうとは考えられないところです〕。
そこで彼は、警察に捕まる前に自分で犯人を探さざるを得ないとしてアチコチ走り回ることになり、ついにエステルの仕事場に行って、……。
最後になって、誰が犯人で、どうやって殺人事件を引き起こしたのか、動機は何かというごくオーソドックスな点が解明されます。なにしろ、犯人が現れて、まだ完結しない復讐行為を継続しようとして自分からいろいろ喋るのですから!
それですべては明らかになり、フィリップも、晴れて、この事件のことを小説に書こうとして「fin」というわけです。
とはいえ、ラストで目覚ましい事実が明らかになるわけでもなく、解き明かされるのは酷く地味な事柄でした。こういう地味な結末になるのも、やはり、ポアロ探偵がいて皆のいる前でなぞ解きをしないからではないでしょうか?
ということで、最近見た『オーケストラ!』で天才ヴァイオリニストのマネージャー役を演じていたミュウ=ミュウ(上院議員の妻の役)とか、“華麗な”肉体を披露するカテリーナ・ムリーノ(ピエールの昔の愛人レアの役)などが登場するものの、全体としてフィット感のしない作品だと思いました。
(2)アガサ・クリスティ原作の映画は、以前同じル・シネマで『ゼロ時間の謎』を見たことがあります(2007年の年末)。

その際に友人に書き送ったメールに、次のような感想を書いています。
「ストーリー自体は他愛ない感じですが、出演者の中に、今年の夏ごろル・シネマで見た「マルチェロ・マストロヤンニ―甘い追憶」に登場していた娘のキアラ・マストロヤンニ(母親はカトリーヌ・ドヌーブ)と、同じ頃渋谷Q-AXシネマで見た「石の微笑」に出演していたローラ・スメットとが入っているので、なにか本年最後に見る映画に相応しい感じがしてしまいました。
ところで、こういう正統派ミステリ映画の場合、犯人は主役(もしくはそれに準ずる役)の俳優が演じます。ただ、最後のギリギリのところまであくまでも真っ当な人物として行動し、他方いかにも何か裏がありそうな雰囲気を漂わせている人物は決して犯人ではないというのが、大体どの作品にも当てはまりますから、見ているうちにおのずと犯人は絞られてしまいます。
これはミステリ映画の宿命かもしれません。ですから、見どころは、謎解き以外の点で映画がどのような魅力を発揮しているのかではないでしょうか?この映画の場合は、フランスの金持階級の豪勢な生活ぶりと、上記した女優の出演とが見どころと言えるでしょう。」
そうだとしたら、今回の『華麗なるアリバイ』についても、謎解きというよりももっと他の点に注意を向けるべきなのかもしれません。
劇場用パンフレットに掲載されている監督インタビューでも、アガサ・クリスティーの原作の「本を読みなおしたところ、推理的要素よりも、登場人物たちの感情が緻密なのが魅力的に思えたので、(監督を)引き受けました」と述べられているところです。
確かに、エステルは、実際に犯行に使われたピストルを、警察より先回りして見つけ出して隠してしまいますし、上院議員の妻もクレールに対して色々気を使ったりします。ただ、この映画に何人も登場する女性の心理状況をうまく観客に伝えるには、1時間半の長さでは大層難しいのではないかと思いました。
(3)映画評論家の論評はあまり見かけませんが、前田有一氏は、「ミステリとしては伝統的な舞台立てだが、それにしても刺激が足りない。かといってクラシカルな風格があるわけでもなく、この古典を引っ張り出して何をしたかったのかが伝わりにくい」し、「もう何もかもが賞味期限切れ。超ベテラン監督の、悪いところばかりが強く出てしまった印象だ」として40点しか付けていません。
その評点は頷けるものの、前田氏は、「のっけから連発される登場人物名の羅列に、原作未読者はついていくのも大変だ」と述べているところ、こうしたサスペンス映画を前にしたら、まず登場人物の名前を何としてでも早めに覚えてしまうというのが当然の了解事項ではないでしょうか〔せいぜい10人くらいのことですから〕?
それに原作は英語であり、舞台も人名もまるで違っているので、仮に原作を読んでいたとしても、名前を覚える努力を払わなければ映画のストーリーについてはいけないことでしょう〔本作はクリスティの手によって「戯曲」化されているとのことですから、あるいはそちらは映画と同じ設定になっているのかもしれませんが〕!
★★☆☆☆
象のロケット:華麗なるアリバイ
(1)邦題を見て、この映画はいわゆる“アリバイ崩し”物かもしれないと思い、それも「華麗なる(grand)」というわけですから、ポアロ探偵も酷くてこずるのではと大層期待させます(アガサ・クリスティの原作によっていることが前もってわかりましたから)。
ですが、実はそんなことは全然ありません。まず、期待したポアロ探偵はいっさい現れず、代わりに登場するのは風采の上がらない刑事であり、別段彼がこの事件を解決するわけでもありません(ラスト近くで、犯人らが一つの家に集まるのを見ていながら、何の手も打たないボンクラなのです!)。
また、犯人と目された人のアリバイが映画の中で重要な争点となるわけではなく、従って“アリバイ崩し”がなされているわけでもありません。
一番犯人らしいのが、殺された精神科医ピエールの妻のクレール。なにしろ、遺体のそばでピストルを持ってしゃがみこんでいたのですから!
そこで、彼女は警察に連行されますが、彼女が申し立てたアリバイが成立したからというわけではなく、単に使われたピストルと彼女が手にしていたピストルが違っていたという理由から、結局釈放されてしまいます。
それに彼女は、事件の舞台となった屋敷を所有する上院議員の妻と一緒にキノコ狩りに行っていたとされますが、なぜ上院議員の妻と別れて遺体のそばにいたのかという点については、映画では何ら問題にされません!銃声を聞いて飛んで行ったというのであれば、上院議員の妻も同行したのではないでしょうか?ここでは当初から「アリバイ」など問題視されてはいないのです。
そこで、クレールでないとしたら犯人と目されるのが小説家フィリップ。というのも、酷いアルコール依存症で、飲んだ時の記憶が全くなくなってしまうことから、特に第2の殺人事件(ピエールの昔の愛人レアが殺されます)について自分の無実を証拠立てられないという点が問題となります。
とはいえ、これでは身を守ってくれる「アリバイ」自体がまったく存在しないわけで、そんなものを「華麗なるアリバイ」とは言えますまい。
それに彼には、最初の殺人事件についても、特に第2の殺人事件については、十分な動機がこの映画からはうかがえません〔最初の犠牲者ピエールに対しては、自分が愛する女性エステルが愛する男性だということで嫉妬はするでしょうが、だからといってまさか殺してしまうとは考えられないところです〕。
そこで彼は、警察に捕まる前に自分で犯人を探さざるを得ないとしてアチコチ走り回ることになり、ついにエステルの仕事場に行って、……。
最後になって、誰が犯人で、どうやって殺人事件を引き起こしたのか、動機は何かというごくオーソドックスな点が解明されます。なにしろ、犯人が現れて、まだ完結しない復讐行為を継続しようとして自分からいろいろ喋るのですから!
それですべては明らかになり、フィリップも、晴れて、この事件のことを小説に書こうとして「fin」というわけです。
とはいえ、ラストで目覚ましい事実が明らかになるわけでもなく、解き明かされるのは酷く地味な事柄でした。こういう地味な結末になるのも、やはり、ポアロ探偵がいて皆のいる前でなぞ解きをしないからではないでしょうか?
ということで、最近見た『オーケストラ!』で天才ヴァイオリニストのマネージャー役を演じていたミュウ=ミュウ(上院議員の妻の役)とか、“華麗な”肉体を披露するカテリーナ・ムリーノ(ピエールの昔の愛人レアの役)などが登場するものの、全体としてフィット感のしない作品だと思いました。
(2)アガサ・クリスティ原作の映画は、以前同じル・シネマで『ゼロ時間の謎』を見たことがあります(2007年の年末)。

その際に友人に書き送ったメールに、次のような感想を書いています。
「ストーリー自体は他愛ない感じですが、出演者の中に、今年の夏ごろル・シネマで見た「マルチェロ・マストロヤンニ―甘い追憶」に登場していた娘のキアラ・マストロヤンニ(母親はカトリーヌ・ドヌーブ)と、同じ頃渋谷Q-AXシネマで見た「石の微笑」に出演していたローラ・スメットとが入っているので、なにか本年最後に見る映画に相応しい感じがしてしまいました。
ところで、こういう正統派ミステリ映画の場合、犯人は主役(もしくはそれに準ずる役)の俳優が演じます。ただ、最後のギリギリのところまであくまでも真っ当な人物として行動し、他方いかにも何か裏がありそうな雰囲気を漂わせている人物は決して犯人ではないというのが、大体どの作品にも当てはまりますから、見ているうちにおのずと犯人は絞られてしまいます。
これはミステリ映画の宿命かもしれません。ですから、見どころは、謎解き以外の点で映画がどのような魅力を発揮しているのかではないでしょうか?この映画の場合は、フランスの金持階級の豪勢な生活ぶりと、上記した女優の出演とが見どころと言えるでしょう。」
そうだとしたら、今回の『華麗なるアリバイ』についても、謎解きというよりももっと他の点に注意を向けるべきなのかもしれません。
劇場用パンフレットに掲載されている監督インタビューでも、アガサ・クリスティーの原作の「本を読みなおしたところ、推理的要素よりも、登場人物たちの感情が緻密なのが魅力的に思えたので、(監督を)引き受けました」と述べられているところです。
確かに、エステルは、実際に犯行に使われたピストルを、警察より先回りして見つけ出して隠してしまいますし、上院議員の妻もクレールに対して色々気を使ったりします。ただ、この映画に何人も登場する女性の心理状況をうまく観客に伝えるには、1時間半の長さでは大層難しいのではないかと思いました。
(3)映画評論家の論評はあまり見かけませんが、前田有一氏は、「ミステリとしては伝統的な舞台立てだが、それにしても刺激が足りない。かといってクラシカルな風格があるわけでもなく、この古典を引っ張り出して何をしたかったのかが伝わりにくい」し、「もう何もかもが賞味期限切れ。超ベテラン監督の、悪いところばかりが強く出てしまった印象だ」として40点しか付けていません。
その評点は頷けるものの、前田氏は、「のっけから連発される登場人物名の羅列に、原作未読者はついていくのも大変だ」と述べているところ、こうしたサスペンス映画を前にしたら、まず登場人物の名前を何としてでも早めに覚えてしまうというのが当然の了解事項ではないでしょうか〔せいぜい10人くらいのことですから〕?
それに原作は英語であり、舞台も人名もまるで違っているので、仮に原作を読んでいたとしても、名前を覚える努力を払わなければ映画のストーリーについてはいけないことでしょう〔本作はクリスティの手によって「戯曲」化されているとのことですから、あるいはそちらは映画と同じ設定になっているのかもしれませんが〕!
★★☆☆☆
象のロケット:華麗なるアリバイ