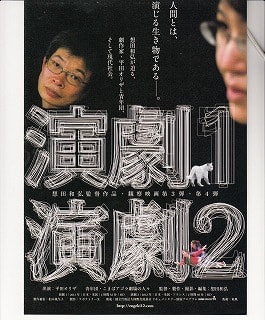『塀の中のジュリアス・シーザー』を銀座テアトルシネマで見ました。
(1)1月に『もう一人のシェイクスピア』を見ており、また演劇関係のドキュメンタリー作品『演劇1、演劇2』を見たばかりでもあり、この映画に興味を惹かれました。
映画の舞台は、ローマの郊外にあるレビッビア刑務所。

同刑務所では囚人による演劇実習が毎年行われ、舞台で上演される際には一般人にも公開されますが、その年はシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』(「ブルータス、おまえもか?」の台詞で有名です)をやることになります(注1)。
俳優の選定に当たりオーディションが行われ(注2)、刑務所の重警備棟に入っている囚人たちが名乗り出ます。
ブルータス役、シーザー役、アントニー役、キャシアス役などが次々に選ばれ、早速稽古に入りますが、さあ、シェイクスピアの戯曲は上手く演じることが出来るのでしょうか、……?
日本だったらこんなことは絶対にあり得ないと思えるところ、本作では、実際の服役囚が画面に素の顔をさらして演じているのですから驚きです(なかには、稽古に熱心な余り、自分と役柄との見境がつかなくなってくる囚人がいたりします)。
それも、皆よく台詞を咀嚼し情熱をこめて演じており、映画全体として戯曲の大体が分かるように大層上手く編集げられてもいます(76分という短さも好ましく思いました)。
(2)予告編などで、本作は本物の囚人によって演じられるとされていても、「本物の囚人」らしくプロの俳優が演じているに違いないと思っていました。
でも、映画のラストに、出演する俳優の犯罪歴までもがはっきりと映し出されると、もしかしたら本当に「本物の囚人」が演じているのではないかと思わざるを得なくなります(注3)。
仮にそうだとすれば、『演劇1、演劇2』と同じように(注4)、稽古と上演の様子が描かれているドキュメンタリー作品ということになります。
でも、映画の途中で、面会から戻ったアントニー役が落ち込んでいる姿が映し出されますが、如何にも“演技してます”といった感じが漂っていますから(注5)、なかなかそうとも言えないのではないかという気もしてしまいます。
それに、舞台が修理中ということで使えないため、刑務所内のあちこちで稽古が行われますが、演出家による駄目出し(注6)なども行われませんし、稽古の場所がむしろ舞台よりもずっと適している感じもするのです。

そこで、仕方ありませんから、劇場用パンフレットに頼ることになります。
すると、例えばこんなことが分かります。
・脚本が作成されている(その際には、シェイクスピアの戯曲の再構成・再構築が行われている)。
・ブルータス役は、2006年に出所しており、その後俳優に転身し、様々な映画に出演している。

・演出を担当した舞台監督のファビオは外部の者で、さらにキャシアス役が演出には協力している(注7)。
要すれば、予め作成された脚本にのっとって、刑務所内の囚人と外部の俳優が一緒になって、最初から最後まで演技をしたということのようです。
であれば、本作は劇映画であって、ドキュメンタリー作品とは言えなくなります(注8)。
尤も、ドキュメンタリー作品とされる『演劇1、演劇2』であっても、まるで平田オリザ氏らの“素”の顔が映し出されているように見えながらも、けっしてそうではなく“演じて”いるようでもあり(注9)、なかなか劇映画とドキュメンタリー作品との線引きは難しいようです。
さらに考えると、本作では、二重の意味で“リアル”が問われているのではないかと思いました。
一つ目は、今申し上げたように、本作がドキュメンタリー作品なのか劇映画(フィクション)なのかという点ですが、二つ目は、本作で描き出されている『ジュリアス・シーザー』に感動するかどうか、という点です。
すなわち、第一点目に関しては、“素”か“演技”かというところで“リアル”について検討できるでしょうが、第二点目については、演じられた戯曲について“リアル”さを感じるかどうか、ということではないかと思われます。
ただ、劇映画とドキュメンタリー作品との線引きが難しいとなると、より重要なのは、第二点目ということになるでしょう。
その場合、“リアル”とは何かということになるでしょうが、とりあえずここでは、観客に感動をもたらすヴィヴィッドなリアリティとでも言っておきます。
本作の場合、台詞が英語からイタリア語に置き換えられ、どんな感じで観客に受け取られるのかはわかりませんが、俳優が喋りやすいように様々な方言混じりの台詞となっているようです。
また、シーザーの暗殺場面とか、ブルータスやアントニーの演説場面とかが、舞台ではなく石の壁で囲まれた刑務所内となっていることはことのほか臨場感をもたらします(注10)。
といったようなことから、クマネズミは本作の『ジュリアス・シーザー』に“リアル”を覚えました。
(3)渡まち子氏は、「監督のパオロとヴィットリオのタヴィアーニ兄弟は、共に80歳を越えるが、本物の刑務所や囚人を使った演劇を映画に収める実験精神や、刑務所内をモノクロで、本番の劇をカラーで描き分ける美的センスなど、感覚はすこぶる若々しい。日本では決して実現しないだろう映画作りで、アートに最大限の敬意をはらうイタリアらしい映画だ」として75点を付けています。
(注1)シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』については、この記事が大変参考になります。
なお、同戯曲には、シーザーやブルータスの妻が登場しますが、そのウエイトが少ないため、男性の囚人による上演に適していると言えるのかもしれません。
(注2)オーディションでは、国境において名前、生年月日、出生地等を申告する際に、悲しみと怒りの2つを表現する、という課題を囚人に課します。
(注3)さらには、映画の中では、ブルータス役が「台詞が覚えきれない、これで観客に上手く伝えられるのか」などと素のようにしゃべったりしますし。
(注4)同作品では、平田オリザ氏の作・演出による『火宅と修羅』や『ヤルタ会談』などといった戯曲について、その稽古風景と上演時の様子がスクリーンに描き出されます。
(注5)他にも、シーザー役とキャシアス役が、稽古の最中に、素に戻ったかの如く喧嘩をし始めたりしますが、その写し方を見ると劇映画風の感じを受けてしまいます。
(注6)何も、『演劇1、演劇2』に見られる平田オリザ氏の精緻極まる「駄目出し」をここに求めるわけではありませんが!
(注7)と言っても、全体の演出は、この映画を制作(監督・脚本)したパオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ兄弟によっていて、ファビオやキャシアス役は演出家及び演出家補の役を演じたようですが(ファビオは、俳優に対して指示を出したりしますが、それも演技なのでしょう!)。
(注8)従って、本作の最初と最後に、刑務所内の劇場に入ってきたり退出したりする一般観客の姿が映し出されますが、それは演出されたものであり、さらには、舞台の模様がカラーで映し出されますが(それ以外はモノクロ)、それもその場面だけの限定的な演技なのではと思われるところです。
劇場用パンフレットによれば、舞台監督のファビオは、『ジュリアス・シーザー』のオリジナルを刑務所内の舞台で上演すべく、レビッビア刑務所に戻ったとのことです。
(注9)『演劇1、演劇2』を制作した植田和弘監督が書いた『演劇vs.映画』(岩波書店、2012年)で同監督は、演劇作家・岡田和規氏との対談において、「平田(オリザ)さんは徹底的にカメラを無視するんですが、それって実は意識しているってことですよね。僕は一体何を映しているのか、この人たちはどこまでが“素”なのか、“演技”なのか、ずっと疑問に思っていました。ただ、よく考えてみると、僕たちも普段そうじゃないかなって」などと述べています(P.202)。
(注10)映画の最初と最後に映し出されるブルータスの自死の場面は、刑務所内の舞台で演じられましたが、ブルータス役の迫真の演技は素晴らしいものがありました(なんだか、『ブリューゲルの動く絵』についてのエントリの「注3」で触れたブリューゲル作『サウルの自殺』を思い出しました)。
★★★★☆
象のロケット:塀の中のジュリアス・シーザー
(1)1月に『もう一人のシェイクスピア』を見ており、また演劇関係のドキュメンタリー作品『演劇1、演劇2』を見たばかりでもあり、この映画に興味を惹かれました。
映画の舞台は、ローマの郊外にあるレビッビア刑務所。

同刑務所では囚人による演劇実習が毎年行われ、舞台で上演される際には一般人にも公開されますが、その年はシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』(「ブルータス、おまえもか?」の台詞で有名です)をやることになります(注1)。
俳優の選定に当たりオーディションが行われ(注2)、刑務所の重警備棟に入っている囚人たちが名乗り出ます。
ブルータス役、シーザー役、アントニー役、キャシアス役などが次々に選ばれ、早速稽古に入りますが、さあ、シェイクスピアの戯曲は上手く演じることが出来るのでしょうか、……?
日本だったらこんなことは絶対にあり得ないと思えるところ、本作では、実際の服役囚が画面に素の顔をさらして演じているのですから驚きです(なかには、稽古に熱心な余り、自分と役柄との見境がつかなくなってくる囚人がいたりします)。
それも、皆よく台詞を咀嚼し情熱をこめて演じており、映画全体として戯曲の大体が分かるように大層上手く編集げられてもいます(76分という短さも好ましく思いました)。
(2)予告編などで、本作は本物の囚人によって演じられるとされていても、「本物の囚人」らしくプロの俳優が演じているに違いないと思っていました。
でも、映画のラストに、出演する俳優の犯罪歴までもがはっきりと映し出されると、もしかしたら本当に「本物の囚人」が演じているのではないかと思わざるを得なくなります(注3)。
仮にそうだとすれば、『演劇1、演劇2』と同じように(注4)、稽古と上演の様子が描かれているドキュメンタリー作品ということになります。
でも、映画の途中で、面会から戻ったアントニー役が落ち込んでいる姿が映し出されますが、如何にも“演技してます”といった感じが漂っていますから(注5)、なかなかそうとも言えないのではないかという気もしてしまいます。
それに、舞台が修理中ということで使えないため、刑務所内のあちこちで稽古が行われますが、演出家による駄目出し(注6)なども行われませんし、稽古の場所がむしろ舞台よりもずっと適している感じもするのです。

そこで、仕方ありませんから、劇場用パンフレットに頼ることになります。
すると、例えばこんなことが分かります。
・脚本が作成されている(その際には、シェイクスピアの戯曲の再構成・再構築が行われている)。
・ブルータス役は、2006年に出所しており、その後俳優に転身し、様々な映画に出演している。

・演出を担当した舞台監督のファビオは外部の者で、さらにキャシアス役が演出には協力している(注7)。
要すれば、予め作成された脚本にのっとって、刑務所内の囚人と外部の俳優が一緒になって、最初から最後まで演技をしたということのようです。
であれば、本作は劇映画であって、ドキュメンタリー作品とは言えなくなります(注8)。
尤も、ドキュメンタリー作品とされる『演劇1、演劇2』であっても、まるで平田オリザ氏らの“素”の顔が映し出されているように見えながらも、けっしてそうではなく“演じて”いるようでもあり(注9)、なかなか劇映画とドキュメンタリー作品との線引きは難しいようです。
さらに考えると、本作では、二重の意味で“リアル”が問われているのではないかと思いました。
一つ目は、今申し上げたように、本作がドキュメンタリー作品なのか劇映画(フィクション)なのかという点ですが、二つ目は、本作で描き出されている『ジュリアス・シーザー』に感動するかどうか、という点です。
すなわち、第一点目に関しては、“素”か“演技”かというところで“リアル”について検討できるでしょうが、第二点目については、演じられた戯曲について“リアル”さを感じるかどうか、ということではないかと思われます。
ただ、劇映画とドキュメンタリー作品との線引きが難しいとなると、より重要なのは、第二点目ということになるでしょう。
その場合、“リアル”とは何かということになるでしょうが、とりあえずここでは、観客に感動をもたらすヴィヴィッドなリアリティとでも言っておきます。
本作の場合、台詞が英語からイタリア語に置き換えられ、どんな感じで観客に受け取られるのかはわかりませんが、俳優が喋りやすいように様々な方言混じりの台詞となっているようです。
また、シーザーの暗殺場面とか、ブルータスやアントニーの演説場面とかが、舞台ではなく石の壁で囲まれた刑務所内となっていることはことのほか臨場感をもたらします(注10)。
といったようなことから、クマネズミは本作の『ジュリアス・シーザー』に“リアル”を覚えました。
(3)渡まち子氏は、「監督のパオロとヴィットリオのタヴィアーニ兄弟は、共に80歳を越えるが、本物の刑務所や囚人を使った演劇を映画に収める実験精神や、刑務所内をモノクロで、本番の劇をカラーで描き分ける美的センスなど、感覚はすこぶる若々しい。日本では決して実現しないだろう映画作りで、アートに最大限の敬意をはらうイタリアらしい映画だ」として75点を付けています。
(注1)シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』については、この記事が大変参考になります。
なお、同戯曲には、シーザーやブルータスの妻が登場しますが、そのウエイトが少ないため、男性の囚人による上演に適していると言えるのかもしれません。
(注2)オーディションでは、国境において名前、生年月日、出生地等を申告する際に、悲しみと怒りの2つを表現する、という課題を囚人に課します。
(注3)さらには、映画の中では、ブルータス役が「台詞が覚えきれない、これで観客に上手く伝えられるのか」などと素のようにしゃべったりしますし。
(注4)同作品では、平田オリザ氏の作・演出による『火宅と修羅』や『ヤルタ会談』などといった戯曲について、その稽古風景と上演時の様子がスクリーンに描き出されます。
(注5)他にも、シーザー役とキャシアス役が、稽古の最中に、素に戻ったかの如く喧嘩をし始めたりしますが、その写し方を見ると劇映画風の感じを受けてしまいます。
(注6)何も、『演劇1、演劇2』に見られる平田オリザ氏の精緻極まる「駄目出し」をここに求めるわけではありませんが!
(注7)と言っても、全体の演出は、この映画を制作(監督・脚本)したパオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ兄弟によっていて、ファビオやキャシアス役は演出家及び演出家補の役を演じたようですが(ファビオは、俳優に対して指示を出したりしますが、それも演技なのでしょう!)。
(注8)従って、本作の最初と最後に、刑務所内の劇場に入ってきたり退出したりする一般観客の姿が映し出されますが、それは演出されたものであり、さらには、舞台の模様がカラーで映し出されますが(それ以外はモノクロ)、それもその場面だけの限定的な演技なのではと思われるところです。
劇場用パンフレットによれば、舞台監督のファビオは、『ジュリアス・シーザー』のオリジナルを刑務所内の舞台で上演すべく、レビッビア刑務所に戻ったとのことです。
(注9)『演劇1、演劇2』を制作した植田和弘監督が書いた『演劇vs.映画』(岩波書店、2012年)で同監督は、演劇作家・岡田和規氏との対談において、「平田(オリザ)さんは徹底的にカメラを無視するんですが、それって実は意識しているってことですよね。僕は一体何を映しているのか、この人たちはどこまでが“素”なのか、“演技”なのか、ずっと疑問に思っていました。ただ、よく考えてみると、僕たちも普段そうじゃないかなって」などと述べています(P.202)。
(注10)映画の最初と最後に映し出されるブルータスの自死の場面は、刑務所内の舞台で演じられましたが、ブルータス役の迫真の演技は素晴らしいものがありました(なんだか、『ブリューゲルの動く絵』についてのエントリの「注3」で触れたブリューゲル作『サウルの自殺』を思い出しました)。
★★★★☆
象のロケット:塀の中のジュリアス・シーザー