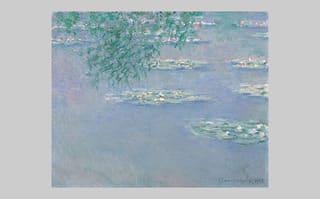『50歳の恋愛白書』を日比谷のみゆき座で見てきました。
時間が空いたので、アラフィフの恋愛模様を描いたお気楽な映画でも見ようか、ということで足を運んだところ、邦題から思い描いていたストーリー(キアヌ・リーヴスを中心とする甘いラブストーリー)とは大違いで、実にシリアスな映画となっています。
(1)原題は「The Private Lives of Pippa Lee」であって、まさにこのタイトル通りの内容になっているのです。
評論家の服部弘一郎氏がいうように、邦題の方が「「ピッパ・リーの私生活」よりは観客にアピールすることは間違いなさそう」です。とはいえ、いくらなんでもあまりにかけ離れているといわざるを得ません〔いったいアメリカでは原題で観客を呼べるのでしょうか?〕。
最後までこの邦題のことが気にかかって、あまり映画に入り込めませんでした。
ただ、ほかにも問題点はあると思います。
この映画では、原題の「ピッパ・リーの私生活」にしたがって、小さい頃、若い時、そして50歳の今の生活状況が映し出されます。ですが、それぞれが別々の物語となっていて、一人の女性像にうまくまとまらない感じがしてしまいます。
特に、ブレイク・ライヴリーが演じる若い時分のピッパ・リーは、麻薬とセックスに溺れる大層荒んだ生活を営み、その母親の隠れた生活を見せる小さい時分とはなんとか接続していると思われるものの、ロビン・ライト・ベンが演じる落ち着いた50歳の美貌の女性とは、あまりにも落差がありすぎるのです。
また、若いピッパ・リーは、30歳年上の小説家と結婚し、それまでの荒廃した生活から足を洗うようになります。ただ、その際に小説家の元妻は派手な事件を引き起こします。元妻がそうするのもわからないではないところ、それが余りに唐突であり、逆にそうであれば、現場にいたピッパ・リーは、簡単にはその衝撃から逃れられないと思われるにもかかわらず、のちに夫の不倫の現場を見つけたくらいで立ち直ってしまうのは、なんだかご都合主義だなと思いました。
さらに、ピッパ・リーの小さい時分の母親との関係を強調するためでしょうか、自分の娘との関係もうまくいっていないように映画では描かれています。ですがこの関係も、ごく些細なことで正常に戻ってしまいます。だったら、わざわざ反抗的な娘に仕立て上げずともよかったのではないか、この点もまたご都合主義といわれても仕方がないのではないか、と思ってしまいます。
50歳になったばかりの主人公のピッパは、夫に従って、現役を引退した高齢者が多く暮らすコミュニティに引っ越すことになります。目につく人たちはみな養老院にいるような人たちばかりですから、隣の友人の息子のクリス(キアヌ・リーヴス)に関心を持つようになるのも当然なのかもしれません。
そこら辺りはこの映画ではじっくりと描かれていて、十分説得力があるように思いました。
ただ、ラストは、ピッパとクリスが新しい生活を求めて車で旅立つ場面となるものの、移動の最中は新しい生活のことで頭が一杯になるにせよ、新天地に落ち着いて日常生活に入った途端に、これまでと大差ない退屈な日々の繰り返しになるのは目に見えているのではないでしょうか?
(2) ところで、この映画では、主人公と深い仲となるキアヌ・リーヴスの胸には聖人の刺青(タトゥー)が大きく施されています。そこで、刺青について若干触れてみようと思いましたが、長くなりそうなので、明日の記事といたします。
(3)総じて評論家の評価はまずまずのようです。
服部弘一郎氏は、「映画自体は「恋愛白書」と言うようなロマンチックなものではない。50歳前後の人たちが経てきた人生の歩みをたどりながら、今ここからどうやって生きていくかを問いかける物語になっている」として70点を、
渡まち子氏は、「センスのない邦題」ながらも、「豪華キャストの割には渋い人間ドラマの本作、いい意味で期待はずれの内容だった」として60点を、
福本次郎氏は、「妻と母の役割をきちんとこなし、それなりに豊かな暮らしを送る50歳の主婦がふとした瞬間に感じる空白」、「愛や幸せなど幻想にすぎず、本心に嘘をついている、そんな家族の虚構に気付いてしまった彼女の心理がリアルに再現される」として50点を、
それぞれつけています。
ただ、前田有一氏は、「なんと女性とは不自由な職業であろう」などと高見の見物的な位置に立って40点しか付けていません。ですが、「女性は常に受身であり、他者に引っ張られることでしか生き方を変えられないという残酷な事実」は、女性という「職業」に付着するものというよりも、むしろ男性との関係の中で生み出されるものと考えられるのではないでしょうか?
★★★☆☆
象のロケット:50歳の恋愛白書
時間が空いたので、アラフィフの恋愛模様を描いたお気楽な映画でも見ようか、ということで足を運んだところ、邦題から思い描いていたストーリー(キアヌ・リーヴスを中心とする甘いラブストーリー)とは大違いで、実にシリアスな映画となっています。
(1)原題は「The Private Lives of Pippa Lee」であって、まさにこのタイトル通りの内容になっているのです。
評論家の服部弘一郎氏がいうように、邦題の方が「「ピッパ・リーの私生活」よりは観客にアピールすることは間違いなさそう」です。とはいえ、いくらなんでもあまりにかけ離れているといわざるを得ません〔いったいアメリカでは原題で観客を呼べるのでしょうか?〕。
最後までこの邦題のことが気にかかって、あまり映画に入り込めませんでした。
ただ、ほかにも問題点はあると思います。
この映画では、原題の「ピッパ・リーの私生活」にしたがって、小さい頃、若い時、そして50歳の今の生活状況が映し出されます。ですが、それぞれが別々の物語となっていて、一人の女性像にうまくまとまらない感じがしてしまいます。
特に、ブレイク・ライヴリーが演じる若い時分のピッパ・リーは、麻薬とセックスに溺れる大層荒んだ生活を営み、その母親の隠れた生活を見せる小さい時分とはなんとか接続していると思われるものの、ロビン・ライト・ベンが演じる落ち着いた50歳の美貌の女性とは、あまりにも落差がありすぎるのです。
また、若いピッパ・リーは、30歳年上の小説家と結婚し、それまでの荒廃した生活から足を洗うようになります。ただ、その際に小説家の元妻は派手な事件を引き起こします。元妻がそうするのもわからないではないところ、それが余りに唐突であり、逆にそうであれば、現場にいたピッパ・リーは、簡単にはその衝撃から逃れられないと思われるにもかかわらず、のちに夫の不倫の現場を見つけたくらいで立ち直ってしまうのは、なんだかご都合主義だなと思いました。
さらに、ピッパ・リーの小さい時分の母親との関係を強調するためでしょうか、自分の娘との関係もうまくいっていないように映画では描かれています。ですがこの関係も、ごく些細なことで正常に戻ってしまいます。だったら、わざわざ反抗的な娘に仕立て上げずともよかったのではないか、この点もまたご都合主義といわれても仕方がないのではないか、と思ってしまいます。
50歳になったばかりの主人公のピッパは、夫に従って、現役を引退した高齢者が多く暮らすコミュニティに引っ越すことになります。目につく人たちはみな養老院にいるような人たちばかりですから、隣の友人の息子のクリス(キアヌ・リーヴス)に関心を持つようになるのも当然なのかもしれません。
そこら辺りはこの映画ではじっくりと描かれていて、十分説得力があるように思いました。
ただ、ラストは、ピッパとクリスが新しい生活を求めて車で旅立つ場面となるものの、移動の最中は新しい生活のことで頭が一杯になるにせよ、新天地に落ち着いて日常生活に入った途端に、これまでと大差ない退屈な日々の繰り返しになるのは目に見えているのではないでしょうか?
(2) ところで、この映画では、主人公と深い仲となるキアヌ・リーヴスの胸には聖人の刺青(タトゥー)が大きく施されています。そこで、刺青について若干触れてみようと思いましたが、長くなりそうなので、明日の記事といたします。
(3)総じて評論家の評価はまずまずのようです。
服部弘一郎氏は、「映画自体は「恋愛白書」と言うようなロマンチックなものではない。50歳前後の人たちが経てきた人生の歩みをたどりながら、今ここからどうやって生きていくかを問いかける物語になっている」として70点を、
渡まち子氏は、「センスのない邦題」ながらも、「豪華キャストの割には渋い人間ドラマの本作、いい意味で期待はずれの内容だった」として60点を、
福本次郎氏は、「妻と母の役割をきちんとこなし、それなりに豊かな暮らしを送る50歳の主婦がふとした瞬間に感じる空白」、「愛や幸せなど幻想にすぎず、本心に嘘をついている、そんな家族の虚構に気付いてしまった彼女の心理がリアルに再現される」として50点を、
それぞれつけています。
ただ、前田有一氏は、「なんと女性とは不自由な職業であろう」などと高見の見物的な位置に立って40点しか付けていません。ですが、「女性は常に受身であり、他者に引っ張られることでしか生き方を変えられないという残酷な事実」は、女性という「職業」に付着するものというよりも、むしろ男性との関係の中で生み出されるものと考えられるのではないでしょうか?
★★★☆☆
象のロケット:50歳の恋愛白書