
小5から小6になるころ小学館文庫を皮切りに漫画の文庫化ブーム(第1次、1976~)が起り、私が最初に手に取った『ねじ式』はそのまま一生ものに。小6の夏休み、親戚の家に泊まったところ当時高3の従姉がたまたま貸本屋から当時再発直前で幻の名作の扱いになっていた『火の鳥・復活編』を借りており、一晩読み耽って人生が変った。未来社会を扱うSFで、狂気の話でもあり、今も手塚のベストは復活編です。この親戚の長男は私と同い年の、例の消防団のネトウヨの。年の離れた2人の姉、私にとって従姉である2人の子ども部屋には少女漫画雑誌がたくさんあって、75年に短期連載となった萩尾望都「11人いる!」も目にした記憶があり、翌年の火の鳥の件も萩尾望都の師匠筋ということからかも。従姉は小学館派(コミック)だったんですね。少女漫画誌の週刊化では講談社(フレンド)と集英社(マーガレット)が60年代に先行し、当時はいかにも少女マンガという陳腐な作風に占められ軽んじられていたのに対し、70年代に萩尾望都・竹宮惠子・山岸凉子・大島弓子らが一挙に少女漫画の枠を広げ、男の漫画読みでもそれらを読んでいなければお話にならないというほど漫画界の空気を一変させたのだった。
76年に朝日ソノラマがマンガ少年という月刊誌を創刊、呼び物は火の鳥の再開で、翌77年には竹宮惠子も本格SF『地球(テラ)へ』を連載、にもかかわらずこの雑誌は週刊月刊が乱立する各社の激しい競争の中で埋没し、男女どちらにも読んでほしいという方針で81年にDUO(デュオ)と改称するも浮上することなく消えてしまう。この頃には後発の白泉社がLaLaと花とゆめの2誌により主流の漫画出版社して定着したが、各出版社のやり方が「雑誌で作家と読者を囲い込んで育て、単行本とアニメ化で儲ける」という一辺倒であるため、あらかじめ読者層を想定して置きにいくような作風の記号化陳腐化とジャンルの細分化が果てしなく進み、そうした弊害の究極として90年代にキャプテン翼などのホモパロディ、いわゆる「やおい」「腐女子」が現れるに至って、少女漫画が先行して漫画文化を刷新する動きは完全についえ、少子化も伴って少女漫画自体の存続さえ危ぶまれる事態に。

人はよりよい生活を目指して再び闇雲に働き始めた。だがしかし〝よりよい生活の為に〟という理由は、その個人が必要とする理由としては〝働かなけれぱ食っていけない〟という理由よりも切迫感に乏しかった。(中略)いまだかつて一度も、自己の充足感を得る為に働いた経験のない人々は、ここで初めて〝家庭〟という概念を必要とし、〝よりよい生活〟というのは自分にとってのよりよい生活なのではなく、自分とは別個に存在する〝家族〟がよりよい生活をおくれるようにしてやることなのだと了解しなけれぱならなかった。〝家族〟とそれによって形成される〝家庭〟とが、自己の幻想の内にではなく、自分とは別個の独立した存在であることが確信されなければならなくなったのである。
だから、父であり夫である人は、妻と子の為に働いた、母であり妻である人は、夫と子の為にこそ働いた。そして、ここに初めて、全き(まったき)家庭を形成する為の全き家族の一員として、子供というものの存在が初めて大きくクローズアップされることになったのである。
子供は、「その子は誰の子か?」という観点から問題にされる時のみ相対的なものではあるが、大人というものに対置される時、子供はどこまでいっても絶対的に〝子供〟である。だから人は、子を持つことによって、そこから逆算して〝親〟という絶対的な関係を持つことが可能となり、子供という〝絶対〟をその中核に据えることによって家庭の独立性を可能とした。それにより初めて、子は子として夢を見ること が許されるようになったのである。
子供であることを許された子供とは何か? それは、徒らに半睡半醒のままでいることを許されたものである。子供は親に庇護されているものであるから、現実に直面する必要がない。現実に直面する必要のない子供は、半睡状態のまま現実を眺めていても一向に差し支えがない。 ─橋本治/花咲く乙女たちのキンピラゴボウ/河出文庫1984・原著1979
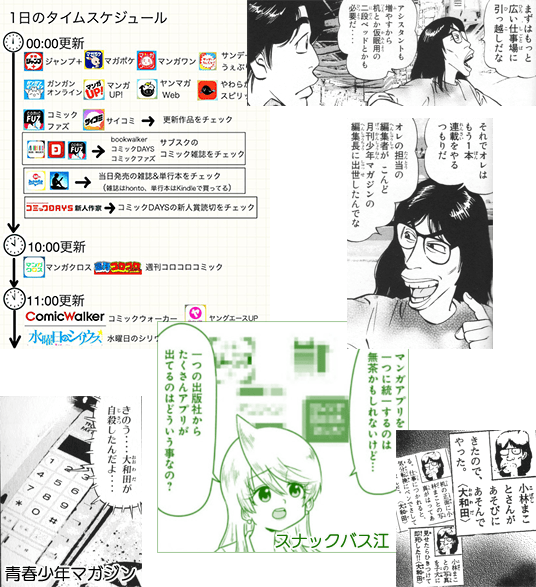
1976年って凄い年だったのか。誰も教えてくれないことを真剣に考えて長文にまとめる若い橋本治にも感服する。私は77年に中学に上がってから「11人いる!」『風と木の詩』『エースをねらえ!』『エリート狂走曲』など少女漫画にのめり込んでゆくが、よりフェミニンな要素の強い大島弓子については畏怖を覚えながらも理解が及ばず、成人してから86年に刊行された選集であらためて知り、萩尾望都と双璧の巨頭と認識。
ところが、これまで名前を挙げてきたような才能は、80年代の後半を迎えるころに軒並み作風が変り、自己模倣的に薄く陳腐化してしまう。萩尾望都は抜きんでた評価を得てはいたが、絵柄の硬直化(ギョロ目で表情のこわばったイケメン)が個人的にどうにも…。これは橋本治に言わせれば「女の都合を考えてくれる男は女の都合を聞こうとはしない」日本のジェンダー事情が、彼女らのファン層の主力が大人になるに連れ、どのみち男尊女卑は動かし難く、会社勤めや主婦の現実と折り合えるよう、せめて漫画で(社会とコミットしない)夢の続きを見せてほしいと求めさせるからなのでは。特に萩尾のファンは高学歴が多いと推定され、四大短大美大かかわらず高学歴女の保身の論理は、受験をはじめ競争から逃避し孤独を好む私の生き方を全否定するので、それらファンを尊重して作風をシフトさせた萩尾望都を私の方でも受け付けなくなったのでしょう。
火の鳥復活編で私の人生を変えた従姉はその後も吉田秋生『バナナフィッシュ』、よしながふみ『大奥』などを教えてくれたが2009年に急死。シブがき隊の本木が好きで、テレビを見ながら女タレントにダメ出しすることなどから彼女の一人息子は極度の面食いに育ってしまった。黄金時代の少女漫画は今見ても物語の完成度が高いと思うが、お手本であるロマン主義の本場ヨーロッパではあまり評価されていないようだ。というのも、大きな目にお星さまキラキラ、背景にお花が咲き乱れ、脚の長い白人的な美人とイケメンしか出てこない、転校先にたまたま幼馴染がいてその兄とだけで物語が展開してしまったりするご都合主義(大島弓子・バナナブレッドのプディング)。これはやはり女を社会から切り離し、恋愛結婚イデオロギーを植え付けて労働者よりも消費者としての自意識を持たせることで、タテの支配をヨコの監視が補完する軍国主義転じてエコノミックアニマル、異例の成功を収めた昭和期と、同じ要因から異例の速さで衰退する現状、昭和に咲いた少女漫画あるいはSFという徒花が、推し・ガチャ・異世界転生・ネトウヨなどなど現実逃避の実を結んだと申せましょう。

























