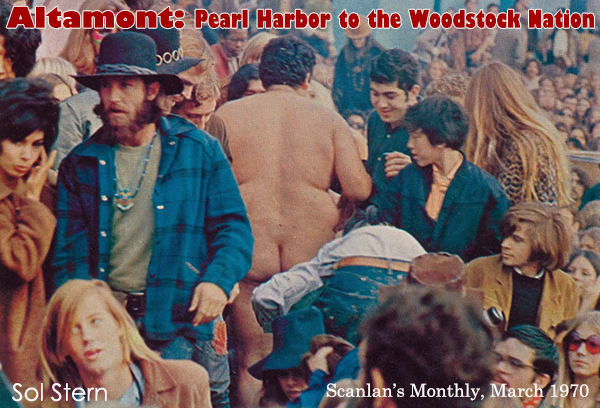

オルタモントは、たんに夢がこわれたというだけでなく、ヴィジョンの腐食作用が最高度に達したことを表わすものであった。マリファナを吸い、LSDを飲み、ハダカになり、公衆の面前で性交し、強烈なパワーをもつ音楽のまわりに一種のコミュニティを見出している若者たちが、おびただしい数にのぼっているということに、マスコミが気づくよりも、ずっと前から、すでに腐食のプロセスは始まっていた。こうした若者たちの現象を『タイム』誌がリポートしだしたころには、コミュニティをつくる方向よりもたんなる多数化の方向を取らせる姿勢をもっていたウッドストック生活様式の中に、す でに確かな変化がおこっていたのである。
この変化は、ある部分、群衆の数の問題にすぎない点ももっている。ウッドストックのわずか3年前の1967年、ゴールデン・ゲイト・パークに2万人の人が集まったが、この最初のビー・インは記念碑的な出来ごとと考えられたのだった。そしてウッドストックの4か月後、ローリング・ストーンズは、指をパチンと鳴らして合図するだけで、50万人近くの人びとを、人里離れた不便な場所に集めてしまった。
最初のころのビー・インや大規模なロック・コンサートは、とくにベイ・エリアでは、聴衆はバンドと同じくらい重要視されており、観察者たちは、踊ったり聞いたりしている連中のことも、演奏者についてと同じくらいのスペースをつかって、書いた。ステージと客席の間には、まったく距離を感じさせなかった。バンドは、政治演説や詩の朗読や踊りやポスター作りと同じように、大きなショウの一部分でしかなかった。
こうした初期の経験からひろがって行った夢は、後の“カウンター・カルチャー”(反体制文化)という、盛んに乱用されたポップ・ソシオロジー的概念ではなくて、音楽とマリファナと共同生活と性の解放を通して、現存の社会機構をぶち壊すような、有機的コミュニティへのヴィジョンであった。カンサス・シティとかニューョークなどで育った若者たちにとって、この時期のサンフランシスコで起っていた出来ごとは、政治や文化の既存体制をくつがえすものであるだけでなく、社会変革の政治主義的な方法論にたいする有力な代案でもあった。そこには、おそらく“喜びのポリティックス”とでも呼べるような、一種の戦略があった。若者たちはいまや、マリファナを吸い、共同生活を送り、ディガーズで無料の食糧を与え、マイム・トループを見物し、グレートフル・デッドやジェファスン・エアプレインのようなバンドを日曜日の公園でロハで聞きながら、彼ら自身を反逆者あるいは革命家と考えることができた。
サンフランシスコ港の向う側、バークレーの強硬派政治的ラディカルたちは、そういった考え方を、真の実践をないがしろにした見当はずれのものとして片づけてしまっただろうが、彼らの中でも最もセンシティヴな少数派は、それがユートピア的かつ非組織的ではあるにしても筋の通ったヴィジョンであること、そのようなヴィジョンが、ハイト・アシュベリーのヘッド・ショップや、ディガーズの無料ストアーや、パイン・ストリートのグレートフル・デッドの家から生まれてきつつあることを、知っていた。彼らは、このようなヴィジョンに、そのうちなにか名前をつけなければならなくなることに気づいていた。当時はコチコチの政治小僧だったジェリー・ルビンが、1967年の、ゴールデン・ゲイト・パークでの大ヒューマン・ビー・インで、政治主義的なストレートな発言をせず、「ぼくは旧世界から新世界へやってきた」と、まるでVDCのリーダーでなくてコロンブスででもあるかのような言葉をくり返していたのは、賢明だった。

ウッドストックやオルタモントのころの、発達しつくしたロック・バンドにくらべて、初期のバンドはかなり違っていた。ロック・ジャーナリスト、マイケル・ライドンは、かつての非暴力と愛と麻薬のヴィジョンの本質を、次のように定義づけている。
《そのコミュニティの中では、みんながロック・スターのようにみえ、そしてロック・スターは一般の人たちのようにみえ始めた。そこには神さまはなかったのだ》
その後ロックは急速にひろがり、商業的に成功し、ショウ・ビジネスとしての全盛期を迎え、とうとうロックはひとつの産業になった。ロック・スターたちの写真は郊外の歯医者の待合室に置かれる雑誌の表紙を飾り、エド・サリバン・ショウに出、運転手やPR係を雇うほどになった。変化は強烈かつ急速だった。ロック・バンドや個々のプレイヤーたちは、彼らを生み出すきっかけを作ってくれたコミュニティや文化革命をしのぐほど、大きな存在となった。ステージと客席の間の距離はますます広がり、ステージから送り出される音楽がすべてであって、群衆からステージにむけられるエネルギーはごく小さなものになってしまった。
バークレーの初期のころ、自分たちを“政治的なバンド”と、自己満足的に呼んでいたカントリー・ジョーとフィッシュを例にあげよう。リード・ギタリストのバリー・メルトンはサンフランシスコ・マイム・トループの急進的人形劇場ゲリラの一員で、ロバート・シアーを国会に送るキャンペーンにたずさわっていた。このバンドはベトナム・デイ・コミッティの非公認メンバーだった。彼らが作った「フィール・ライク・フィキシン・トゥ・ダイ・ラグ」 は、2年間のあいだ、反戦運動のナショナル・アンセムだった。それなのに、フィッシュが大きくなった──たくさんの公演をし、たくさんのレコードを出し、たくさんの金を得るようになった──後は、政治的な集会には出てくれなくなってしまったのである。
いくつかのロック・グループ、たとえばグレートフル・デッドは、このような傾向に抵抗した。彼らはコミューン的な生き方をつづけ、聴衆との特別な結びつきを保ってきた。(ストーンズのコンサートをゴールデン・ゲイト・パークで完全なコミュニティ方式で行なおうと努力したのはグレートフル・デッドであり、彼らはまた、かつてのモントレー・ポップ・フェスティバルをも無料にし、もしくは収益をディガーズに寄付しようと主張した)。彼らは、彼らの公演を自分自身の手で行ない、業者を間に入れなかった。
グレートフル・デッドとジェファスン・エアプレインは、ビル・グラハムのフィルモアに対抗し、サンフランシスコのカルーセル・ボールルームを、自分たちの共同運営によるコミュニティ的ダンス・ホールにしようと試みた。デッドは、よき夢想家たちではあっても、よき企業者たちではなかったので、カルーセルは、運営のまずさ、能率の悪さのために失敗してしまった。カルーセルがつぶれたあと、ビル・グラハムが乗りこんできて、フィルモア・ウェストと名をかえ、彼の拠点にした。“ザ・コミュニティ”のうわさは、きびしい損益計算簿の騒音の中に沈没してしまったのである。

ロック企業家としてのビル・グラハムの成功は、ウッドストックからオルタモントのような事件を生み出した、ロック界の根本的変化の徴候であった。グラハムは、マイム・トループに純益を寄付するために、サンフランシスコで最初の大がかりなロック・ダンス会を組織した。ロックの丘に金鉱を発見したグラハムは、マイム・トループをやめ、ロック・コンサートを定期的に行ない始めた。鋭い組織感覚をもった頭の切れる、タフなビジネスマンであるグラハムは、民衆のための音楽を組織するには、コミューンの倫理よりもビジネスの倫理のほうがより効果的な方法だということを、実地に証明してみせた。
同じような方向への発展は、ロックの出版物にもみられる。はじめての良質なロック・マガジンである『クローダディ』(ロンドン郊外リッチモンドにあるクラブの名をとったもの。ローリング・ストーンズは、このクラブで初めて演奏した)は、1966年に、若くてセンシティヴな、スワースモア・カレッジ中退生、ポール・ウィリアムズによって創刊された。『クローダディ』は、ときにはキラリと光り、しばしば常軌を逸した月刊誌で、2万5000部の発行部数に達したが、運営の仕方が悪く、ときどき発行されなかったり、レコード会社の広告など追っかけなかったりしていた。ウィリアムズは、スターたちのゴシップよりも、ロックやそれを聞く人たちの体験そのものに関心をもっており、しばしば田舎に行ってコミューンの生活を送ったり、彼自身の著作に没頭したりした。
『クローダディ』は『ローリング・ストーン』に、急速に地位を奪われた。『クローダディ』がダメになると、『ローリング・ストーン』が頂点に立った。グラハムの企業と同様、それは、最初は、ロック界の商業化の進展から自然に出てきた結果であり、同時にまたその商業化を促進するものでもあった。それはまもなく“業界紙”になってしまい、国じゅうのロック・ファンたちにとって、インフォーメイションやゴシップの主要な供給源となった。同紙は、スター・システムやある種のロック帝国主義のあと押しをした。自意識的なカウンター・コミュニティの本来の考え方からすれば、『ローリング・ストーン』はひとつの悲劇であった。
2年前の夏、ジェリー・ルビンがシカゴでィッピーのデモを組織し、ロック・グループたちにも参加を呼びかけたとき、『ローリング・ストーン』の若くて頭のいい編集長ヤン・ウェナーは、ロック・グループが政治集会などで演奏してくれると考えるなんてジュリー・ルビンは厚かましい奴だと、同紙の社説の中で非難した。ロック・ミュージックとより大きな革命との関係についてのウェナーの社説は、ロック音楽界の反政治性それ自体の中にある種の政治的選択が表明されているという、少なくともオルタモント以前において、一部の人びとが真面目に信じていた意見を、完全に代弁したものである。
《ロックンロールは若者たちの巨大な、しかし形のない力というものを、構築する唯一の道であり、それが明確な形をとりうる唯一の道である。ロックンロールの形式と内容が、何百万人という若者たちのイマジネーションと経済力と知的関心をとらえた。
それは、まったく驚くべき力をもち、可能性にみちている。それは、独自のユニークな道徳性をもっている。物識りで教養豊かな人が、それを観察し、定義づけようとすればするほど困難なものであり、"なぜ"という疑問詞で尋ねつづけたとしてもけっして理解できるものではないけれども、それにもかかわらず、それは存在し、じょじょに動的な形をそなえてくる》
これは、『ローリング・ストーン』が、ロックだけが革命なのであるという理論をおし進め、革命につながる多くの試みや、より広い政治的視野を無視し去ろうとするときに、今もなお用いている、一種のオブスキュランティズム 〔大衆を無知なままにさせておこうという考え方〕の言いまわしである。

ロックが産業として発展し、大きく広がってくると、新しくロックの世界に入ってきた人たちは、ロックを共有する人というより、ただたんなる消費者の立場におかれる。ロックがその人たちにひき起こした行動といえば、何度も行なわれる大きなコンサートを高い金を払って聞きにいくことだけなのだ。
初期のロック反体制文化の夢想家たちは、ロック人口の大半がハィト・アシュベリー、ゴールデン・ゲイト・パーク、フィルモアなどの中に限定されていたころ、ロックの世界の状況をコントロールすることができた。しかし、あらゆる独創的急進的な生活様式をも商品化、画一化してしまわずにはおかないアメリカの伝統が、ロックの世界を巨大なものにふくれ上がらせてしまったとき、夢想家たちには手のほどこしようもなかった。文化救済の名目を保ちながら、ロック文化はひとつのビジネスになってしまい、ウェナーやグラハムのような実利家たちが、新しい波を表面だけのさざ波にしてしまった。彼らは、今もなお、ロックこそ新しい反体制文化の中心だと、声を大にして唱えている。しかし、実際の行動をみてみると、お客さんの開拓を第一に考える彼らのチャッカリしたやり方は、荒廃した現実社会を社会的政治的に変革して行くのにどうしても必要なコミューン的体験から、ロックをますます遠く離して行くだけだ。
結局、ウッドストックやオルタモントのような大規模なコンサートだけでなく、本来ダンス・ホールだったフィルモアでさえ、人びとはバンドの前で踊ることをやめてしまった。ダンス会はコンサートと化したのだ。最近ニューョークのロック・パーティで、ジャニス・ジョプリンは、若者たちに、前に出てきて踊るように繰り返して誘わなければならなかった。
それと同様に、だが、とてつもなく大きなスケールで、オルタモントの群衆は、自分たちから何の音楽も発散しなかった。音楽はただステージから一方的に与えられるだけだった。そうした受動性と消極性の中で、われわれは、ステージから与えられるものは何でも有難く頂戴しなければならなかった。
ウェナー「評論家やら学生やら、多くの人たちが、あなたの音楽や、あなたが歌詞で言ってることを聞いて、すごく感動していますね」
ディラン「そうかしら?」
ウェナー「本当ですよ。あなたの歌が彼らの生活に特別な結びつきをもっていると感じています。つまり、人びとがどんなふうにあなたとかかわりをもっているか、それをあなたは気づくべきじゃないでしょうか」
ディラン「わかんないな。説明してくださいよ」
ウェナー「ごく簡単にいってしまうなら、ぼくのよく知ってるあなたのファンたちが期待してるのは、──つまりファンたちがほしがってるのは、あなたが答を与えてくれるってことだと思うんです」
ディラン「何の答を?」 (『ローリング・ストーン』1969年11月号、インタビューから)

カウンター・コミュニティという言い方は、説得力があると同時に漠然としている。この言葉は、人びとに、オートパイに乗った無法者たちまでも共同体的カウンター・コミュニティの一部であるかのように信じさせさえした。彼らは人びとを轢いて傷つけてきた長い歴史をもっているというのに、彼らもロックをきき、LSDを飲んでいるというだけのことで仲間のように思っていたのだ。例えば、かつてラルフ・グリースンは、ロックのもつヴァイブレーションは「ヘルス・エン ジェルスをビー・インの迷子たちの守護者に変え、ダンス会の平和の保証人にしてしまう」ほどグルーヴィだ、と書いたことがある。
もちろんそれは2年前のことだ。オルタモント以後、独善的な非難が渦巻いている。グリースンは、コミュニティにはロックとLSDがつきものだ、エンジェルスもロックとLSDを好む、ゆえにエンジェルスもコミュニティの一員なり──という三段論法を否定した。 エンジェルスは人を殺したのである。ストーンズと、グレートフル・デッドと、もとディガースのひとりエメット・グローガンとが、エンジェルスを警備員として傭うよう手配した。したがって、理の当然のこととしてグリースンは質間する。「ミック・ジャガー、サム・カトラー、エメット・グローガン、それにグレートフル・デッドは、黒人殺害に関して罪はないのか?」
グリースンも編集の一員になっている『ローリング・ストーン』紙は、賛成する。「グリースンはオルタモントに関して、ほかのだれもあえてしなかったほど力強く、真実の質間を投げかけた」
だが、ウッドストック神話と夢との間の違いをハッキリさせなければならない。神話はそれを利用するものにとって麻薬注射の針であるにすぎず、音楽の力への度はずれな要求でしかない。夢は、かりにそれが希望と可能性のひとつでしかないにしても、真実である。そこに何か殺されねばならぬものがある。
それは、LSDや音楽やサイキデリック・バスを用い、あちこちを旅行し、力をもって人びとと敵対し、破壊的、 魔術的、陶酔的なコミュニティを太ったアメリカの尻に一瞬のあいだ実現しうる可能性を実証したヘルス・エンジェルスや、トム・ウルフの「エレクトリック・クール・エイド・アシッド・テスト」のメリー・プランクスターとケン・キージーや、そういったものの中にある。
《メリー・プランクスターズとヘルス・エンジェルスの、神聖ならざる同盟は、すばらしかった。…(でも)…エンジェルスは時限爆弾のようなものだ。でもまあ、それまではどうにかやってきた。ある日などは、エンジェルスはあたりをきれいに掃除したことさえあった。だが、彼らは、いつでも爆発して大虐殺をやらかす可能性はあった。それはアドレナリンを胸に吸いこむようなものだ。それに、本当のことをいうと、エンジェルスと本当に話合うことのできるプランクスターはきわめて少数だった》
サンフランシスコのロック・サイキデリック・シーンのうちで、ウルフが描いたもっともいきいきとした、エキサイティングな部分は、皮肉なことに、まさにマクルーハン的理論(その理論を広めたのは、ウルフ自身だった)の手をわずらわさねばならなかった。ウルフの原稿が古くさいグーテンベルグ方式で出版されたときには、彼が描写したシーンは過去のものになっていた。オルタモントに来た若者たちのほとんどは、トム・ウルフもメリー・プランクスターズも知っちゃあいなかった。

本来のカウンター・コミュニティは希望のない難破状態である。ハイト・アシュベリーは、スラムになってしまい、そこでは暴行殺傷は日常茶飯事になっている。ディガーズも去ってしまい、エメット・グローガンはエンジェルスといっしょに車で行ってしまった。ケン・キージーはオレゴン州に帰り、プランクスターもほとんど消滅した。ほかの多くの人びとは田舎に移った。残ったのは主に音楽関係者と、政治的ラディカルと、街をうろつく連中だけだ。街の片方にはフェスティ・ハル のオルガナイザーたち(バンド・マネージャーたちやもちろんビル・グラハム、ラルフ・グリースン、ヤン・ウェナーなど)、もう一方には街の人びと、政治的ラディカルやサンフランシスコ・マイム・トループたちがいた。マイム・ トループは、芸術家が社会的政治的変革に加担して何が悪いか、という考え方をもっていたころからの、数少ない生き残りのひとつである。
マイム・トループのロニー・デヴィスは、何がもっとも大切であるかということについての、答えにくい質問にぶつかった。なぜ舞台装飾に金をかけるか? 無料のフュスティ・ハルと思っていたのに、なぜ入場料をとるのか? なぜ黒人は入っていないのか? 質問は容赦なく、騒々しく、ときには破壊的でさえある。ラルフ・グリースンは、デヴィスと仲間たちに、美を破壊するだけで建設の見通しをもっていない政治狂ども、と非難の言葉を投げつけた。どうせ、彼らは大衆の代弁者ではない、とグリースンはいう。それは正しいだろう。だがグリースンやウェナー、グラハムらが代弁しているのは、大衆ではなく、ロックンロール産業のパワー・エリートたちの利益なのだ。ウェナーやグリースンたちロックに基盤をおいたカウンター・カルチャーの理論を唱える人たちが、集会や音楽の中に先天的、必然的に存在していると主張するノンポリティカルな革命の力を、まさに発揮するのに失敗したオルタモントの何十万の人たちは、代弁してくれる人をもっていなかった。
オルタモントでは、群衆は酔うこと以外に、自己を主張する方法を失い、ヘルス・エンジェルスの暴力の標的と、 ブロモーター(その中には、ストーンズ・コンサートを金もうけのために撮影し、バークレーの若者の殺害という願ってもないオマケのついた、ベストセラー間違いなしの映画を製作したカメラマンも含む)の材料にされてしまった。
オルタモントの事件にもかかわらず、ウェナーやグラハムのような操縦者、デヴィッド・クロスビーのような音楽家たちは、若者たちには音楽さえあれば十分で、政治などは不要だと、いまも主張しつづけている。「政治なんてクソクラエだ」と発言するのは簡単だし、カッコいい。その言葉はロックの世界を何か特別な、切り離されたものにする。あなたは、あなたに魔術をもたらしてくれる人たちのように、答えにくい質問を発することもないだろう。そして、そういう質間を誰もしないならば、あなたはラルフ・グリースンの次の言葉のようなナンセンスから逃れることもできるだろう。
《ビートルズはキリストよりもポピュラーであるだけでなく、SDS〔急進派の学生団体〕よりも力をもっている。ウッドストックにとじこもっていたとき、ディランは何をしていたのだろうか。 金の勘定だろうか。でも、誰も芸術家であることを放棄するわけにはいかない。ディランもビートルズも、政治を超越したところから出発した。政治家の描いた未来図などは追い越してしまい、世界の頭をかえ、マクルーハン的境地に達した。そこからこそ真の未来図が描かれ、時が来れば、彼らの予定表のとおりになるのだ。だが多分まだその時は来ていない。でもそう遠くない。かなり機は熟しつつある。今のところ、ビートルズによって実現された予定表は、レノンとョーコが24時間をベッドの中で過ごし、何千ドルかの金をアド・インに費して、『ニューヨーク・タイムズ』に「もしあなたが望めば、戦争は終るのです」と広告したことだ》
残念ながら、貧しく、非政治的で、連帯を失ったオルタモントの若者たちは、"未来図と予定表"をまだ待ちつづけている。そして待っているあいだに、彼らは彼らの旧友ヘルス・エンジェルスに踏みつけにされてしまったのである。


























