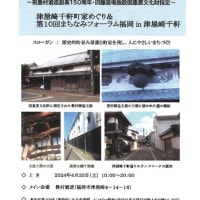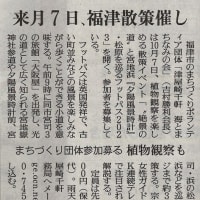写真①:津屋崎海岸に設置された朝鮮通信使と相島(向こう=福岡県新宮町)交流の石碑
=福津市津屋崎1丁目で、2009年4月5日撮影
・琢二と清の郷土史談義
『津屋崎学』
第33回:2010.05.13
朝鮮通信使と津屋崎
清 「この前、福津市津屋崎1丁目の津屋崎海水浴場の東外れば歩いとったら、『朝鮮通信使』の石碑=写真①=が駐車場の砂地に設けられとったよ。なんで、あんな石碑が、あの場所にあるとね?」
琢二 「清も、そう思うか。朝鮮通信使と相島(あいのしま)交流の案内板として、2009年3月11日に設置されとる。玄界灘に浮かぶ福岡県新宮町の相島が、朝鮮通信使との交流の島だという歴史を伝えたいのなら、相島に設置するのが当然だな。相島にではなく、なぜ津屋崎に設置するのか説明はない。設置場所も、津屋崎海水浴場の砂浜に接する駐車場の南端中央にあり、駐車場から砂浜に降りる人には障害物に思えるな」
清 「そうやね。朝鮮通信使って、江戸時代に朝鮮から日本に派遣された外交使節というぐらいの知識しかないけど、その相島での交流の石碑がなんで津屋崎にと考えても、よう分らん」
琢二 「石碑は御影石製で、縦約80㌢、横約160㌢、高さ約60㌢。『福津・慶州文化親善交流協会』(金光烈会長)が、二千七年の『朝鮮通信使四百周年』に当たり約110万円で制作、設置場所は福津市の許可を得たとされとる。碑文=写真②=には、朝鮮通信使と相島での交流について〈福間浦、津屋崎浦、勝浦からも多くの故郷の先祖たちが動員され、喜んで通信使の為に波止場の新改築、客館建築(中略)等に活躍したと伝えられています〉などと説明されている」
 ">
">
写真②:「『相島(あいのしま)』は『朝鮮通信使』の島」と書かれた碑文
=福津市津屋崎1丁目で、2010年5月10日撮影
清 「相島には、津屋崎海岸にあるような石碑はないとね?」
琢二 「平成8年9月に新宮町教育委員会が立てた『朝鮮通信使客館跡』の説明板=写真③=が、あるぞ」
 ">
">
写真③:『朝鮮通信使客館跡』の説明板
=福岡県新宮町相島で、2010年5月9日撮影
清 「へー、どんな説明文になっとうとね?」
琢二 「書き出しから引用すると、次のような説明だ。
〈江戸時代に、唯一国交を持ったのは朝鮮です。十一回にわたり、朝鮮からの使節団が、首都漢陽(かんよう)から、壱岐・対馬を経て、相島に寄港し、瀬戸内海をとおり大阪で上陸し江戸に向かいました。
最初の三回は、豊臣秀吉の二回にわたる朝鮮出兵の戦後処理のための使節で『回答兼刷還使(かいとうけんさつかんし』といわれました。その後は、徳川将軍の代替わりのお祝いなどのための使節で、『朝鮮通信使』〉といわれています〉
『回答兼刷還使』という呼び方の時期があるとは、現地に行くまで知らなかったな」
清 「叔父(おい)しゃん、いつ相島に行ったとね?」
琢二 「5月9日の日曜日たい。新宮町の新宮漁港から町営渡船に乗り、17分後に7.5㌔離れた相島漁港に着いた。釣り客が、多かったな」
清 「お土産は、ないと」
琢二 「ハハハ、相島地域産物展示販売所の食堂でウニ飯を食べたが、胃袋に収めただけだ。それより、この『朝鮮通信使客館跡』の説明板の続きには、面白い記述があったぞ。
〈外国からの使節団なので、幕府は通過経路の各藩に手厚く供応するよう命じました。黒田藩は、相島を供応の場と決め、一年ほど前からその準備にとりかかりました。
客館は毎回新築し、波止場の新修築や諸施設を建設しました。水は井戸や水溜場をつくり確保しました。食糧も天保二年の例では、豚は長崎から購入し、猪(しし)、鹿は立花山、能古島、津屋崎の渡山(わたりやま)で捕り、伊勢エビは大島から、鯛は広島から取り寄せています。黒田藩の相島での接待がいかに心をこめたものであったかがわかります〉
……と、ここに津屋崎の渡山でイノシシやシカを捕ったということが書かれとる」
清 「なるほど。面白いね」
琢二 「このことは、『津屋崎町史 通史編』にも載っているぞ。相島に一泊する『朝鮮通信使』を接待した福岡藩については〈福岡藩の運命を左右するほど大変なものであった。一般領民のなかで諸準備や福岡藩領内の安全な通過を確保するための中心的な役割を演じたのは主として浦の者であり、その中でも相島・新宮・津屋崎の三浦が被った迷惑は相当のものであった。(中略)朝鮮通信使の来日に際して津屋崎が果たした役割は、第一に藩主の相島への渡海地であり、第二に鯛を中心とした魚の提供であり、第三に相島への諸荷物の運送であり、第四に水夫役の遂行であった〉と書かれてとる。家老以下の渡海の場所が新宮だったのに、藩主は津屋崎から船に乗ったから、藩主乗船の漕ぎ船はその多くを津屋崎が受け持ったと思われる。鯛の準備についても、延享五年(1748年)には津屋崎の漁船13艘が鯛網漁を行っていた。水夫役の動員は通信使の相島一泊に際し、津屋崎と勝浦の両浦だけでも百人程度が50日程度、つまり延べ5千人ほどが動員されたと考えられると『津屋崎町史』の記述にあり、朝鮮との交流という場が一般領民、漁民には日々の生活に大変な迷惑事だったということがうかがえるな」
清 「藩主が津屋崎から乗船したんが、災いのもととも言えるね。ところで、客館って通信使の宿泊所のことやね」
琢二 「そうや。現在、客館跡は畑になっており、『朝鮮通信使客館跡』の小さな立て札=写真④=が立っている。新宮町教育委員会が平成6年、この畑を発掘調査し、大規模な建物跡を見つけ、この場所に壮大な客館があったことを確認した。また、井戸跡からたくさん見つかった下駄や漆器椀、肥前系の陶磁器など接待に使ったと思われる道具類の一部は、新宮町歴史資料館に展示されとる」
 ">
">
写真④:畑わきの道路に立つ「朝鮮通信使客館跡」の立て札
=相島で、2010年5月9日撮影
清 「新宮町は、客館跡の資料を大事に扱っているとやね」
琢二 「客館跡の畑の一角には、相島伝統文化保存会の『朝鮮通信使客館図』=写真⑤=も立てられていたぞ」
 ">
">
写真⑤:畑の一角にある「朝鮮通信使客館図」の立て札
=相島で、2010年5月9日撮影
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=33.756601,130.492516&spn=0.114461,0.3368&z=12&brcurrent=3,0x35423c2035c8ad97:0xad8b9faab6351b0,1&output=embed">大きな地図で見る
「相島」(福岡県新宮町)と福津市津屋崎の位置図
=福津市津屋崎1丁目で、2009年4月5日撮影
・琢二と清の郷土史談義
『津屋崎学』
第33回:2010.05.13
朝鮮通信使と津屋崎
清 「この前、福津市津屋崎1丁目の津屋崎海水浴場の東外れば歩いとったら、『朝鮮通信使』の石碑=写真①=が駐車場の砂地に設けられとったよ。なんで、あんな石碑が、あの場所にあるとね?」
琢二 「清も、そう思うか。朝鮮通信使と相島(あいのしま)交流の案内板として、2009年3月11日に設置されとる。玄界灘に浮かぶ福岡県新宮町の相島が、朝鮮通信使との交流の島だという歴史を伝えたいのなら、相島に設置するのが当然だな。相島にではなく、なぜ津屋崎に設置するのか説明はない。設置場所も、津屋崎海水浴場の砂浜に接する駐車場の南端中央にあり、駐車場から砂浜に降りる人には障害物に思えるな」
清 「そうやね。朝鮮通信使って、江戸時代に朝鮮から日本に派遣された外交使節というぐらいの知識しかないけど、その相島での交流の石碑がなんで津屋崎にと考えても、よう分らん」
琢二 「石碑は御影石製で、縦約80㌢、横約160㌢、高さ約60㌢。『福津・慶州文化親善交流協会』(金光烈会長)が、二千七年の『朝鮮通信使四百周年』に当たり約110万円で制作、設置場所は福津市の許可を得たとされとる。碑文=写真②=には、朝鮮通信使と相島での交流について〈福間浦、津屋崎浦、勝浦からも多くの故郷の先祖たちが動員され、喜んで通信使の為に波止場の新改築、客館建築(中略)等に活躍したと伝えられています〉などと説明されている」
 ">
">写真②:「『相島(あいのしま)』は『朝鮮通信使』の島」と書かれた碑文
=福津市津屋崎1丁目で、2010年5月10日撮影
清 「相島には、津屋崎海岸にあるような石碑はないとね?」
琢二 「平成8年9月に新宮町教育委員会が立てた『朝鮮通信使客館跡』の説明板=写真③=が、あるぞ」
 ">
">写真③:『朝鮮通信使客館跡』の説明板
=福岡県新宮町相島で、2010年5月9日撮影
清 「へー、どんな説明文になっとうとね?」
琢二 「書き出しから引用すると、次のような説明だ。
〈江戸時代に、唯一国交を持ったのは朝鮮です。十一回にわたり、朝鮮からの使節団が、首都漢陽(かんよう)から、壱岐・対馬を経て、相島に寄港し、瀬戸内海をとおり大阪で上陸し江戸に向かいました。
最初の三回は、豊臣秀吉の二回にわたる朝鮮出兵の戦後処理のための使節で『回答兼刷還使(かいとうけんさつかんし』といわれました。その後は、徳川将軍の代替わりのお祝いなどのための使節で、『朝鮮通信使』〉といわれています〉
『回答兼刷還使』という呼び方の時期があるとは、現地に行くまで知らなかったな」
清 「叔父(おい)しゃん、いつ相島に行ったとね?」
琢二 「5月9日の日曜日たい。新宮町の新宮漁港から町営渡船に乗り、17分後に7.5㌔離れた相島漁港に着いた。釣り客が、多かったな」
清 「お土産は、ないと」
琢二 「ハハハ、相島地域産物展示販売所の食堂でウニ飯を食べたが、胃袋に収めただけだ。それより、この『朝鮮通信使客館跡』の説明板の続きには、面白い記述があったぞ。
〈外国からの使節団なので、幕府は通過経路の各藩に手厚く供応するよう命じました。黒田藩は、相島を供応の場と決め、一年ほど前からその準備にとりかかりました。
客館は毎回新築し、波止場の新修築や諸施設を建設しました。水は井戸や水溜場をつくり確保しました。食糧も天保二年の例では、豚は長崎から購入し、猪(しし)、鹿は立花山、能古島、津屋崎の渡山(わたりやま)で捕り、伊勢エビは大島から、鯛は広島から取り寄せています。黒田藩の相島での接待がいかに心をこめたものであったかがわかります〉
……と、ここに津屋崎の渡山でイノシシやシカを捕ったということが書かれとる」
清 「なるほど。面白いね」
琢二 「このことは、『津屋崎町史 通史編』にも載っているぞ。相島に一泊する『朝鮮通信使』を接待した福岡藩については〈福岡藩の運命を左右するほど大変なものであった。一般領民のなかで諸準備や福岡藩領内の安全な通過を確保するための中心的な役割を演じたのは主として浦の者であり、その中でも相島・新宮・津屋崎の三浦が被った迷惑は相当のものであった。(中略)朝鮮通信使の来日に際して津屋崎が果たした役割は、第一に藩主の相島への渡海地であり、第二に鯛を中心とした魚の提供であり、第三に相島への諸荷物の運送であり、第四に水夫役の遂行であった〉と書かれてとる。家老以下の渡海の場所が新宮だったのに、藩主は津屋崎から船に乗ったから、藩主乗船の漕ぎ船はその多くを津屋崎が受け持ったと思われる。鯛の準備についても、延享五年(1748年)には津屋崎の漁船13艘が鯛網漁を行っていた。水夫役の動員は通信使の相島一泊に際し、津屋崎と勝浦の両浦だけでも百人程度が50日程度、つまり延べ5千人ほどが動員されたと考えられると『津屋崎町史』の記述にあり、朝鮮との交流という場が一般領民、漁民には日々の生活に大変な迷惑事だったということがうかがえるな」
清 「藩主が津屋崎から乗船したんが、災いのもととも言えるね。ところで、客館って通信使の宿泊所のことやね」
琢二 「そうや。現在、客館跡は畑になっており、『朝鮮通信使客館跡』の小さな立て札=写真④=が立っている。新宮町教育委員会が平成6年、この畑を発掘調査し、大規模な建物跡を見つけ、この場所に壮大な客館があったことを確認した。また、井戸跡からたくさん見つかった下駄や漆器椀、肥前系の陶磁器など接待に使ったと思われる道具類の一部は、新宮町歴史資料館に展示されとる」
 ">
">写真④:畑わきの道路に立つ「朝鮮通信使客館跡」の立て札
=相島で、2010年5月9日撮影
清 「新宮町は、客館跡の資料を大事に扱っているとやね」
琢二 「客館跡の畑の一角には、相島伝統文化保存会の『朝鮮通信使客館図』=写真⑤=も立てられていたぞ」
 ">
">写真⑤:畑の一角にある「朝鮮通信使客館図」の立て札
=相島で、2010年5月9日撮影
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=33.756601,130.492516&spn=0.114461,0.3368&z=12&brcurrent=3,0x35423c2035c8ad97:0xad8b9faab6351b0,1&output=embed">大きな地図で見る
「相島」(福岡県新宮町)と福津市津屋崎の位置図