
写真①:新装なったJR大阪駅のコンコース
=大阪府大阪市北区梅田3で、2011年8月20日午前9時45分撮影
〈大阪・町歩きスポット〉 10
:「大阪ステーションシティ」
8月18日にスタートした京都―大阪への小旅行の最後の20日、新装なった大阪市北区梅田3にあるJR大阪駅=写真①=の「大阪ステーションシティ」を初めて訪問。福岡市でも、「阪急百貨店」や「東急ハンズ」などが新駅ビルに入居した「JR博多シティ」が、九州新幹線開業前の3月3日に開業して売り上げが好調なだけに、興味深く見物しました。
「大阪ステーションシティ」は5月4日、大阪の新たなランドマークとして「大阪駅が〝まち〟になる」をキャッチコピーにオープン。総事業費2,100億円で、駅北側の「ノースゲートビルディング」(地下2階、地上28階)と、駅南側の「サウスゲートビルディング」(地下4階、地上27階)の2棟を建設。大阪駅構内を含む総延床面積は、約53万平方㍍もあります。
「ノースゲートビルディング」に入居している「JR大阪三越伊勢丹」前のアトリウム広場には、NTTドコモが、携帯端末向け高速通信サービス「Xi(クロッシィ)」をPRするため、高さ8メートルの巨大な「鉄人28号」を公開するイベントを開催していました=写真②=。中に空気が入った特殊な布製のバルーン鉄人でしたが、ちょっと驚かされました。

写真②:「JR大阪三越伊勢丹」前の広場に立つ巨大な「鉄人28号」(向こうは、2013年春完成を目指し建設中の「うめきた(大阪駅北地区)」先行開発区域プロジェクト施設・「グランフロント大阪」のビル)
=「大阪ステーションシティ」で、8月20日午前9時55分撮影
「ノースゲートビルディング」には、西側地下2階―地上10階にキーテナントの「JR大阪三越伊勢丹」が、東側地下1階―地上10階に約2百店が入居した専門店ビルの「ルクア」がそれぞれ出店。10階に設けられたレストランゾーンは、「JR大阪三越伊勢丹」と「ルクア」が事実上一体化し、西日本最大の広さという。11階には、松竹、TOHOシネマズ、東映グループのティ・ジョイの大手3社が共同運営するシネコン「大阪ステーションシティシネマ」が入っており、12スクリーン、約2千5百席と西日本最大級。
「JR大阪三越伊勢丹」入り口には、午前10時の開店待ちの買い物客の列ができていました=写真③=。開店以来の売り上げ高は、同百貨店より専門店の「ルクア」が予想以上の健闘ぶりという。

写真③:開店待ちの買い物客の列ができた「JR大阪三越伊勢丹」入り口
=「大阪ステーションシティ」で、8月20日午前9時56分撮影
「JR大阪三越伊勢丹」前の広場は、多くの乗降客や買い物客らが行き来して、にぎわっています=写真④=。

写真④:多くの人が行き交う「JR大阪三越伊勢丹」前の広場
=「大阪ステーションシティ」で、8月20日午前9時58分撮影
「JR大阪三越伊勢丹」10階からは、眺望が楽しめました=写真⑤=。「ノースゲートビルディング」は、「ヨドバシカメラマルティメディア梅田」と向き合う形。これまで商業施設は少なく「駅裏」だった場所ですが、今後は再開発で発展しそう。
「大阪ステーションシティ」は、「JR博多シティ」のスケールを大きくした印象でしたが、「JR博多シティ」は「東急ハンズ」が入居した魅力や、新幹線駅がある交通の便など九州の中核駅としての今後の発展が期待できそうです。

写真⑤:「JR大阪三越伊勢丹」10階からの眺望
=「大阪ステーションシティ」で、8月20日午前11時10分撮影






























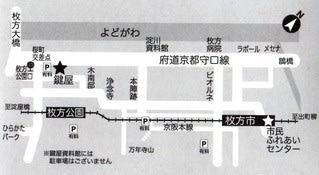








 ">
"> ">
"> ">
">
 ">
"> ">
">
 ">
"> ">
">



