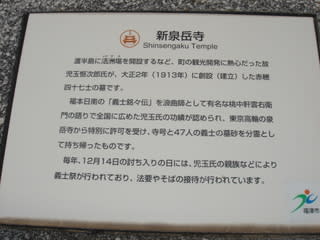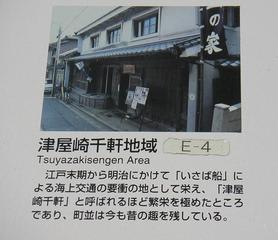●写真①:戦艦三笠のブリッジや砲台を模した日本海海戦記念碑がある「東郷公園」展望園地
=福津市渡で、2007年2月14日午後5時05分撮影
・琢二と清の郷土史談義
『津屋崎学』
第23回:2007.2.14
東郷公園
清 「2月11日に宮地嶽神社に参ったら、〝開運桜〟が満開になっとって、綺麗やったよ。おいしゃん(叔父さん)も、桜見に行ってきたらよかとに」
琢二 「早咲きのカンヒザクラの一種だな。本殿横の1本だけが毎年、早く咲くけん、神様のご利益を受けているというて、〝開運桜〟の名が付いたったい。宮地嶽神社は、福津市津屋崎のソメイヨシノの名所でもある」
清 「宮地嶽神社が津屋崎の東にある桜の名所なら、福津市渡の東郷公園=写真①=は津屋崎の西にある桜名所やね。ソメイヨシノが、500本もあるげなよ。晴れた日には、北西に玄界灘の孤島・沖ノ島や、壱岐・対馬まで遠望できて、眺めもいいよ。眼下の東方に広がる津屋崎海岸の美景は、吉村青春さんの第一詩集『鵲声―津屋崎センゲン』の表紙カラー写真にも使われとったね。それはそうと、東郷公園の謂われをよう知らんけん、教えちゃらんね」
琢二 「津屋崎小学校の遠足で、子供のころから行っとって、よう知らんとか。日本海海戦で世界最強とされていたロシアのバルチック艦隊を撃破し、日露戦争を勝利に導いた旧日本海軍連合艦隊司令長官・東郷平八郎元帥にちなんで、東郷公園の名前が付けられたったい。渡半島の突端にある標高114㍍の大峰山から、日本海海戦のときには日露両軍の船影が遠望でき、両軍艦隊が放つ砲声は津屋崎町まで響いたと伝えられとる」
清 「へー、そうなんだ」
琢二 「東郷公園の広さは、約千平方㍍。大峰山山頂に建てられた〈日本海海戦記念碑〉=写真②=は、連合艦隊の旗艦・三笠の艦橋をかたどってあり、記念碑の8文字〈日本海海戦祈念碑〉は〈記念〉を〈祈念〉と書かれ、東郷元帥の揮毫たい。記念碑は、勝利の日の明治38年(1905年)5月27日の〈海軍記念日(現〝海の記念日〟)〉にちなみ、高さ38尺(11.4㍍)、幅5尺(1.5㍍)、マスト27尺(8㍍)になっとる」

写真②:東郷元帥が揮毫した8文字が彫られた〈日本海海戦記念碑〉
=福津市渡の東郷公園で、2006年5月14日午前11時55分撮影
清 「東郷公園から玄界灘を遠望しても、明治の時代に日本の運命を決する日本海海戦があったとは、信じられん気がする。記念碑の下部側面には、東郷元帥肖像のブロンズ製レリーフ=写真③=や、〈海戦説明盤〉もあったよ」
琢二 「日本の海戦史を記念する場所の一つとして、若い人にも見てもらいたいな」

写真③:日本海海戦記念碑の側面に飾られた東郷元帥肖像のブロンズ製レリーフ
=福津市渡の東郷公園で、07年2月14日午後5時03分撮影
清 「東郷公園ができたのは、いつごろ?」
琢二 「地元の獣医だった安部正弘さんが、私財を投げ打ち、全国的にも寄付を募って、地元有志で組織した〈日本海々戦偉績保存会〉が昭和9年(1934年)6月27日に東郷元帥を顕彰しようと〈日本海海戦記念碑〉を建て、公園や資料館も造った」
清 「東郷公園は、これからハイキングに行くのに良い景勝地だね」
琢二 「東郷公園を含む一帯の130㌶は、福岡県が昭和57年から5年がかりで〈大峰山自然公園〉として整備し、キャンプ場や遊歩道もある。次回は、東郷公園近くの大峰山中腹に建てられた東郷元帥を祀る〈東郷神社〉=写真④=のことば話しちゃろう」

写真④:東郷公園への階段登り口南側にある東郷神社の鳥居
=福津市渡で、07年2月14日午後5時09分撮影
東郷公園(福岡県福津市渡):◆交通アクセス=〔電車・バスで〕西鉄宮地岳線津屋崎駅下車、徒歩40分。JR鹿児島本線福間駅下車、西鉄バス津屋崎橋行きに乗って「津屋崎橋」で下車し、徒歩30分〔車で〕九州自動車道古賀インターから約30分。駐車場(60台収容)あり。

福津市渡の「東郷公園」位置図
(ピンが立っている所)
=福津市渡で、2007年2月14日午後5時05分撮影
・琢二と清の郷土史談義
『津屋崎学』
第23回:2007.2.14
東郷公園
清 「2月11日に宮地嶽神社に参ったら、〝開運桜〟が満開になっとって、綺麗やったよ。おいしゃん(叔父さん)も、桜見に行ってきたらよかとに」
琢二 「早咲きのカンヒザクラの一種だな。本殿横の1本だけが毎年、早く咲くけん、神様のご利益を受けているというて、〝開運桜〟の名が付いたったい。宮地嶽神社は、福津市津屋崎のソメイヨシノの名所でもある」
清 「宮地嶽神社が津屋崎の東にある桜の名所なら、福津市渡の東郷公園=写真①=は津屋崎の西にある桜名所やね。ソメイヨシノが、500本もあるげなよ。晴れた日には、北西に玄界灘の孤島・沖ノ島や、壱岐・対馬まで遠望できて、眺めもいいよ。眼下の東方に広がる津屋崎海岸の美景は、吉村青春さんの第一詩集『鵲声―津屋崎センゲン』の表紙カラー写真にも使われとったね。それはそうと、東郷公園の謂われをよう知らんけん、教えちゃらんね」
琢二 「津屋崎小学校の遠足で、子供のころから行っとって、よう知らんとか。日本海海戦で世界最強とされていたロシアのバルチック艦隊を撃破し、日露戦争を勝利に導いた旧日本海軍連合艦隊司令長官・東郷平八郎元帥にちなんで、東郷公園の名前が付けられたったい。渡半島の突端にある標高114㍍の大峰山から、日本海海戦のときには日露両軍の船影が遠望でき、両軍艦隊が放つ砲声は津屋崎町まで響いたと伝えられとる」
清 「へー、そうなんだ」
琢二 「東郷公園の広さは、約千平方㍍。大峰山山頂に建てられた〈日本海海戦記念碑〉=写真②=は、連合艦隊の旗艦・三笠の艦橋をかたどってあり、記念碑の8文字〈日本海海戦祈念碑〉は〈記念〉を〈祈念〉と書かれ、東郷元帥の揮毫たい。記念碑は、勝利の日の明治38年(1905年)5月27日の〈海軍記念日(現〝海の記念日〟)〉にちなみ、高さ38尺(11.4㍍)、幅5尺(1.5㍍)、マスト27尺(8㍍)になっとる」

写真②:東郷元帥が揮毫した8文字が彫られた〈日本海海戦記念碑〉
=福津市渡の東郷公園で、2006年5月14日午前11時55分撮影
清 「東郷公園から玄界灘を遠望しても、明治の時代に日本の運命を決する日本海海戦があったとは、信じられん気がする。記念碑の下部側面には、東郷元帥肖像のブロンズ製レリーフ=写真③=や、〈海戦説明盤〉もあったよ」
琢二 「日本の海戦史を記念する場所の一つとして、若い人にも見てもらいたいな」

写真③:日本海海戦記念碑の側面に飾られた東郷元帥肖像のブロンズ製レリーフ
=福津市渡の東郷公園で、07年2月14日午後5時03分撮影
清 「東郷公園ができたのは、いつごろ?」
琢二 「地元の獣医だった安部正弘さんが、私財を投げ打ち、全国的にも寄付を募って、地元有志で組織した〈日本海々戦偉績保存会〉が昭和9年(1934年)6月27日に東郷元帥を顕彰しようと〈日本海海戦記念碑〉を建て、公園や資料館も造った」
清 「東郷公園は、これからハイキングに行くのに良い景勝地だね」
琢二 「東郷公園を含む一帯の130㌶は、福岡県が昭和57年から5年がかりで〈大峰山自然公園〉として整備し、キャンプ場や遊歩道もある。次回は、東郷公園近くの大峰山中腹に建てられた東郷元帥を祀る〈東郷神社〉=写真④=のことば話しちゃろう」

写真④:東郷公園への階段登り口南側にある東郷神社の鳥居
=福津市渡で、07年2月14日午後5時09分撮影
東郷公園(福岡県福津市渡):◆交通アクセス=〔電車・バスで〕西鉄宮地岳線津屋崎駅下車、徒歩40分。JR鹿児島本線福間駅下車、西鉄バス津屋崎橋行きに乗って「津屋崎橋」で下車し、徒歩30分〔車で〕九州自動車道古賀インターから約30分。駐車場(60台収容)あり。
福津市渡の「東郷公園」位置図
(ピンが立っている所)