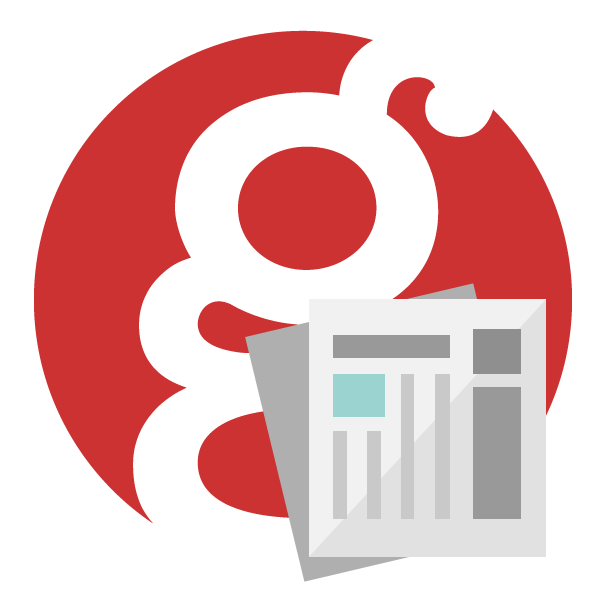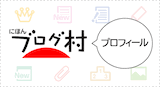昨 11/6、東京都主催による 都内の一部で北鮮などからの弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練が持たれた様だ。過去何度か 我国上空を通過して大平洋上に着弾したケースもあるだけに、5年ぶりとされる同訓練の意義は理解したい。
あらゆるケースから住民の命と暮らしを守る責務ある 国・自治体の当然の対応ともいえるが、これに対して「予定調和」ともいえる「左」からの妨害的反対行動もあった様だ。この勢力が用いる「定石」ともいえる 一見市民運動を装った左派野党主導による動きだろうが、TV報道をチラ見した限りでは若い世代はほぼ見受けられず、多くはよく指摘される「高齢左翼」の面々だった様だ。まぁこの連中「後継不在」の方が日本及び日本人の為にはなるとも思う者だが。
本題です。臨時国会の合間を縫っての 岸田総理のフィリピン、マレーシア訪問などで知られる所だろうが、対中露を睨んでの防衛安保面の拡充が 我国にとっての一急務たる事は論を待たないだろう。これに伴う防衛予算増額や 最低限の増税に安易に走るべきでないのは勿論だが、その一方で やはり必要な補強は不可欠ではないか。これに伴う防衛装備品の必要な移転緩和策も議論される様だ。当然の流れと心得る。以下 昨日の産経新聞ネット記事を引用して、みて参る事に。
「防衛装備移転、防空ミサイル解禁議論へ 与党実務者協議」
防衛装備品の輸出などのルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しを巡り自民、公明両党の実務者が 安全保障面などで協力関係の深い一部の国に対して地対空ミサイルなど防御目的の武器の輸出解禁を議論する方向で調整していることが 11/6、分かった。
現指針で輸出が容認される「救難」など 5類型「地雷処理」など新たに 3類型を加えることも検討する。与党実務者協議の関係者が明らかにした。
地対空ミサイルなどの輸出は、ロシアによる侵略を受けるウクライナ支援が念頭にある。防衛装備品を他国に無償提供することを認める一方、弾薬を含む武器は対象外と定める 自衛隊法第 116条の 3を改正し、運用指針を書き換える案などが浮上している。
現在、輸出が認められる「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の 5類型には「地雷処理」「ドローン対処」「「教育訓練」を追加する方向で検討を進める。政府は 8月の与党協議で、5類型に該当すれば殺傷能力のある武器を搭載していても輸出可能との見解を示しており、与党も容認する。
自公(両党)は 内閣改造で休止していた実務者協議を 11/8に再開する。12月にも意見集約し、政府に運用指針の改定を求める考えだ。11/8の会合では、国際共同開発する装備品の扱い議論する。政府は 英国、イタリア(両国)と開発する次期戦闘機の第三国への輸出を可能にしたい考えで、与党協議では参加国の事前同意を前提に 認める見通しだ。(引用ここまで)
これまでも輸出可能とされた 防衛装備品移転に関する 5類型に加え、「地雷処理」「ドローン対処」「教育訓練」の 3類型に絞っての追加なら 現実に即した合理的な範囲といえる。徒に拡大すべきでないのは勿論だが、地雷、ドローンの両対策などは 既にウクライナ国などからの支援要請も表されているとかで、速やかに実現への道を開くべきだ。
我国から輸出の 防衛装備品に関する教育訓練も欠かせない。くれぐれも間違った用い方をさせない為にも、この対応は不可欠だろう。自衛隊各位の任務内容が増えるのは事実だが、我国の安保にも確実に資する事共だけに、無理のない所で是非進めて頂きたい。
防衛装備品移転三原則の運用指針見直しの動きは、我国の今、そしてこれからも必要な「自由で開かれたインド大平洋地域」の構築にとっても不可欠なもの。何よりも 現状、エネルギー輸送の大半をこの地域に安定に頼っている現状を強く踏まえるべき。先日の 岸田総理による東南アジア 2国訪問も、この必要に沿ったものだったろう。
媚中露朝の左派容共勢力にとっては「発狂」ものだろうが、騒ぎたくば勝手にやらせておけば良い。より真に近い「日本及び日本人」にとっての国益保持の為、防衛装備品移転緩和に取り組んで頂きたいのは勿論だが、それに際し 例えば消耗品の寸法規格などを複数国で共通化を図ったり、それら諸国の装備との互換性を図ったりする配慮も是非必要だろう。状況にもよるが、そうした諸国の消耗品が品薄となった場合に 我国から現物支援する事も可能となろうから。又 我国内の自衛隊装備向上との整合も考慮されるべき。(末尾の関連記事)
とに角 アジア大平洋地域における我国の重い役割から逃げる訳には参らない。少しでも大きな貢献とし得るべく これからの防衛装備品移転緩和議論を見守る事としたい。今回画像は 当地都心近くの JR名古屋的を通り、首都圏方面へと向かう 東海道本線・臨時貨物便の様子を。以下に 関連記事をリンク致します。「読売新聞 11/6付」