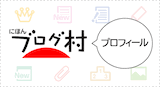コナサン、ミンバンワ!約2週間ぶりの拙ブログです。今年2007=平成19年8月ももう終盤、処暑の時期にも関わらず、厳しすぎる残暑ではある。お互い何とか健康留意の上、次の9月に繋げたいものであります。
さて表日記にても綴っている様にこの盆期間中、岐阜の悪友と共に長野県下へ避暑に参ったのだが、その折に岡谷市の天竜川水源地を訪ねた。長野の名湖「諏訪湖」西岸に位置するこの場所は治水施設「釜口水門」と言う所でもある。湖が水源と言うのは小学生時分より知ってはいたが、まさかこんな街中とは夢想だにしなかった。
釜口水門自体は昭和初期からあるそうで、当時の発想と技術からすれば防災上止むを得なかったのだろう。現在の水門は1988=昭和63年に竣工した2代目で、魚道なども備えてはいるが、過剰設備ではないかと勘ぐりたくなるものがあったのは事実である。高度成長の頃は、諏訪湖も湖沼汚濁の問題に苦しんだ様だ。改善への取り組みは認めるべきだろうが、それでも生活廃水とかは流入している模様で、水面よりはメタンガスの発生している気配も感じられた。
諏訪湖の標高は約760m、同湖に流れ込む川もある事を考えると、ここを厳密に天竜川の水源と呼ぶには向かない面もあるのかも知れないが、それにしても正直やや落胆を禁じえなかった遺憾な光景であった事は認めざるを得ない。次回は天竜川河口の事に少し触れる予定です。最後に、釜口水門の模様をお目にかけます。