校條剛氏は『ザ・流行作家』でこんな指摘もしている。
捕物帳と股旅物は、大衆時代小説の二大ジャンルである。この二つには明確な差異がある。捕物帳は「定住者のお話」であるのに対して、股旅物は「住所不定者のお話」である。そして、定住者は住所不定者に対して温かく接したりしないものである。住所不定者は、渡世人であり、人別帳から外れた無宿人である。捕物帳は、いわば警察の物語であり、股旅物は、犯人のほうの小説といっていい。追うものが主体となって語られるものと追われるものが主体となった物語というまるで正反対の方向性を持つのである。
決して日本人だけの特性ではないが、読者というものは、警察の物語が大好きだということである。追うほうの、取り締まる側の位置に立つのが好きなのだ。
決して日本人だけの特性ではないが、読者というものは、警察の物語が大好きだということである。追うほうの、取り締まる側の位置に立つのが好きなのだ。
「鬼平」や「剣客」が継続的に多くの読者を長年にわたり獲得してきたのに対し、「紋次郎」の低迷の原因の一つは、日本の読者の警察好きにあるのではないだろうか。
捕物帳と股旅物についてのこの指摘は一種の日本人論だと思う。
「定住者のお話」を好むということを、風が吹けば桶屋のヘリクツでこじつけると、よそ者を嫌うムラ社会が好む話が捕物帳である。
あれこれあったけど、結局はメデタシ、秩序は回復されました、ということで安心するわけである。
秩序を回復するのは権力によってということになると、水戸黄門は捕物帳と似た構成の物語ということか。
で、校條剛氏は新潮社出身なのにもかかわらず、『ザ・流行作家』は講談社から出版されている。
たぶん新潮ジャーナリズムについて批判しているからだと思う。
校條剛氏によると、新潮ジャーナリズムとは「週刊新潮の論調をつくり、八十歳を過ぎても最高決定権を握っていた斎藤十一という編集者・役員の思想」である。
「色、欲、金、他人の不幸」
「調子に乗っている人間を叩くのは面白い」
これが斎藤イズム。
斎藤が、小さな犠牲者を見つける天才であったことは間違いない。自分は安全地帯から動かないで、犠牲者の蟻ん子たちが右往左往する様を悦に入って眺めているという姿勢である。自分は、他人を裁く権利があると理由もなく信じている。いつも偉そうにしていられるのだから、プライド高く、コンプレックスなお強い編集者や記者にはなんとも魅力のある思想ではないか。
「小さな犠牲者」とは言い得て妙である。
斎藤イズムは小さな犠牲者を叩くだけではなく、持ち上げもする。
一度、池に落としてから、今度は逆に手を差し伸べて救助してやれば、恐れと感謝が同居することになり、以後、いかようにも便利使いができるという計算
斎藤イズムは「週刊新潮」だけではなく、マスコミ全般に共通する。
スキャンダリズムを基調としたマスコミの病の特徴を、校條剛氏は次のようにあげている。
一つには、正義感から発している告発に見せながら、正義の下敷はないということ。編集者の価値基準は、正義ではなく、順法精神でもなく、話題性=スキャンダリズムであること。倫理的な物差しは探すべくもない。皆無なのである。結果として、他人が苦しもうが、没落しようが、破滅しようが知ったことではない。要は、「色、欲、金、他人の不幸」にしか興味のない大衆が満足すればそれでいいという考えである。大衆というのは、もちろん、マスコミ人たちが口にする言い訳に過ぎず、実は、自分たちが満足感を味わいたいのだ。
筆者も実はそうした無神経なマスコミ人の一員であった。
筆者も実はそうした無神経なマスコミ人の一員であった。
こうした正義感は捕物帳を喜ぶ気持ちと同じではないかと思う。
一方でまた、校條剛氏は次のように言う。
大衆は実際の警察が嫌いなのである。少なくとも、好きではないだろう。大衆が好んでいるのは、こうあって欲しいという想像上の警察である。つまり、警察に関しても、読者は集団的な幻想を抱いているのだ。
権力をも嫌うのである。
だからこそ、週刊誌は雅子妃の悪口を毎号掲載するわけである。
自分は正義の立場に立ち、被害者に共感しているつもりでいても、実際には安全な立場で楽しんでいるにすぎない。














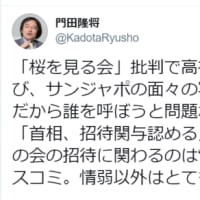
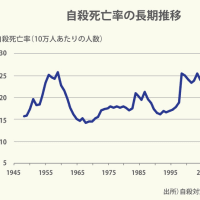
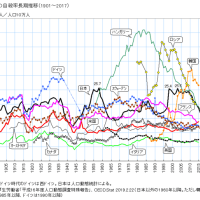

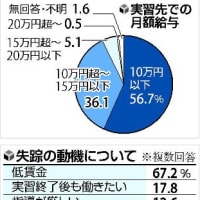






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます