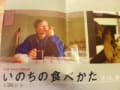農水省は昨年末の12月にまとめた、第3回食料の未来を描く戦略会議資料『これからの世界の食料需給は我が国にどう影響するか』のなかで、現状分析をA4で14枚にまとめ、結論として
① 途上国を中心とした人口増加や所得向上が進むことに加え、バイオ燃料用需要の拡大により、世界の食料需要は大幅に増加する見通し。
② 農地面積の増加や単位面積当たり収量の伸びには限界があり、食料生産が需要の増加に追い付けない可能性が大。
③ この結果、現在高騰している穀物価格は、さらに上昇する可能性。
④ さらに、気候変動等の要因が食料供給の不安定化を招き、価格高騰につながる可能性。があると以上4点を挙げ、
『このような世界の食料需給の見通しを踏まえ、食料の6割を海外に依存する我が国として、どのようにして食料の安定供給を確保していくのか。
また、そのために、消費者、生産者、食品製造・流通・外食関係の事業者にも、どのような行動が期待されるのかを考える必要がある。』とおよそ管轄省庁の導く結論とは、思えないような結論でレポートを締めくくっている。
誰がこのような国を望んだのか、明日の食料が見えない国とはどんな国なのか、中国の餃子問題は決して中国の衛生管理上の問題ではないことに一日も早く気づき、戦後いち早く飢餓や貧困からは開放されたけれど、自国で何とかしない限りはいくら貨幣を持っていても、食料が一切入って来なくなる危険性を大いにはらんでいる我が国の明日の食のあり方について、もうそろそろ他人事のように考えている国には任せてはいられない。