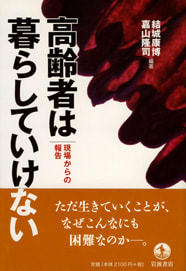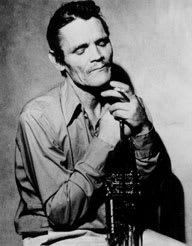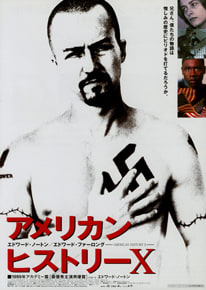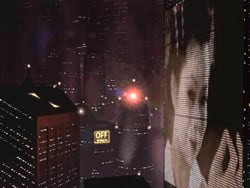Papillon@NHK-BShi、フランクリン・J・シャフナー監督(1973年アメリカ)
監獄島からの脱獄に成功し、後にベネズエラ市民権を取得した実在の男の伝記小説を映画化した、迫力満点のアクション大作。
1930年代。胸に蝶の刺青を入れていることから「パピヨン(蝶)」と呼ばれる金庫破り犯(スティーヴ・マックィーン)。彼は殺人の罪を着せられて終身刑の判決を受け、祖国フランスを追放されて、生きては戻れぬと噂される南米ギアナのデビルズ島で強制労働を科される。島へ向かう船中で、国債偽造の罪で同じ服役囚となった、芸術家肌の知能犯ドガ(ダスティン・ホフマン)と知り合い、彼のボディガードを引き受けることで、脱獄のため看守を買収したりボート等を入手するためのカネとツテを得ようと図るパピヨン。
島の環境は想像を絶するもので、生き延びるのに巧みなドガは看守とのコネを築いて減刑の機会を探るのだが、かたときも脱獄を忘れないパピヨンは、老獪な囚人クルジオ(ウッドロー・パーフリー)、ハンサムな若者だが同性愛の囚人マチュレット(ロバート・デマン)と組んで、チャンスをうかがう。
反抗的なパピヨンは密室の独房に閉じ込められ、果実を差し入れてくれたドガの名を白状するのを拒んだため2年間も半分の食事で、多くの者は衰弱死してしまう独房生活を耐え抜いた。
そしていよいよ脱獄のとき。ドガは同行せず、看守の目を3人からそらす役を引き受けたが、実行の際のアクシデントでクルジオが命を落とし、行きがかり上ドガがパピヨン、マチュレットと3人で脱走行。柵を乗り越える際、足を骨折したドガを、医療の心得のあるマチュレットが手当てするなどして、なんとか逃げ延びようとするが、追っ手の追及も激しく、やがて1人きりになって原住民のやハンセン病患者の集落へ身を寄せるパピヨンも、ついには追っ手に引き渡される。
今度は5年の独房生活。それが終わったとき、マチュレットの息は絶え、パピヨンも総白髪となるが自由への執念を失ってはいないのだった─。監獄から解放されて、いちおう自主的な暮らしを営めるが、死ぬまで出られない小島でパピヨンと再会したドガは、複雑な表情で「あんたにここへ来てほしくなかった」と─。

尖閣沖で中国漁船に追突された映像を、国民に見せないのはおかしいと思って流出させたのは「義憤」による行為なので、その海保職員が「自分は悪くない」と思うのは勝手である。
が、それに対してわれわれが喝采を送り、彼を英雄視するのは、まことに短絡的で、国難の兆しが漂っているともいえよう。
幸い今回はそれほどでもないが、下手をすると戦争を招きかねないような、国と国との問題にまつわる証拠物件。それを国民に見せようとせず、船長を釈放して、早期に沈静化を図ったのは、民主党政権の判断である。
民主党が危機管理については素人同然だというのは、すでに故・永田議員の騒動のときから分かっていたことで、それでもなお、自民党政権のままでは駄目だから、われわれが選挙で政権交代させたのだ。彼らに、負託したのである。
民主党政権が失政を行なっても、それは国民にも責任があることなので、やはり駄目だと分かったら、再び選挙で自民党政権に、いや自民党もバラバラに分かれているので、自民・公明・みんな・たちあがれとかのわけわからん連立政権にすればよろしい。
問題は、政治家はわれわれの手で選んだり政権交代させることができるが、官僚はそうではないということだ。
国という媒体・制度にまつわる、さまざまな役目に殉じる役人。公務員。公務員が役目を逸脱し、主権者たる国民が選んだ政権の足を引っ張るようなことをするのを見逃していると、やがて官僚的悪徳が国を覆いつくしギリシャ化・ビルマ化を招く気がしてならないのだが。
「事業仕分け」とかで政治家が不必要な役目を削ろうとしても、官僚は表面的に「ああそうですか」と受け流しておいて、あの手この手で予算・役職の温存を図る。しぶとい。政治家には時間が限られるが、官僚には任期がなく、いつまででも自らの利権のため取り計らうことができる。時間が彼らに味方する。彼らが長期間にわたって我田引水するうちに、われわれ国民は干上がってしまいかねないというのがオラの見立てだ。
あの神戸の航海士が刑事罰を受ける必要まではないと思うが、当然、国家公務員の職は依願退職してもらって、文春・新潮・講談社とかの国恥マスコミに雇ってもらって、突撃リポートでもすればいいんじゃないか。
で、この映画『パピヨン』を見ていて、リベラル色のある『暴力脱獄』とかよりも、もっと血沸き肉踊る劇画調のアクション大作かという先入見があったもんだから、その不屈の、2年とか5年とかの絶望的な時間にも耐え抜いて、支配からの脱出を求める人間の魂に、胸が震えた。

脱走を目論む3人、主人公パピヨンに、老獪な策士クルジオ、同性愛者マチュレット、そしてクルジオが欠けてユダヤ人ダスティン・ホフマンの演じる知能犯ドガが加わる。この構図が、それぞれ代表的人類だという気がする。
南米のジャングルではことに顕著だが、地球は、人類に対して優しくない。人類は、ほかの動物に比べ、肉体的にはとても貧弱。しかし、くじけない魂がある。近眼で、やや体力の劣るドガは、脱走よりも、さまざまに工夫して計らって、看守と持ちつ持たれつの関係を築こうと。最後の「絶対に出られない小島」でも、野菜を育てたり動物を飼ったり、それなりに生きようと。そんなドガが、檻の中では絶対に満足しない、たとえ死ぬことになっても自由をつかもうと苦闘するパピヨンに向ける視線はまぶしそう。「大きな人間」。人類はいかに生くべきかを示せる人間。
ひるがえって、オラ深夜に酒飲みながら自分のブログを見たりするんですが、深夜に食べると胆石系に要注意ですが、先日の「マガジンひとり on Twitter - Vol. 5」など、つくづく小さい人間だと思わざるをえない。ことに、再三にわたって横浜ベイスターズ等プロ野球の凋落をおちょくってるあたり。
オラだって子どものころは野球をやったし、プロ野球選手を英雄視したし、さんざん野球のおかげで楽しませてもらったのにね。『闇金ウシジマくん』の進行中のエピソード「トレンディーくん」の主人公・鈴木斗馬(とうま)32歳が、苗字もそうだけど、人相がどこかイチロー選手と重なるように思えて。
リア充のモテ男なのだが、努力家なんだよ。コツコツ積み重ねる。人に接するのに長じるための「ひとり焼肉」↓はどうかと思うが。
やっぱり、われわれの時代の代表的な野球選手が、努力型のイチローでよかったと思う。それは、彼のように生きたいと思わせ、将来にわたって影響をおよぼす、代表的日本人=「大きな人間」だから。
直接的な子どもがいるとかいないとかより、たとえ小さくても、大きくなろうとする気持ちを死ぬまで持ち続けることが大切ではないだろうか。

監獄島からの脱獄に成功し、後にベネズエラ市民権を取得した実在の男の伝記小説を映画化した、迫力満点のアクション大作。
1930年代。胸に蝶の刺青を入れていることから「パピヨン(蝶)」と呼ばれる金庫破り犯(スティーヴ・マックィーン)。彼は殺人の罪を着せられて終身刑の判決を受け、祖国フランスを追放されて、生きては戻れぬと噂される南米ギアナのデビルズ島で強制労働を科される。島へ向かう船中で、国債偽造の罪で同じ服役囚となった、芸術家肌の知能犯ドガ(ダスティン・ホフマン)と知り合い、彼のボディガードを引き受けることで、脱獄のため看守を買収したりボート等を入手するためのカネとツテを得ようと図るパピヨン。
島の環境は想像を絶するもので、生き延びるのに巧みなドガは看守とのコネを築いて減刑の機会を探るのだが、かたときも脱獄を忘れないパピヨンは、老獪な囚人クルジオ(ウッドロー・パーフリー)、ハンサムな若者だが同性愛の囚人マチュレット(ロバート・デマン)と組んで、チャンスをうかがう。
反抗的なパピヨンは密室の独房に閉じ込められ、果実を差し入れてくれたドガの名を白状するのを拒んだため2年間も半分の食事で、多くの者は衰弱死してしまう独房生活を耐え抜いた。
そしていよいよ脱獄のとき。ドガは同行せず、看守の目を3人からそらす役を引き受けたが、実行の際のアクシデントでクルジオが命を落とし、行きがかり上ドガがパピヨン、マチュレットと3人で脱走行。柵を乗り越える際、足を骨折したドガを、医療の心得のあるマチュレットが手当てするなどして、なんとか逃げ延びようとするが、追っ手の追及も激しく、やがて1人きりになって原住民のやハンセン病患者の集落へ身を寄せるパピヨンも、ついには追っ手に引き渡される。
今度は5年の独房生活。それが終わったとき、マチュレットの息は絶え、パピヨンも総白髪となるが自由への執念を失ってはいないのだった─。監獄から解放されて、いちおう自主的な暮らしを営めるが、死ぬまで出られない小島でパピヨンと再会したドガは、複雑な表情で「あんたにここへ来てほしくなかった」と─。

尖閣沖で中国漁船に追突された映像を、国民に見せないのはおかしいと思って流出させたのは「義憤」による行為なので、その海保職員が「自分は悪くない」と思うのは勝手である。
が、それに対してわれわれが喝采を送り、彼を英雄視するのは、まことに短絡的で、国難の兆しが漂っているともいえよう。
幸い今回はそれほどでもないが、下手をすると戦争を招きかねないような、国と国との問題にまつわる証拠物件。それを国民に見せようとせず、船長を釈放して、早期に沈静化を図ったのは、民主党政権の判断である。
民主党が危機管理については素人同然だというのは、すでに故・永田議員の騒動のときから分かっていたことで、それでもなお、自民党政権のままでは駄目だから、われわれが選挙で政権交代させたのだ。彼らに、負託したのである。
民主党政権が失政を行なっても、それは国民にも責任があることなので、やはり駄目だと分かったら、再び選挙で自民党政権に、いや自民党もバラバラに分かれているので、自民・公明・みんな・たちあがれとかのわけわからん連立政権にすればよろしい。
問題は、政治家はわれわれの手で選んだり政権交代させることができるが、官僚はそうではないということだ。
国という媒体・制度にまつわる、さまざまな役目に殉じる役人。公務員。公務員が役目を逸脱し、主権者たる国民が選んだ政権の足を引っ張るようなことをするのを見逃していると、やがて官僚的悪徳が国を覆いつくしギリシャ化・ビルマ化を招く気がしてならないのだが。
「事業仕分け」とかで政治家が不必要な役目を削ろうとしても、官僚は表面的に「ああそうですか」と受け流しておいて、あの手この手で予算・役職の温存を図る。しぶとい。政治家には時間が限られるが、官僚には任期がなく、いつまででも自らの利権のため取り計らうことができる。時間が彼らに味方する。彼らが長期間にわたって我田引水するうちに、われわれ国民は干上がってしまいかねないというのがオラの見立てだ。
あの神戸の航海士が刑事罰を受ける必要まではないと思うが、当然、国家公務員の職は依願退職してもらって、文春・新潮・講談社とかの国恥マスコミに雇ってもらって、突撃リポートでもすればいいんじゃないか。
で、この映画『パピヨン』を見ていて、リベラル色のある『暴力脱獄』とかよりも、もっと血沸き肉踊る劇画調のアクション大作かという先入見があったもんだから、その不屈の、2年とか5年とかの絶望的な時間にも耐え抜いて、支配からの脱出を求める人間の魂に、胸が震えた。

脱走を目論む3人、主人公パピヨンに、老獪な策士クルジオ、同性愛者マチュレット、そしてクルジオが欠けてユダヤ人ダスティン・ホフマンの演じる知能犯ドガが加わる。この構図が、それぞれ代表的人類だという気がする。
南米のジャングルではことに顕著だが、地球は、人類に対して優しくない。人類は、ほかの動物に比べ、肉体的にはとても貧弱。しかし、くじけない魂がある。近眼で、やや体力の劣るドガは、脱走よりも、さまざまに工夫して計らって、看守と持ちつ持たれつの関係を築こうと。最後の「絶対に出られない小島」でも、野菜を育てたり動物を飼ったり、それなりに生きようと。そんなドガが、檻の中では絶対に満足しない、たとえ死ぬことになっても自由をつかもうと苦闘するパピヨンに向ける視線はまぶしそう。「大きな人間」。人類はいかに生くべきかを示せる人間。
ひるがえって、オラ深夜に酒飲みながら自分のブログを見たりするんですが、深夜に食べると胆石系に要注意ですが、先日の「マガジンひとり on Twitter - Vol. 5」など、つくづく小さい人間だと思わざるをえない。ことに、再三にわたって横浜ベイスターズ等プロ野球の凋落をおちょくってるあたり。
オラだって子どものころは野球をやったし、プロ野球選手を英雄視したし、さんざん野球のおかげで楽しませてもらったのにね。『闇金ウシジマくん』の進行中のエピソード「トレンディーくん」の主人公・鈴木斗馬(とうま)32歳が、苗字もそうだけど、人相がどこかイチロー選手と重なるように思えて。
リア充のモテ男なのだが、努力家なんだよ。コツコツ積み重ねる。人に接するのに長じるための「ひとり焼肉」↓はどうかと思うが。
やっぱり、われわれの時代の代表的な野球選手が、努力型のイチローでよかったと思う。それは、彼のように生きたいと思わせ、将来にわたって影響をおよぼす、代表的日本人=「大きな人間」だから。
直接的な子どもがいるとかいないとかより、たとえ小さくても、大きくなろうとする気持ちを死ぬまで持ち続けることが大切ではないだろうか。